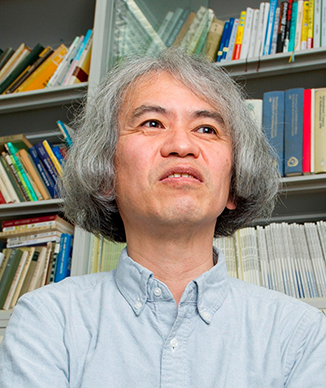公文式 水巻教室 指導者
伊藤 ゆう子(いとう ゆうこ)
熊本県出身。『公文式算数の秘密』(廣済堂出版)※を読み公文式を知り、教室を開設。公文式の創始者と直接親交があり、障害がある生徒の指導に熱心に取り組んできた。障害児指導の自主研究活動に取り組み、その活動は九州・沖縄のみならず全国に広がっている。全国各地での公文式指導者向け講座の講師も務めた。Baby Kumonと学習療法の創成期には指導者モニター活動に携わった。※1974年出版、現在は絶版で入手不可。
公文教育研究会 広報部長
景山 忠男(かげやま ただお)
1993年入社。国内教室事業に30年以上携わり、国内4地域でジェネラルマネージャー・リージョナルマネージャーを歴任後、2023年7月より現職。
「できること」を探そうと思って関わると
その子の力はどんどん高まっていく
景山:伊藤先生が教室で、生徒を観るときに大事にしていることをお聞かせいただけますか。
伊藤:「この子はできない」と思えば、できないところがどんどん目に入り、全部ができないように見えてしまいがちです。また、44年の中で、いろんな生徒さんが入会当時には想像もできなかった成長ぶりを見せてくれたことから、どんな子もどこでどんな花を開かせてくれるかわからない、私が子どもたちのもつ可能性を「こんなもの」と決めてしまわないように、「この子は、尊く、賢い存在」と思って接しています。

障害のある子たちや診断はなくても、例えば多動の子も、よく観察していると教材をちらっと見た、とか、じっと見た、という瞬間があります。そういう瞬間を見つけられたとき、この子は絶対に伸びる、伸ばせるんだ、と身が引き締まります。
障害名にとらわれず、生徒をよく観察すれば、どの子もキラリと光るものをもっています。それが見えにくい子は、私たちがまだ発見できていないだけ。「できること」を探そうとして関わると、その子の力はどんどん高まっていきます。
前編でお話しした水頭症のAさんは、地域の小学校・中学校で、いろんな方に助けてもらいながら学校行事もすべて参加し、充実した学校生活を送りました。手足の麻痺は残りましたが、言葉については異常なしと判定され、頭の髄液も減り続け、中学生の時、髄液をとるための管の入れ替え手術が不要と診断した主治医は、髄液の減少は知的刺激を継続したためではないか、と大変喜ばれました。学習を始めた当初、発語がなくお母さまとしかコミュニケーションが取れなかったときには、私には想像できなかった姿でした。
もう一人、小学校に上がる直前に全く発語がなく、小学校から支援学校に通い、支援学校の高等部を卒業したASD(自閉スペクトラム症)のBさんは、教室に来られた初日はイヤだイヤだと泣いて寝転がりました。その後も教室に来ても教材を見向きもしない日が続きましたが、小学校3年生の時にラジオ英語に興味をもったことがきっかけで英語に興味をもち、公文式英語学習を開始しました。
今に至るまで、毎日おばあちゃんに電話をして英語を聞いてもらい、忙しい両親に代わってほめられながら学習を進めてきました。中学生くらいまでよだれが大変でしたが、ほめられて自信や意欲をもって学習を続け、高校レベルの英語を学習する時にはお話の続きが読みたいから次の教材が読みたいと、復習せずにどんどん進んでいき、コンプリーターズコース※1を学習するまでになりました。教室では昔から彼が英語を音読すると、その真剣さに教室の雰囲気が変わります。いろんな子が彼の音読を聞き、あんな風になりたいと目標にして頑張っています。
※1 英語の最終教材はO教材で高校相当程度。O教材の後に大学教養課程相当の「コンプリーターズコース(XP・XQ教材)」が用意されています(2025年6月現在)。
Bさんは学習後、必ず今日読んだお話がどんな内容だったか話してくれたり、その内容を私に知っているか問いかけたり、復習せずに次のお話しが読みたいと言ったりしてきます。Bさんの丁寧な日本語でのそのやりとりが面白いらしく、スタッフだけでなく、小学生が「あのお兄ちゃん今日まだ来てない?」と楽しみにしています。彼の会話を聞いたら気持ちが明るくなるそうです。愛されて育ってきたことがにじみ出ているのだろうなと思います。

Bさんは17歳の時、英語の先生になる夢ができました。いつか支援学校でも英語の授業ができるかもしれない、そのとき自分が英語の先生になって、英語の楽しさを伝えたいそうです。まずは、大学受験のために、高校卒業資格を取ろうと働きながら単位制の高校に通う予定です。学習に向き合う姿勢も学習を通して夢を掴みに行く姿も、障害のない子たちとまったく変わりないと実感します。
景山:子どもには一人ひとりに自分の輝き方があるという、まさに見方ひとつで、子どもの個性の捉え方が変わりますよね。
伊藤:学習を続けていれば自信や意欲が育ち、得意なものが浮き出てきて、顕著だった障害の特性が気にならないくらい目立たなくなって見えなくなったら、日常生活でも困らなくなるように思います。私たち指導者に必要なのは、「できること」をもっと伸ばしていくこと、子どものどんな瞬間もいかに見逃さないようにするかを勉強し、それを指導に生かしていくことなのだと思います。
訂正が一番大事
教室は完結を経験する場

景山:伊藤先生は「人は間違うもの。だから、直すことが大事」とおっしゃっていましたよね。素晴らしい考え方だと思いますが、根底にある思いをお聞かせいただけますか。
伊藤:人間は人生の中で決して正しいことばかりをやれるものではありません。間違ったら改めることで、その人がその人らしく成長していくことができます。子どもたちにとっても、教材で間違うという経験がとても大事で、公文式の学習の中では「訂正」が一番大事だと思っています。
いつも子どもたちには、人間だれしも間違うことがあるんだよ、間違ったときには「ごめんなさい」と言うことと、教材も同じように間違ったときはきちんと訂正をすることが大事なんだよ、と話しています。訂正を嫌がる子にも、「あなたの生き方の中で大事な要素になっていくから、諦めないで最後までやろうね」と言っています。
脳性麻痺のあるCさんは、体を自由に動かすことができないので、やりたくないときは消しゴムや鉛筆を落として反抗していたことがありました。訂正のときは「手伝ってあげるね」と言って消しゴムでこちらが消すなど、試行錯誤しながら中学2年生まで学習を続けました。
訂正は誰しも嫌なものではありますが、間違いを恐れずに挑戦する、間違ったらやり直す、そしてできるようになるまで何度でも挑戦する、といったことから自分の障害を理由にして逃げてほしくなかったのです。
公文式学習を卒業した後、何度か教室に来てくれました。ある時は、「手伝わんでいい!一人でできるから」と言いながら自分で玄関から這って入ってきました。次の時は装具をつけて一人で歩いていました。そしてその後、福岡市内の大学に合格して、「一人暮らしをしたい」と言い、実家を出てヘルパーさんの支援を受けながら生活を始めました。
彼は物理的にできないことが多いので、いろんな人にサポートしてもらうことになります。サポートしてくれる人が間違えてしまったときに、その間違いを受け入れる、人間だから間違えることもあり、間違えても大丈夫だと思う気持ちはとても大切です。自分だけでなく、サポートしてくれるまわりの人が間違えたときにどう対応するとよいのか、彼は公文式の学習や訂正を通して学び、リハビリがつらくても何度も挑戦して、自分の人生を切り開いています。

景山:伊藤先生は、「自分でできた喜びの瞬間に人は人になる」と以前私にお話しいただきました。公文式教室では自分のことは自分でする、間違ったら訂正する、そして最後まで自分の力でやり遂げる。まさに「完結を経験する場」として教室が存在しますし、そこには一連の様子を見てほめてくれる先生がいる。毎回小さな成功体験を積み重ねることができる、子どもにとってすごく大事な場ですよね。
伊藤:今そういう経験ができる機会が少ないですよね。大人も子どもたちも時間に追われて、生活の中で「早くしなさい」と言われることが多く、子どもたちがひとつのことを完結させるという経験をすることが難しくなってきている時代です。子どもだからこそ、一つひとつ、問題の一問一問を自分ごとと捉えてきちんと完結させていくことが大事だと思います。
景山:教室の様子を見せていただきましたが、指示命令語がないですよね。否定せずに、常に生徒が主役。ただし生徒本人のその日の学習が完結するまでは必ず解いてもらい、訂正する。そのこだわりを伊藤先生は行動、姿勢で伝えていらっしゃいました。そして、伊藤先生も教室の子どもたちも丁寧語で話していますよね。
伊藤:言葉に障害がある子たちもいますので、主語・述語に気をつけ、話し言葉ではなく、書き言葉を意識しながら、子どもたちには話しているつもりです。私と子どもとのやり取りをみて、わが子への接し方を意識してくださる保護者もいらっしゃいます。いろんな子がいること、そしていろんな接し方があることを学べるのが教室という場、とも言えるのではと感じています。
教室の卒業生の活躍が誇り 生きることは学ぶこと、学ぶことは生きること
景山:伊藤先生の教室の卒業生との交流についてお聞かせいただけますか。
伊藤:小1から高3までの公文式学習だけで第一希望の国立大学に合格したDさんは、大人になって小学校の先生になり、担任として初めての卒業生を出す時に、卒業する生徒たちにエールを送る授業をしてほしいと連絡をくれました。他のクラスの先生方は車いすの方やちんどん屋さんをお呼びになっていました。

言語聴覚士でもある私は、小学6年生100名余りに向けての2時間の授業で、二人一組になって、目が見えない、耳が聞こえないという疑似体験をしてもらい、東京大学 福島智教授の本『ぼくの命は言葉とともにある』(致知出版社)をご紹介しました。福島さんは3歳で右目を、9歳で左目を失明し、14歳で右耳を、18歳で左耳を失聴した後、高校の教師ら周囲の人たちの励ましと支援により、全盲ろう者として日本で初めて大学に進学なさった方です。児童たちは皆、キラキラと目を輝かせたり、神妙な面持ちになったりしながら真剣に話を聞いてくれ、自分の考えたことを丁寧に感想文で記してくれました。
気持ちが暗くなるニュースをしばしば聞く最近ですが、こんな子たちがいる日本の将来はまだまだ捨てたもんじゃないぞと、その姿に感銘を受けました。公文式で学び、念願の大学に入って教師になり、指導技術を学んで児童に囲まれているDさんも本当に輝いていました。
私たち指導者一人ひとりが出会う生徒の人数は限られていますが、公文式で学び巣立っていった教室の卒業生たちは、私たち指導者が知らないところで、志をもって確実に歩みを進め、世界を広げています。指導者という存在はただ支えるだけで、いずれはその姿が、あたかも生徒が自分で歩いてきたかのように消えてしまう、それでいいんです。私たちは影の力となって、私たちの知らないところで、生徒たちが社会のいろんな場面で活躍している。そういう志をもって生きていく子どもたちを育てるというのが、私たち公文式指導者の仕事だと思っています。
景山:公文式指導者は、教室の中でも卒業してからもずっと影の伴走者ですね。生徒は幸せです。
伊藤:この学習法では過去に間違いを恐れずに挑戦し、間違ったらやり直す、それを何度も経験したことが、その子の人生の大きな支えになっていきます。44年も同じ地域で教室をしていると、卒業生がお父さん、お母さんになって、自分の子どもを教室に連れてきてくれます。たまにおばあちゃんがお迎えに来てくれたりもします。世代をまたいだ交流は本当に嬉しいです。
景山:保護者の皆さま、公文式の先生方へのメッセージをお聞かせください。
伊藤:今、いわゆるタイパ(タイムパフォーマンス)が重視される世の中の風潮があり、促成栽培のように生活そのものにスピード感が求められています。忙しい人たちに向け、料理もできたものがすぐ食卓に出せる便利な時代ですが、子どもたちの成長は促成栽培というわけにはいきません。子どもたちの成長にあたってはゆったり時間をかけてほしいと思っています。
私の教室の生徒で、生後8か月のダウン症のお子さんと保護者が、定期健診で「親子の笑顔が増えている」という変化があり、公文式に関心をもってくださった小児科の先生は、ほめられ慣れていない親が多くなっているとおっしゃいました。高度成長期に共働きが増え、大人が忙しくなり、子ども時代にほめられることが少なくなった世代が大人になったからではないかと推察されます。ほめられずに育った世代の人が親になると、わが子をどうほめていいかわからないようなのです。
公文式では、子どもができることをまず探し、できることをさせて、できたことをほめるところから学習が始まります。そしてサポートしてくださった保護者の方を労います。そうすることで、子どもが意欲的に学習でき、できることが増えていきます。怒ってさせても、あまり続かないことが多いようです。子どものできることを探すことも、ほめることも、気持ちに余裕がないと難しいですが、「できた」という結果だけでなく、是非、がんばったことや、やろうとしたこともほめてほしいです。
また、最近は、子どもたちの語彙が減っていると言われています。保護者の方も忙しいので、読み聞かせをする時間なども減ってきているのだと思います。筋肉の発達についても、昔と比べて生活が便利になった分、例えば蛇口をひねることも少なくなり、ドアノブを回すことも少なくなり、昔より発達がゆっくりになってきているように思います。
公文式の教材は、非常に丁寧なスモールステップでできており、子どもたち一人ひとりの状態にあった教材を、その子に必要なだけ何度でも使えるという大きな特徴があります。例えば、国語教材はイメージしやすいイラストと言葉・文にたくさん触れながらひらがな文を読み書きできる力を養う教材が8Aから2A教材まで7教材もあります。これだけ豊かな教材は、公文式指導者にとって、子どもたちを指導する唯一無二の道具です。
私の場合は、特別養護老人ホームでモニターとして公文式指導をさせていただいていました。だんだんとできることが減ってきても、「でもまだ見えます」「見えないけれど耳があります」と最後にカーディー※2の音量を最大にして英語を聞かれて復唱なさり「私は英語がしゃべれるんばい」と誇らしげに笑い、亡くなる前まで満面の笑みで「I’m happy.」とおっしゃっていた方がいらっしゃいました。その生き様から私は多くのことを学ばせていただいたのと同時に、公文式の指導者とはこんなにも尊い仕事なんだと気づかされました。
※2 当時使用されていたCDプレイヤー
私の教室でも、おじいちゃんやおばあちゃんが英語を勉強したいとおっしゃり、一緒に学習をしたり、学習の達成感をわかちあったりしています。自分よりもやさしい内容でも誇りをもって自分の学習を楽しんでいるおじいちゃんやおばあちゃんの姿を見たりしながら育つ子たちは、もしかすると広い視野を自然ともつようになるのではないでしょうか。

「志あるところに道あり」
公文式教室を開設して44年間、いろんなことがありました。重い障害のある子たちが、学ぶことが楽しくて仕方がない幼児が、そして目が見えなくなったり耳が聞こえなくなったりした高齢の方が、みんなそれぞれに人間のもっている可能性の大きさを教えてくれました。公文式で鍛えられた子は人を理解できる人間として育っていくという確信がもてます。
いろんな人が一緒に学びあう場をつくりたい。公文式教室を開設するきっかけとなった思いは、44年かけて現実のものになりました。これまで本当にいろんな先輩の先生方から子どもの見方を学ばせていただきました。また、様々な指導について自主研究活動をしている多くの先生方からの貴重な学びをいただくことで、私の子どもの見方が変わったら子どもたちが伸びるようになりました。
脳科学者の先生方の講座に行き、大学の先生方との共同研究でいろんなことを勉強させていただくこともできました。子どもたちをもっと伸ばせるのではないかと一緒に研究する仲間に出会い、教室見学しあったりもしながら、44年間学び続けることができました。新しく指導者になられた方にお伝えしていく立場になっても、まだまだ子どもたちから、仲間の先生方から教えられ、学ぶことがたくさんあります。
生きることは学ぶこと、学ぶことは生きること。公文式に出合ったおかげで私の人生は楽しく豊かになりました。本当に心から感謝しています。
障害のあるお子さんの公文式教室での学習について
KUMONの学習に関するご相談、教室のご紹介はこちらへ。教室の設備、人員などの事情により、教室によっては学習していただくことが難しい場合があります。担当者へお取り次ぎいたします。
-
-
【フリーダイヤル】0120-372-100
- 受付時間
9:30~17:30 (土日、祝日を除く)
-
-
- ウェブサイトから
- お問い合わせフォーム
なお、フリーダイヤルがつながりにくい場合は、以下からもお問い合わせいただけます。
関連リンク 小児科医・白川嘉継先生(前編)|KUMON now! スペシャルインタビュー|公文教育研究会 療育の現場で活用される公文式|KUMON now! トピックス 大阪大学大学院医学系研究科 小児科学・教授、医学博士 北畠康司さん(前編)|KUMON now!スペシャルインタビュー 公文式の原点① <個人別・能力別>|KUMON now! トピックス 公文式の原点② <自学自習>|KUMON now! トピックス 公文式の原点③ <可能性の追求>|KUMON now! トピックス 公文式の原点④ <家庭教育>|KUMON now! トピックス 公文式の原点⑤ <学年を越えて進む>|KUMON now! トピックス 公文式の原点⑥ <ちょうどの学習>|KUMON now! トピックス 公文式の原点⑦ <学習習慣>|KUMON now! トピックス 公文式の原点⑧ <低い出発点>|KUMON now! トピックス 公文式の原点⑨ <100点主義>|KUMON now! トピックス 公文式の原点⑩ <標準完成時間>|KUMON now! トピックス 公文式の原点⑪ <高校でできるようにする>|KUMON now! トピックス 公文式の原点⑫ <悪いのは子どもではない>|KUMON now! トピックス
 |
前編のインタビューから -公文式なら、障害のあるなしに関わらず 同じ教室で学習することができる |