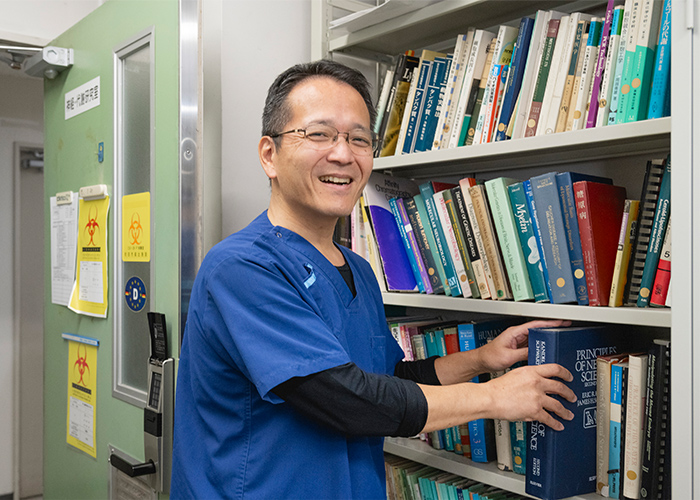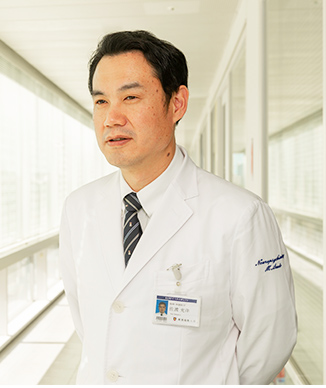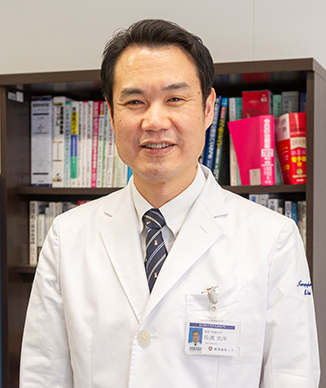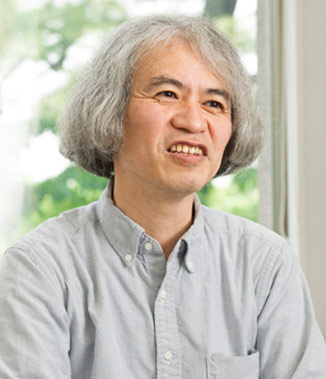目の前の子どもたちのための診療と将来花開くための基礎研究に従事
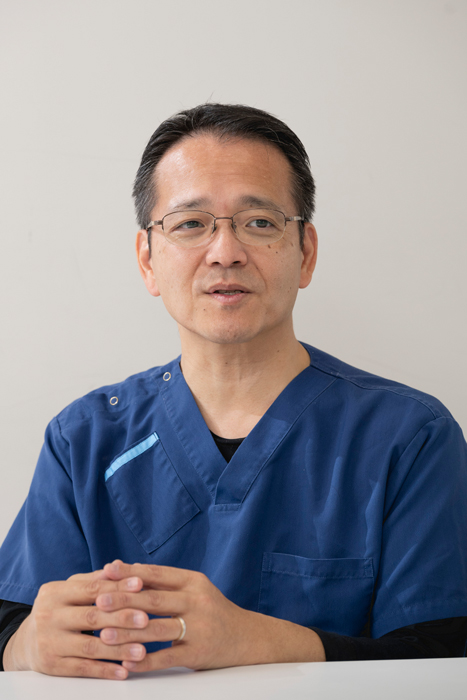
新生児集中治療室(NICU)は、早産児や低出生体重児、またはお母さんのおなかにいるときから、心疾患や脳疾患などの先天性の病気がある赤ちゃんたちを集中的に治療するところです。私はそこで新生児科医として赤ちゃんたちのケアをすると同時に、退院後もすくすくと育つことをフォローする外来診療を行っています。
もうひとつの仕事が基礎研究です。心疾患がありそうだと診断された場合、ダウン症を抱えている場合が多いこともあり、特にダウン症の研究をしています。近年はiPS細胞を使って進めています。iPS細胞は、山中伸弥教授らが2012年にノーベル生理学・医学賞を受賞したのでご存じの方も多いと思いますが、ごく簡単にいうと、“時間が巻き戻った細胞”といえます。どういうことかというと…。
私たちの体は細胞でできています。心臓も皮膚も血液も違う細胞ですが、元々はたったひとつの受精卵です。たったひとつの受精卵がそれぞれの細胞に変化することを「分化」といいます。分化は一方通行というのがこれまでの大原則でした。ところが分化した細胞に、山中教授が発見したある因子を加えると、細胞が初期段階に戻ります。そうしてできあがったものがiPS細胞です。
たとえば心臓や神経を調べたくても、心臓や神経の細胞を取り出すわけにはいきませんし、皮膚の細胞は取れますが痛いですよね。そこで血液から細胞をとってiPS細胞をつくり、もう一度心臓や神経などに分化させます。するとその細胞の状態や機能がどう変化するかを研究できるので、様々な病気の原因や治療法の確立が期待できます。ダウン症もそのひとつで、現在、治療法の研究を進めているところです。
医療技術の急速な進歩により、ダウン症のあるお子さんをもつ保護者にかける私の言葉も変わってきました。「ダウン症の研究」をテーマに保護者向けに講演をすると、終了後、保護者から「すごくよくわかりました。でもその研究は、私の子に役立つのでしょうか?」と必ず聞かれ、言葉に詰まってしまうことがありました。
しかし最近は、「いまはまだありませんが、どんな病気でも必ず治療法が出てくるでしょう。だから希望は捨てずに、治す薬が出てくるための、また開発された治療薬を広めるためのネットワークをつくってください」と言っています。時代はすごい勢いで変わりつつあるので、治療薬の開発も遠い未来ではないと期待されます。臨床医も研究者もとてもやりがいがある時代になってきていると思います。
転機は医師になって3年目のNICU勤務時代
「神経と細胞死」を学びたいと各大学を回る

私の父は仏画師で、母は書道の先生でした。姉二人も書道の師範を持っています。私も書道をしていましたが、じっと座っているのが苦痛でした。でも本だけはよく読んでいました。週末になると電車に乗って親が私たち3人を図書館へ連れ出してくれました。小4の頃には山岡荘八の「徳川家康」全26巻を読み終わっていました。孔子や孟子などの中国の歴史書も好きでしたね。
「小児科医になりたい」と思うようになったのは中学生ぐらいです。なぜか「医者」じゃなくて、「小児科医」でした。ぜんそくでお医者さんのお世話にはなっていましたが、それがきっかけでもなく、自分でも理由がよくわかりません。ただ、子どもは好きでした。当時は自分も子どもでしたが(笑)。
その後も夢はぶれることなく、医学部へ進学しました。目の前に山があるから登るのと同じように、目の前に受験勉強があるから勉強していました。ところが大学時代はラグビー三昧で、授業はまじめに出ず、筋トレばかりしていましたね。研究への関心も薄く、臨床医を目指していました。
いまの道に進む契機となったのは、大阪母子医療センターのNICUで働いていたとき。「いくらがんばっても治らないものがある」と実感したときです。それが脳にダメージを受けている知的障害です。
研究して治療法を見つけようと、当時勤務していた阪大病院内はもちろん、北海道大学や東京大学などいろいろな大学を回って、知的障害に関係すると思われる「神経と細胞死」をキーワードに研究したいとアピールしました。
ところがなかなか見つからず、ようやく巡り会うことができた素晴らしい先生が京都大学大学院の中西重忠先生です。中西先生は「業績」と「学生への愛情」の両方をお持ちのすばらしい方で、私も大いに刺激を受けました。

5年間学び、基礎研究の地盤を固めた上で、もう少し臨床に近いことをしたくて、今度は米国のジョンズ・ホプキンス大学の幹細胞の研究室へ留学しました。研究室のボスは若くてものすごくアグレッシブ。その影響を受けたのか、帰国後はよく「変わったね」と言われました。
帰国後、阪大病院のNICUに戻り、いまに至ります。NICUでは、そこで治療した子の発達をずっと見守ることになります。外来診療で長く関わることができるのがひとつのやりがいになっています。
いまは「子どもを助けたい」のはもちろんですが、それに加えて「その子の親を助けたい」と思うようになりました。昔からその気持ちがあったのかもしれませんが、それに気づいたのは自分が親になってからです。
子どもの学びの「リズム」になる公文式
保護者にとっても「育て方の学び」に
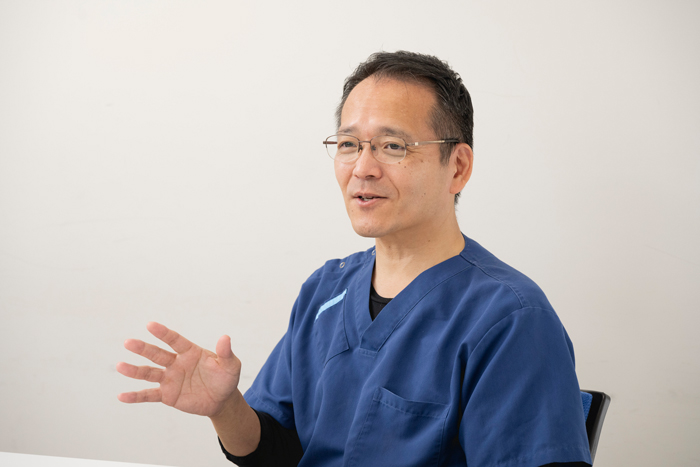
公文式学習は、実は私自身も小学生時代にやっていて、3人のわが子も3歳頃から学んでいます。公文式は無理なくステップアップできるのが、とてもいいシステムだと思います。ただ先生にお任せではなく、いかに家庭で子どもが同じ時間に学習できるようになるかが肝心で、私も子どもたちに手を変え品を変え、つきあっています。それが子どもにとってはもちろん、保護者にとっても育て方の学びになると実感しています。
もともと馴染みがあった公文式学習ですが、それをダウン症のあるお子さんの保護者に勧めるようになったのは、10年ぐらい前からです。ある保護者から紹介されたのがきっかけでした。
1年生はこれ、2年生はこれ、とレールが敷かれていると、ダウン症のあるお子さんの場合、そのレールから外れてしまうことが多く、そうすると「自分は外れている」と思わされてしまいます。でも、公文式学習は自分のペースで進むことができるので、それを感じることがありません。加えて「繰り返し」のステップがあるのがいいですね。ダウン症のあるお子さんのように、ちゃんとステップを上がる能力があるのに、筋力がやや弱い場合は、ゆっくりと、繰り返しやり続けることが大切です。そうすれば無理なく上がっていくことができます。
保護者には、こう伝えています。「どんな学習方法でもいいと思いますが、ペースメーカーになるものがあるといい。公文式学習はそのペースメーカーになってくれます。“このプリントに取り組めればいい”とやることさえわかれば、あとはいかにそれに集中させてやるか、ということになるので、保護者としてもやりやすいですよ」と。
要は、公文式は日々の学習のリズムをとってくれるということです。もちろん、主体はあくまでも本人と保護者です。そして、本人と保護者が意欲を持つことは欠かせません。しかし、時には親子だけでは進めるのが難しい場合もあると思います。そんなときは、公文の先生と相談してリズムを調整してもいいと思います。相談できる相手がいるというのは大きいですよね。うまくリズムをとれるようになったら、できるだけ生涯教育として続けてほしいと思います。
 |
後編のインタビューから -「同じ時間にこれをする」と保護者が関わることがコツ |