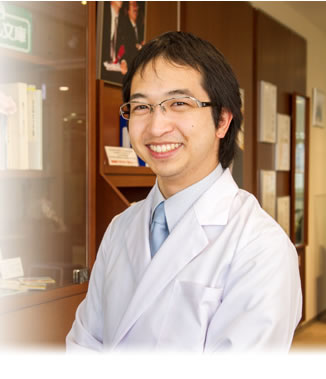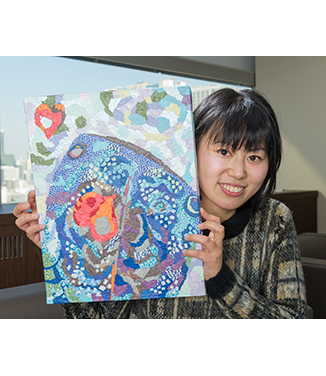社会的な問題を医療の視点で捉える
それも、科学的な視点と分析で捉える

大学に入学してしばらくして、ある研究室に入りました。その研究室は、医学部内にあるものの、医療過誤や訴訟や薬害などをはじめ、社会のなかで医療はどうあるべきかという方向で、社会的な問題を医療の視点で捉える研究をしていました。そこで僕は社会と医療の接点を深く考えるようになりました。研究室でお世話になった教授には、現在も大学院の研究科で指導していただいています。
そうして冒頭(前編)でお伝えしたように、医学部6年生のときに東日本大震災が起き、その研究室の先生方とともに震災2ヵ月後に飯館村に入りました。そのときも放射線量はけっこう高かったので心配でしたが、「なんとかなるだろう」と何の根拠もなく思っていました。線量計はずっと鳴りっぱなしでしたが、とにかく現地入りすることが最優先でした。
医学生として福島に何度も行って感じたのは、「復興が形として見えるまでには、かなりの時間がかかるだろう」ということ。だからこそ、「ここで医者をやりたい」との思いを強くしました。初期研修は千葉の総合病院に決まっていたので、それが終わって医師免許を取得し、すぐに福島の相馬市の病院に赴任することにしました。
多くの医師は、医師免許を取得後、つぎのステップとして「専門医」や「認定医」をめざしますが、僕はその道を選びませんでした。もちろん、今後もこのままかどうか、まだ具体的な未来像が見えていないのでわかりませんが、「専門医」をめざすよりは、より多くの人を診たいという思いで医療活動を続けたい、という考えです。
たしかに専門医となって最先端の医療を担うことも大事で、その最先端医療で10人を救うという道もあります。ですが、それとは別に、もっと安価で簡便な方法で10万人を救うという道もあると思います。どちらが大事かという話ではなく、僕としては10万人を救うほうに賭けたいのです。その糸口が、いま相馬で携わっている医療活動のなかにあるのではないかと考えています。
自分の専門性を高めることに時間を費やすよりも、僕にとってはもっと大切だと思うことがあります。それが、社会のさまざまな問題や課題に対して医療は何ができるか、を考えること。そして、その大きな問題や課題のひとつが「高齢化社会」です。それに、きちんと向き合いたいと思うのです。
これから日本はどんどん高齢化が進みます。若者2人で高齢者1人を介護しなくてはならない時代も、そう遠くない未来にあると思います。そのときが来たとき、現状のままでは立ち行かないことは明白です。やがてくる、必ずやってくる、その問題に向き合う人も知恵も必要です。いま相馬の病院で働いている、というよりもがいていると表現したほうが合っているのかもしれませんが、毎日が困難や迷いの連続です。けれども、そのことが、近い将来、日本が直面する問題の解決や改善に、きっと役立つとも思っています。
大学院の研究科に籍を置こうと思ったのも、未熟な自分にはもっと学ぶ機会が必要ですし、なにより相馬での医療活動を科学的にきちんと分析したいとの思いからです。被災によって高齢化が加速する現場で、高齢者を中心とした方たちを診て、いま何が起こっているのか、何に困っているか、どうすればもっと良い状態になるのか。そういったことに対して、医療従事者としてアドバイスしたり診療したりすることがいちばん大切です。
ですが、そうした医療活動を続けるうち、そこで得られた記録やデータや情報を科学的に分析すれば、さらに地域の人たちへのより良い医療につながっていくのでは、と考えるようになりました。そして、その分析や研究は、未来の日本にも必ず役立つはずですから。
「専門医」「認定医」の道をあえて選ばなかった2つの理由とは?
専門医の道を進むよりも
自分のペースで医療を究めていきたい

僕が専門医の道を選んでいないのには、もうひとつ理由があるかもしれません。それは、自分のペースで医療を学ぶ、ということです。専門医をめざすには、何を何年、何を何年で学ぶというのがある程度決まっています。そういう学び方もあるのでしょうが、自分は自分で納得がいくまで調べ、不足なところは専門医に聞いて、というように、自分のペースで学び、患者さんに向き合うほうが、僕にとっては性に合っていると思います。
そもそもなぜ僕が、医師をめざそうとするおおもとになる、「社会の役に立ちたい」と思うようになったのか、正直わかりません。なんとなく思い当たるのは、小学1年の終わりごろに起きた阪神淡路大震災でしょうか。そのころ大阪に住んでいましたが、すぐとなりの都市で起きたことですから、強烈な印象でした。そのあと被災地はすごい勢いで復興していきました。ああいうときに役に立ちたいな、と幼な心に思っていたのかもしれません。
司馬遼太郎の小説や考え方が好きでよく小説を読んでいたことも、少なからず影響しているのでしょうか。フィクションを織り交ぜてですが、世の中に影響を与えた人物の生き様が描かれているので、「こんなにすごい人がいるんだ」と、中学時代にとても感銘を受けながら読んだことを憶えています。
「社会とのつながり」を大切にして
高齢者の「孤立」を防ぎたい

いまの僕の仕事は「高齢者」「介護」がキーワードです。病院内での診療はともかく、自分だけでやるのには限界があります。そのためにはやはり、地元の人と仲良くなることがいちばん大切だと思います。病気を治すだけの医療ではなく、地元の人たちが病院や医療を介在させることによって、その生活がもっと良いものになることをめざしています。
とはいえ、現実は厳しいものがあります。いま病院で診療をしていてとても気がかりなのは、やはり高齢の患者さんのことです。退院できない人が増えているのです。医学的には退院ができる状態なのに、自宅でサポートしてくれる家族がいない。介護施設も満床が続き、もどるべき家も場もないのです。幸い現在の相馬市長は医師でもあるため理解があり、高齢者が自立して生活することをめざした「相馬井戸端長屋」という公営住宅を建てるなどして、少しでも「孤立」を防ぐ工夫を実践しています。
僕が相馬に赴任してもうすぐ1年、東日本大震災からは4年という年月が流れました。良い意味では、被災地のみなさんが少し落ち着きを取り戻す時期ですが、別の意味では、抑えていた気持ちが噴きでてきたり、がまんしていた持病が悪化していることに気づく時期でもあります。そのため、日常の健康診断を含め、医師としてさらにしっかり地域と向き合っていくことが求められます。
地域と向き合うとき、いつも心がけているのは、人と人とのつながり。社会での「人とのつながり」が健康に与える影響はとても大きいと思います。つながりを失った高齢者は、地域のなかで孤立しやすい。そうなると、孤独死やアルコール依存、病気の悪化など、さまざまな影響がでてきます。孤立してしまう高齢者を一人でも少なくするようにしなくてはなりません。そのためには、どうやって地域全体で高齢者を支えていくのか、現状と課題、そして未来を交えて考え、行動に移していく必要があります。
僕はまだまだ駆けだしの医者です。自身の将来については、まだ語ることはできませんが、ただひとつ言えることは、被災地に限らず、多くの地域で経験を積み、もっと多くのことを学ばなければいけないということです。けれど、まずいまは、この相馬で、高齢者を地域全体で支える医療と向き合い、そのための実践を重ねていきたい。これからも病院の内であろうと外であろうと、専門があろうとなかろうと、信念をもって自分の思いを貫き、医師として多くの人の役に立ちたいと考えています。
関連リンク
医療法人社団茶畑会 相馬中央病院
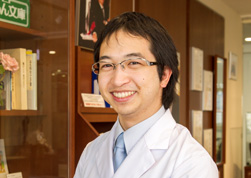 |
前編のインタビューから – 「東日本大震災の被災地で急速に進む高齢化は、日本の近未来の姿です」 |