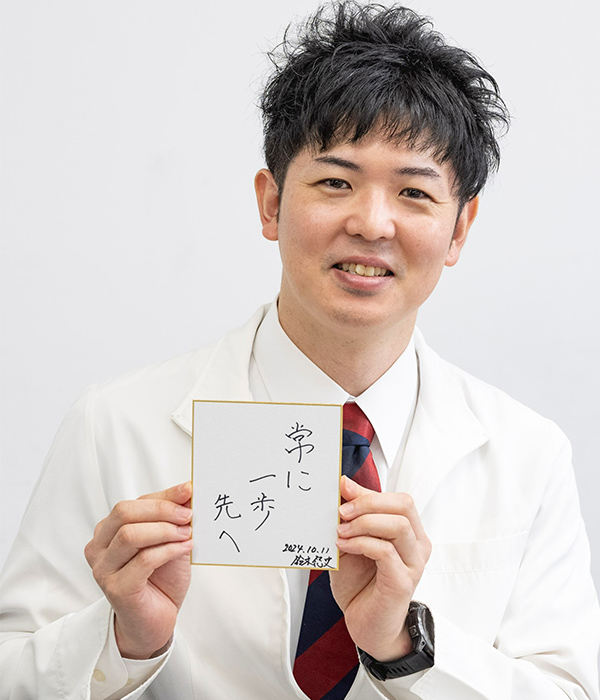「今やりたいこと」が将来も続くとは限らない
私が10代のとき、国際関係論などの国際系の学部の数が増え始めていた時代であり、日本でもNPOやNGOというフレーズを一般の人も使うようになった時代でした。高校に入るまではゲームクリエイターになりたいと思っていましたが、そういう時代の影響を受けて国際的な仕事への憧れも抱いていました。

高校に入ってから、周りの大人たちから東大や京大を勧められました。東大を勧める人も、京大を勧める人も、同じ理由なのが面白いところでした。東大は2年間専門を決めない教養学部で学びます。京大を勧める人は、東大と同じく3年生から専門を選ぶ総合人間学部を勧めるんです。そういう助言を聞いていて、「私は入学して様々な分野に触れ、その上で何かを選ぶタイプなんだな」と。知的に欲張りなところはあるので、その観察に自分でも納得しました。綿密な人生設計はしていないんです(笑)。
「今決めなくてもいいかな」という感覚になったのは、大学に入る前に抱いていた「学問ってこうだろう」というイメージが、はたして大学の学問と一致しているのか疑問に思ったからです。例えば、心理学部だって、別に人間関係を上手く乗りこなせるようになる学部ではない。文学部は、孤独に本を読むだけの学部ではなくて、フィールドワークをしたり、実験機器を使ったり、統計を使ったりする人もいる。これは仕事選びも一緒で、銀行の仕事としてイメージすることと、実際の銀行業務がどれだけ重なっているかというと、疑わしいですよね。
想定しているものと実態は違う、ということはよくあるじゃないですか。「きっとこれはこんな感じだから、私に合っているに違いない」と選んだとしても、そんな予想が当たっている保証はない。にんじんを食べていないのに、想像や伝聞で好きとか嫌いとか言っているようなものです。進路選択はもっと気楽に考えていい。
「将来の自分がどうなるか」ということも、あまり考えすぎないようにしています。というのも、将来の自分が、今とは違ったことを言い、今とは違ったことを感じている可能性があるからです。そういうときに頼りになるのは、自分の不快さの感覚、避けたいと思う感覚です。何を不安で不快に思うかは、相対的に変化が小さい。だから、「何ができるか」よりも、「何がやりたくないか」をはっきりさせるのは役に立つと思います。

例えば、私は英語圏の哲学を研究しているので「もっと早くに英語を学んでいれば楽だっただろう」と後悔したこともありますが、これは考えてもしょうがない。小中学生の時期に、「私は英語圏の哲学の専門家になるだろうから、今から英語をがんばろう」なんて思えるはずないですからね。私は今の勉強を将来に役立てようとしてきたわけではなく、その都度の「今やりたいこと」を最大限にやってきただけです。
身体も好みの感覚も、何を大切に思うかも、時がたてば変わるものです。今やりたいと思っていること、今やるべきだと思っていることが将来もずっとそうかはわからない。そう思っておいたほうがいい。その時に応じて「自分なりの生き方」をつくり、その都度改訂していくしかないと思います。
なのに、保護者も子どもも、なぜそんなに振りかぶって将来を設計してしまうんだろう、と思います。自分の好みや将来のあり方についても、「答え」があると思って取り組まずに、「無知」なスタンスをとった方がいいのではないでしょうか。何も考えないのはよくないけれど、考えすぎてこわばる必要はないんですよね。
「公文の算数をやめたい」と親に伝えたとき、詳しく聞かずに「いいよ」とすんなり受け入れてくれました。それがよかったんだと今になって思います。あのまま続けていたら算数が嫌いになっていたでしょうね。少しぐらい失敗してもいいじゃないですか。自分や子どもに無理強いしないことが大事だと思います。いやだって言うなら、一時的にやめとけばいい。無理強いされなかったら、また自分からやりたいと言うかもしれない。
「学問が身近にある社会」になることに貢献したい

大学の学部では、アメリカの哲学者ジョン・デューイを研究していました。当時、「何者かになりたい」という思いで研究していたのですが、4年間必死にやっても、たかが知れています。だから「大学院に進んで研究者になる」というのは、ひとつの道だろうとなんとなく思ったんですね。大学院で5年かけて取り組めば、何者かになるだろうなと。
学部生のときには、思い描いていた語彙の運用能力、言語化スキルにたどり着いた気がしませんでした。文章を読んで得られる知見も、先輩たちに比べたら自分にはまだまだ足りない。文章は情報の宝庫ですが、それを読み取れるかは読み手の能力次第なんです。だから大学院に進んでもっと勉強すれば満足できる、何者かになれるのではないかと思いました。
でも「何者かになる」というのは、努力に後からついてくるものですよね。だから、あまりそれを考えてもしょうがないんです。運のいいことに、大学院で研究がどんどん面白くなって、のめり込むようになりました。だから、「何者かになりたい」という思いはそのうち忘れて、研究それ自体を楽しむようになったことは大事だったと思います。だから今があるわけですね。
今の私が思い描いているのは、「学問が身近にある社会をつくる」ということです。大学の4年間、大学院、企業研修、書籍、市民講座など、いろいろな機会を通して、「学ぶって楽しいかも」「そういう専門家もいるんだ」「この研究いいな」と思うようになる人を増やしたい。学問が身近にある社会は、みんなが研究者を目指す社会ではなくて、自分の知らないこと、自分のピンとこないものを尊重できる社会です。
2017年に人体に有害なヒアリというアリが話題になったことがありました。そのとき地道にヒアリの研究をしていたある専門家が、たった一人で、いろんなメディアのインタビューに答えていました。2020年にルイーズ・グリュックさんがノーベル文学賞を受賞したとき、日本で一人だけ翻訳や研究をしていた人がいたことで話題になりました。一見すると、何の役に立つかわかりにくい研究、自分に興味がわかない研究をしている人がいるって貴重なことなんですよね。
「鶏鳴狗盗(けいめいくとう)」という中国の故事が好きです。鶏の鳴き声のうまい食客がいて、そんなことができても役に立たないと思われていた。敵から逃げているとき、朝にならないと開かない関所で立ち往生して困っているとき、彼が鶏の鳴きまねをしたら門が開いた。そういう内容です。研究も、基本的には「鶏鳴狗盗」なんです。いかにも役立ちそうなテーマや手法ばかりに研究者が関心を払うようになると、分野はやせ細っていく。ふだん役に立たないと思われているけれども、役立つことがあるかもしれない。役に立たないこともあるかもしれないけれど、ひとまずはそれでいい。そういう大らかな構えを持つことが大事だろうと思っています。
昨今の「大学」は多くの人にとって通過点でしかなくなっているように感じます。就職のための資格取得みたいになっているとすれば、残念なことですね。そうじゃない社会と学問の関係をつくりたいと思って、そのために文章を書いたり、こういう場で話したりしているんだと思います。
「やりたいこと」はなくても大丈夫
「やりたくないこと」を考えてみよう
今、子どもたちのスマートフォンやSNSの使用について、保護者はいろいろ悩まれているようですが、禁止するとむしろ気になってしまうものなので、「スマホの使用禁止」はやめた方がいいでしょう。かえって中毒に追いやっているようなものですから。大事なのは別の楽しさを持ってもらうこと。漫画や本でも何でもいいですが、何かひとつのことについて腰を据えて掘り下げさせるような環境を整えるのがいいんじゃないかと思います。
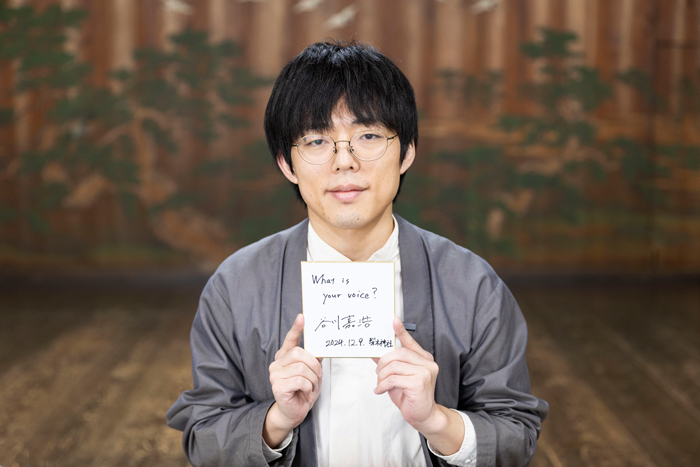
「What is your voice?」
子どもに「うまくネットとつきあってほしい」と望むのはいいですが、そう語る大人がスマホばかり見ていたら仕方がないですよね。子どもは大人の背中を見るので。それよりも、大人が何かを楽しんでいる姿を子どもにちゃんと見せることです。それで子どもが何かに興味を持ったら、それを掘り下げるサポートをする。その手段がネットだけにならないようにした方がいいですね。
それと、子どもたちには、「大人の言うことは話半分でいい」と伝えたいです。「こうしないと危ないよ」と不安を煽る大人の話は、たとえそれが親でも聞き入れない方がいいと思います。不安を煽って言うことをきかせる状態は健全ではないですから。それよりも、将来の仕事につなげなくてもいいから、何か夢中になれることに全力を費やしてほしい。「夢中になっているこの時間は大事だな」と思って過ごしてほしいですね。
最後に、やりたいことが見つからない場合の参考に、3つのアドバイスをお伝えしたいと思います。
1つめは、「やりたくないこと」をはっきりさせること。どんな仕事が自分には向かないかとか、講演や講義をするような仕事はつらいとか。「これだけは嫌だ」ということは、子どものこれまでの人生の中だけでもわかることは多いんじゃないかと思います。
2つめは、「本当にやりたいこと」が見つからなくてもいい、ということです。たまたま行ったところで、何かフィットすることを見つければいい。それが夢みたいなものでなくてもいい。たまたま選んだ中からでも、それなりに楽しめるはずです。私も行った先でその都度考えていて、その結果、気がついたら哲学者になっていました。ここを目指してきたわけではなくて、いろいろな偶然に流されてここにいます。でも、それでいいんですよね。
3つめは、自然の中に身を置くこと。タブレットやスマホの中もそうですが、都市部には基本的に人工物や人工的なものばかりです。これって、「何かのためのもの」なんですよね。でも、自然は何かのために存在するものではない。そういう無目的なものに慣れると、「何かのために~しよう」と考えなくて済む。意味もなく海を見たりすると、ちょっと気が楽になるのはそういうことです。これは、大人たちにもお勧めしたいです。
 |
前編のインタビューから -「勉強」とは「他人の頭を使って考える」こと |