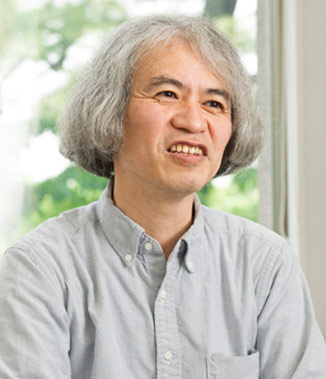「自作執筆」と「他者作品の英訳」の二刀流
“未知のこと”へのチャレンジが楽しい

小説家では類例がなく出版関係者にも驚かれますが、私は「自分の本を書く」ことと、仲間の作家さんから頼まれて「他の作家さんの作品を英語に翻訳」もしています。翻訳の仕事については、当初は自分の小説のみを英訳しようと考えていました。それを仲間に伝えたら「私のも英訳して」と頼まれて、今は仲間の書籍の英訳をしていることが多いです。
自分の執筆活動もしながら他の作家の作品を定期的に英訳して世に出す、という仕事をしているのは、日本では私以外にいないのではないでしょうか。大谷翔平選手は二刀流で知られていますが、私も出版界でかなり珍しい二刀流だと自負しています。
私は主夫でもあります。妻は勤め人なので朝起きて夜帰宅する生活ですが、私は完全に夜型。夕方4時から5時頃に起きて寝るのは午前8時から9時頃です。夕方に起きて、買い物、掃除、洗濯、料理などの家事をすませ、メールチェックをするのですが、メールを書いている時間が長いんです。相手は仕事先がほとんどで、いただくメールは数行程度なのですが、私はまるで大河ドラマのような起承転結を考えてつい長文メールを書いてしまいます。結果として仕事にとりかかるのはだいたい深夜0時を回ります。
以前はその仕事時間を毎日全力疾走していましたが、それでは体調を崩してしまうので、無茶しすぎないよう毎日コツコツ同じペースで進めるようにしています。その方がクオリティも高くなることに気づきました。
こだわっているのは、「自分がワクワクする仕事しかしない」こと。やりたくない作業を嫌々やっても、いいものはできません。小説だけでなくモノづくりもそうだと思いますが、自分がつくりたかったものが形になると達成感がありますよね。
完成したものが読者によろこばれたらもちろん嬉しいですが、自分でも納得できる作品に仕上がると、本当に幸せを感じます。実はそれ以上に、納得感を目指している“最中”が一番幸せです。完成してしまうと寂しくなって、だから次の作品にチャレンジする、というサイクルをくり返しています。誰もやったことがないテーマにチャレンジするのが好きですね。そのひとつが、後ほど(後編)お話しする、くもん出版から出す『名探偵の英単語』です。
公文式をやっていなければ
ただの病弱な、さえない子どもだった

男3人兄弟の末っ子として生まれた私は、兄弟の中で自分が一番両親の勤勉さを受け継いでいる自覚があります。母はファッションデザイナーでありながら、編み物や油絵、木彫り、ステンドグラスなどを毎日ひたすら創作しているアーティストでもありました。何かの賞に応募すると必ず受賞するような人で、80歳を超えた今でもとてもパワフルです。公認会計士だった亡き父も、とにかく勉強好き。二人とも休むことなくそれぞれの仕事に熱中していました。どこかに連れて行ってもらった思い出はほとんどありません。
わが家はスポーツ万能の家系で、父も兄二人も県大会に出るレベル。ところが私だけ喘息持ちだったこともあり幼い頃は運動ができず、病弱で背も低い。年子の兄たちと私は年も離れており、おまけに近所の遊び友だちも親戚も全員が年上。どこに行ってもダントツ年下で体も弱いから、よくつらい思いをしていました。
でも、それによってメンタルは相当鍛えられました。作家になってから年上の人に対して萎縮したことはないし、ひるむこともありません。幼少期のつらい経験でメンタルが強くなったからで、今では感謝しているほどです…と、今でこそそう言えますが、当時はやはりつらかったですね。
そんな苦悩の時代を救ってくれたのが公文式です。5歳から9歳まで算数と国語を続けていました。教室に通うのではなく通信でした。病弱だったので家でできるスタイルが自分には良かった。採点をしてくださった先生が、どんどんプリントを進ませてくれ、夢中になってプリントを解いていました。もし私のやりたい気持ちにストッパーをかけられていたら、面白くなくなって途中で投げ出していたと思います。
「本を自分で読めるようになりたい」と言って公文の国語で漢字もどんどん覚えていきました。小学校低学年の時に大人向けの本をふつうに読んでいたら、親戚のおじさんから「きみの年齢でこんな難しい本を読めるわけがないだろ、嘘つくのはやめなさい」と偏見で決めつけられたこともありました。本当に余裕で読めていたのですが、その頃から、世間の小さな常識と戦う人生が始まっていたのでしょう。当時、英語という選択肢はなかったのですが、もし公文式で英語を学べていたら、子どもの頃からきっと英語が得意になっていたと思います。
とくに算数のプリントを解くのが気持ちよくて大好きでした。年上の子たちの中でつらい思いをしていた私にとって、公文式だけが私と対等に付き合ってくれた「友だち」のような存在でした。キャプテン翼はボールが友だちでしたが、私にとっては公文が友だちで、付き合っているうちに計算が得意になっていきました。小学校低学年までは自分には秀でたものは何もなく冴えない子どもでしたが、やたら計算が速い子ということで一躍人気者になりました、それが人生最初の成功体験。小学校って足が速い子とか人気ですよね。計算が速い子もそれと同じでした。
しかも小学校低学年までは給食が苦手で、昼休みになっても食べ終わらないので教室に独りで取り残されていましたが、小4になると急に喘息も治り、体力がついてきて、兄たちのように運動でも頭角を表すようになりました。給食も食べられるようになって、私の黄金期が始まります。すべて絶好調だったのは中2ぐらいまでの期間限定でしたが、幼少期とはガラッと変わりました。
今私は好きな小説を書くことを生業にしていますが、ふり返ると「好きなことをとことんやって結果を出す」ことのルーツは公文式だったのだと思います。大人になると、どうしても無意識にストッパーをかけてしまいがちです。しかし、物理的な意味だけでなく、質的にも「ここまででいいだろう」と制限を設けないことが、仕事でも勉強でも大きな結果を出せる成功法則なのだと確信しています。
中学・高校時代は勉強が嫌になり
当時の夢はゲームクリエイター

私は元々本好きで、子どもの頃から作家志望でした。一番古い記憶は5歳の頃。知り合いのおばさんがやっている喫茶店で「ぼく、将来作家になりたい」と口に出したことがあります。するとおばさんは「作家になると自殺するからやめなさい!」と真剣な顔で言うんです。その表情が怖かったことを今でもはっきり覚えています。
小4の頃、イギリスの作家エドマンド・ウォレス・ヒルディックの『マガーク少年探偵団』シリーズにはまって、自分でも少年探偵団をつくりました。自室に「探偵事務所」と紙を貼って事務所を設けたのですが、事件が起きない。それで道ばたで拾った小さい何かを「これは事件のにおいがする」などと言って事件らしきものを創作したり、ホームズのまねごとをして、道ですれ違った人の職業を推理したりと探偵活動をしていました。親が電話しているのを、聞き耳を立てて内容を推察し、電話相手を当てることも好きでした。結構当たるので親は喜んでいましたね。
当時の私の愛読書のひとつに、ポプラ社の『少年探偵・江戸川乱歩』があります。これは関西圏だけでテレビドラマ化されていました。その撮影が偶然にも私の町内で行われていたんです。「小林少年が近所にいる!」とリアルに感じていました。
中学受験をした進学先の中高一貫校には優秀な子が集まっていました。最初はやる気に満ちていたのですが、中1の時に風邪で数日休んだら、たまたまガラッと単元が変わるところでつまずき嫌になり…勉強暗黒期の始まりです。当時は野球部でしたが骨折してやる気もうせて、ゲームに現実逃避するようになりました。
ゲームにはまるだけでなくゲームそのものをつくることに熱中し、相棒の友人とふたりで徹夜でプログラミングすることもありました。相棒とは本気で一緒にゲームクリエイターになることを目指し、高校を卒業したら大学には行かずにふたりで会社を作る予定だったのですが、高2のとき、彼が父親と同じく医師になる道を選択したんです。「おまえも現実を見ろよ」と諭(さと)され、自分一人でできることを見つけなきゃと真剣に考えた末に、「作家」という選択肢が浮かびました。きっかけをつくってくれた相棒には感謝しています。それまでも毎日、小説や漫画を書いては友人らに見せて、「面白い」「作家になれよ」と好評だったんです。清涼院流水というペンネームもこの頃から使うようになりました。
京都大学に進んだのは、「京都大学推理小説研究会(通称:京大ミステリ研)」に入りたいがためでした。大好きな綾辻行人さんもそこの出身ですし、入ればミステリー作家に会えると思ったんです。とはいえ、中学・高校と全然勉強しなかった劣等生の自分がどうしたら京都大学に入れるのか。当時の京大には8時間論文受験という特殊な入試制度があることを知り、自分は書くのが得意だからもしかしたら受かるのでは、と考えました。
ほとんどの先生方が「きみが合格する確率は0%」と断言していた中、論文を指導してくれた今西昭先生だけが、「五分五分」と言ってくれました。後に今西先生は母校甲陽学院中学校・高等学校の校長先生となり、2017年の創立100周年記念イベントでは、2万人のOBから選んだ登壇者4人にダントツ最年少の私を入れてくれました。1,500人の前で話をしたところ、皆がおおいに沸いて、そんな感動体験は後にも先にもこのときしかありません。
 |
後編のインタビューから -英語にはまったのは30歳を過ぎてから |