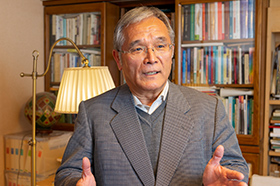「いのちの電話」と「公文式」に共通する「人のぬくもり」
 |
「いのちの電話」の相談員として電話に出るのは、私も含め一般の人たちです。学歴や職歴は関係なく、電話1本で、「この人は私を大切にしてくれているか?」と、相談者が感じ取れるかどうかが勝負です。
それには3つのことが大切です。身近な「思いやり」、相談員の人生経験からくる「知恵」を伝えられること、そして「素人」ではなく「素の人」、すなわち人として当たり前のことをしていくこと、です。この3つについて、「いのちの電話」の広報誌に書いたことがあります。そのちょうど同じ時期に、「くもん相談ダイヤル」のスーパーバイザーにならないか、との話をいただきました。
公文の名は知っていましたが、公文公先生や指導者がされていることを知れば知るほど、私のアプローチとまったく重なることに驚きました。とくに共通するのは「人のぬくもり」です。子どもにとっては、丸付けのやり取り自体が「自分を大切してくれるのだ」との思いにつながります。ですから、それを無意識にやってしまうのではもったいない。公文の指導者だけでなく、スタッフの先生方も、意味を分かった上で丸付けをしていただければと思います。
公文式の特徴のひとつ「ちょうどの学習」も、臨床現場や教育現場と共通しています。「ちょうど」は、「ジャスト」ではなく、「フィット」「マッチ」「チューニング」という言葉が適切で、これらは「関わり」の中で大切なキーワードです。
中でもチューニングは、相手の発しているものにこちらが合わせていき、合ったときに澄み切った音が聞こえる、という意味を持ちます。これは相手をちゃんと見ていないと実現しません。丸をもらってから次に進む公文式は、「濁っている状態」を「澄んだ状態」にしていく作業です。「一つひとつていねいに、コツコツとやっていく」と言い換えられます。人との関わりでも同じことが言え、心理面接や学校現場でも、本当に大切にしたいことです。
「学び」は「喜び」
自分が学んだ「学ぶ喜び」を伝えていきたい
 |
「学び」とは何かと問われると、きれいすぎるかもしれませんが、「知ること=愛すること」とお伝えしたいと思います。これは哲学を学んでいたころに出会った、イタリアの神父さんの言葉です。「学ぶ」とは「知っていく」こと。そして、知れば知るほど、その対象に愛着が出てきます。
すなわち、学ぶことは喜びであり、学びがあると、より豊かに過ごせます。「生きる力」にも直結します。しかし、「どうせお前は」と言われて自信をなくした子たちは、「学ぶことの喜び」を知らずに自分で見切ってしまいがちです。すると、「さらに学んでいく」ことに向かわないので、社会に出たときに職業が限定されてしまいます。学びは生きていく上で大切な栄養なのです。
しかし、それでも「人との出会い」があれば変わることができます。「人との出会い」を可能性に結び付けられるように育てるのも、教師をはじめ大人の大事な役割です。
史跡やお寺がそこここにある奈良県で育った私は、遊ぶうちにいつの間にか歴史の勉強ができるようになりました。「本を読んでから現場に行く」のではなく、「体験」した後に教科書を読んで「ああ、あれか」と納得するのが私の学び方のようです。
意識していませんでしたが、心理臨床活動でもそこは一貫していて、一般的なことはわかっていても、「その人と会ってみないとわからない」と考えています。自分で納得しないことは、相手にも伝わりません。納得とは、「こういう理由でこうした」としっかり言えること。「言っていること」と「やっていること」が一致しない、つまり「言行一致」でないと人には響きません。
「言行一致」は、子どもの頃から母親に言われてきたことでした。それで私は、本や授業などからの学びと、現場や実践での学びを繰り返し、自分が納得するまで学んでいるのかもしれません。私が学びを重ねてきたのは、やはり「学びたい」「学んで自分で納得したい」という思いがあったからです。「このままでいいのか」という感覚を持ち続けているのも学びの原動力となっています。
じつは私は、学びで得たことに対し、お金をいただくことに抵抗がありました。現在も私のスーパーバイザーであるヴァン・ジョインズ博士の考えを聞いたところ、答えは「学んでいくものを返していけばよい」でした。そうか、「学ぶ喜び」を知ったからこその私の体験、そしてこれから学んでいくことを、求める方に伝えていこう。それが、私が今後やっていきたいことです。
表情が変わったときに気づいて
声をかけてあげよう
近年気になるのは、子どもたちの「感情を味わう」「感情を表現する」体験が少なくなっていることです。SNSですぐ反応し合うため、感情が自分の体と心に落ちていく時間がなさ過ぎるのではないでしょうか。例えば「カチンときた」場合、「カチンときた」以外の、違う心の動きもあるはずですが、それを味わうことが難しくなってきているように思います。人は、感じて、考えて、行動していくものです。知的にはレベルが上がっているのかもしれませんが、身近な関わりに対する情緒的な感覚が伴っていないと、成長していく上では心配です。
 |
子どもを育てることは、小中学生までは、植物を育てることに似ていると思います。種を植えたら終わりではなく、苗も見てあげる。若木になっても、ちょっとしたことで倒れてしまうこともあるので、見守ってあげる。そして、子どもの表情が変わったときが、心にも変化があるときなので、そこで気づいて声をかけてあげる。それをするかしないかで、その後が大きく違ってきます。
この頃は、受け身の「学び」で、「今まで知らなかったことが見えてくる体験」をする時期です。その体験が本人の力になります。高校生以上になれば、新しい体験を恐れずに、自ら歩みを進めることが「学び」となります。そしてこの年頃になれば、親ライオンが子を谷に落とすような覚悟が必要です。子離れには勇気がいりますが、それが子の成長につながります。
子どもたちに伝えたいことは――ある程度の「木」がしっかり育っている子の場合は、大志を抱いて本人の好きに進んで欲しいと思います。そうでない子には、「自分が思っている以上の力を、自分は持っている」ことを知って欲しいですね。そして、どんなことでもよいから、自分が一生懸命になれるものを見つけてください。そうすれば、そこから学びが広がっていき、自信もつきます。もともと備わっているものが、開かれていくということです。
スクールカウンセラーをしていて、つくづく感じるのは、子どもは「ぬくもり」を求めているということ。今の時代、大人は忙しすぎますが、保護者のちょっとした声かけ、目を合わせること、にっこり笑いかけることだけでも、子どもにとっては喜びとなります。ぜひ、実践してみてください。
 |
後編のインタビューから -現在の活動は「“人を支える”人」のサポート |