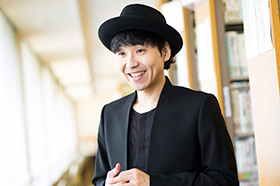日常生活に役立つ魔法のことば
 |
オノマトペはドイツ語では、「音の絵」と言われるように、絵のようにリアルにイメージが浮かび上がる特性を活かして、さまざまなシーンで活用できます。スポーツでは「グッ」と発した時に力が入るけれど、「ニャー」では力が入らない。イメージに合わない音だと効果が見込めないことが実験でわかっています。
実験とはたとえばオノマトペを発声して、動きの速度や筋電の量など行動を測定し、この音韻はこの動きに効く、声の高さはこの時に一番力が出る、ということを量的な見地から解析するんです。
子育てにおける効果もたくさんあります。車は「ブーブー」、馬は「パカパカ」というように、オノマトペはリズムがあって楽しくて、子どもは発したがります。自主的に発声すると、言葉をたくさん覚えるだけでなく、横隔膜や声帯が鍛えられます。
また「モグモグ」と言いながら食べるとよく噛む習慣がついたり、玄関の鍵をしめるとき「カチャ」と声と動きを連動させると、戸締まりしたことを忘れないようにしたりもできます。日本語はあまり抑揚がないのですが、オノマトペにはあるので、声の抑揚から相手の気持ちを察知する力や、会話力、プレゼン力もつきます。
とくにぼくが学生に対して実践し、学習に効く魔法のことばをいくつかご紹介しましょう。まず、教室が騒がしい時は、口の前に人差し指をたて小さな声で「シーー」と言い、最後の「ン」で口を閉じます。「うるさい!」「静かに!」と違って、怒りがのらないので、学生も素直に静かになります。
次に緊張感のある「ピーン」。集中力がない子は姿勢が悪いことが多く、「ピーンとしよう」とか、授業中に寝ている子には「目をぱっちりしよう。ピーンだよ」と言います。
教育でぼくが大事だと思っているのは、相手が子どもであっても一人の人格者として認めること。上から目線でタテの関係で叱ってしまうと反発をうむんですね。行動にダイレクトに働きかけるオノマトペを使って、ぜひ水平目線で接してみてください。
「グングン」「スイスイ」進めるのが自分に向いた学び
 |
オノマトペが日本語に多くあるのは、一説によると外国語に比べて貧弱な音節を補うためだと推察されています。ちなみに日本語の112音節に対して、英語は数千種にものぼると言われています。ほかにもたとえば「みる」は、英語ではsee、look、watchなど複数ありますが、日本語は全部「みる」。そのため、伝えたいことを言い当てるために「フワッとみる」、「パッとみる」、「ジーッとみる」という表現が生まれたのかもしれません。
一方で、ことばの乱れが気になるという声もあるかもしれませんね。ぼくは、辞書にも載っていないことばを使うのは、若者が時代の中でひらめいた「感性」だと思うので、ある程度は尊重したいですね。オノマトペに関しても、例えば「てへぺろ」「クチャラー」などが創作されていますが、これは一種の流行です。やがて使わなくなり、「そんなことばを使っていたこともあったね」と、思い出として引き出してくれればと思います。ただ、あまり品があるとはいえない言葉も多いですね。ことばというのは人の一部分だと思うので、学生には「汚いことばを使ってしまうと性格も損じられてしまうよ」と伝えています。
「学び」をオノマトペで表現すると、「グングン」「スイスイ」。「これやりたい」と思ったら、その瞬間に全身全霊でやるべきです。興味をもったことはグングン進め、加速できなければ学びとしては弱く、本人には向いていないものなのかもしれません。学ぶにはとにかく実践、体験すること。とくに五感を使って体験してほしいですね。それにより「気づいた」ことが学びだと思います。
子どもは原石であり、それをどう磨くかが大切です。ぼくは運良くオノマトペを磨き続けることができました。実験に失敗しても根気よく続けてきたように、ひとつのことに対してどれだけ時間を投資したか、量が質に転化するのだと思います。これからは総合力よりも、何かに突出した力が求められる時代になるでしょう。その中で「これでグングンいきたい」という学びを、強化していくことが必要だと思います。
オノマトペを使って子どもを思いっきりほめよう
 |
ぼく自身、ほめられて伸びたタイプなので、親御さんにはほめる力をもっと養ってもらいたいと思います。「やめなさい」「何度言ったらわかるの」と言いたくなる時は、「プーッ」と言ってほっぺたを膨らましたり、「ブッブーッ」と言って両手の人差し指で小さくバッテンにしてみてください。炸裂音は明るい印象を与えるので、親御さん自身の怒りも抑えられ、コミュニケーションが円滑になりますよ。
ほめる時は「すごいね!」ではなく、「ほーっすごいね!」と、「ほーっ」をつけると、その深い息の勢いで思いっきりほめられます。「やった!」も「わーっ、やった!」と、一語添えるだけで伝わり方が全然違います。身振りなどの動きもつけるとなおいいですね。
アメリカの心理学者アルバート・メラビアンの研究にもありますが、コミュニケーションはことばだけでなく、顔の表情、声の抑揚、身振り手振りを総合したものなので、その技術を使って思いっきりほめれば、子どもはほめられたことを強く認識します。「またがんばろう」となり、自己肯定感が高まって何でもチャレンジするようになります。チャレンジして失敗すると気づきが得られ、それが多いほど人として成長していきます。そうして夢にチャレンジしてもらいたいですね。
ぼく自身の夢は、さまざまなジャンルのオノマトペをプロジェクションマッピングの技術と融合させ、世界中でオノマトペの魅力を伝えること。プロジェクションマッピングを搭載したトラックで全国の保育園や幼稚園を駆け回り、オノマトペの声と連動して壁やモノに投影した立体物が動く――具体的に言えば、ぼくが「ブンブン」と言うと建物からハチが飛んで来る、「ガォー」と言うとライオンが飛び出してくる、というイメージです。
今子どもたちに、オノマトペ絵本を使って読み聞かせなどの活動をしていますが、立体物の投影と融合させてより臨場感を出せば、もっともっと子どもたちの目がキラキラするんじゃないかなあ。想像しただけでワクワクします。それで「オノマトペって楽しいな」「楽しいことをしている人ってこんなにイキイキしているんだ」なんて思ってくれて、夢をもちキラキラな人生を送るきっかけになればうれしいですね。
関連リンク
私のオノマトペスタイル 藤野良孝