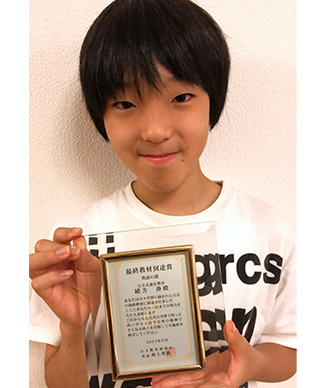アドバイザーとして「“人を支える”人」をサポート
 |
現在私は、公立の中学・高校のスクールカウンセラーや大学の非常勤講師を務めるほか、「いのちの電話」「チャイルドライン」「子育て支援」など、地域でボランティア活動をされている方々をサポートする仕事をしています。子育てなどの悩みを電話で相談できる「くもんダイヤル相談」の相談員の対応についてアドバイスしたり、指導者対象の「コミュニケーション講座」のお手伝いをしたりと、公文教育研究会ともお付き合いもあります。
個人事務所である末松TA研究所では、個人やカップルを対象とした心理面接やカウンセリングの勉強会を行っています。勉強会は、ソーシャルワーカーや臨床心理士などプロの方のグループもあれば、カウンセリングに関心がある主婦の方のグループもあります。また、TA(Transactional Analysis:交流分析)の国際資格を持っているので、学びたいという方にTAを教えることもあります。
「TA」というのは、1950年代半ばに、アメリカの精神科医エリック・バーン博士によって開発された心理学の理論です。「精神分析」(当人が“気づいていない意識”を理解していくための、心を分析する手法)を取り入れながら、人と関わる中で自分を活かしていくために、さまざまな“とらわれ”を解放していくアプローチです。
例えば私がある人を面接したとします。そのとき、「この面接で自分が何をしているか」ということを本人にわかってもらいながら、「自分でどう変えていきたいのか」を明確にしていく。最終的には、私のような立場の人がいなくても、自分で“人と関わる力”を身につけられることをねらいとしています。「自分や他の人との関係の中で何が起きているのか」を理解するための理論であり、日本では心療内科で使われるほか、教育界ではエゴグラムなどが知られています。
このように、今でこそ私は“心”に関する支援活動をし、学びを追求していますが、最初に進んだ法学部時代は学ぶことにそれほど真剣に取り組んでいませんでした。「学問」の喜びを知ったのは、2回目の大学時代です。
転機は26歳のとき
会社を辞めて「学問」に目覚める
 |
私の転機は26歳のとき。大学卒業後に就職した老舗百貨店を辞めたときです。この百貨店への就職は、「親が喜ぶだろう」と考えて決めたものでした。ところが配属先は、婦人用品売り場。大学時代に柔道や剣道に熱中し、男気があると思っていた私は、想定外の配属に「なんで自分が」とやる気をなくし、投げやりな生活を送るようになりました。
逃げたくなる自分、葛藤する自分、荒れている自分、いい加減な自分……と、それまで考えていなかった「自分」が現われ、「自分はダメなやつだ」と追い込んでいきました。今思えば、心理臨床に縁を持つようになったのは、この体験があったからなのでしょう。
そして、3年半勤めた百貨店を、思い切って辞めました。「自分はダメだ」と思うのは、「心の危機」であり、今では「それこそが成長の機会」だととらえられますが、当時はそんなことはわかりません。先は何も決まっておらず、怖くて不安でいっぱいでした。
奈良の実家に戻り、これまで読んだことのない分野の本を読んだり、昔の友人と話したりして、私なりの模索をしました。あるときミュリエル・ジェイムズの『自己実現への道』を読み、「親孝行とは、親にいきいきとしている姿を見せること」というような記述があり、ハッとしました。それまで私は「親が喜ぶことをすること」が親孝行だと思っていたのです。視点が変わり、「では、自分は何をしたいのか?」に、目を向けるようになりました。
私が「自己実現」と書かれた本を手にとったのはたまたまです。人は、そういう心の状態になると、それに向かって答えを得たくなるのでしょう。書籍だけでなく、臨床心理学者の霜山徳爾先生との出会いもあり、「哲学」が自分の答えを見つけるひとつの道ではないかと考え、再び大学へ行き、中世哲学を学びました。
そこで一番心に残ったのがソクラテスです。ソクラテスが基本とした考え方「無知の知」「汝自身を知れ」、つまり「自分自身の無知を自覚すること」が大事だと考えるようになりました。この2回目の大学時代が、私が本当に「学問」を始めたときです。「次から次へと自分で答えていかねばならない」という学問の喜びを味わうようになり、学びの質も生き方も変わりました。
高校教師時代の体験が
「本当の支援とは何か」を考える原体験に
 |
2度目の大学卒業後は、都立高校の社会科教員になりました。30歳の時です。最初に赴任した高校では、「どうせ自分たちは……」と卑屈になっていた生徒たちが何人もいました。彼らをなんとかしたくて、休部中だった柔道部と剣道部を再開したところ、生徒たちの成長が目に見えるようになりました。
ところが、練習では強いのに試合になると勝てない。なぜなのか? 中学の頃から「どうせお前は……」と言われ続け、自信を持てず、公的な場では萎縮して力が出し切れていないことがわかりました。そこで、私立の強豪校と合同合宿をしたところ、「彼らも僕らと同じ高校生なんだ」と実感したようで、それ以降、試合でも自信をもって活躍するようになりました。
「自信をつけること」の大切さを痛感したものの、彼らを卒業させた後、「生徒に対し、雑ではなかったか」という思いが残りました。例えばいじめられている生徒はかばっても、いじめている生徒とゆっくり話したことがなかった。彼らは、私の姿が見えるといじめはやめますが、心から納得していないので、私がいなくなれば繰り返します。同時に、いじめられている生徒をかばうということは、その子が自分で立ち直ろうとする機会を奪っていることになります。
これでは本当の教育とはいえません。その子が「自分の力でできる」と思うように導かねばならないのではないか。そう感じた当時の経験が、「本当の支援とは何か」を考える原体験となっています。
そうしたこともあり、仕事のあとにカウンセリング養成研究所に通うことにしました。さらに大学院で臨床心理学を学び、夕方から定時制高校で教える生活を続けました。そして38歳のとき、「いのちの電話」のボランティア相談員のトレーニングを受けます。先に相談員をしていた妻から勧められたのがきっかけです。
2年間の相談員を終えると、相談員のケアや研修を担当するディレクターを務めることになりました。1年間は教員と二足のわらじでしたが、どちらかにしないと失礼になると思い、「いのちの電話」での仕事を選ぶことになります。
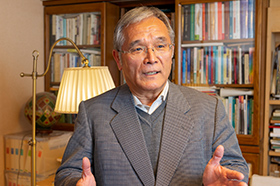 |
後編のインタビューから -公文式の「ちょうど」は相手を見て合わせていく関わり |