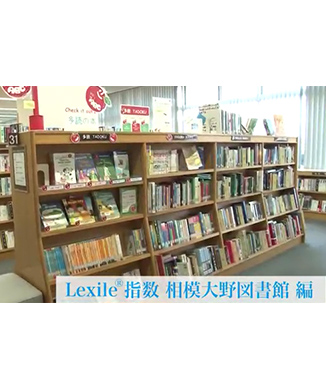9年間で成長を見られる楽しさ
国際交流ではタイに引率も

私が勤務している京都教育大学附属京都小中学校は、国立大学附属では初めての「義務教育学校」です。義務教育学校は2016年にできた新たな制度で、「小中一貫校」とは異なり、小学校6年と中学校3年という区切りがありません。
本校では、1~4年生が初等部、5~7年生が中等部、そして中2・中3に相当する8、9年生が高等部になります。私は中等部と高等部で英語の教員をしており、2024年度は5年生と8年生を教えています。
小学校から中学校に上がると、環境に馴染めず、学習意欲をなくしたり、学校に行きにくくなったりする「小中ギャップ」が指摘されていますが、義務教育学校は9年間の垣根が低いので、教員の目が届きやすいことが特徴です。
学習面でも1年生から9年生までひとつの教科の部会があるので、その中で議論しながら授業内容を決めることができるのもメリットです。9年あるので長いスパンで子どもたちの成長を実感できるのも楽しいです。私は英語科主任として、全国の学校教員向けの研究発表会で公開授業をしたり、日本の学校教育において英語の指導法について提案したりもしています。
本校はタイのアユタヤ地域総合大学の付属学校との交流活動を行っていて、その引率をすることもあります。2024年で28回目となるこの活動は「これからはアジアの国の人々と協力して生きていかないと」と考えた当時の齋藤栄二校長(京都教育大学名誉教授)が始めました。今年は8年生の約半分に相当する50名近くの応募があり、そのうち20名が選抜され1週間タイでホームステイをしました。行く前は不安がっていた生徒たちが、最終日にはホストファミリーと涙を流して別れを惜しむなど、子どもたちの変化には引率のたびに驚かされます。

校外の活動としては、英語の教科書の編集協力をしているほか、ETS公認トレーナーとして、TOEFL関係のレポートを書いたりもします。2022年は1年間サバティカル休暇をもらい、ロサンゼルスの小学校で英語や算数の指導や調査研究をしてきました。そのほか、長期休暇時は災害ボランティアに行くこともあり、2024年の夏休みには能登半島地震の被災地へ1週間ほど泊まり込みました。そこでの得がたい体験も生徒に伝えています。
Lexile®指数を活用した多読のすすめ

本校では7年前から、5年生以上の全員がTOEFL Primary®を毎年受験しています。「使える英語の力」を見るにはTOEFL®が適切だと考え、私が提案して始めました。
TOEFL Primary®の問題の設定は、どこそこで待ち合わせすることになったとか、友だちとの会話やレシピなどで、テストでは「日常生活の中でいろんな表現が出てくる場面に対応できるか」を見ています。こうしたことは試験範囲がないので対策をしようとしても難しいものがあります。むしろ暗記などの試験対策をするのではなく、「今の自分ができること」「苦手なこと」を知って、次のレベルに進むには何が大事かを知るためのテストです。
他人との比較ではなく、「去年の自分」と「今の自分」を比べるのに有効ですし、世界基準の英語能力測定試験なので、大学入試時や留学時に必要な英語能力を測るTOEFL iBT®を受ける際にも役立ちます。ほかの英語の先生たちも、TOEFL®のような問題が出た時に対応できるのが「使える英語」だと実感するようになり、授業の仕方も変わってきています。
語学学習においては、聞いたり読んだりするインプットが十分に与えられてこそ、話したり書いたりするアウトプットができるようになると言われています。ただ、十分なインプットには8万~10万語を読む必要があるとされ、学校の教科書では全然足りません。ちなみにハリーポッターの原書1冊が8万~9万語です。
そうした中でどうしたら読解力を高められるか。私は「Lexile®指数」に着目しました。これは英語の「読解力」と文章の「難易度」を表す指数でTOEFL Primary®、TOEFL Junior®を受験すると受験者の英文を読む力が数値化されて出てきます。

本を選ぶ時に、すらすら読みたいのであれば本人の数値より低めの指数の本を選べばよく、逆に高めの指数の本にチャレンジして、レベルアップを図ることも可能です。例えば宇宙マニアの子が、「宇宙に関する単語をもっと知りたい」と、自分の指数よりも高い本を選び、「これはどんな意味だろう」と学びながら読むこともできるのです。
このように、「Lexile®指数」は学習者と洋書をマッチングするために非常に有効なものさしだと感じています。Lexile®指数は現在、180の国・地域で使用され、1億の書籍・記事・ウェブサイトがマッピングされています。
本校では紙の洋書約3,500冊、オンラインではタブレットから5~7年生は120~130冊、8、9年生は1,000冊以上の洋書が読めるようになっており、生徒たちはLexile®指数を参考に本を選んでいます。動画や音声がついていることもあり、英語だけど見たい、読みたいという気持ちになるようです。
洋書をたくさん読むことについて本校の生徒に英語学習に関するアンケートをしたところ「難しいけど楽しい」という数値が高く出ました。Lexile®指数に合わせて自分に合った本を自分で選ぶので、楽しいと思えるのでしょう。
英語が好きでたくさん本を読んでいる子だけでなく、英語が苦手な子でもたくさん読めば、次のTOEFL®のスコアはぐっと上がります。もちろん学校の教科書も、文法を習うためのコースブックとして意味があります。一方洋書には、教科書には出てこないけれども日常会話で使う単語やフレーズが多く出てきてバラエティに富んだインプットができるので、教科書も大事にしながら洋書を楽しくたくさん読むのがいいと思っています。
公文式で「根性」をつけ、
日本人的な考えが変わった米国留学

じつは私は学生時代、とくに英語ができたわけではありません。数学は得意で、高校時代の全国模試で満点を取ったこともあります。小学生の頃、公文式教室に通っていたお陰です。数学は解けないと“答えがあるところにたどり着けない悔しさ”があって、公文ではプリントを解くことで「悔しさの訓練」をさせてもらいました。自分に足りない「根性」がついたと思っていて、今でも鉛筆の匂いを嗅ぐと公文の教室を思い出します(笑)。
公文は、友だちと競いあうのではなく自分のペースで進められ、苦手があったら戻ることができます。わからないまま進んだり、不得意なわけではないのに他の子と比べられて「自分はダメだ」と思ったりすることがありません。
私は算数しか学習していませんでしたが、公文の英語には音声が聞けるE-Pencilがありますよね。英語は文字だけ、あるいは音だけから学び始めると後で難しくなるので、音と文字と両方一緒に学べるのはいいと思います。スマホでも音声は聞けますが、E-Pencilは子どもがポロッと落としても壊れないし、手に持ったときのフィット感もいい。進度が上がったときの長文も、中高生が知りたいような内容なので楽しく学べそうですね。
とくに英語好きでもすごくできるというわけでもなかった私が英語と深く付き合うようになったのは、高校2年のときの約1年間の米国留学がきっかけです。留学から帰国した従姉が、「楽しかった」と言っていて、叔母にも「行ってみたら」と言われて行くことにしたのです。
最初はロサンゼルスで、ホストブラザーと一緒に公立高校に通っていたのですが、英語のネイティブが少なく、英語もなかなか上達しませんでした。言葉があまりにも通じなくて、雨の中公園で一人泣いていたこともありました。悩んでいたとき、ホストマザーがミシガン州に住む妹さんを紹介してくれ、そこで通った高校でやっと自信をつけることができました。やっぱり言葉が通じると楽しいですよね。

ロサンゼルスのブルワリーにて
留学は修行だったと思っています。でも、多様な考え方に触れ、大切にしたいこと、どうでもいいことなどが、日本とは全然違うことに気づきました。多くの国ではみんなと違うことがいいとされています。みんなと一緒や目立ちたくないという考えが、日本人特有のものだと知ることができました。世界に出ると見え方が違うことを実感し、子どもたちにも異文化体験をしてもらいたくて、海外留学を勧めています。
その頃から教員になりたいと思い、帰国後は国立大学受験のためにもう1回高校2年生をやり直しました。現地で単位を取っていたので留年せずに進級することもできましたが、あえてそうしなかったんです。それは当時かなり珍しく、先生に驚かれました。私は、「そんな日本人的考えに縛られるのは、もう終わったぜ」と意に介しませんでした。
留学前の私は苦手なことはやらず、人と違うことを恥ずかしいと思っていましたが、留学後は他人の目よりも自分のしたいことを大事にしたいと思うようになったんです。子どもたちにも、自分のやりたいことは自分の判断でできるようになってほしいと思っています。私が教員を目指したのは、中学時代の数学の先生がステキだったから。最初は数学教師を考えていましたが、留学を経験し、海外のことをもっと知ってもらいたいと思うようになり、英語科に転身しました。
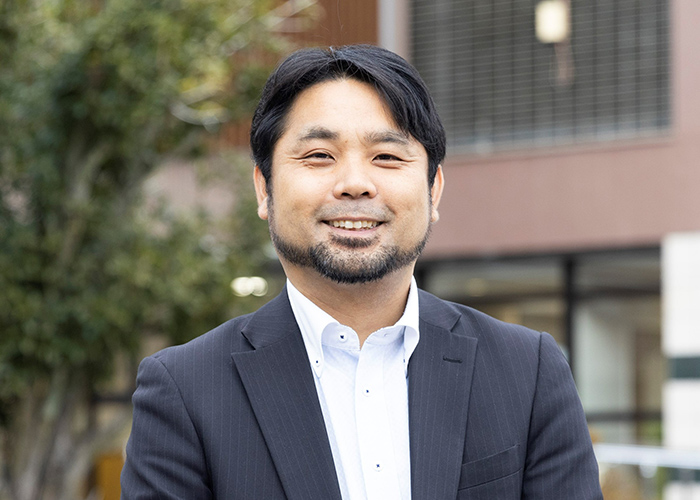 |
後編のインタビューから -「英語の授業はできるだけ楽しく」がモットー |