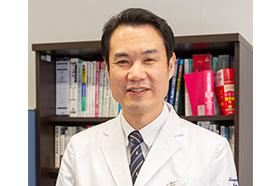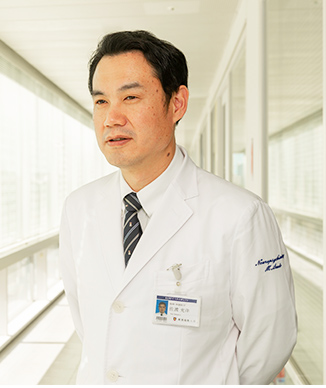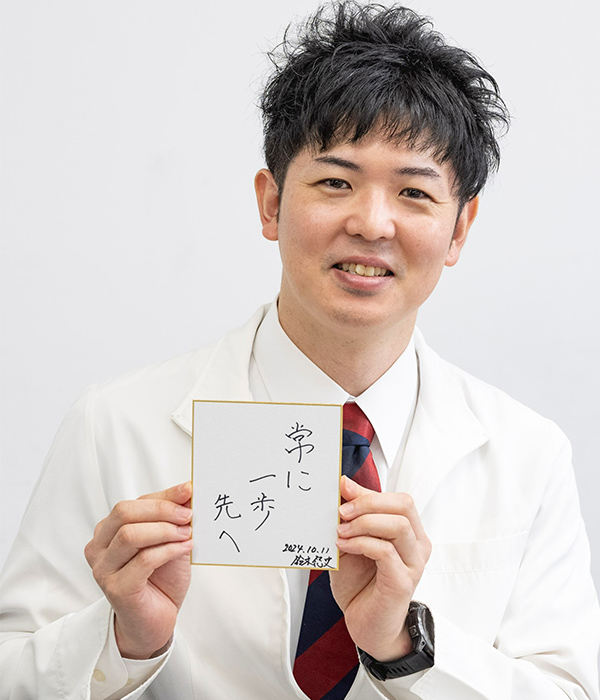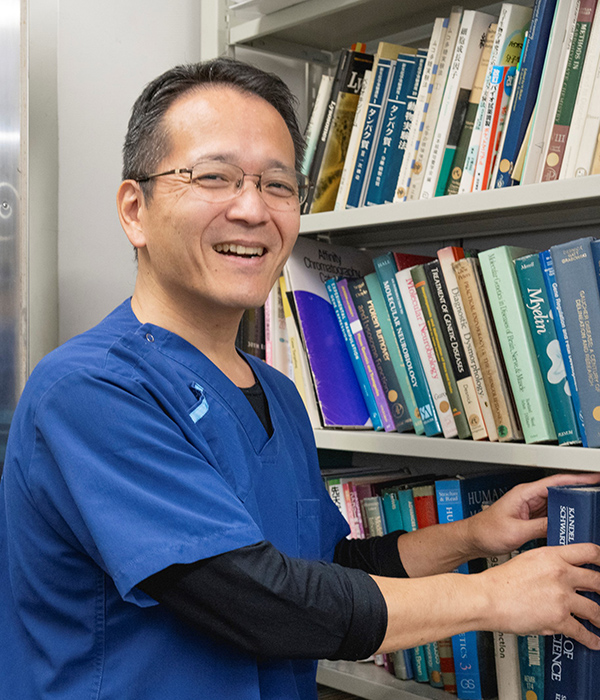スポーツを通じて「情熱と理論がそろうと、人や組織は動く」と実感
 |
大学卒業後は、岡山大学の麻酔科で2年間研修しました。当時の医学部は、卒業後すぐに専門を決めていくのですが、私には行きたい専門科がありませんでした。当時の岡山大学の麻酔科は、2年間の研修修了後、好きな科に行くことを認めてくれる珍しい科でした。そこで、基本的な蘇生法や全身管理など、この先どの科に進んでも役立つ技術を身につけながら自分の進路を考えようと思い入局しました。
そんな理由で入った麻酔科は、体育会のような厳しさもありましたが、とてもアットホームな雰囲気で、人間関係もとてもよく、充実した研修生活を送ることができました。そうしたこともあり、2年の研修が終わるとき、そのまま麻酔科に残ることも考えました。しかし、自分が本当に取り組みたいことは何なのか?と自問した時に頭に浮かんだのは、スポーツで体験した「人間がモチベートされたときに発揮されるパフォーマンスの素晴らしさ」でした。
特に大学時代に体験したアメフトは、戦術(理性)と闘志(感情)という正反対の要素が同時に求められるスポーツで、多くのものをここから学びました。
アメフトは戦術がものを言うスポーツで、ひとつひとつのプレーでそれぞれの選手がどのように動くか細かくデザインされています。そしてその戦術の優劣が勝敗を大きく左右します。しかし戦術が優れていれば必ず勝てるかと言うとそうでもありません。それを遂行する選手のモチベーションが低いと、いかに優れた戦術であってもあまり役に立たないのです。アメフトは体が激しくぶつかり合うスポーツだけに、選手の闘志がそのままパフォーマンスに表れてしまいます。試合中、誰が闘志を保ち、誰の心が折れてしまったか、周囲の者にもはっきりとわかるくらい、闘志やモチベーションでパフォーマンスが大きく変わってしまうのです。
一方で、そうしたモチベーションは言葉によって大きく変えられることも体験しました。試合前、円陣を組んだ選手に向かって監督やコーチが語りかけるのですが、そこでは、厳しい練習をやり抜いてきた選手を承認すること、これまでの練習の意味、そして試合という場が与えられることへの感謝などが、ひとつの「物語」として語られます。そうした物語から、自分たちの取り組みに大きな「意義」を感じられたとき、選手たちのモチベーションに「火」がつくのです。たった1分程度の監督やコーチの話で選手の目の色がガラリと変わる、「絶対にやり抜いてやる!」とモチベートされるという体験から、言葉のもつ力のすごさを体感しました。こうしてモチベートされた選手たちが、優れた戦術を遂行するとき、ものすごい力を発揮するのです。
そうした体験から、「人はどうしたらモチベートされるのか」「どういうときに達成感を感じるのか」を追求していきたいと考え、医学の中でそれができるとすれば精神科しかないと思い、精神科医になることに決めました。
振り返ってみると、自分の人生はつくづくスポーツにその根幹があったのだと実感します。小さい頃、野球を続けていたことで、努力することの大切さを学びましたし、大学時代に「モチベーション」に興味を持ったのも、「何かに取り組むときの姿勢によって、結果が大きく変わる」ということを実体験として学んだことがあったからでしょう。またこうしたスポーツの体験から、「情熱と理論が揃うとき、人や組織が動く」ということも学びました。子どもの頃「なんとなく関心があった」ことが、このころにようやく明確になったのです。
マインドフルネスとの出合いは、2003年、勉強の一環で講演を聞いたのがきっかけです。しかし、その時はその必要性や意味、なぜうつ病などの症状が良くなるのかといった理屈がさっぱりわかりませんでした。そのためしばらくは距離を置いていました。ところが、2010年にたまたまマインドフルネスの本を手にする機会がありました。「ああ、あれね」と半ば冷ややかに思いながらパラパラページをめくっていたら、そこにはマインドフルネスを取り入れたら、うつの症状がなぜよくなるのか、そのメカニズムが臨床的な観点からしっかり書かれていたのです。
見よう見まねで自分もやってみると、心のありようが変わり、ストレスが減りました。もっとしっかり勉強したいと、翌年オックスフォード大学の研修に参加。以来、研究を続けています。
「自分の存在が肯定できる」感覚を多くの人に持ってもらいたい
 |
私は、学びとは「気づき」であると考えています。それは、知的理解だけで完結するものではなくて、知的理解と身体、感情との統合作業だと思っています。心理学に「アハ体験」という言葉がありますが、これはドイツ語圏で何かを理解した時に発する言葉「a-ha(アハ)」に由来します。「ああ、そうか!」「ああ、これだったのか!」という気づきやひらめきです。本当の意味で学びがある瞬間には必ず感情や身体感覚が伴っています。
公文式でもそうですよね。「あ!こうすれば解ける!」と閃いたとき、喜びという感情が動いています。悲しみや苦しみといったネガティブな体験についても同じことが言えます。物事がうまく進まないとき、その理由がわからなければもっと苦しくなります。しかしふとした瞬間に「ああ、コントロールできないことを無理にコントロールしようとしているから苦しくなっていたんだな」といったように、自分が苦しんでいた理由にハッと気づくことで、スッと楽になるということだってあるわけです。ネガティブな体験が起きている理由を理解することが、実はポジティブな学びにもなるのです。
マインドフルネスは、海外では、うつ病の再発予防、不安障害など様々な症状に対して効果があることが確認されていますが、日本ではまだ十分なデータがありません。そこで我々は、不安障害の方々や健康な方々にも参加してもらうプログラムを実施し、マインドフルネスの医学的効果の検証を進めています。
近年は、well-being(幸福感や人生の充実感を意味する)を高める効果が期待されています。「well-beingが高い」というのは、「いつも楽しい」「いつもポジティブ」ということではありません。悲しさやつらさ、「落ち込んでいる自分」など、ネガティブな感情もきちんと受け入れ、抱えていられることが大事で、それが自己肯定感につながるのだと思います。
well-beingについては公文教育研究会とも調査を進めています。介護者自身のwell-beingが高いことがケアを受けている方のwell-beingの向上にもつながり、自立機能もあがるのではないかと考えていて、今後、それを検証していきたいと思います。
現代には「自分には存在価値がないのでは」という感覚をもつ人がたくさんいます。そう思うのはもったいない。「生きる意味や意義を見出す」というと仰々しく聞こえますが、それなりに「まあ楽しいよ」「生きていたいな」と思っていられることは大事なことだと思います。そうなる手段のひとつがマインドフルネスなので、その効果を検証しつつ、「自分の存在を肯定できる」感覚を多くの人に持ってもらうには、どうしたらよいのかを考え続けていきたいと思っています。
「コントロールしようとしない」ことを意識し、そのままを受け入れる
保護者は子どもの「存在」を否定するのではなく「行動」を指摘する叱り方を
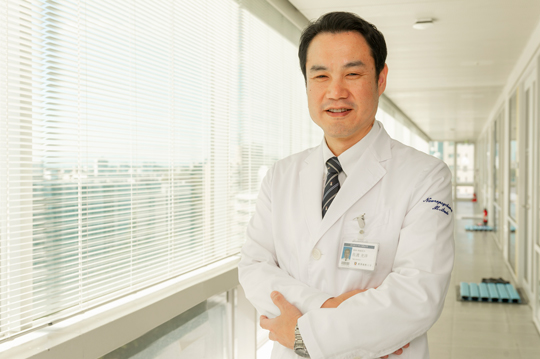 |
私は、マインドフルネスをする中で、「コントロールしようとしない」ことを意識しています。結末や未来が「こうあるべき」と思いすぎない、ということです。そうでないと、執着ばかりが先行して、物事がうまく進まなくなってしまいます。
たとえば、目標を立ててそれに向かって進んでいくのは極めて大事なことですが、その過程で思うようにいかないことが必ず出てきます。そんな時、「こんなことがあってはならない!」と現実を否定してしまわないことが大事です。そうではなく、「問題が起きている」という現実をまずしっかりと認めることです。その上でこの状況にどのように対応できるかを考え、それに最大限コミットするのです。
これは子育てにも応用できます。子どもに「なぜこんなこともできないのか!!」と思うことがありますよね。そんな否定的な感情が湧いてきたとき、感情の赴くままに反応しないことが大事です。まずはそうした感情があることを受け入れ、「なぜ自分は怒っているのか」と自分の感情を見つめてみる。すると、怒りの裏に「子どもを思うようにコントロールしたい」といった自分本位な要求があることに気づけたりします。
自分の感情、気持ち、思考をそのまま捉える練習をすることで、「ああ、またコントロールしようとしている」「またいつものパターンで、怒りの感情が出てきている」といった具合に自分の反応のパターンに気づきやすくなります。そうすると「じゃあ、今言うのはやめておこう」と考え直せたり、「できない理由は何か、一緒に考えてみようか」などの声かけができるようになったりするのです。
親子関係は、期待もありますし、距離も近いのでとても難しい。叱る時も、行為ではなく存在を否定するような言葉になってしまいがちです。私もいつも四苦八苦しています。妻の方がよほど上手に関わっていて、いつも助けられる立場です。ですから、とても人様に何かを言える立場にはありません(苦笑)。しかし、叱るときも行動を叱るのであって、存在自体を否定してはいけないはずです。「あなたのため!」と言いながら、実は、できないことがある子どもを受け入れられず、怒りをぶつけているだけということもあったりします。そうならないためには、怒りなどの否定的な感情が出てきたときには、その背後に自分のどんな欲求や考えが隠れているかにしっかり耳を傾けてみることが大事です。
わが子に対して意識しているのは、しっかり「甘やかせてあげる」、つまり存在を肯定してあげるということです。というのは、私は知らず知らずのうちに「こうあるべき」という「べき論」を子どもに押し付けてしまうという傾向があるからです。なので「抱っこ」といえば抱っこして、「遊ぼう」といえば一緒に戯れる。決して得意ではないからこそあえて意識して取り組むように心がけています。
子どもたちには、「何ごとも一生懸命体験しなさい」と言っています。長男はスポーツをしていますが、その中でもめごとや感情のもつれもあります。そうした体験をすること、そしてそれに対処することも、ものすごく重要な体験です。私自身、そうした体験が自分の基盤になっています。
前向きな自分だけでなく、落ち込んだり怠けたりすることも含めて「自分」です。その「今の自分」をまずは受け入れる。その上でできることに精一杯取り組む。お子さんはもちろん、保護者自身も、自分の存在自体を肯定していってほしいと思います。
関連リンク 慶應義塾大学ストレス研究センター学習療法センター
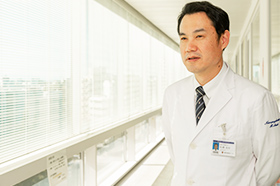 |
前編のインタビューから -「マインドフルネス」の考え方とは |