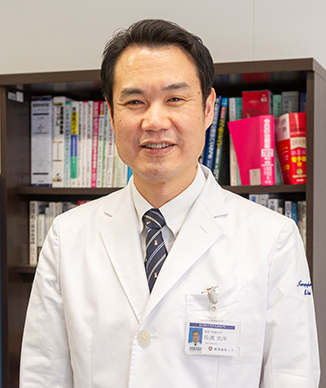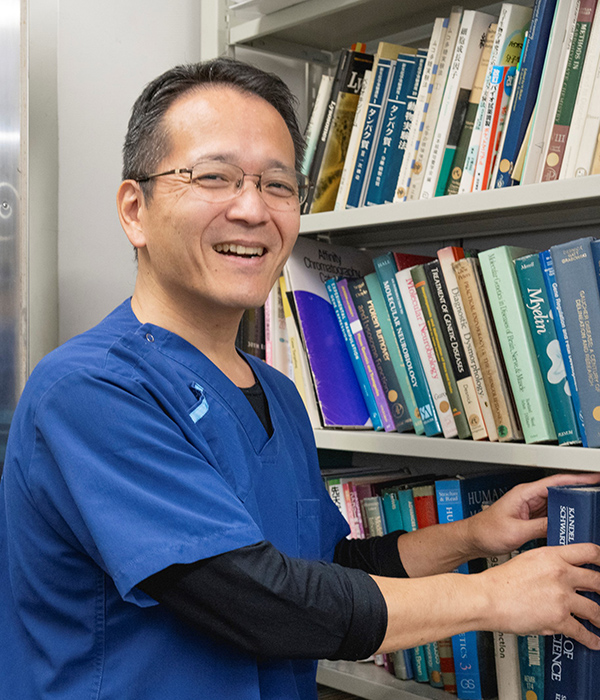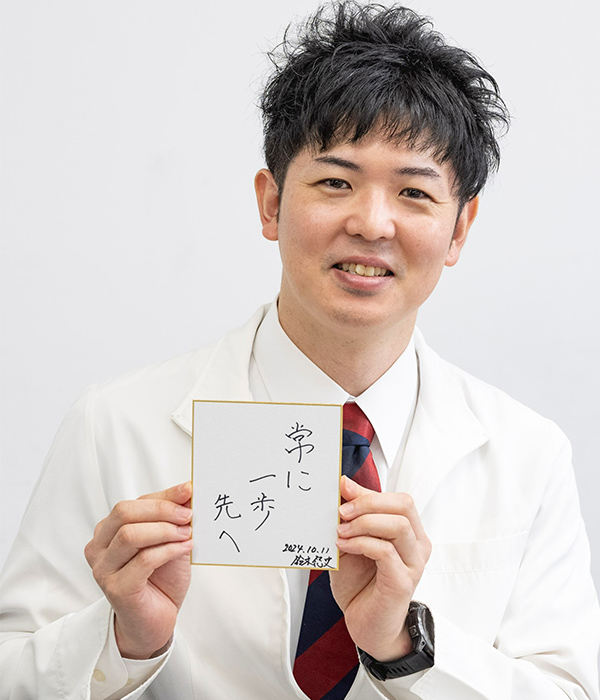「不快」を忌み嫌わずにそのまま受け入れる
「マインドフルネス」の医学的効果を研究
 |
現在の私の研究活動は、おもに2つあります。ひとつはマインドフルネスなどを活用した心理社会的な介入の効果研究です。もうひとつは、そうした心理社会的な介入の費用対効果に関する研究、つまり医療経済的な観点からの研究です。
マインドフルネスとは、ごくシンプルに説明すると、「今、この瞬間の体験に気づいて、それをありのままに受け入れる態度および方法」です。精神医療にも役立つのではないかと考え、研究を進めています。
もう少し詳しくマインドフルネスの根底にある考え方を説明しましょう。マインドフルネスでは、人間が苦しみを抱えるのは、不快な経験を忌み嫌うからだと考えます。ですから、「不快な経験や不快な感覚があっても大丈夫」という態度を身につけることで、苦しみから解放される、と考えるのです。
うつ病や不安障害などの患者さんは、落ち込みや不安、慢性的な痛みなど、不快な体験をしたときに、「一刻も早くなくなってほしい」と思います。それは当然のことですが、慢性的な症状はすぐにはなくなりません。すると、「いつまで続くのか」と不安になったり「なぜ私ばかり」と怒りが湧いてきたりして、かえって辛くなってしまうのです。
これをマインドフルネスの原理に当てはめると、不快な感覚を嫌悪するのではなく、むしろ「やさしい好奇心」を向け、これをありのまま受け入れるというスタンスをとることになります。不安や落ち込み、ストレスといった不快な感覚を好きになる必要はありません。ただ「好きではないが、それがあっても大丈夫」という「嫌悪しない関わり方」を身につけることで、結果として不快な体験を抱えるキャパシティが広がり、症状が楽になるのです。
私自身、ほぼ毎日マインドフルネスを実践しています。寝る前や朝、寝たまま呼吸に集中するのです。電車の中でもやりますよ。数分のこともあれば15分くらいのときもあります。「呼吸に意識を向ける」というのは、文字通り「息を吐いた」「吸った」という自分の感覚に集中するということです。
「学習療法」とは
「できた」「認められた」ことで自己肯定感が高まる
 |
私は2014年に認知症の社会的コストの研究をしていたことがあり、2015年、公文教育研究会 学習療法センターの「SIB実証調査事業」に、第三者評価機関の立場として協力することになりました。これは、経済産業省の委託事業で、認知症高齢者向けの非薬物療法「学習療法」と、認知症予防プログラム「脳の健康教室」の社会的・費用対便益の効果を調査するものです。私は「学習療法」によって介護度がどのように良くなり、公的コスト削減につなげられるかを評価しました。
施設入所の認知症の方57人のうち、30人には学習療法を1日30分週5日、1年間続けてもらいました。その結果、学習療法をしなかった27人に比べ、要介護度で1くらいの差がつきました。学習療法をしていた方たちは介護度が維持され、していなかった方たちは介護度が悪化したのです。そして、介護度が1違うと年間で一人平均20万円近い介護費用の差がでることもわかりました。
経産省の話が来た時、私は公文教育研究会が認知症の方を対象にした事業をされていることは知りませんでしたが、じつは最初はお断りするつもりでいました。というのは、これまでも民間企業から検証協力のお誘いをいただいていたのですが、「やるからにはきちんと研究したい。将来的には臨床研究につなげたい」と希望すると、「そこまでは必要ありません」という企業ばかりだったからです。ところが、公文の担当社員にそれを伝えると「ぜひやりましょう」と乗り気の返事をいただき、驚きました。
「学習療法」については、人を勇気づけるもの、人生に意味を与えるものだと捉えています。認知症の場合はとくに、できたことができなくなるという喪失体験が続いたり、自分のせいで周りに困っている人がいるとわかったりするので、自分の存在自体を否定してしまいがちです。しかし、「力や機能が落ちていくこと」と、「自己肯定感が低くなること」は必ずしもパラレルではありません。できることが減っても自己肯定感を維持できる人もいます。「学習療法」はそれを支えるひとつの方法だと言えるでしょう。プリント学習をして「できた!」という事実も大きいですが、それを「認めてもらう」という社会的な関係性が、自己肯定感につながるのだと思います。
スポーツ大好き少年だったが
将来の進路に迷い、目標のないまま医学部へ
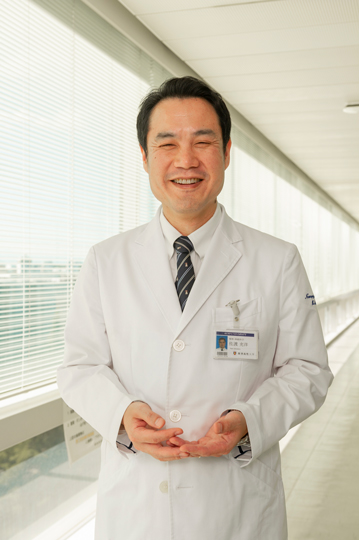 |
私は岡山県倉敷市で生まれ育ち、スポーツが大好きな子どもでした。幼稚園の頃から野球を始め、将来の夢はプロ野球選手。広島カープに入りたいと思い、野球に明け暮れる小学生でした。けれども「電車通学が楽しそう」という動機で受験・進学した岡山大学教育学部附属中学には野球部がなく、仕方なくバレーボール部に入部しました。
その後進学した高校にも野球部はなく、男子ソフトボール部に所属。高校三年生の時には国体選手に選ばれたのですが、受験が控えていることを理由に、監督が勝手に断ってしまい結局行けずじまいでした。
私の父はエンジニアでしたが「努力」と「根性」がモットーで、温かくも厳しい人でした。少年野球をしていたときも「プロ野球選手になりたいなら人の3倍努力しなさい」と言われ、チームの練習が終わったあとも、近くの山まで走らされていたほどです。一方母は、そんな父をフォローする感じでしたが、おっちょこちょいで好奇心旺盛。いろんなものごとに興味を持っていて、その部分は私も受け継いでいるかもしれません。
自分の将来については、中学生くらいから「社会の動きや人のモチベーションに関わることに携わりたい」と、漠然と思うようになりました。でも、具体的な仕事としては何も思い浮かびませんでした。大学進学時は悩みました。理系が得意な一方、経済学や社会学にも関心があり、それを先生や親に伝えると、「大学卒業後何するの?」と聞かれます。でも、答えられない。大学を卒業したら何をやればよいのか、さっぱりわかりませんでした。
唯一誰からも何も指摘されなかったのが医学部です。その後に何をするかといえば医者しかありませんから。そんな理由で医学部に入学したものだから、入ってからがとても大変でした。細胞学や体の仕組みにも関心がもてず、苦痛で苦痛で(苦笑)。
部活は医学部の部活ではなく、全学のアメフト部に入っていました。とてもハードな部活でしたが、自分の気持ちに負けてしまったときの挫折感、コミットした先にある大きな達成感など、人間として重要な価値観の多くはこのアメフト部での体験から学ばせてもらいました。
関連リンク 慶應義塾大学ストレス研究センター学習療法センター
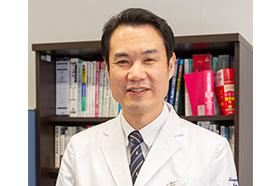 |
後編のインタビューから -スポーツでの学びから精神科医へ、マインドフルネスに出合う |