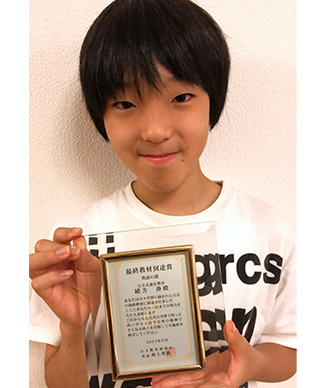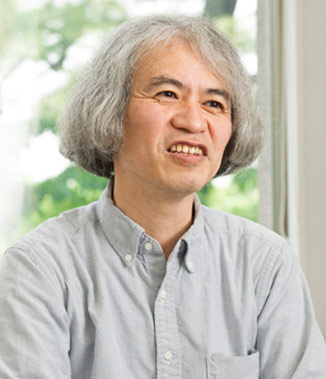「加齢」は人の発達プロセス
それに賢く対応する「スマート・エイジング」を提唱
 |
現在、私は東北大学のスマート・エイジング学際重点研究センターに所属しています。このセンターは「加齢医学研究所」での研究活動を発展してできたところです。「学際」という言葉がついているように、医学だけではなく、工学、文学、宗教学、経済学、農学など、学部横断的に加齢を科学しています。
例えば認知症ケアに関する問題は、医学の領域だけでは解決できませんし、介護の現場だけでも解決できません。そうしたことを横断的に研究して解決していこうというのがセンターの役割です。そこで私は特任教授として、センターで研究者が生み出した知見を、企業の皆さんと共同研究あるいは共同事業の形にして、社会に根づかせていく任務を担っています。
「スマート・エイジング」とは、私が提唱した概念です。そもそもどんな概念なのかを説明しましょう。「エイジング」を日本語で表現すると「加齢」です。ただ、加齢は「老化」と同義と捉えられがちで、「格好悪くなって衰退する」という非常にネガティブなイメージがあります。しかし、これは誤解です。
加齢というのは、受精した瞬間からあの世に行くまで人間が発達するプロセスをいいます。つまり「生き続けること」です。人間は歳を重ねるに伴って、いつまでも成長できる。私はそういう気持ちを込めて「スマート・エイジング」という言葉を使っています。「スマート」とは「賢い」という意味ですが、私は「人間として成長する」と捉えています。
人も社会も、経年によるいろいろな変化があります。そうした変化に賢く対処し、個人としても社会としても知的に成熟していく。それが「スマート・エイジング」ということです。
もうひとつの肩書きにある村田アソシエイツというのは、私が40歳の時に独立起業した会社です。ここでは企業のシニアビジネスのコンサルティングを行っています。もともとは、シニアビジネスに限らず、さまざまな新しい事業の企画開発をし、社会に展開させてきました。海外のビジネスを日本に普及させたものもありますし、逆に日本発のビジネスを海外に展開させたものもあります。そのひとつが、KUMONの「学習療法」のアメリカへの展開です。
グローバル企業と堅実な日本企業、2つの顔をもつKUMON
 |
私が学習療法に関わるようになったのは、2009年に現在のセンターの前身であるスマート・エイジング国際共同研究センターを立ち上げ、川島隆太先生が取り組まれているこの研究を知ったことがきっかけでした。学習療法を知り、これはアメリカで絶対受け入れられる、と直感しました。
その理由は2つあります。ひとつは、アメリカでは認知症は不治の病として非常に恐れられていたことです。それを改善できるメソッドが日本にあるというのは、絶対にインパクトがあるはずだと思いました。もうひとつは、日本と違ってアメリカには公的介護保険がなかったことです。
日本では、認知症が改善すると要介護度が下がり、介護報酬が減り、介護事業者にとっては実入りが減ることにはなります。ところがアメリカはそれがないので、学習療法で改善すると介護が楽になり、コストも下がります。スタッフもやる気が出て、もちろん本人も家族も喜びます。アメリカのほうがわかりやすく、受け入れられやすいと思いました。
そこで、アメリカの高齢者施設で説明会を実施したところ、ものすごい反響がありました。「もしこれが本当なら、これは天からの光だ」とまで言ってくれるアメリカ人もいました。施設側も学習療法の凄さを評価し、やる気満々。とんとん拍子でアメリカ進出計画が決まりました。
ところが、当時のリーマン・ショックの影響で施設が突然倒産し、進出計画は頓挫してしまいます。私も関係者も大ショックでした。しかし、説明会で感じた施設入居者の皆さんの熱が忘れられず、もう少し受け入れ先の探索を続けようと、あらゆるところに説明に行きました。そうして学習療法が日本で誕生してから10年が経過した2011年5月、オハイオ州クリーブランドにてアメリカでの学習療法がついに始まりました。
学習療法がグローバル展開する以前から、KUMONは世界に進出していますよね。現在では50を超える国と地域で事業展開されていると聞きます。KUMONは、そんなグローバル企業の顔と、非常に堅実な日本企業の顔の両方を兼ね備えている、とても珍しい企業だと思います。世界でこれだけの展開をしているのにもかかわらず、実直で、流されない。
「世界の潮流に乗り遅れるな」という風潮もありますが、KUMONは不易な部分をとても大事にされている。それは時々事業推進上のネックになるかもしれませんが、大筋ではアドバンテージです。この企業は絶対安心できるという信頼感は、大きな財産だからです。
子どもの頃から「新しいこと」「人がやらないこと」が好き
 |
学習療法がアメリカで受け入れられると直感できたのは、私がそれまでアメリカ企業と多くのビジネスを実践していて、しょっちゅう渡米しており、アメリカでの人的ネットワークが豊富で、現地の状況も熟知していたからです。私のキャリアの多くは、簡単に言えば、日本と海外との懸け橋となり、新規事業を海外あるいは日本に定着させること、と言えます。その基盤は生い立ちが影響していると思います。
新潟県の豪雪地帯で生まれ育った私は、幼い頃から「こんな田舎にいたくない、早く外に出たい」と、ずっと思っていました。海外に目が向くようになったのは、中学生時代の修学旅行で京都に行ったときの経験が最初のきっかけです。英語は好きで成績も悪くありませんでしたが、オーストラリア人のグループに道を尋ねられてまったく答えられなかった時、先生が英語で説明するのを見て、「外国人と英語でコミュニケーションできるといいな」と漠然と思ったのです。
その後も受験英語は勉強したものの、大学院1年のときに、アメリカから来日した研究員の生活サポートを命じられたとき、まったく英語が通じませんでした。これはまずいなと思い、そこから本気で英語を勉強し始めました。
花井等(政治学者、筑波大学名誉教授)の『国際人新渡戸稲造』を読んだことも、外向き志向になったきっかけのひとつです。当時の日本の黎明期を作った人間との交流も多く登場していて、私は後藤新平(明治~昭和初期の政治家)とのやりとりの場面がすごく好きです。最初に読んだのは学生時代ですが、社会人になってからも何度も何度も読みました。大事なところを決める時にはこんな呼吸が必要なのだな、など参考にしています。
昔から人がやらないような新しいことに興味があり、小5の時にはアマチュア無線の免許をとりました。新潟の超田舎にいながら、北海道でも小笠原諸島でも交信できたのが楽しかったですね。アマチュア無線をしていると、つきあいがあるのが年上のおじさんばかりで、そのせいか、ませた少年でした。機械いじりも好きで、ジャンク屋で部品を買ってラジオなどをつくっていました。
結構好きなことができていたのも、両親が自由放任だったからでしょう。父は地方の銀行員で、朝早く出て夜遅く帰宅する生活です。一方で母は自営業。紡績工場の下請けをしていて、朝5時から夜11時まで働いていました。姉、兄、私の3人兄弟、次男坊ということもあったかもしれません。
当時はまだ将来の夢は具体的には思い描いていませんでしたが、オイルショックの時に、「日本は資源がなくて石油の問題で右往左往している。だから資源の問題を解決したいな」と、なんとなく考えていたことは覚えています。まだ小学5年生の頃です。
大学では機械工学科に在籍しました。2ヵ月間岩手の八幡平という山にこもって、地下を掘り、高温の岩に水を注入し熱水を取り出して発電させようという実験をしていました。日本は地熱が豊富な国だから、これが実現すれば資源の問題が解決する、と考えたのです。結局実現はしませんでしたが、その時の看板が採掘場所に今でも残っていて、それを発見したときはうれしかったですね。山の中で熊に間違われて撃たれそうになったこともあります。そんな経験をずっとしてきたので、たいていのことは、何があっても動じません。
 |
後編のインタビューから -外国企業への就職を模索しフランスへ |