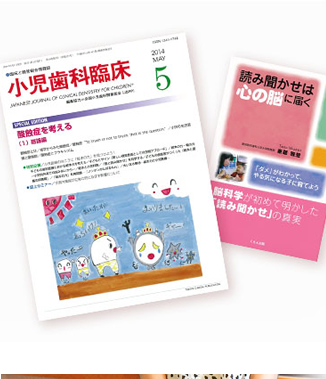教育とは次の世代に文化的な資産を伝えていく営み
 |
私の専門のひとつは「教育方法学」です。小学校で授業を見せていただき、先生方と教材研究や授業研究などを通じて、「子どもたちにどうやって教えるのがよいのか?」を深く掘り下げていく学問です。私が学んだ大学の教育学部には著名な心理学者の方々が教授陣に揃い、発達心理学的なアプローチで教育学を研究していたため、私も教育と発達の両方の領域に関わるようになりました。
私は、教育とは世の中にあるさまざまな知識や理論、技能などの文化的な資産を次の世代に伝えていく営みだと考えています。それらの文化が人から人へ、学校でいえば、教師から子どもたちへどうやって受け継がれていくのか、あるいは受け継いでいくこと自体がどうやったら可能になるのか、といったことを考えるのが教育方法学です。
たとえば人は「りんご」ということばを介して、「ああ、りんごね」とりんごを思い浮かべます。人によって経験上知っている「りんご」は異なるはずですが、ことばを通じてちゃんと伝わります。ほんの一握りのことばや体験を通じて、人と人との間で豊かなものが伝えられていくのはなぜだろうと、小学生の頃から不思議に感じていました。高校生くらいになると、教育に引き寄せて考えるようになり、「媒介になるものの制約があるにも関わらず、文化はどうやって伝えられていくのか」ということが教育学の核心的な問いだと気づき、その問いに対して研究を続けています。
一方で、私は「日本子ども学会」の常任理事も務めています。子ども時代のさまざまな問題について学際的に考察することが目的で、たとえば「子どもとメディア」というテーマでは、医学、心理学、工学などの研究者のほか、作り手であるメディア関係者も参加して議論します。さまざまな立場の人が集まって、子どもの教育のあり方をデザインする「チャイルド・ケアリング・デザイン」に取り組んでいますが、こうした活動は学会としては珍しいと思います。
他人を思いやることにつながる「教示行為」に着目
 |
私が現在関心をもっている研究テーマは「教示行為の発達」です。「教示行為」とは、教えること。子どもは子ども同士、あるいは大人にも、年少の子に対しても教えることがあり、そのような行為がどう発達していくのかに着目するものです。「教える」と「発達」という領域にまたがる研究を進めている私にとって、非常に重要なテーマであり、2016年4月に白百合女子大学にできた初等教育学科の教員として、これを中心テーマにしようと学んでいるところです。
発達心理学では、いま「心の理論」というテーマが注目されています。これは「相手の心のうちで何が考えられているのかを推測する」というもので、教示行為にも関係しています。教える立場である教師が、いまこの子はどういうことがわからないのか、理解してもらうためにはどんな教え方がよく、どんな素材を使えばいいのかなど、相手の心の内を理解して教えるプロセスをつくっていかないと、一方的な教え方になってしまうからです。「教える」ということの研究は、「他者を理解する」という発達心理学の根本的なところとつながっているということです。
相手の思いを推測する力ともいえる「心の理論」が成立するのは4~5歳前後と考えられています。それ以前の子の場合、自分が知っていることを相手に伝えるとき「やってみせる」ことがほとんどで、たとえば大人に折り紙を教える場合、折ってみせて教えます。言葉が発達してくると、「最初に三角に折って」など、言葉による説明ができるようになります。そして年長児くらいになると、その人が何を期待しているのかを推し量れるようになり、それによっては「すべて教えるのが良い教え方ではない」と、理解して行動するという研究結果もあります。
このように、幼児期までは教示行為の発達に関してある程度の知見はあるのですが、小学校にあがると、教えたり教えられたりということが教室内で組織的に促されていくため、自然な文脈で教示行為がどう発達していくのかにはあまり関心はもたれていません。そこで私は、それを自分の研究課題にしたいと思っているのです。
子どもは読み聞かせを通じて世界とつながるようになる
 |
子どもの発達は、「やりとり」のなかで生じます。そのことを検討した研究のひとつが、公文教育研究会との共同研究である「読み聞かせ交流会」です。小学生と高齢者が読み手になって、幼児に読み聞かせていくというプロジェクトで、そこではいろいろな交流が生まれ、幼児の発達はもちろん、小学生や高齢者にも意味があるという結果を得ました。
私たちは自分以外の外界について理解していくとき、五感だけを使って理解していくわけではありません。必ず「私」と「外界」の間に「媒介」があります。それは「大人」であったり「絵本」や「ことば」などであり、それを通じて人は発達していきます。読み聞かせは、絵本、あるいは絵本を読んで聞かせるという行為を媒介として、読み手と聞き手とがやりとりしながらお互いの発達を支えていきます。
おもしろいのは、大人がテキスト(本)を介して世界とつながって行く様子を、子どもは読み聞かせを通じて見ていて、書いてあることに意味があり価値があることを知り、自分もそれを深めていきたいと自ら学び取っていくようになることです。そこには文字が読めるようになる以上の意味があります。
また、高齢者が読んでこそ味が出る昔話などもあり、読み手によって伝わり方が変わるのもおもしろいですし、読み手にとっても、子どものころに読んだ本と受け止め方が違うと気づき、自分の成長を跡づけることもできます。このように読み聞かせは「媒介」としてさまざまな効果をもたらします。
関連リンク 白百合女子大学
 |
後編のインタビューから -宮下先生が研究者になるまでの経緯 |