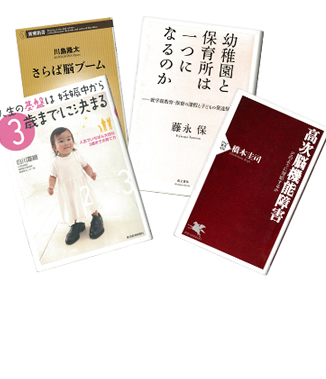国立大に合格するも1か月で辞めて再受験
 |
富山県の教師一家に育った私は、小さい頃から教師になろうと思っていました。ほめられることがうれしくて、小さい頃からいわゆる「いい子」でした。中学・高校になると、そのことに疑問を抱くようにもなりましたが、実際には大きな反抗はなく、生徒会長や部活の部長をするなど、期待される人物像にはまっていました。部活は中学・高校とブラスバンドで、高校ではホルンを担当していました。両親はとくに厳しいということもなく、高校生くらいのころ、「お前はどこに出しても大丈夫だ」といわれたことが自信になったことを覚えています。
高校時代は教育行政に携わりたいと考えるようになり、官僚をめざして東京大学文科一類を受験しましたが、失敗。東京に出て予備校に通い、翌年再び受験したものの見事に不合格。当時の二期校の経済学部に合格しましたが、1か月で退学。そこにできた経済法学科で法学を学べば行政に関われるのではと考えての入学でしたが、肌に合いませんでした。それでまた予備校へ。本当にやりたいことは何かと考え、教育研究者か、教師への道を探りました。
結局二浪して東京大学文科三類に合格。2年次後期からの専門科目となった教育学の授業で出会ったのが「教育方法史」という領域を開かれた稲垣忠彦先生です。先生が紹介してくれた教育実践の中に、大阪の小学校の先生による版画の授業がありました。秋田県にある八郎潟の伝説を版画で表現した大作で、「子どもたちはこんなことができるんだ」と圧倒され、「教育はおもしろい」と実感。このことが教育研究の道に進む決め手となりました。教師として現場に立つのも魅力的でしたが、枠にはまらない形で教育を考えたく、研究者となって現場の教師を支える側に回ろうと考えました。
その後、教育心理学の東洋先生や家族心理学の柏木惠子先生、生涯発達心理学の田島信元先生など、一緒に研究する方々に恵まれ、挫折というのは幸いあまりありませんでした。目の前の仕事を一歩ずつ進めてきたことが現在につながっていると思います。
私は押しの強い研究者タイプではありません。ただ、教育実践をテーマにした場合、学校現場とのつながりが重要になってくるため、管理職である校長先生をはじめ担任の先生方とのやりとりが円滑にできる人が必要です。実際、大学のある調布市内の小学校と継続的な関係がつくられており、その意味では、私のようなタイプの研究者も必要なのかなと思っています。
社会には学ぶべきことがたくさんある
子どもが「自ら学ぶ」機会を奪わぬ努力を
 |
教示行為や読み聞かせの研究を続けるなかで感じているのは、子どもは生活の中でいろいろなことを見つけるので、その生活の中に学ぶ機会をどれだけ豊かに仕組んでおけるかが大切だということです。ところが現代は、核家族など家庭の構造が単純化しているため、どうしても関わる人が限定され、豊かなやりとりをするのが難しくなっています。
一方で教育とは、「教室で先生に教えてもらうこと」という理解になりがちで、子どもたちの生活環境が「教育的」あるいは「学校的」になってきていることに課題を感じます。地域や社会にも子どもを育てる仕組みがたくさんあるのですが、それが見えにくい。会社員家庭が増え、親が何をしているかがわからない子も多く、社会の仕組みの中で大人たちがどう生きているのかは、子どもが意識的に見に行かないとわからない時代になっています。
そうやって子どもの経験が限定されていくのはとても残念なのですが、それを補う役割がまた学校に期待されてしまいます。総合的学習もそのひとつで、働く人を調べるなど教科中心から幅広く学べるようにする努力はされています。ただ、学校的な学びは、教師が意図的・組織的に教えるため、「先生に教えてもらっていないからわからない」となりやすい。大学生からもそんな発言が飛び出します。
子どもは自ら学ぶ力をもっており、就学前は遊びのなかでいろんな経験をしながらそれを獲得していきますが、小学校にあがったとたん、教室での勉強が中心となり、「先生が教えようとすることを、子どもたちがいかに学んだか」という観点で評価されてしまいます。総合的学習がはじまったときは、子どもの学ぶ力を活かせるのではと期待しましたが、変えるのはなかなか簡単なことではありません。ただ最近は企業が出前授業として、自分たちの仕事の教育的な意味を伝える試みが行われています。「社会には学ぶべきことがたくさんある」ということを知るだけでも、子どもにはプラスになると歓迎しています。
現場に役立つ実証研究を続けたい
 |
学ぶ場面は、生活のあらゆるところに存在しています。学校で学ぶことだけが子どもの発達を支えているのではありません。家庭での学びの場面では、やはり親子のコミュニケーションが大事です。忙しいでしょうが、ぜひ見直していただければと思います。
子どもたちには自由にのびのびと過ごしてほしい、その一言に尽きます。私は、いきいきといい表情をしている子どもたちに触れるなかで、子どもに一番必要なことは、制約を与えたり方向付けを厳しくしたりすることではなく、子ども自身の学ぶ意欲をいかに引き出して、いかに力を発揮させるかだと考えるようになりました。
子どもの力とは何か。たとえば私の息子は、子どもの頃、150余りのポケモンの名をすぐに覚えてしまいました。親としては、世界150か国の名を覚えてほしいと思うものですが、じつはそこに子どもの力が発揮されていることに気付くことが大切です。生活のあらゆる場面で発揮されている子どもの力を見極められる親の目が求められているといえるでしょう。
私は、研究を続けるにあたり、自分がやっていることが回り回って子どもたちにどんな意味や影響があるのかを、常に考えるようにしてきました。自分のやりたい形でやりたい研究をして、それをいかに学問の成果にしていくかということはあまり考えたことはなく、学生の頃から、どういう形で現場に役に立つかを大事にしています。
今取り組み始めている「教示行為の発達」についても、ゼミで立ち上げたばかりですが、白百合発の「教える」ことと「発達」の研究として、学生たちを通じて教育現場に活用されていくことを期待しています。初等教育学科はできてまだ2年目なので、実際に教員採用試験に合格して現場に出るのは今から2年後。そのときに現場にどう活かされるか。それを楽しみに研究を続け、学生たちを育てていきたいと思っています。
関連リンク白百合女子大学
 | 前編のインタビューから -教育とは何か? |