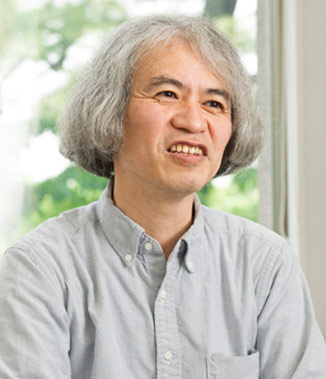「もう空襲がない!」終戦時の喜びをたいせつにして生きたい
 私は日本人がまだ外国へは自由に行けなかった1961年に、ユネスコの本部があるパリに行き、31年間を国際公務員として働きました。ユネスコは、教育、科学、文化という3つの分野で各国の協力と交流を通じて、国際平和に貢献することを目的とした国際連合の専門機関で、第二次世界大戦後の1946年に創設されました。
私は日本人がまだ外国へは自由に行けなかった1961年に、ユネスコの本部があるパリに行き、31年間を国際公務員として働きました。ユネスコは、教育、科学、文化という3つの分野で各国の協力と交流を通じて、国際平和に貢献することを目的とした国際連合の専門機関で、第二次世界大戦後の1946年に創設されました。
ユネスコで働くことは、私の夢でした。なぜそこで働きたいと思うようになったか。その原点は、疎開先で終戦を迎え、平和のありがたさをかみしめたことにあります。戦時中、両親の故郷である岩手県に疎開していた私は、「空襲が来そうだぞ!」という警報にびくびくしながらも友だちと遊ぶ日々を過ごし、アメリカ軍の戦闘機に追われたこともありました。そして国民小学校6年生のときに終戦となり、「これでもう、空襲がない!友だちと遊んでいられる!」と、大きな喜びを感じたことを覚えています。
そのときはただうれしかっただけですが、振り返ると、そのときの喜びが自分の体内に記憶されていて、「平和となったこの喜びをたいせつにできるような社会にしたい」という思いになったことが、私の人生を方向づけていったのではないかと思います。
私は岩手県から裸一貫で上京してきた苦労人の父と、その父をじっと支える母の間に生まれました。父は自分が苦労してきただけに、私が勉強するためには何でも自由にやらせてくれて、必ずサポートをしてくれました。そんな父に一度だけ、反対されたことがあります。「パリのユネスコで働く」という私の夢が実現しようというときに、「親の死に目にあえないようじゃ困る」とポツリと言ったのです。喜ぶと思っていただけにショックでした。
しかしその後、赴任が本決まりになる直前に父に手紙を書いたところ、今度は喜んで認めてくれました。20代の若者が異国に就職するというのは、当時の日本においては月に行くようなものでしたが、私がユネスコで働くということが、日本にとってどういうことを意味するのか理解してもらえたことが、一転して喜んでくれた理由のようです。後に家族から聞いたところによると、父は「なぜあのとき、最初に反対するようなことを言ってしまったのか」と悔やんだといいます。
教科書の丸暗記で英語が得意に 認められるとうれしくて、さらにがんばった

小さいころの私は、からだが小さくて病弱でした。かといって勉強ができるわけでもない。そんな子がどうやって英語を話せるようになり、世界を飛び回るようになったのか不思議に思うでしょう?何しろ英語の成績も底辺をさまよっていましたから。他の教科も先生からまともに相手をしてもらえないほどでした。
ただ戦後、ある先生からノーベル賞の存在を教えられ、そのスケールの大きさに感動して、友人と「どちらが先にノーベル賞をもらうか」なんて会話をしていたことが、勉強ができないながらも高等教育を受けたい動機づけになっていたように思います。
そんな私が高校で希望の大学を書かされたときに、「ハーバード大学」「ケンブリッジ大学」など、世界の名だたる名門大学の名を書いて、先生にかんかんに怒られたことがあります。底辺の生徒がそんなことを書いたので、冗談にもほどがあると思われたのでしょう。
ただ、そこでハーバード大などの名前を出したからには、せめて英語くらいは成績を上げないと、と本気になって中学1年から3年までの英語の教科書を丸暗記して勉強するようになりました。参考書も塾もない当時、手にとれるのは教科書しかなかったんです。それで英語力が伸び、その後の私の人生を左右することになりました。
もうひとつ、勉強することで先生に質問ができるようになり、「勉強しているんだね」と言われたのが励みになったことも、伸びる要因だったと思います。その一言で認められた気になり、「よし、次は先生がわからないことを質問しよう」と、いろいろ考えるようになりました。
こうして英語力を身につけ、私は国際基督教大学(ICU)の第一期生として入学することになりました。ICUに進学したのは、高校3年生のとき「国際性を身につけ、幅広い教養をつくりだす教育。明日の大学」という同校の紹介記事を読み、ノーベル賞のような国際的に大きな夢を描ける大学を探していた自分にぴったりだと思ったからです。
大学在学中には仲間と地域の子どもたちの勉強をサポートするボランティア活動をはじめ、それを機に、教育への興味が膨らみました。教育は人間を成長させ、よい教育を受けた心の豊かな人が、平和で民主的な社会をつくる原動力になっていく、ということに気づいたのです。
同時期には、ユネスコに加盟した日本が、積極的にユネスコの活動を実施している様子が連日報道されていました。当時ユネスコは、「平和な世界を築くにはお互いが理解することが大事で、それを教育で広めていく」ことを推進していました。そのとき私のなかで、これまでの漠然とした将来への思いがつながって「ユネスコで働きたい!」という具体的な夢になったのです。ただ、どうしたらそれを実現できるかはわからず、まずは大学院へ進み、ユネスコの活動に関連することを学ぶことにしました。
念願のパリ本部へ忘れられないパレスチナでのできごと

「マンガの登場人物に見られる人種偏見」という論文を書いて大学院を卒業した私は、教授の勧めで文部省(いまの文部科学省)のなかに置かれた、日本ユネスコ国内委員会の事務局に応募して、採用されました。
しかし、私の夢はあくまでもパリの本部で働くこと。その実現を夢見て一生懸命働き、1年ほどたったころ、チャンスが来ました。日本で開催したセミナーにユネスコ本部の担当者が来日し、私が通訳をすることになったのです。無事役目を終えたとき、その担当者に私がパリ本部で働きたい思いを打ち明けたら、しばらくして連絡がきて、本部の教育局アジア課に勤められることになったのです。
ここでは、さまざまな国籍、さまざまな人種の職員が働き、英語、フランス語、スペイン語などが飛びかっていました。そうしたなか、私は教育局のたったひとりの日本人職員として、仕事を始めることになったのです。
正直なところ、私の英語力はそれほど高いレベルではありませんでした。ただ私自身の経験からいえば、大事なのは外国語を使うとき、けっして難しい単語や言葉を使おうとしないこと。やさしい言葉を組み合わせて自分が自信をもって話をするほうが、相手には伝わると思います。
ユネスコでは、さまざまな国で多岐にわたる仕事をしましたが、なかでも印象に残っているのが、パレスチナで試験監督をしたときのことです。イスラエル国内に住むパレスチナ人難民の子どもたちは、高等教育を受ける機会がありませんでした。そこで、ユネスコはイスラエル政府から、高等学校の卒業試験(バカロレア)に合格すれば、イスラエルを出てアラブ諸国の大学に行ける、という約束を取りつけたのです。
そのような背景で実施された試験、その試験場でのカンニング事件は忘れられません。もちろん、カンニングは悪いことです。しかし、民族対立が続き、不自由な環境下にいるパレスチナ人にとって、試験に合格することは、単に個人が大学で学ぶ資格を得るだけでなく、家族みんなが人間らしい生活を得るための唯一の希望でもあったのです。自分たちの運命を決める試験に合格するために、必死に行われた行為でした。私はカンニングをとがめませんでした。それが正しかったのかどうか、今でも答えは出せません。
関連リンク 世界寺子屋運動/日本ユネスコ協会連盟
 |
後編のインタビューから -実体験を交えた識字授業への反響と「世界が教室」という思い |