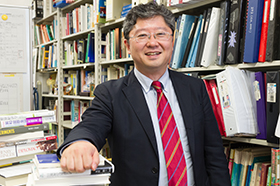開発経済学は、発展途上国の幸せを達成するための学問
 |
経済学というと、「お金儲けのための学問」で、経済学者は「市場の競争があれば世の中が良くなると考えている」と思われているかもしれません。しかしそれは大いなる誤解で、経済学とは、お金、しごと、モノなど、人間活動に関する総合的な学問であり、「世の中を良くするために、市場がうまく機能しない部分を、政府や人びとの力も合わせてどう動かすかを考える学問」です。
私の専門とする開発経済学はその一分野で、特に途上国の人びとの幸せを達成するには何をすればよいかを考えています。この分野で行われていることは主に3つで、1つめは、「実証的な分析」つまり「ある論」です。途上国ではなぜうまく経済発展しないのか、すでに発展している日本のような国はなぜ発展したのか、そのメカニズムを明らかにすることです。
2つめは、いま貧困状況にある国々が望ましい姿になるために、その国の政府や国際機関あるいは日本のような政府開発援助(ODA)供与国どうすればいいのか、「政策論を考える」という「べき論」です。
3つめは、「フィールド実験」と言われる実践的な研究、いわば「する論」です。研究者が政府やNGO、企業などと共同で、現地に政策介入のプログラムを導入し、実践・検証します。それは、たとえて言えば、理科系の実験室の中でやっている統御実験を世の中のフィールドで行う、とも言えるような研究です。
私がかかわっている具体的な研究例を挙げると、バングラデシュの貧困地域の子どもたちに対して提供されている公文式学習の厳密な効果測定や、自然災害の被災地における経済的な影響などを分析して復興復旧につなげる研究、また開発経済学ではないですが日本の自殺対策の研究などにも取り組んでいます。自殺対策というと、経済学と関係ないと思われがちですが、自殺の背景には抑うつ傾向の増加があり、さらにうつの原因の一つとして経済的問題があります。つまり、有効な自殺対策のためには経済問題に切り込む必要もあるわけです。これと関連して、鉄道駅のホームに青色灯を設置すると、自殺者が8割削減されるとの研究結果が数年前に話題になりましたが、これは私たちの研究の成果です。
公文式は「非認知能力」も高める学習法
 |
私は兵庫県西宮市に4人きょうだいの末っ子として生まれました。絵が得意で、幼稚園を卒園する時は、代表として答辞を述べるような子でした。
父は陸士(陸軍士官学校)在学中に終戦を迎え、その後一念発起して内科医になりました。1950年代に渡米し、ボストンの病院でレジデントとして勤務するなど稀な経験も持っていました。時代に翻弄された経験があったためか、私に対しては「世の中のためになることをやりなさい」と言い続ける一方、自身の仕事について「病気の患者さんからお金をとるのは心苦しい」とよく話していたことを覚えています。
母は女学校を卒業後、会社勤務という当時は珍しいOL経験を経てずっと働いていました。性格はなにか超越した感じで、誰にでも親切、何があっても落ち着いて構えていて、私が「来るものを拒まず」という性格なのは、母の影響かもしれません。
公文に通っていたのは、小3から小4の頃。今は優れた医師となっている兄と一緒に通い、毎回自分が先に終わって兄が出てくるのを教室の入口で待っていたことを覚えています。そのため、私自身の公文の思い出としては、いつも待たされていたという印象が強いです(笑)。
しかし、現在、バングラデシュで公文式学習の導入の研究に関わってわかったことは、公文式は単に計算力をつけるだけでなく、やる気や忍耐力、自分の学力を客観視して「こうすればできるんだ」ということを理解する力をつけてくれるということです。これは、経済学でも最近注目されている「非認知能力」も高める学習法ということです。
また、学習のシステムも優れていると思います。私は自己規律がゆるくて、じつは夏休みの宿題をやるのは必ず9月1日の始業式の夜、という子でした。これは、行動経済学でいう「先送り行動型」。ところが公文式は「教室が週2回あり、その日の教材は最後までやる」また「教室以外の日も家で毎日やる」ので、先送りできません。先送り思考型の子にとっては、やりきる習慣がつく非常に良いやり方なのだと改めて思います。
「経済学のプロになる」ことをたたき込まれた修士時代
 |
さて、私は東京の私立中高一貫校に進学するため、中1で親元を離れ、にぎやかな家族から一転、1人下宿生活を始めました。東京の学校がどんなところかよくわからないままの進学でしたが、とくに抵抗感はありませんでした。陸士出身の父からすれば、昔の子どもはそのくらいの年で親元を離れていたのだから大丈夫、との思いがあったようです。中学・高校は質実剛健で自由、大家さんご一家には大変良くしていただきましたが、親元はなれての下宿生活だったため、自主性は育ったかもしれません。
経済に関心をもったのは高校時代からです。数理的な教科が好きで、なおかつ人間行動にも関心がありました。人の活動の根本にあるのは「お金=経済」であり、それによって人が動くことに興味が湧き、経済学部へ進みました。転機は大学2年の終わりころ。3年からゼミが始まるので何を勉強しようかと、書店で本をパラパラめくっていたら、渡辺利夫先生の『開発経済学――経済学と現代アジア』(日本評論社)という本に出会いました。
当時NICs(新興工業国)と言われていた韓国や台湾などは成長しつつある一方、バングラデシュなど南アジアは成長しておらず、それはなぜかを、データと簡単な数理モデルを織り交ぜて実に手際よく示していて、「おもしろい!」と思ったのです。
慶応大学で大変な人気ゼミだった高梨和紘先生の開発経済学ゼミに幸運にも入れていただき、途上国とくにアジアに興味をもつようになりました。同じころ友人とタイへ行き、日本では見ないような光景の数々に強い印象を受け、貧困問題への関心が高まりました。
大学卒業後は、実家から通える大阪大学の修士課程へ進みました。当時の日本の経済学はまだマルクス経済学も根強かったのですが、阪大の経済学部は100%近代経済学で完全にアメリカ型の大学院プログラムを導入していました。最初の1年間は徹底した詰め込み教育。修士課程にもかかわらず全て講義形式の授業で、宿題や期末試験もありました。ガリガリ徹夜で勉強せねばならず、正直面喰いました。ところが、ここで徹底的に学んだことが非常によかった。どんな学生でもステップ・バイ・ステップで研究者の入り口までたどり着くことができる仕組みで、経済学のプロになるということをたたき込まれたのです。ここでの学びが、自分の研究者としての礎になったと言っても過言ではありません。
関連リンク東京大学大学院経済学研究科・経済学部
 | 後編のインタビューから -アメリカで得たのは人との「出会い」と「つながり」 |