育児に専念した2年間
「自由になりたい」と空を見上げていた
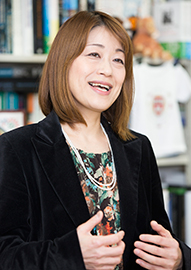 |
教育学部に所属しながら、週5日を京都大学霊長類研究所(以下、霊長研)で過ごす生活を続けました。研究は楽しかったのですが、親に申し訳ないという気持ちもあって就職活動をし、内定も得ることができました。ところが卒論に取り組み始めたら、やっぱり研究がおもしろくなって……。秋になり、「大学院に進学してもいいかな」と母にきくと、「いいよ、なんとかなるよ」と。本当に、母には頭が上がりません。
大学院に進学し、本格的にチンパンジーの研究に着手しました。当時、チンパンジーの心にまつわる研究の多くは、「チンパンジーは(ヒトと同様に/ヒトよりも優れて)こんなことができる」という発見が主流でした。しかし、もともとヒトの心の独自性に関心の強かった私は、「ヒトには簡単にできて、チンパンジーには難しいこと」のほうに面白さを感じ、「真似(身体模倣)」をテーマに選びました。意外に思われるかもしれませんが、チンパンジーは真似が苦手なのです。ニホンザルは真似をしません。「サル真似」ということばはじつは間違っているのです。サル真似が得意なのは、ヒトだけです。
チンパンジーに意味のない行為、たとえば、飲むときに使うコップを頭の上にのせるといった行為をみせても、真似することはありません。でも、ヒトの赤ちゃんはそっくりそのまま真似してしまう。ヒトは、ことばを獲得する前から他者の行為を真似し始めます。そこには、他者の行為から効率よく学習したり、行為の背後にある心を読み取ったりするという、発達における重要な意味があると考えられています。
研究は、うまくいかないのが当たり前。想定どおりの成果が得られなくても、ストレスはさほど感じません。しかし、出産と育児で研究をセーブしなくてはならなかったときには、これまでにない大きなストレスを感じました。研究を始めてから10年くらい経ち、独立した研究者として軌道に乗り始めたころ、子どもを授かりました。うれしかった。でも、同僚は海外留学など新たな世界に挑みはじめる時期でもありました。焦りを感じたのも事実です。私もそうした夢を描いていましたから。女性のキャリア形成は、プライベートとのバランスが難しいですね。
妊娠中も研究は続けていましたが、子どもをちゃんと育てなくては、という思いが強く、産後はいったん研究から離れることを決意しました。2年間、専業主婦として育児に専念しましたが、正直つらかった。毎日、買い物に行って、オムツを換えて、お風呂に入れて……。研究が、とても遠い世界となってしまいました。ベビーカーを押して散歩しながら、子どもの頃のように空を見上げて、「自由になりたい」と思っていました。これ、多くの母親の本音だと思います。
親だって完全ではない
子どもたちは社会みんなで育てよう
 |
悶々とした日々を過ごしていたあるとき、京都大学の田中昌人先生のゼミの先輩であった滋賀県立大学の竹下秀子先生から声をかけていただき、同大に専任講師の職を得ました。松沢先生の教えなのですが、「この分野なら私にまかせて」という研究への信頼を築き上げる努力は重ねてきました。やりたいことを、責任をもって果たす。竹下先生は、私の地道な活動を見ていてくださったのだと思います。私も指導学生たちには、「いろんなことに振り回されず、貫きなさい。頑張っていれば、誰かがどこかで見ていてくれるよ」と言っています。
出産後は、チンパンジーからヒトへ研究の軸を移しました。ヒトの心の起源を探るために、ヒトの胎児や新生児の研究を始めました。ヒトの心は他者との関係なくして育ちませんから、ヒトの心を育む環境、つまり、親や社会が果たすべき役割についての科学的解明にも力を注いでいます。そこで得た結論のひとつは、「ヒトの子育ては共同養育が基本」ということです。チンパンジーは、子どもが6歳くらいになり親離れしてから次の子を産みます。一人ひとりをゆっくりと育て上げます。しかし、ヒトは2~3年間隔で出産することが多い。そのうえ、ヒトの子どもは自立するまでに、たいへんな時間と労力がかかります。ヒトは本来、子どもを複数の手で育ててきました。共同養育を基本として進化してきた動物であるはずです。
実際アフリカに行くと、母親以外のおっぱいを飲んでいる赤ちゃんがいて、子育ての気安さに驚かされると同時に、ヒトは共同養育が基本だと確信します。それに対し、現代日本の子育ての状況はありえません。赤ちゃんをベビーカーに乗せ、もうひとりの幼子の手を引いて歩くお母さんの姿を見るたび、胸が張り裂けそうになります。ヒトの進化を考えると、母親ひとりの手で子どもを育てることなど無理なのです。ましてや精神的・経済的に余裕がないと、母親のストレスが過度になってしまうのは当然でしょう。そうした状況を不幸だと放っておかず、母親以外の者―それは他人でもいい―が、いかにおせっかいに子育てにかかわるかが大事です。母親は、母性というものをもった完璧な養育者ではありません。子どもの育ちを守るのは、母親だけでなく社会全体です。これは理想論ではなく、人類の未来にとって必要な営みなのです。
基礎研究者である私に、今できること。それは、ヒトの子育てのあり方を科学的に検証し、その成果を正しく社会に伝えることでしょう。「ヒトとは何か」をつねに考え、責任をもって発信していく。“子育てがうまくいかない”と自分を責め続ける母親に、そうではないよ、ときちんと説明する。子育てに科学で迫る試みはまだ始まったばかりですが、これは人類の未来がかかった最重要課題のひとつです。それが学術界でもここ最近ようやく認知されてきたように思います。とてもうれしいことです。
この子がハッピーで生きていられれば、それでよし
笑顔でいられることを見つけよう
 |
私自身も子育ての悩みは尽きませんが、子どもがどんどん自分とは別の存在になっていくにつれ、「こうなってほしい」と求めるのは無理だなぁ、と思います。子どもにとっての幸せと、親が子どもに願う幸せが同じとは限らない。だから、「何をやったら自分が笑顔でいられるか、考えてみよう」と言っています。毎日、自然と笑っていられる。それに勝るものはありません。
親がやるべきことは……あまり口出ししないことでしょうか。朝、学校に行く前に「忘れ物ない?ハンカチ持った?」なんて言わないほうがいい。実際に忘れて、本人が困ったときにはじめて、「次は持っていこう」と自覚するはずですから。私が母にしてもらったように、「信じて待つ」ことを大事にしたいですね。ヒトの脳には、他人から信頼されることに喜びを感じるシステムがあります。そういう経験を、早いうちからたくさん積み重ねていってほしいです。
もうひとつ、読書についてですが、子どもには読書に没頭する時間をぜひもってもらいたいですね。読書は、視覚、嗅覚、触覚など、五感を総動員してそこに描かれている世界を具体的にイメージする、きわめて創造的な活動です。私の母は、知人から古本をたくさんもらい受け、自宅の一部屋を「本の部屋」にしてくれていました。次はこの本を読んでみようかな、と自然と思わせてくれる環境。「この主人公はこう思っているけど、あの主人公だったらそうはしないだろうな。私だったらこう思うな」など、たくさんの本に出会うことで、自然にイメージ力が鍛えられたと思います。イメージ力こそ、まさしくヒトが特異的に進化の過程で獲得してきた素晴らしい能力。昨今ブームのAI(人工知能)にも、まだまだ太刀打ちできない能力です。
「本の部屋」が、私の学びの原点だったとしたら、私にとって学びとは、「何かの役に立つからやろう」と考えてやるものではなく、「知りたいと思うことが次々浮かび、それを探る作業自体に喜びを感じるもの」といえるかもしれません。研究者として日々学び続ける中で、苦しいこともたくさんありますが、少しずつ高い目標を設定し、到達していくことにわくわくするのは、今も昔も変わりません。「次は、何をやったらうれしいかな?」と考えることこそ、道を切り拓くための原動力です。進むべき道を自らの意思で選択することに喜びを感じられるかどうか、これが人生を豊かにする鍵のひとつだと思います。
これから私がやりたいことは、自分の研究成果を検証するための実践の場をつくること。基礎研究の成果から確信してきた「ヒトらしい心」と「それを育てるための条件」を実際の社会で実装する挑戦です。うまくいかなくても、検証を繰り返すことでさらにヒトの育ちに必要な条件がみえてくるはずです。学ぶことの喜びは尽きません。
関連リンク 京都大学大学院教育学研究科 明和政子研究室


























