アメリカで得た「人との出会い」と「さまざまな人とのつながり」
 |
大阪大学大学院では、経済学について徹底したトレーニングを受け、修士論文は開発経済学で最も権威のある国際的な学術雑誌 Journal of Development Economicsに掲載されました。安場保吉先生、高木信二先生、コリン・マッケンジー先生、柴田章久先生など素晴らしい先生に恵まれ、研究の精神や経済学とは何たるかをたたき込まれたからこその結果でした。このことは、後になって効いてきます。研究の世界では、とにかく良い研究をして認められることが最重要だからです。
その後は、スタンフォード大学に留学して、開発経済学のプログラムで学びました。ところが、しばらくして私が所属していたプログラムが廃止になることがわかり、同大の経済学部に入り直します。この開発経済学のプログラムの学生は皆、現地に行って自分でデータを集めたり経済実験をやったりして、それを解析して論文を書くという、今から思えば当時としては先進的なスタイルの研究を行っていました。社会人類学のフィールドワークと、経済学のミクロ実証研究を合わせたようなおもしろさで、私もそうしたスタイルに倣いました。
そうしてまとめた博士論文が、パキスタンの村の子どもの就学に関するものです。農村では不作などにより所得が変動し、それによって子どもが就学できないことがあります。その問題について、何ヶ月もかけ多くの村を訪れてインタビューを重ね、最終的に23の村の2000人以上の子のデータをとって解析し、まとめました。この研究もその後、Journal of Development Economicsに掲載されました。
大学院の夏休みに、世界銀行でインターンをしたのも良い経験だったと思います。アメリカで学んでよかったことは、人との「出会い」と「つながり」です。本や論文でしか見たことのない綺羅星のような教授たち、世銀の著名エコノミスト、世界中から集まった超優秀な学生たちから、日々新しい様々な考え方に触れることができ、大いに刺激を受けました。今でもそのネットワークが活かされています。これらはアメリカ留学したからこそ経験できたことです。就職もアメリカでしようといくつかの大学からAssistant Professorのオファーももらったのですが、東大から開発経済学の専門家を探していると終身雇用(テニュア)のある条件で誘われ、悩みましたが、帰国を決めました。そうして現在に至っています。
いかに「良い研究」と認めてもらうか、あきらめずにやり抜こう
 |
研究者にとっては、良い研究をしてそれが認められることが大事です。しかし、自分の研究を国際的な学術雑誌に投稿し、厳しい査読のプロセスを突破して認めてもらうプロセスはとてもシビアで、今でも非常に苦労しています。私が考える「良い研究」とは、革新的なアイディアを緻密な手法で研究し、社会で課題となっている根本問題の解決の糸口を見つけることができるような研究です。
良い研究をするには学び続けることが大事です。現在は情報量が多くなってきていて、学ぶ機会は増えていますが、私は学びとは、「誰も気づかなかったことを発見すること」だと思います。ただ、それが独りよがりになってはいけなくて、科学としての厳密な手続きに基づき、現実に当てはまるロジックに即した新しい「エビデンス(科学的根拠)」であるべきです。
現在取り組んでいるバングラデシュ貧困地域の子ども達の学力向上のプロジェクトもまさにそれだと思います。ここでは公文式という日本の組織ならではの特長をとり入れた解決策を打ち出していて、国際的な研究競争の場でも戦える、絶妙な組み合わせのプロジェクトだと思っています。
ゼミの学生を指導していると、驚くような優れたアイデアをもつ学生に出会います。研究を料理に例えると、私は料理人のプロで、後進の料理人を育てているようなものです。日ごろ学生から提供されるのは、見た目も味もいまいちの料理ばかりかもしれませんが、たまにハッとする料理をつくる学生がいます。例えば、ごはんにマヨネーズと醤油をちょいちょいとかけて持ってくる、実においしい料理(笑)。我々玄人だと絶対やらないことを、若い人は柔らかい頭で考えます。かつそれが真理のど真ん中を突いていたりします。こうしたことが学びの本質であり、そういう場面に遭遇すると教育者としてとてもうれしく感じます。
学びをさらに前進させるには、困難があってもとにかくあきらめないことです。目の前の課題には何らかの解決方法があると前向きにとらえ、手を抜かないでやり抜くことが大事です。ただそれには努力が必要。逆に言えば努力すれば道は開ける、私はそう思います。
社会問題の解決につながる新しい発見を導き続けたい
 |
学生から思いもよらぬ料理を出されてハッとするのと同じように、私自身、現場で調査を重ね、データをとって解析していくと「これが核心だ!」と新しい発見をすることがあります。これこそ研究者冥利に尽きる瞬間です。
最近では、東日本大震災での被災地とフィリピンの洪水被害を受けた地域とで、「先送り行動」について共通のパターンを発見した時にはかなり興奮しました。双方とも、被害が大きかった人々ほど先送り傾向が強まることがわかったのです。先送り行動とは目の前のことを優先して問題を先送りしてしまう傾向のことで、健康や金銭の管理などに問題を生じやすいことが知られています。現在、得られた知見をより深く検討していますが、最終的には被災地域の方々に寄り添ったサポートの仕方を考え、ひいては地域のよりよい復興に貢献したいと考えています。
NGOや役場と連携しながら現地に出向いてデータを積み重ね、分析し、その過程で「こうではないか?」と仮説を立てて、それをさらにデータで厳密に検証していくわけですが、私がテーマとする被災地も発展途上国の貧困地域も、実にさまざまな問題を抱えていることが分かります。研究者の立場でできることは限られているかもしれませんが、人々が抱えている問題の解決に少しでも役立つよう、長期にコミットしていくのが不可欠だと考えます。
これからも、社会問題――とくに自然災害や貧困問題の根本にあたるような質の高い科学的論拠、「エビデンス」をつくり続け、「国際公共財」として誰しもが使える形にしていきたいと思っています。
関連リンク東京大学大学院経済学研究科・経済学部
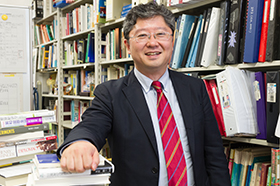 | 前編のインタビューから -開発経済学とは? |

























