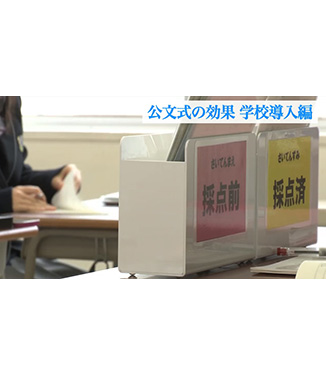労働経済学とは「働く世界」を分析する学問
 |
私が専門とする「労働経済学」は、失業までも含めて「働く」という世界、つまり社会での人の動きを分析する、経済学の中でも「人」を扱う学問です。そのなかで最近力を入れているのが「人事の経済学」と「教育の経済学」です。
そもそも「経済学」とは、モノについている値段の決定メカニズムと、それを人為的に変える、いわば「環境を変える」ことで結果がどう変わるかを研究する学問です。
「人事の経済学」とは人の労働の値段、つまりある人の給料を上げることによって、皆よく働くようになるのかどうか、といったことを研究する学問です。「皆よく働くようになろう」といった意識への働きかけが先にくるのではなく、労働価格という環境を操作することで、うまくいくようにする。社会や組織がつける労働の価値を変えることで、人の動きが変わっていく側面を重視し、それをどう変えたらよい方向に導けるのかを研究しています。
「教育の経済学」も同様で、教育の環境を変えることで、人がどう変わっていくかを研究しています。たとえば最近では公文式を導入している学校における公文式学習の教育効果測定に携わりました。公文式学習を外から与えることによって、すなわち環境を変えることによって生徒の態度や意欲がどう変化したか、さらにはそれが能力や成績にどう影響を及ぼしたか、といった観点で研究をしたのです。
教育によって個人がどう成長するかということは、その先の就職や人生にも影響を及ぼします。ところが学問的には教育学と労働経済学は離れています。教育学では、学校教育から労働市場に入るところまでは気にしますが、そこから先は気にしません。一方、労働経済学は、学校が労働市場に送り出してきた人材を元に議論をしますが、彼らが具体的にどんな教育を受けてきたのかは意識の外です。
しかし学校に行く理由は、その後社会に出て幸福に生きていくためであり、学校教育とその先を考えることは本来切り離せません。その意味で、私の中では教育学と労働経済学は一本につながっていて垣根がありません。最近は、それらを総合的に捉えて研究することに特に注力しています。
環境の変化に大きな影響を受けた小中学生時代
 |
私は香川県の詫間町(たくまちょう)という漁師町に生まれました。当時三階建ての建物は学校くらいしかなく、信号機も町にひとつしかない。電話をかけるとカエルの声がうるさいと言われる。そんな自然に囲まれた環境で育ちました。
出生時、私は未熟児で逆子だったそうで、母は「この子は20歳まで生きられないかも」と思ったそうです。小学4年生くらいまでは、からだも小さく病弱で、季節の変わり目には必ず風邪を引いて学校を休むような子でした。目立たず、運動も勉強もできない。落ち着きがない。忘れ物も多い。学校に行ってランドセルを開けると中はからっぽ、なんてこともしょっちゅうで、ほかの子ができることができなかったりしたので、母は心配したでしょうね。小学校は小高い丘にあったのですが、私は全然授業を聞かずに、よく窓の外を見ていたので、授業中に火事を発見したことが2、3回あるくらいです。
小学校のころ、母は世界の名作文学全集と百科事典を買い与えてくれていました。これがいまでも母に感謝していることの1つです。楽しくて時間を忘れて読んでいましたね。いま思えば、これらの本を読んで得た知識は、私の中にしみ込んでいったのでしょう。中学に入って最初のテストで、270人中5番になったんです。このとき「自分はできるかもしれない」と自信が生まれたというか、初めて自分にも肯定できる部分がある、と自分を見直すことができました。これが、私が物事に少しずつ積極的になっていった転機だったと思います。
とはいえ、他の地域からも生徒が集まる地元の中学校はとても荒れていました。父親が漁師で不在がちな家が多かったためか、年頃の子どもたちはやりたい放題。学校では、そんな生徒たちを先生が力ずくで押さえつけようとするような感じでした。大きなギャップを感じました。皆、勉強もせず、人生を真面目に考えることもない。穏やかな小学生時代を送っていた私は、衝撃を受けながらその教育のあり方に疑問を持ち、将来は学校の先生になり教育を変えたいと思っていました。
「どんな人間になりたいか」に葛藤し続けた高校時代
 |
中学ではよい成績をとっていた私は、高校は地域の進学校に進みました。エリート揃いの学校で、中学とは環境が180度変わり、これまた大きなショックを受けました。一番衝撃を受けたのは、授業中に先生から当てられた子が間違えたら、それをクスクス笑う生徒がいて、笑った子を先生が注意もせずに許していることでした。それまでの自分の価値観からすると、「笑うのは失礼だ」と許されないことです。それなのに、高校の先生は許している。そのことに違和感を覚えたと同時に、「そんな世界があるんだ」と、自分が知らない世界があることを認識しました。
中学時代は吹奏楽をしていた私ですが、進学校では部活動も中途半端になると思い、続けませんでした。ところが、エリートの生徒たちは音楽も運動もやりながら受験勉強をしていく。うまく生きていく姿を見せつけられたのもショックで、高校では、小学生だった頃の目立たない生徒に戻った感覚でした。
この頃は、「中学までの自分」と、「うまい生き方をするエリートの中での自分」とで、葛藤があり、その整理がつけられませんでした。ただ、「世の中には違うものがある。整理できないものがたくさんある。それはなぜなのか」という疑問が積み重なっていきました。
そうした疑問を抱えていたこともあって、進路を決めるにあたっては、いまでいう社会学的な分野に気持ちが向いていました。先生に相談すると、当時は社会学系の学部は少なかったこともあり、文系ということで法学部か経済学部を勧められました。そこで、式や図が出てくるほうがおもしろそうだと、経済学部を希望することにしたのです。ただ、当時抱えていた、「どういう人間になりたいか」という葛藤と大学進学や学部選びは、まったくつながっていませんでした。
関連リンク大阪大学COデザインセンター
 | 後編のインタビューから -積み重なった疑問がなかなか解けずに苦悩した大学・大学院時代 |