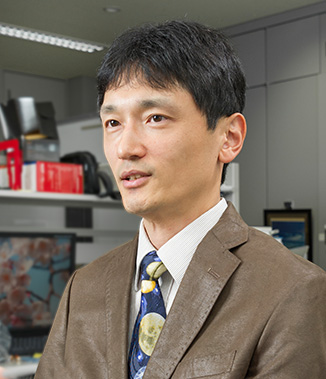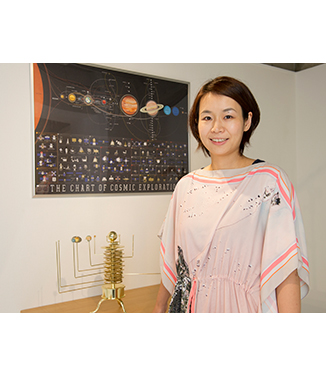自然に「ゴール」はない ゴールは人間が決めるもの

はるかかなたにあって手に取ることはできない「星」ですが、テクノロジーの進化は、より天文学を私たちに近づけてくれています。みなさん、昼間に星を見ようとは考えないでしょう? でも実際には、昼間の空にも星はあり、星座が並んでいるんですよ。明るい太陽光があるので目では見えないだけなんです。もちろん、昔は昼間に星を見ることはできなかった。その後、望遠鏡によって宇宙が観測され出したのは1610年のことですが、それでも昼間の星を見ることはできませんでした。昼間には、どこに星があるのかわからないですからね。それが、いまは望遠鏡の駆動モーターをコントロールするパソコン画面をクリックさえすれば、望遠鏡が自動的に動いて昼間でも星をとらえることができるようになりました。
ただ、どこまで技術が進歩しても、星に手が「届いた」という感覚はありません。ひとつわかると、ひとつわからないことが出てくる。宇宙の謎のすべてが解明されることはないのかもしれませんね。例えば医療であれば病気を治すというゴールがありますが、天文学のゴールはとても遠く、それこそ不思議が無限に広がっているような気がします。
私が書いた一冊『なぜ、めい王星は惑星じゃないの?』(くもん出版)では、「いまの大人たちが子どものころは9個だった惑星が、めい王星が惑星ではなくなって8個になった」ことをテーマにしています。それは人間が決めたルールに則って「惑星は8個」と規定されたということなんです。大事なのは、そのルールが果たして正しいのか、つねに考えることです。あくまでも現在ある情報や知識や経験を基にしてそう規定しただけで、100年後には「当時の研究者は、惑星が8個なんてバカなことを決めたものだな」と言われるかもしれません。
つまり、宇宙や天文学に「ゴール」はないような気がしています。地元のFMラジオ局の私の番組には、子どもたちからたくさんの質問が寄せられます。答えるのが難しい質問のひとつは、「宇宙は、どうしてはじまったのですか?」というもの。私の答えは「正直、私にもわからないのです。もし君が将来研究者となって答えが見つかったら、最初に私にこっそり教えてね」(笑)。わからないことはわからないと言えることも大切だと感じています。
10年後の自分のために、いま何をやるべきか
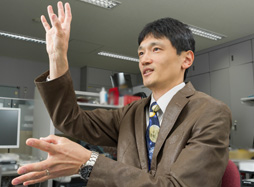
先日、私の研究室で修士課程の研究をしたいという大学生が私のところにきました。彼は、「宇宙という言葉がつく職業に就職したい」と言っていました。でも多くの学生は、宇宙飛行士とか、人工衛星を作るメーカーとか、それくらいの職種しか思いつかないようです。例えば、科学館や博物館で宇宙のことを伝えたり、中学や高校の理科の先生になって授業で宇宙を教えたりする仕事も考えれば、結構あるんですよ。現役の大学生たちも、気づかないことが多いと言えます。
いまの世の中は、“先に知った者勝ち・情報を持っている者の勝ち”というところがあると思います。どこに辿り着くかは分からないけれど、色々な引き出しを持って、広くアンテナを張って行動し続けることが大事だと思います。“得意技”をたくさん持っていれば、いざというときに使えるものです。たくさんの引き出しを持つことは、回り道のようで回り道ではないと言えます。
子どもたちに対しては、「大きくなったら何になるの?」という問いかけもとても大切だと感じています。しかも、それを継続的に聞く。まだ子どもなのだから、なりたいものがどんどん変わってもいいわけです。実際、うちの上の子はずっと宇宙飛行士になりたいと言っていて小学4年のいまも変わっていませんが、小学2年の下の子はハワイに住んでいたころはパイロット、日本に帰ってきて自転車に乗れるようになったら自転車屋、その次は大工で、いまは建築士です。
ただ、なりたいものが変わるたびに、親として「ヒント」を与えてあげるといいと思います。たとえば、いまなら下の子の「どうしたら建築士になれるのか?」という問いに対して、すべての答えではないけれど、インターネットで建築士の試験問題を見せたり(まったくわからないと無視されましたが・笑)、私の友人の建築士の話をしたりしています。親として、子どもの夢に制限をしないで、将来につながるきっかけと、それを考え続けるための情報を与えていきたいと思います。
「将来」という言葉の範囲が広すぎるなら、「10年後」で考えてみるといいでしょう。それは大人も同じです。「10年後の夢・目標」と考えるとイメージが具体的になります。「10年後にこうなっていたいな、こうしていたいな」と思い描くことで、そのときまでに何をやればよいのか、何をやるべきなのかが自動的に見えてくると思うのです。
科学の進歩は人間が決めたルールを変える

最近、取り組みだしたプロジェクトが地球の周りを回る「人工衛星の開発」です。これまでも、有名になった「はやぶさ」プロジェクトなどに関わってきましたが、衛星開発って本当に大変なんです。車なら開発して、作って、使ってもらって、問題があれば改善して…ということができますが、人工衛星は開発して作ったら、使ってみて改善するということができないんです。最初で最後のひとつが完成品であり、それで成功するか失敗するか、という世界になります。私の10年後のゴールは、開発に携わっている人工衛星が成功して目的を達成してくれるようにすることですね。
私はいま、地元の小学校や幼稚園に出かけて、子どもたちに宇宙の話をしています。これまでに私の話を聞いた何百人何千人というなかで、大人になるまで宇宙に興味を持っていてくれるのは、もしかしたらほんのひと握りの人かもしれない。でも、そのきっかけがなければそういう子どもはゼロになる可能性もあります。だから私のもうひとつの仕事は、子どもたちが宇宙に興味を持つきっかけを作ることだと感じています。
私の人生を支えてくれた最初のきっかけは、5歳のときに買ってもらった一冊の図鑑でした。世の中がどれだけデジタルになっても、「紙」や「本」の持つ特別な価値は消えることはないと思います。形として残っていると、いつでも見返すことができますよね。私のこの図鑑には、めい王星は惑星として載っています。手元に図鑑という形で見られるからこそ、それを通して科学の進歩を楽しむことができる。うちの子どもたちを見ていると、公文式学習も同じだと思います。やってきた教材がさわれる形として残っていると、きっと将来に向けた自信になると思うんです。
紙に記されたその当時の「真実」は、つねに書き換えられていきます。科学の進歩はそれまで人間が決めたルールをどんどん変えていくのです。私の本にも、「科学は変わるものです」とはっきり書いています。「この本に書いてあることが嘘になったら、それは科学が進歩したということ」と、私の間違いではないですからね、と書いている本は他にはないかもしれませんね(笑)。だから、子どもたちが、私の本に書いてあることを将来書き換えてくれる、その役割を担ってくれたら、それこそ最高の喜びですね。
 | 前編のインタビューから – 天文学との出会いは、一冊の図鑑だった |