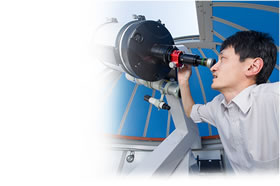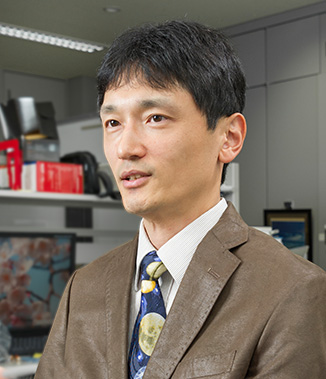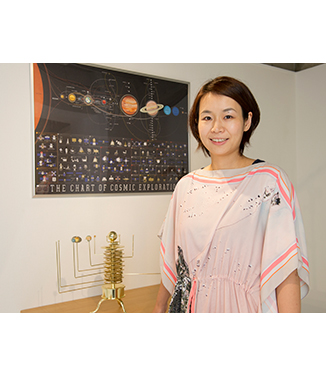天文の世界を“不思議なもの”と思い続けた子どものころ
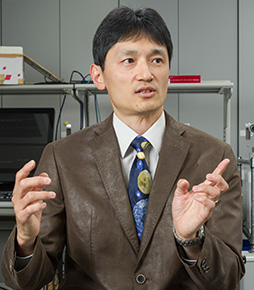
私の仕事は天文学を研究することです。星空は、国も地域も年齢も、道具を持っている・いないにも関係なく誰もが楽しめます。どこの国から眺めても、夏の大三角やオリオン座はあの形。星座はメソポタミア文明が起源と言われていますから、数千年前ですね。天文学は最も古い学問の一つでもあります。記録を残す以前から、人間は星の輝きや動きに注目していました。
数多くのアマチュアが活躍しているという点も、他の学問との違いと言えるでしょう。星空を見上げて「キレイだな」と思うだけでもいいし、道具を使って本格的に観測して深く追求してもいい。門戸が広い天文学は、学問であり文化だと私は思っています。
私と天文学の出会いは5歳のころ、近所の書店で両親が買ってくれた『宇宙』という図鑑です。これを読んだときに感じた不思議さは、いまでも強烈に憶えています。「月は地球の四分の一の大きさか」とか、「でも太陽に比べると、地球はこんなに小さいのか」とか。“わからないな、すごいな、不思議だな”という思いが興味の出発点でした。
また、実家から歩いて5分くらいのところにプラネタリウムを併設した科学施設があったんです。図鑑を見るだけでなく、近所の施設に足を運べたことも大きかったですね。もう一つの実体験としては、小学1年生のときから毎年夏に父親に連れて行ってもらったキャンプがあります。丸い天井に写し出されたプラネタリウムの人工の星とは違って、真っ暗なキャンプ場で見た星々は立体的に見えたんですよ。そのときの怖さに近い驚きを覚えています。
小学生時代の私と天文学との接点は、図鑑とプラネタリウムとキャンプ、この3つがミックスしている状態でした。宇宙の世界を“身近だけれど、手に取れない、すごく不思議なもの”として思い続けていられる環境で過ごせたことは、私にとって幸福なことだったと思います。
たくさんの引き出しを持つことが有利な時代
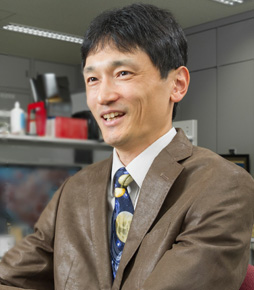
ただ、小さいころからずっと星のことだけに携わってここまできたかといえば、決してそうではありませんでした。公文をはじめ、色々な習い事をやっていました。習字もやったし、学校のクラブ活動とは別に、バスケットボールやソフトボールもやっていました。まさに、つまみ食いですね(笑)。
「ひとつのことに集中する」という考え方もあるとは思いますが、私は色々なことをやるのが楽しかった。趣味の釣りも徹底的に自分で研究しましたね。いまになって思うのは、たとえ一つひとつに取り組んだ時期は短くても、子どものころに色々とやっていたことは決して無駄ではなかったなということです。大人になってからでは短期間で習得できないようなことも、子ども時代の持ち前の吸収力で身につけられることってあると思うんです。私の場合、子ども時代に独学で弾き始めたギターやドラムはいまでもできるので、うちの子どもたちもびっくりしています。
それはおそらく仕事も同じではないでしょうか。ひとつのことだけを10年、20年やってきました、というのが強みとなる職業もありますよね。例えば、スポーツ選手とか、アーティストとか。ただし、それを本当に仕事にできるのは、ごく限られた人たちだけと言えます。
それに対して、取り組んだ時間は短かったけれど、あれもこれもやったという経験を持つ人は、そうではない人に比べて、物事を解決できるキーを多く持っていると言うことができるのではないでしょうか。昔と違って、いまはマルチな人材を求める時代ですから、子どもたちに必要なのは、たくさんの“引き出し”なのではないかと思います。
ずっとひとつのことをやり続けてきた人には、大きな引き出しがひとつ。一方、色々なことをやってきた人には、小さいけれどたくさんの引き出しがある。人生の岐路に立たされたとき、どちらかといったら多くの引き出しを持っている人の方が有利になる時代だと思うんです。
未知のものに挑戦しようと思ったとき、引き出しの多い人は解決の手助けとなるものが自分の引き出しのどこかに入っている可能性が高いわけですよ。「それって、前にやったあれに近いかもしれない」と考えることができれば、より“きっかけ”をつかみやすいというか。幸い私の両親は「何でもやってみたらいい」と言ってくれるタイプだったので、振り返ってみればそれは本当にありがたかったです。
引き出しの多さが幸いしてつかんだ未来

私がいまこの職業に就いているのは、天文学や宇宙の不思議と出会った当時の気持ちがずっとどこかに残っていたからでしょう。大学院で太陽系の研究していた当時は、昼ごろに研究室に来て、夜中ずっと研究し、明け方に帰るという生活を送っていました。いまの大学院生たちにも共通の気持ちだと思いますが、そのころは研究所や大学の研究職に就職できるかどうかわからないので、不安でいっぱいでした。
ある日の夜中にふと研究室で、あの図鑑―― 5歳のときに買ってもらった図鑑『宇宙』をパラパラとめくっていたんです。そのとき、子どものころは読むことがなかったモノクロページで手が止まりました。そこには国立天文台の航空写真が載っていたんですが、私はそのときまさにその写真に写る建物にいたんですよ。「あっ、いま、自分はここにいる!」と夜中に叫んでしまいました。
そのときは、運命みたいなものを感じましたね。ただ、だからといってそれで研究職に就ける確約はありません。どの研究分野も、博士課程を修了してからしばらくの間は短い期間の雇用契約で仕事をする人が多いのが実情です。私は幸い、博士号を取得してすぐ期限のない研究職に就くことができました。その理由のひとつは、先ほどの「引き出し」がたくさんあったからだと思います。
天文学も他の学問も、大まかに二種類の研究に分かれています。ひとつはコンピュータを使う理論的なもの。もうひとつは実験や観測です。私は学生のころから欲張って両方に取り組んでいました。また、自分の体験や研究を他の人に話す機会をもらって、人に話す楽しさも感じていました。たぶんそれらのことが、求められていた人材としてフィットしたのでしょう。結果的に、国立天文台ハワイ観測所の広報担当研究員という仕事につながったのだと思います。
関連リンク
情報通信研究機構 鹿島宇宙技術センター
 | 後編のインタビューから – 天文学にゴールはない。ゴールは人間が決めるもの |