夢は「魚博士になるぞ」だった少年時代

生まれ育ったのは静岡県富士市田子の浦で、サラリーマンの父とパート勤めの母、僕と弟と妹という一家でした。小学校に行く前に早朝から駿河湾で釣りをして、釣り上げた魚を持って帰り、夕食はそれをさばいて家族で食べるのが日課でした。小学校入学のときから剣道もやっていましたが、子どものころの夢は「魚博士になること」でした。世界中の魚を釣ったり、静岡の大学の海洋学部で魚の研究をしたいと思っていました。お風呂に入ると湯船につかって100種類の魚の名前を言う練習をしたり(笑)、水族館でそれまで見たことのない魚が目に入るとデータに残したり、釣った魚が10センチのサバであっても、魚拓にとって記録に残したりしていました。今でも魚釣りが大好きで、取材先に海や湖があると釣竿とリールを持っていきます。
性格的には穏やかで、釣りをしながら禅問答のような時間を過ごし、ひとりの時間が小さいころから好きでしたね。中学では生徒会長を務めましたが、決して自分からというわけではなく、気が付いたらそうなっていました。かといって優秀な生徒だったわけではなく、成績はまん中より下くらいでした。高校受験も「ここはやめたほうがいい」と進路指導の先生にいつも言われていました。当時は受験を失敗すると当人だけの問題ではなく、地域の人たちの目というのも非常に厳しいものがありました。
それでも県立高校を受けると決めたのは、剣道をやっていたからかもしれません。剣道の稽古はとても厳しく、稽古日になると気持ちが動揺するほどでした。でもそれを続けてきたことで、こうした選択を迫られたとき、良い意味で“勝負師”になれたんです。「ダメだったらダメでいい」と腹をくくり、受験勉強も真剣にしました。結果、高校には無事合格しましたが、合否に関わらず、挑戦してよかったと思います。
今も、自分が納得したことなら、入念に準備をして挑戦するようにしています。すると道が拓けたり、いろんな人との出会いがある。そして、その先にまた挑戦がある。目の前に壁があるとき、それを超える方法もあれば、穴をあけてトンネルを作る方法も、右側からすっとS字型に入って行く方法もある。挑戦すればするほどいろんな選択肢が見えてきます。これからも、いろいろ試していきたいです。
人生の師に学んだ「ていねいに取り組めば、必ず答えは見つかる」
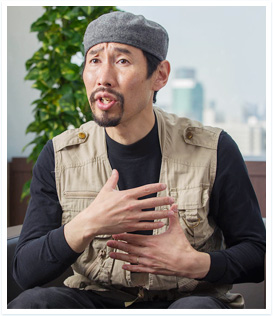
両親も穏やかで、穏やかな風の吹く家でしたから、僕がフォトジャーナリストになると話したときには大反対を受けました。そこで、両親と約束をしました。戦場に飛び込んだときでも常に近くにいる感覚を持てるよう、必ず毎日、何度でも電話をかけること、手紙を書くこと。21世紀に入ってからは、メールを打つこと。そして現場で撮った写真は必ず形に残るよう、発表すること。これを実行しながら、今日までカメラマンを続けています。日本にいるときも、両親には毎日電話をかけていますね。電話一本で、気持ちがスーッとつながるし、大きな心の支えになるんです。実はこれ、外国の友人たちから学んだことなんです。
両親以外で僕にとって大きな存在といえば、公文の先生です。公文の教室には小学校から高校を卒業するまで通っていました。先生はいつも僕に、「字を書くときには、ゆっくりでもいい、ていねいに書くのですよ」と言葉をかけてくださいました。ていねいに名前を書き、数字を書き、解答していく。ゆっくり、ていねいに、物を見て行けば、必ず答えは見えてくるのだということを、シンプルに教えてくださった気がします。素早い計算が必要なときもありますが、ていねいに解けば、知りたいことが滲みだしてくるのです。
それはもしかしたら、僕の話し方にも影響を与えているかもしれません。小さいころからゆっくり話す方ではありましたが、外国に飛び出したとき、言葉の分からない国で意思を伝えるときには、単語をゆっくり相手に伝えていくことで、どの地域の人たちも、話を理解してくれたんです。公文教室での先生の生徒への接し方、言葉のやりとり、すべてが好きで、先生は、僕にとって人生の師だと思っています。
公文といえば、先日、あるテレビ局のインドネシア取材で現地の公文教室を訪れ、感動しました。教室に入ってみると、子どもたちはこちらに背を向けて、一心不乱に机に向かっていたんですね。その背中から集中力が、やる気がむんむんと伝わってきたんです。そしてそのかたわらでは、先生が日本と同じように分からない生徒に教えてあげていたり、赤ペンをプリントにすべらせて採点していました。スーッ、100、スーッ、100と赤ペンをすべらせる様子も、プリントの匂いも同じで、懐かしく、嬉しかったです。子どもたちの一所懸命な姿に、胸が熱くなりました。
日本の若者には大きな可能性がある

日本の子どもたちは勉強に部活、テレビゲームと忙しさに追われている毎日を送っていると思いますが、機会があればぜひ試してほしいことがあります。それは、どんどん外国に飛び出してみること。世界中の人たちの声を聞き、たくさんの人に出会ってほしいです。驚きもあれば、さまざまなことが降りかかってもくるでしょう。大人になってそういったことが、必ず、勉強、仕事、スポーツなどの大きな支えや力になってくれると思います。外国に行くチャンスがなくても、もし街中で外国の人に出会ったり、ふれあえる機会があれば、どんどん世界の声を聞いてみてください。
若者のなかには、ネットやテレビで映像が見られるから、わざわざ外国に行く必要性を感じない、という人もいるかもしれません。けれど、人間はネットというバーチャルな世界に満足しているようでいて、やっぱりお腹がすくとごはんを食べて、冷たさや熱さや美味しさを感じたがる。実は人間は究極のアナログ的存在で、デジタル文化を使ってアナログしたいという本音があると思います。そのアナログの究極が、旅行に出ること。誰しも、旅に出ると最初にそこの特産グルメを食べて大満足し、それをネットにアップしています。聞いた、触れた、食べたことを、ネットという媒体を利用して、よりリアルにアナログに感じたいのではないでしょうか。若者たちはこのネットのスピード感を吸収できているので、それをもって究極のアナログを感じることができると思います。
ネットの力を理解している若者たちは、世界中で必要とされています。そこでは国籍や民族は一切関係ありません。シリコンバレーでもインドのバンガロールでも、ネットの技術をもっていれば誰でも歓迎されます。部屋をなかなか出られない引きこもりの若者でも、ネットの力を極限まで高めれば、世界に出ることは十分できる。世界が日本の若者たちを必要としていると思います。僕は日本の若者たち、「いける!」と思います。心の底から応援していますね。
関連リンク
渡部陽一オフィシャルサイト
























