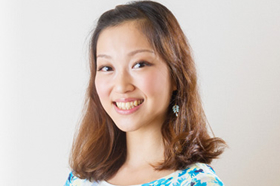なかなか慣れなかった「日本のしきたり」

ドイツに留学していたときには、そのまま海外でプロのバレエダンサーになろうと思っていたのですが、私が入団を希望したバレエ団には身長の規定もあり、そのときの私には条件を満たすことができず、厳しい現実をつきつけられました。
それでもいくつかオーディションを受けていた、スクール最終学年のときでした。年末に日本へ里帰りをしたおりに、「そうだ、プロを目指すきっかけになった熊川さんのバレエ団を受けてみたい」と思ったのです。幸運にも合格することができ、帰国して19歳でKバレエカンパニーに入団したのですが、それからも順風満帆からはほど遠い日々が続きました。
ドイツのバレエスクールでは、先生方はとても厳しかったけれど、それだけに同期がみんな「がんばろう!」と結束していたのですが、Kバレエでは私が一番年下で、同期もいない。話し相手や相談する人もいないという状態でした。もちろん、私から話しかければ相談にものってくれたのでしょうが、スクール時代との環境の違いにも馴染めず、孤独感が募る毎日を過ごしていた時期もあります。
日本の「しきたり」的なことにもなかなか慣れませんでしたね。海外ではあまり意識されないように感じますが、日本では会社でもスポーツや芸能の世界、日常生活でも同じだと思うのですが、先輩・後輩の上下関係が大切にされますよね。また、ドイツ語や英語には敬語がないので、ふと気がついたら先輩に敬語を使っていない!という失敗をして叱られ、落ち込み、委縮してしまう。そのくり返しでした。
ダンサーとしても、入団当時の自分としては一生懸命やっているつもりでも、芸術監督である熊川さんからは何度も甘い点を指摘されていました。今になって思えば全然努力が足りていなかったとわかるのですが、一時は「ここは自分には向いていないんじゃないか?」と悩み、やめてしまおうか、そんなふうに考えてしまったこともありました。
カンパニーを代表するダンサーになって、日本のバレエが置かれた状況を変えるのが夢
 |
| 『ドン・キホーテ』 |
退団せずに踏みとどまれたのは、やっぱり「バレエが好き」という思いがあったからです。自分を支えてくれた両親に、この日本で、私の舞台を観て欲しいという思いもありました。それとともに、「まだ自分は何も達成できていないのに、途中であきらめるのは嫌だ。ここまでやったと自覚できてから次のことをすべきだ」という信念を持っていました。
「なんとかやっていけそうだ」という手応えをつかめるようになったのは、ごく最近のことです。今年1月にソリスト(バレエ団内の階級のひとつ)に昇格したのですが、その前月の稽古で、これまでにないくらいの限界まで踊りこんだことで、それまで熊川さんに言い続けられた、「まだ何かが足りない」という言葉の意味がよくわかったんです。それから、理想の形をいつも思い描きながら踊ることができるようになってきました。
最近は大きな役をいただくことが増えてきて、年末には『くるみ割り人形』で初めて主演を務めさせていただきます。それだけプレッシャーも責任もひしひしと感じるようになり、自分は失敗してはいけない立場なんだという自覚も強くなりましたね。そのためにはやはり練習を重ねるしかないので、より練習に打ち込めるようになりました。
私は演目のストーリーに入り込みやすいタイプなので、表現力を要する役が得意なのかもしれません。次回作は『カルメン』なのですが、貞淑な婚約者のミカエラと、カルメンの親友で破天荒な女の子の二役を演じます。まったく異なるキャラクターをどう演じ分けようかとすごく楽しみです。
これからも持ち前の「あきらめない心」を忘れず、お客様からの喝采を浴びながら踊る喜びをもっと増やしていきたいです。「Kバレエカンパニーで“センター”と言えば浅野さん」と言われるようになるのが夢ですね。夢のまた夢ですが。
Kバレエは熊川さんが、日本のバレエの現況を変えたいと考えて創設したバレエ団です。日本も海外のように、ふつうに映画を観に行くような気軽さでバレエを観に来てくださるような社会になるよう、私も努力していきたいです。言葉がなく、音楽と踊りだけでその世界が表現されるバレエの魅力を、ぜひ多くの人に味わっていただければと思います。
公文で培った基礎があったからこそ、今の自分がある

私にとって公文でとくに役立ったのは、英語でした。もし公文で学んでいなかったら、もちろん英語は話せなかったし、留学しようなんて思わなかったと思います。今ふり返るとちょっと大胆な考えだったと思いますが、小学6年で英検3級をとって、「海外に行っても英語は話せるだろう」という自信のようなものもありました。
ドイツのバレエスクールでは、生徒も先生方も国際色豊かだったので、必然的にドイツ語と英語を話す必要がありましたが、公文でリスニングに慣れていたからか、発音を真似るのも得意でした。日本人が周りにまったくいなくて助けてくれる人もいなかったこともあり、必要に迫られる場面も多く、話せるようになったのは比較的早かったと思います。
といっても最初の3か月くらいは「ドイツ語が全然分からない…どうしよう…」と困惑の毎日。でも、そのまた3か月後には自分でもびっくりするほど上達していました。単語もたくさん憶えましたが、とにかく友だちと言葉でコミュニケーションするようにしました。理解できないときは、ドイツ語のフレーズや単語を英語に直してもらって、ということをくり返しているうちに両方話せるようになっていたんですね。こういうときにも、人見知りしない性格がプラスになっていたのかもしれません。
両親への感謝を胸に、自分も子どもたちの“夢の後押し”をしたい
 |
| 2014年12月、Kバレエカンパニー『くるみ割り人形』にマリー姫役で初主演予定。 公演期間:2014年12月20-26日(浅野さん主演は20日ソワレと23日マチネ)、会場:赤坂ACTシアター |
両親はつねに私の意思を尊重し、応援してくれています。バレエ仲間では、留学を望んでもご両親に許してもらえなかった友だちもいましたので、私の場合はやりたいことをさせてもらっているのでとても感謝しています。でも別の見方をすると、自分で決めたことなので後にはひけない。頑張るしかないんですよね。両親としては「自分が納得いくまでやる」ということを大切にしてくれているのだと思います。
最近、Kバレエスクールで子どもたちに講師の立場で指導をするようになりました。これが自分にとっても大きな学びになっています。バレエでは、この筋肉をこう使うからこう見えるというような理論と実践が体系化されています。これまでは、あまりそういったことを細かく意識せずに踊っていたんだと思います。しかし、子どもたちに説明するにあたって、まず自分の姿勢や動きを見直す必要がでてきます。そうすると、自分の体の動かし方も以前とは変わってくるんですね。
まず教える側の私が、癖のない、正しい姿勢と動きをしなければいけないので、生徒と同じくらい、私も初心にかえって学び直しています。子どもたちを指導するということが、いかに自分自身の成長につながっているかを実感できます。その感謝の気持ちもこめて、子どもたちが将来プロになって「こうなりたい」と思える夢や目標が持てるよう、全力でサポートしていきたいですね。
講師をして興味深いことにも気づきました。どういう子がとくに上達するかが分かるようになったのです。一言で表現すれば「まっすぐな子」。いま何ができる・できないという技術的なことよりも、「できるようになりたい」という意思がポイントだと思います。いまはできなくても、できるようになろうと必死に頑張ってる子は、教える側も一生懸命応援したくなる、もっと成長して欲しいと思う。そういう意味で、くらいついてきてくれる子には同じだけ返すことができます。
切磋琢磨という言葉がありますが、初めのうちはできるようになりたいという気持ちが薄い子でも、周りの子が伸びていくと「自分もがんばらなきゃ」と思うようで、やっぱり伸びていくんですね。自分のやりたいことも見つけられ、みんな顔が輝いてきます。まずはやりたいことを見つける。そして、あきらめない心でそれにくらいつく。バレエにとどまらず、どんな世界でもきっと大切なことではないかと思います。
関連リンク
Kバレエカンパニー
 |
前編のインタビューから – プロのバレエダンサーを目指すきっかけとなった小5のときに受けた衝撃とは? |