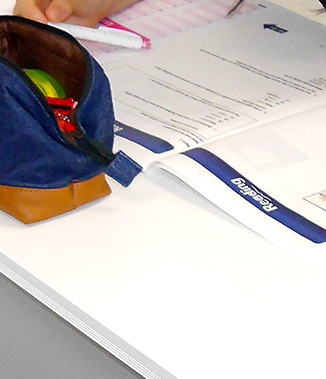TOEFL®など大規模英語テストを研究し、日本の英語教育に活かす
 |
私が専門とする応用言語学とは、ごく簡単にいえば、言語と学びの関係性を探求していく学問です。その中身は幅広く、「人はどのようにして言語を習得するのか」「言語をどのように教えればいいのか」「指導の効果はどのくらいあるのか」など、言語習得や指導法、測定・テストといったことが含まれています。その中で私がおもに研究しているのは、言語能力の測定に関する「言語テスト」の部分です。大学では、英語教員養成を担う学科に所属しているので、学部生・大学院生に、英語教育や指導におけるテストの役割、その使用などについて教えています。
「言語テスト」研究とはどのようなものか、私が関わってきた研究を例に説明しましょう。私は大規模英語テスト、とくにTOEFL®において、4技能(リーディング:読む、リスニング:聞く、スピーキング:話す、ライティング:書く)の関係性の研究に関わってきました。
TOEFL®とは、英語を母語としない人々の英語コミュニケーション能力を測るテストで、アメリカの非営利教育団体Educational Testing Service(ETS)により開発されました。現在、「TOEFL Primary®」「TOEFL Junior®」「TOEFL ITP®」「TOEFL iBT®」があります。
私はETSで研究員をしていたつながりで、現在もTOEFL®の研究を続けています。ちなみにETSには、TOEFL®に関するビジネスプランや研究内容に助言する「TOEFL Committee of Examiners」という外部専門家委員会があるのですが、そのメンバーとしてもアメリカでの定期的な会議に参加しています。
ETSに勤務していた時に行っていた研究の一つに、このTOEFL®のリーディングやリスニングの結果を見て、語彙や要点を理解するなど「とくにここができる」「ここができていない」という部分をデータ分析により取り出し ――これを「言語能力のプロファイリング(診断的な情報を取り出す)」といいますが、これを学習者へのフィードバックに活かせないかを検討するという研究があります。このような言語能力の診断と指導に関する研究テーマには、今も興味を持って取り組んでいます。
いま進めているのは「要約」の研究です。英文を読んで、その「要約を書く」あるいは「口頭で要約する」など、複数の技能を統合させる ――これは、Integrated Task(統合課題)といいますが、「要約の力」とはどういうものかを分析したり、要約をうまく指導していくための教材開発をしたりしています。
たとえば「あなたの家族について教えてください」というように自分の経験や意見の表現を求められる場合、その内容は自分しか知らないので、言葉にしづらい内容は避けることができます。しかし要約は、内容を読んで正確に理解し、それをうまく言葉にできないと良いものにはなりません。これは学問をするうえでは非常に大事なことです。なぜなら、理解が正確でなく、要点を押さえていなければ、学んだ内容から知識を得て、それを次の学びにつなげることができないからです。
Integrated Taskは、最近は英語の資格・検定試験でもよく取り上げられているので、今日的な研究といえます。学問をするうえだけでなく、日常生活の中でも聞いたり読んだりした内容が「要するに」何のことだったのかを他の人に口頭で伝えたり、書いたりすることはよくありますので、要約の力はいろんなところに応用ができます。現在やっている研究を通して、日本の英語学習者が英語力を伸ばしていく手助けをしていくことができればと考えています。
日本の英語教育で気になる「4技能のバランス」と「言語を使う経験」
 |
日本の英語教育で気になるのは、4技能をバランスよく身につけることがうまくいっていないことと、英語を使う経験の少なさです。教科書で「この場面ではこういう表現を使うんだよ」と、文法的な要素や道具は習い、ある程度の繰り返し学習をして理解を深めることは学校でもしていると思います。しかし、それをいろいろな状況、いろいろな文脈で使っていく経験が不足しています。考えなくても言葉が出るようになる(これを「自動化」=Automatizationといいます)まで、とにかくたくさん「言語を使う経験」をする必要がありますが、授業時間数も限られており、そのための時間が圧倒的に足りていません。
リーディングを例にして説明しましょう。たとえば「過去形」のチャプターであれば、教科書には過去形の文章がたくさん出てきます。それらを読むのはもちろんですが、それだけでなく、過去のできごとについてメールでやり取りしたり、友人と話したりと、聞いたり読んだり話したり書いたりする必要があります。書くにしても、手紙やメールなどさまざまなコミュニケーションがあり、そうしたコミュニケーションの中でいろんな形で出てこないと使えるようにはなりません。とはいえ、基礎となる文法や語彙を疎かにしてはいけませんから、そのバランスが難しいところです。
先にETSのテストとしてお伝えした「TOEFL Primary®」は小中学生を主な対象に、「TOEFL Junior®」は中高生を主な対象にした英語の運用能力を測定するテストですが、これで測ることができる「読む」「聞く」という2技能は、言語能力を育てるうえで非常に重要なものです。読んだり聞いたりすることで、「こういう時にはこういう言葉を使うんだな」など、知識が増え、それが自分が書いたり話したりするときのモデルとなるからです。ですから、“いいインプット”がないと、“いいアウトプット”ができないといえます。
じつは私がETS在職中は、この2つのテストはまだありませんでしたが、TOEFL®はかなり上のレベルから始まるので、当時から、根っこから育てるようなプログラムの必要性が議論されていました。基礎的なものからアカデミックな内容への橋渡し役として、意義があるプログラムとして機能していると思います。
また、「TOEFL Primary®」や「TOEFL Junior®」は熟達度を測るテストです。覚えたことがどれだけ定着したかをみる到達度のテストとは性質が異なります。言語の熟達度は言葉を使った情報処理をたくさんしないと目に見えて変化がみえませんから、目に見える形でスコアが上がるにはかなりの時間と労力を要します。スコアに一喜一憂せず受験結果を普段の勉強に生かしていただきたいです。
「知らない世界」に憧れ、通訳者を夢見て毎日英語を勉強
 |
私は両親をはじめ、親戚の多くが教員という教員一家に育ちました。だからなのか、自然と「教える」ことは好きになりましたが、じつは教員になるつもりはありませんでした。目指していたのは通訳者です。
子ども時代の私は好奇心の塊のような子で、知らないことを知りたい、やったことのないことをやってみたいと、水泳、ピアノ、吹奏楽、合唱、バスケットボールなど興味のあることは片っ端からやっていました。「知らない世界へ行ってみたい」と、海外にも憧れるようになりました。小学校6年生になったころ、中学で新たに習う英語も楽しみで「英語が上手になりたい。毎日英語を勉強しよう!」と決めました。
中学入学後は、「英語が上手になりたければ、とにかく毎日勉強しなさい」との先生の方針で、毎日1ページずつ、教科書の英語を音読しながらノートに書き写していました。ラジオの基礎英語も毎日聞いていました。そうして英語は得意教科となり、通訳者になろうと思い、高校時代には、国際会議通訳者だった方が開設された通訳塾にも通いました。
ところが進路については両親とは意見が合いませんでした。紆余曲折の末、大学は教育学部の中学校教員養成課程英語科へ進みました。教えることは好きでしたし、教員にならなくても何かにつながるだろうという気持ちもあったんです。一方で入学直後は、なかなかやる気が起きませんでした。
それが一変したのは、言語学のゼミでの恩師との出会いです。なぞなぞの論理や人間の言語知識に関する構造の話など、授業がとてもおもしろく、また言葉が好きだったこともあり、言語学が楽しくなりました。さらに学年が上がるにつれ、専門授業が増えていき、その課程で教材開発に目覚め、「中学の英語教師になろう」と思うようになりました。
 |
後編のインタビューから -大学院で出合った「言語テスト」という分野 |