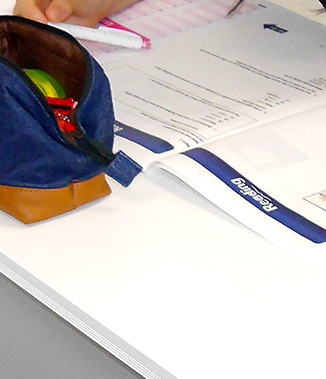「こんなにおもしろい分野があるのか!」と言語テストに熱中
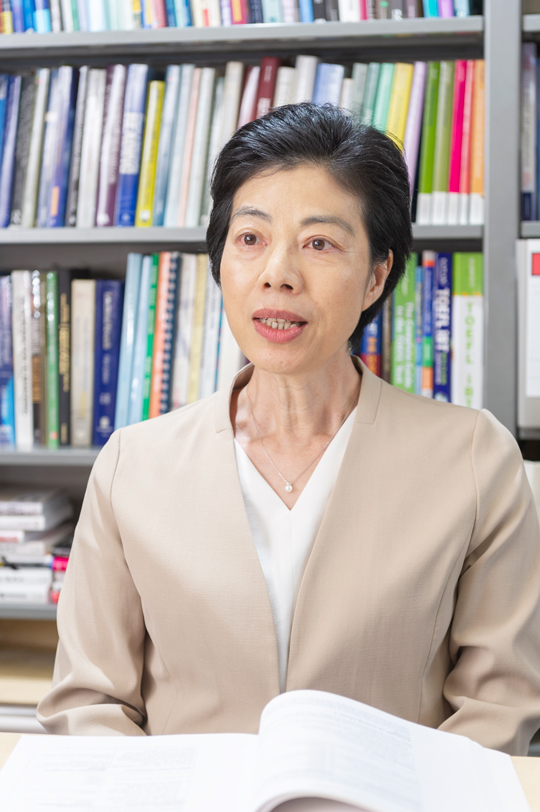 |
初めての海外経験は、大学4年次に交換留学生として1年間アメリカで過ごしたことです。アメリカの外国語教育がどうなっているのかを知りたくて、ドイツ語の授業もとりました。英語を使わず、ドイツ語だけの授業です。コミュニケーション活動主体の教え方で、ジェスチャーやイラストなどの視覚情報も交えることで、こんなにコミュニケーションがとれるんだと驚きましたね。中学校教員時代から今に至るまで、この方法を適宜授業に取り入れています。
大学卒業後は地元の熊本県立中学校の英語教員になりました。中学を選んだのは、英語を初めて学ぶ子どもたちに英語の楽しさを伝えたいと思ったからです。教えることも楽しかったのですが、まだまだ勉強が足りない、もっといい教師になりたいと考え、英語教授法に定評のあるイリノイ大学大学院で学ぶことにしました。
よりよい授業をやるために留学したので、帰国後はまた中学で教えるか、そうでなくても日本の英語教育に何らかの形で貢献できればと考えていました。ところが、大学院で「言語テスト」という分野に出合い、この研究を突き詰めたいと思うようになりました。当時日本では「言語テスト」を教えている大学は少なく、このような学問があるとは思ってもみませんでしたが、「こんなにおもしろい分野があるのか!」と衝撃を受けたのです。
言葉の仕組みそのものだけではなく、言葉をどれだけを学べているのかを測定し、さらにそれにより国の教育政策など、さまざまなことにテストが影響を与えている点に興味をそそられました。担当教授は、アフリカで教育政策や言語テストに関わった経験をお持ちで、「言語テスト」が、いかに現地の人の生活にとって大事なものか、いかに教育政策に影響するかといった話をしてくださり、「私もそんな研究をしたい」と思うようになったのです。
一度帰国し、昭和女子大学で助手として研究を続けましたが、まだまだ勉強が足りないと感じたんです。それで、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の応用言語学博士課程に進みます。同大の「言語テスト」の第一人者、ライル・F・バックマン先生に師事したいと思ったからです。念願かなって入学でき、博士号を取得しました。卒業後は、研究をしっかり続けたいと思い、ETSに就職。5年半勤務し、「この知見を日本の英語教育に活かしたい」と、2009年に帰国して現在に至っています。
TOEFL®受験は合計10回!
自分で目標を決め、「基礎を大事に」コツコツと
 |
もともと勉強するのが好きだったこともありますが、素晴らしい恩師の方々との出会いに恵まれ、転機のときには導いてくださったことが、今の私につながっていると思います。加えて、「自分で目標を決めた」ことも、学びの推進力になっていたと思います。
こんなエピソードがあります。大学4年次のアメリカ留学の際、親からの支援は一切ありませんでした。父から「本当に行きたいのなら、自分でチャンスをつかんでこい」と言われ、自分で奨学金を探したんです。奨学金対象者に選ばれるには、TOEFL®の成績が重要視されるので、1年次から「しっかり勉強して、4年生になったら絶対に選ばれよう」と固く決めて勉強を続けました。その後大学院修士課程、博士課程に行く際も、また別の奨学金をいただく機会を得て、現地ではティーチング・アシスタントやリサーチ・アシスタントとして働き、博士号まで取得することができました。
そんなわけで、TOEFL®は大学1年の時から計10回受けています。ETSの同僚には「君は新しいビジネスモデルだ」と笑われてしまったくらいです。10回目は博士課程に行く直前でした。自分が在職していたから勧めるわけではありませんが、大規模テストの受験は進度チェックにも役立つと思います。長い時間をかけてではありましたが、少しずつ点数が上がっていくのも楽しみでした。
もともと小さいころから計画を立てて勉強し、伸びていくことを実感するのが好きだったんです。そんな私にとって、学びとは、知るよろこびを知り、進むよろこびを感じること。ほんのちょっとずつなんですが、「毎日これだけやっていれば1年でこんなにできるんだ」と思うとすごく楽しい。勉強の計画表を作り、終わったところから線で消していくのが好きでした。「ラクしてもいいことはないだろうな」ということも頭の中にありましたね。それこそ公文式学習と同じで、日々コツコツ、一歩一歩が大切だと思います。
「基礎を大事にすること」も心がけています。どんな学問でも、基本的なコンセプトが頭の中に入っていなくては応用はできません。研究で生まれる「AとBはつながるんじゃないか」という発想は、AとBがどういうことなのか、それぞれを深く知っていないと生まれません。一つひとつについてていねいな基礎からの積み上げがあるからこそ、次につながります。英語学習でも、「コミュニケーション能力は大事」といわれている中、話す練習、書く練習なども大切ですが、それだけでなく、単語や語彙を学ぶなど、地道な努力を疎かにしてはならないと思います。
心の垣根をつくらずに、相手を理解しようという気持ちをもとう
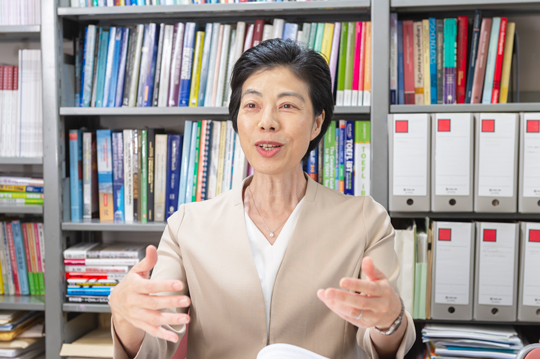 |
私はアメリカに計14年住んでいたので、その知見や経験を活かし、「表現するための英語力をつける」ためのテスト、学習方法、フィードバック方法などを整備していくのが今後の目標です。
保護者の方は、幼少時からの英語教育の是非について関心があるかもしれませんが、焦る必要はありません。早期教育は「英語に慣れる」メリットはあるかもしれませんが、私自身、中1からやり始めても困っていません。子どもの性格や学習スタイルは人それぞれなので、本人の興味に沿ってやっていければ良いと思います。
私の2人の子どもたちも、学習スタイルはまったく違います。上の子は他の子とおしゃべりしたり、ゲームやスポーツをするような英語のアフタースクールに通わせましたが、下の子はどちらかというとドリル派でした。親が無理強いせずに、本人が好きなようにやらせるのがいいのではないでしょうか。
ちなみにわが家で大切にしているのは「ありがとうと言う」ことです。アメリカにいたときの経験ですが、親はものを子どもに渡す際、無言で受け取ろうとする子には渡しませんでした。子に「Say thank you.(=ありがとうといいなさい)」と言い、子どもが「Thank you.」と言ったら「よく言えたね」とほめてから初めて渡すんです。我が家でも「ありがとう」と言わないと、ものは受け取れないことにしています。
語学の上達に必要なのは、月並みですが、「楽しみながら英語でコミュニケーションをとる」こと、「間違いを気にしないこと」でしょうか。大人になると「間違えたら恥ずかしい」となりがちですが、やはり様々な背景を持つ人と意思の疎通ができる楽しさを味わうことが一番。表現が不十分であっても、意味が通じるかどうかが重要で、語学力は経験とともについてきます。
英語に限らず、ある言語を知ることによって、今まで知らなかったことを知ることができるし、いろいろなところに仲間ができます。それはとても素敵なことです。そして、コミュニケーションのためには語学力はもちろん必要ですが、何より大切なのは「心に垣根をつくらないこと」。これは留学して実感しました。個性を認めるおおらかさ、どこの国の人であろうと心を開く。すると世界が広がります。基礎を大事にして、一歩一歩進みながら、学ぶ楽しさ、世界が広がる楽しさを、多くの方に味わってもらいたいと思います。
 |
前編のインタビューから -専門は英語テストにおける「言語能力のプロファイリング」 |