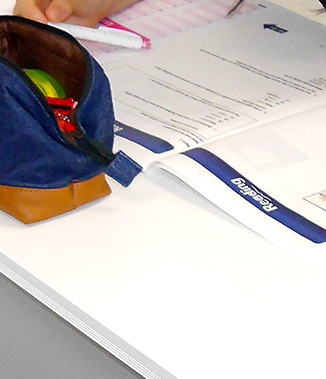指導法、教材、評価……
英語教育現場での課題解決に向けて研究中
 シンガポールの幼稚園 英語の音と綴りの学習 |
私の専門は、義務教育における英語教育の教授法や、子どもたちの言語習得に関することです。研究対象は主に日本ですが、アジアの子どもたちが母語とたとえば英語など2つの言語をどう学んでいくかというバイリンガル教育についても関心があり、日本との比較もしています。また、CEFR (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment)の日本語版である「CEFR-J」のプロジェクトにも関わり、Pre-A と A1 level(小学校レベル)を研究しています。その成果として『英語到達度指標CEFR-Jガイドブック』(大修館書店、投野由紀夫(編))等があります。
日本では、2011年度から小学校5・6年生での外国語活動が必修となりました。2020年度からはグローバル化に対応した英語教育改革が計画され、外国語活動は3・4年生からとなり、5・6年生では教科となります。教科になるので、教科書もあり、評価もされます。この改革では、「聞く」「話す」「読む」「書く」の4技能が求められるようになり、子どもにとっても教える側にとってもハードルが高くなるでしょう。
2018年4月からの2年間は移行期と位置づけられ、私はそれに伴う小・中の連携についても研究しています。現在、すでに小学校、あるいは先生によって指導方法に違いがあり、塾など学校外で学ぶ子とそうでない子の差などもあります。
また2020年の改革に向かうなか、大きく3つの課題があると思っています。まず指導法です。「聞く」「話す」能力はALT(外国語指導助手)のおかげもあり、少しずつ力がついてきたと感じますが、「読む」「書く」という文字を媒介にしたコミュニケーションの小学生に適した指導法は、まだ明確には確立されていません。
次に評価の問題です。これまでは、たとえば「積極的にコミュニケーションを図ろうとしている」などと曖昧さがありましたが、今後は学習の到達目標を「~することができる」という形で指標化し、英語を使って具体的に何ができるようになったのか、明確にしなくてはなりません。その評価を的確にすることができるのか、日本中同じ物差しで本当にできるのかが疑問です。
3つ目は教材についての課題です。移行措置の教材として『We Can!』(暫定版)が文部科学省から提示されました。2018年度から2年間、子どもたちが使用することになります。この教材は、新しい学習指導要領を踏まえて制作されていますので、「三人称の表現」、「副詞や形容詞、動詞等の語彙の増加」、「過去形の導入」に加えて「読むこと」や「書き写すこと」等、これまでの教材よりもレベルが高くなっています。これらの教材を使って教える指導者の研修の機会は少なく、また、この教材の効果についての検証はなされないまま、2020年度から使用する「教科書」が出版されます。的確な教材やそれにともなう指導方法については、しばらく時間がかかりそうです。
共通語としての英語は
他国の人とコミュニケーションをとるための手段
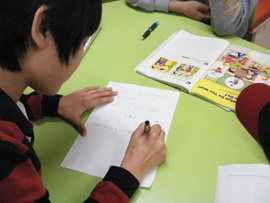 韓国の小学6年生の英語の授業 |
文部科学省では、「日本はアジアの中でトップクラスの英語力を目指すべき」としていますが、現在アジアの中で英語力のトップクラスはシンガポールです。実は中国や香港、韓国等では、シンガポールの語学教育の内容や指導法、評価等をお手本にしています。また、シンガポールが国定教科書(Primary English Thematic Series)から Pearson Education Asia 等が出版している教科書の使用へと変遷したように、東アジア諸国でも、LongmanやOxford で出版されている教科書を指導者が選択している場合もあります。
低学年はリスニング(聞く)から始まり、「聞いて読む」「聞いて書く」「聞いて話す」とつなげ、高学年になると音声よりも「読むこと」「書くこと」が重視されており、文法や内容把握の問題、自己表現として文章を書く内容もあります。日本も移行期に使う教材を見ると、レベルの差はありますが、同様の活動があり、アジア諸国の英語教育に近づいた気がします。
英語が母語でないシンガポールなどの子どもたちが英語を上手に使えるのは、学校での教育用語や友達との会話が英語であったり、子ども向けの英語のテレビ番組が多く、英語が日常生活に入ってきているからです。でも日本はそうではないので、「日本にいるのになぜ英語を?」と疑問も湧きがちです。ただ、日本人が日本で日本人とだけで暮らせばいい時代ではなくなってきています。そうした時代に、外国人と日本語以外でコミュニケーションをとるとしたら、共通語としての役割のある英語が必要です。インターネットの普及により、リアルタイムでのコミュニケーションやネット検索でいろんなことを誰でも調べることができるようになりましたが、英語ができればもっともっと多くの事象や考え方なども学べます。
もう1つ、私が英語を学んでほしいと思うのは、日本語に置き換えずに、相手の文化として吸収してほしい言葉があるからです。たとえば「identity(アイデンティティ)」は日本語にピッタリ当てはまる言葉はありません。日本語の「おもてなし」と「hospitality(ホスピタリティ)」も少しニュアンスが違いますよね。独自の文化を背景にした言語は、そのまま受け入れることで相手理解につながります。
また、外国語習得の過程では、言葉だけでなく話し方も学べます。たとえば日本人は結論を最後まで言いませんが、外国人はまず結論を言ってからその理由を述べますよね。話し合いのときはそのほうが合理的だということを知ることができます。こうして考えると「英語を」学ぶというより「英語で」学ぶことが大事なのです。
私は英語初級者の小・中学生向けの英語力を測るTOEFL Primary®の開発にも関わっています。これは「どれだけ英語を覚えたか」ではなく「どれだけ英語を使って〇〇することができるか」を測る世界共通のテストです。各国の特徴のあるものが登場することもあり、「この国ではこういう文化があるんだな」と、解きながら楽しめ、違いを知ることにもつながります。たとえば、南の国の子どもたちにとって、雪や手袋、マフラーは珍しいでしょうし、登場人物の名前ひとつとっても日本では聞いたことがないような名前が出てきたりします。グローバルなテストだからこそ、テストを受けながら文化も学ぶことができ、他者理解につながる。テストを受けながらグローバルな人間へと成長できる。英語を学ぶうえでの楽しさを感じられるのも、TOEFL Primary®の大きな魅力だと思います。
「英語を英語で学ぶ」ことが語彙力向上の秘訣
基礎力の蓄積が「使える」英語になる
 |
小学校での英語教育は、2020年には小学校3・4年生では年間35時間(週1回)、小学校5・6年生では70時間(週2回)になりますが、中国は週4コマ(40分と30分の混合)、韓国は高学年週3コマ、中学年週2コマ(40分)、シンガポールは英語で他教科を教えているので、諸外国と歩調が並ぶには時間数が足りません。その不足分を補う選択肢の1つが公文式学習といえます。子どもは言語を学ぶとき、何度も繰り返しながら覚えていきますが、公文式のよいところの1つは、教材がその「繰り返し」である点です。そうしてある段階を確実に定着してから次の段階に進むので、子どもの言語能力獲得法としては適切です。
加えて画期的なのは、ペンの先端を教材の音声マークにタッチすると、その教材に合った音声が再生される「E-Pencil」を使用していることです。正確な音を耳で聞きながら絵で認識できる、また、語彙から文にしていくときも「英語を英語で学ぶ」のはとても大事なことなのです。
こうして子どものときから習得していくことで、子どもたちの人間形成に大きく影響するでしょう。今後、英語教育改革によって、「英語はできて当たり前」という人と、英語が大嫌いになり「日本では英語を使わなくてすむから」という人と、今以上に二極化が進むと思いますが、グローバル化が進むなか、使わなくて済むわけにはいきません。
こんな例があります。愛知県岡崎市の特産品の八丁味噌は、海外でも売れています。売りに行く人がいるからですが、商社を通さず、「自分がつくった商品の思いを語りたい」と、自ら現地に行く人が現れています。そのとき必要なのは共通語としての英語です。さらには現地で作りたい、現地の人を雇いたい、ということになればなおさら必要です。つまり、これまで英語を使う環境でなかった人が、英語を使わざるを得ない状況になってきていて、しっかり使えれば仕事のチャンスも広げられるのです。
最初の交渉時はよくわからなくても、相手の言うことを真似して使っていくうちに英語力はついてきます。そのとき、学校で学んできた英語がどのくらい基礎力として蓄積されているかにより、上達具合が違ってくるでしょう。そして、使う場があれば、さらに磨かれていきます。
関連リンク
TOEFL Primary®/TOEFL Junior®公式サイト
愛知教育大学TOEFL®の小中学生版、TOEFL Primary®に挑戦しよう!|KUMON now!『くもんのシールでワーク 英語絵じてん』※こちらの書籍は高橋美由紀先生に編集にご協力いただきました。
 |
後編のインタビューから -高橋先生のこれまでのあゆみとは? |