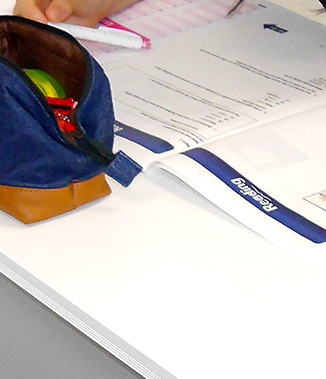英語教師の「不安」や「自信のなさ」の軽減が
子どもにとってのよい授業につながる
 |
私の研究テーマは大きく2つあります。ひとつは小学校英語教育です。小学校の先生方がどういう教え方をしたらより子どもたちにとって効果的か、教え方の研究をしています。具体的には現在、秋田県教育委員会や県内各市の教育委員会と協力しながら教員向け研修プログラムを作っています。今年で6年目になりますが、毎年夏休みに、40人の先生にここ国際教養大学に集まってもらい、一週間缶詰になって英語教育を学んでもらっています。
このプログラムの狙いのひとつに、先生方の「英語を教える不安」を軽減することがあります。それが私のもうひとつの研究テーマ「外国語不安」です。日本人の多くは「英語は苦手」といい、私が実施した調査では小学校の先生の85%が「英語が不安」と回答しているほどです。2020年から英語が教科化されるのに、その状況ではいい授業はできません。そこで、先生方の英語への不安を和らげるプログラムを実施しています。
日本の小学校の先生には、ネイティブスピーカーのALTにはない小学校の先生ならではの「強み」があります。まず、当然のことですが日本語で子どものわからない部分を聞き取れること。そして他の教科も教えているのでその関連性を考えながら授業ができることなどです。
プログラムでは、そうした強みがあることをまず、理解してもらいます。そのうえで、本学には留学生が大勢いますから、参加した先生方が彼らと話す場を用意します。今まで外国人と話したことがない先生もいますが、「英語が通じた」ことが成功体験になり、それを積み重ねながら、授業で使えるフレーズを学んでいきます。
こうしたプログラムを受けることで、県内に「自信がついてきた」という先生が増えてきました。夏休みの研修プログラムでは毎年40人しか受講できないので、本学で受講した先生がリーダーとなって地域に広めてもらっています。この4月からは、これまでのプログラムを凝縮した校内研修用のDVDを秋田県内の小学校に配布する予定です。
自分の考えや思いを相手に伝えられる
「英語力」を身につけよう
 |
子どもに求められる英語力とは、「自分の考えや思いを、身振り手振りを含めて相手に伝えられる」ことだと思います。たとえば相手が言ったことがわからない時「もう一回言ってください」と言ったり質問したりできるコミュニケーション能力です。
小学生なら、「私はこれが好き。きみは?」「きみは毎朝何時に起きているの?」という身近な会話ができれば十分です。中学生になればより正確に話したり自分の住む地域について伝えたりでき、高校生では日本や海外についてディスカッションできるというように、コミュニケーションのレベルが向上できればいいですね。
もちろん母語ではないので日本語と同じレベルで話すのは無理でしょうが、自分の発達段階に応じて言えることも広げる必要があると思います。先生方は、そうしたことを視野に入れて子どもたちを指導しなくてはいけないわけです。その指導や評価に役立つものとして私が活用しているのがTOEFL Primary®です。
TOEFL Primary®の良さは、第一に小中学生のための英語のコミュニケーション能力を測るテストだということです。これからの教育はコミュニケーション能力が問われるので、時代に合ったテストだと思います。また「放課後、サッカーの練習があるんだよ」というような、学校や家庭などでの身近なシーンがテスト問題になっていて「こういう場面ではこうしゃべればいいのだな」と、テストでありながら目標とする英語表現が示されるところが良いと思います。
第二に、アメリカのテスト機関ETSが作成している世界基準のテストだということです。世界での自分のレベルがわかることに加え、アメリカの大学・大学院への留学に必要なTOEFLと同じ形式なので、早いうちからそれに慣れることができます。
第三に、リスニングとリーディングというインプットが中心のテストであることです。水を撒くにはたくさんの水をじょうろにためないといけないように、初級学習者はたくさんインプットを受けることが大事です。それがアウトプット(ライティングとスピーキング)につながります。
第四に、テストの結果が合否ではなくスコアで出ることです。合格してしまえば点数は気にしませんが、スコアが出れば、「次はここ」と次の学習につながりますし、どの辺ができなかったか確認もできます。文科省も使っているCEFRのレベルを参考にして世界の中での自分の位置がわかることや、リーディングに活かす上でLexileスコアがわかることも非常に便利です。
TOEFL Primary®で子どもの潜在能力に気づき
教員の意識が大きく変化
 東大曲小学校での指導の様子 |
現在、県内2つの小学校でTOEFL Primary®を実践しています。1校は、文部科学省「英語教育強化地域拠点事業」の地域拠点校となっている由利本荘市立由利小学校で、1年生から6年生まで全学年、英語の授業はすべて英語です。最初、先生方は躊躇されましたが、研修を受けてもらい、今では先生も子どもたちも「英語の授業は英語で」が普通になっています。
由利小では6年生は週に2時間英語を学習し、その6年生を対象にTOEFL Primary®を実施したところ、リスニングで4分の1が国際標準規格「CEFR」のA2レベル(中学卒業レベル)と、非常に高いスコアがでました。それも成果ですが、何より先生方の意識が大きく変わりました。「子どもたちはやればできるのだ。自分もがんばろう」と。その波及効果が大きいと思います。
もう1校は大仙市の東大曲小学校で、週1回、私が通って6年生を対象に、担任の先生と一緒にオールイングリッシュの英語の授業をしています。3年目になりますが、毎年違う先生と一緒に行ってきました。どの先生も最初は乗り気ではありませんでしたが、3ヵ月もすると英語で授業をするようになります。やはり上から言われるのではなく、子どもたちが実際に変わっていくのを目の当たりにすると先生方も一生懸命になります。教員のあるべき姿です。教材用のCDを登下校中に聴くなどして自学された先生もいます。この学校の6年生は21人しかいませんが、TOEFL Primary®のリスニングで CEFR のA2レベルに到達した子どもが5人いました。
もともと日本の小学校の先生の指導技術は非常に高いです。英語もふだん算数や国語での指導方法を活用して教えれば問題ないと思います。しかも英語の授業は、その場で子どもが単語を完全に覚えなくても、何度も同じ単語がくり返し出てくるので、次に進んでも大丈夫なのです。逆に言えば知らない単語を出してもよく、「なんとなくこんな意味かな」と子どもに推測させることが大事です。構えず気楽に、楽しければ子どもたちも英語を使うようになります。
最近オリンピックなどでもスポーツ選手が英語を使っているのを見て「あんな風に話せばいいんだ」という雰囲気が出てきていると思います。「I eat rice.」を「I eat lice.」と発音してご飯でなくシラミを食べるのか、などと言う人もいますが、前後の状況から考えればそんなものは食べないことくらい理解できます。発音を気にしすぎずに、まずは話をしてみることが大切です。
関連リンク国際教養大学TOEFL Primary®/TOEFL Junior®公式サイト公立小学校初!大仙市立東大曲小学校TOEFL Primary®実施レポート
 |
後編のインタビューから -「外国語不安」をテーマにしたきっかけとは? |