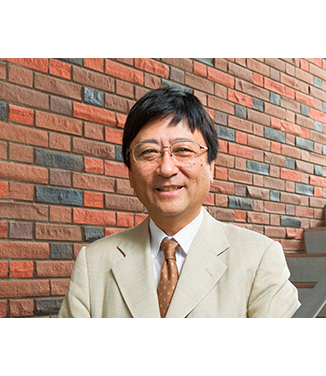意見を言いやすい「ディベート」という指導法
 |
大学では経営学部に入ったのですが、とくに経営学を学びたかったわけではありません。「英語でディベートができる」ことだけを考えて、社会科学系の学部をいくつか受けた結果でした。入学式の翌日にはESSに入り、英語漬けの大学生活が始まりました。母は近所の方から「お宅のお風呂から英語が聞こえる」、「茂くんとすれ違ったら英語でブツブツつぶやいていた」などと言われたそうです。ただ、私は「英語が好き」なのではなく、「英語でディベートがしたい」ために英語を勉強していました。
入部したESSは部員250人の大所帯でしたが、その中でディベートをやろうという人はごく少数。社会人の先輩が来て講評してくれることはありましたが、基本的には上級生が下級生を教えるスタイル。私は仲間をつくって「日本一になるんだ!」と計画を立てて勉強し、実際に日本一になりました。それが私の唯一の成功体験です。
そもそもディベートとは、「1つの論題について、2チームの話し手が肯定する立場と否定する立場に分かれて、それぞれの議論の優位性を聞き手に理解してもらうことを意図した上で、証拠資料に基づいて議論を進めるコミュニケーション形態」です。中高生・大学生を対象とした大会では、審判による投票によって勝ち負けが判定されます。スポーツの試合に似ています。
ディベートの目的は「相手を言い負かすこと」と誤解されがちですが、じつはすぐれたコミュニケーション教育の手法だと言えると思います。ディベートでは、客観的な資料をもとに論理的に考え、冷静に自分の意見を述べることが必要とされるからです。ディベートを通じて、相手の立場に立って考えることができるようになったり、自分が当たり前だと思っていることに対して「そうじゃないかもしれない」と疑問をもつ習慣がついたりします。つまり、「みんなが言っているから正しいわけではない」ということを理解することができるのです。
教師はよく、中高生に「自分の意見を言いなさい」と言いますが、思春期の子どもたちは周囲の目が気になり、自分の意見を言いにくいものです。「あなたはどう思う?」と聞かれて、個人としての意見をまとめて発言するのは気が重いでしょうが、「イエス」か「ノー」かどちらかの立場が割り当てられて、あくまでもその立場から議論をすればよいとなれば、気持ち的に楽なはずです。
人との「縁」を大切に歩んできたこれまで
 |
大学卒業後は大学院に進んで国際経済学を学ぼうと考えていましたが、大学3年のときにある転機が訪れます。全日本のディベート大会で優勝し、日本代表としてアメリカへ2ヵ月間行けることになったのです。20州近くをもう一人の学生ディベーターと二人だけでまわりました。その際に訪問した大学で、アメリカにはコミュニケーション学部という学部があることを知ったのです。
さらに、アメリカの大学にはディベートの授業があり、専属のディベート・コーチが雇われていました。学生がクラブの一環としてやっていて、指導者もいない日本とは大違い。驚いた私は、国際経済学からの方向転換を考えるようになりました。すると、アメリカのコミュニケーション学の教授から、「うちに来ないか?」と声をかけられ、留学することになったのです。大学院の授業を受けつつ、ディベートチームにも籍を置き、現地の高校などで模擬ディベートをしていました。そして、その大学でディベート・コーチとして雇われました。
しばらくして帰国したら、日本の大学にはまだコミュニケーション学の授業がなく、職がありませんでした。最初は英語学校でスピーチを教え、大学では英語を教えていました。その後は「ディベートのプログラムを作りたい」「付属高校の教育改革をしてほしい」など、さまざまな大学から請われ、職場を変えてきました。現在在職している立教大学は専任としては5つめの大学ですが、「新しく設立する経営学部で英語と経営を融合するプログラムを作ってほしい」と声をかけていただき、今に至っています。
これらの仕事はすべて自分がやってきたコミュニケーション教育と関連していますが、じつは「これをしたい」と私自身に強い希望があったわけではありません。ただ、「人とのご縁を大事にしよう」「期待されて声をかけられたのならそれに応えよう」という思いでやってきました。
「なりたい」のではなく「なる」と言い切れば、
今自分が何をすべきかが見えてくる
 |
小中高の授業における話し合いやディスカッションの活動を見ていると、一見きれいに意見をまとめて述べているように見えても、予定調和といいますか、彼ら自身の言葉でしゃべっていないように感じることがあります。日本の子どもたちは、もっと自信をもって考えを述べることができるといいなと思いますね。
ディベートはそれを克服できるきっかけになるはずです。通常の授業での先生の指導の仕方も工夫できると思います。現在行われている授業の多くは、「正解のある問い」を投げかけ、それに対する生徒の答えを「正しい・正しくない」と指導するスタイル。正解がない発問をして、生徒をペアやグループにして話し合う形式にしたら効果があると思います。大切なのは、結論ではなく、思考プロセスなのですから。
今の中高生たちが40歳、50歳になったときの日本を考えると、論理的に考えられる力、多様性を受け入れられる力がこれまで以上に重要になるのは間違いなく、それらを今から養っておくべきです。そのためには画一的な教育では限界があります。なるべく多くの違う意見を聞き、なるべく多くの異なる体験ができるような授業を行うことが、未来につながると思います。大学入試の結果も大事ですが、それだけではなく、何十年か先を見据えたとき、今の授業のスタイルでいいのかを先生だけでなく、親御さんにも考えていただきたいですね。もちろん先生にはアンテナを立てて、時代の風を感じていてほしいですね。子どもの将来のために、大人が発想を変えるべきでしょう。
そのように「発想の転換ができる瞬間」こそが、「学んだ」ということだと私は思います。「常識と思っていたことは違うかも」と、疑問に思う習慣がつくディベートは、学びそのものと言えるかもしれません。さまざまな体験も学びにつながります。特定の活動を一生懸命やるのもいいことですが、授業と部活だけになってしまうと、ほかの体験が少なくて、人間関係が狭くなりがちです。子どもにたくさんの体験をさせてあげてください、と親御さんには伝えたいです。
私は子どもたちに将来の話をするとき、「“なりたい”と“なる”は別だ」と伝えています。「なる」と言い切れば、今自分が何をすべきかが明確になります。私の現在は、多くの人に導かれた結果ですが、高校3年のときに、「大学生になってESSに入り、英語のディベートで日本一になる」と決めたことが原点にあります。「なる」と決めた時に、今の自分と理想の状態のギャップが認識でき、何から始めなくてはいけないかがわかったから動き出すことができたのです。子どもたちには、小さなことからでかまわないので、「なる」ことを決めて、今やるべきことを見つけてほしいと思います。
 | 前編のインタビューから -松本先生の現在のご活動とは? |