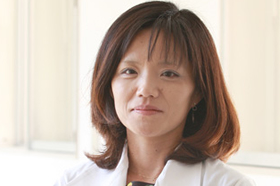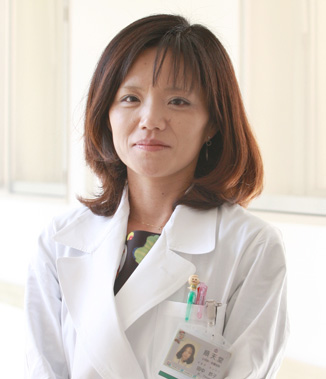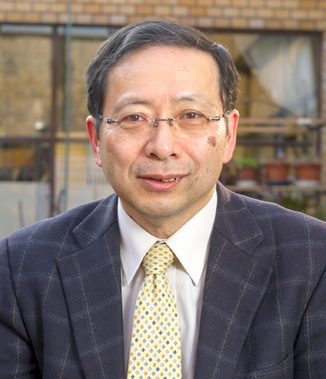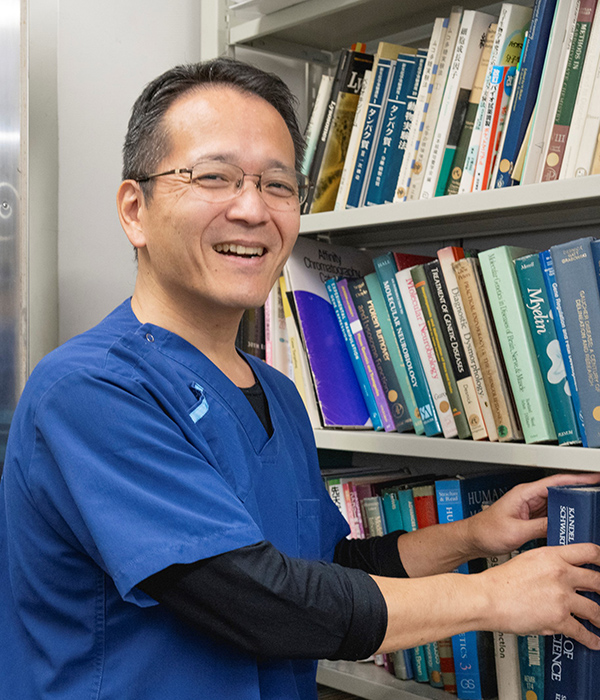入院したクラスメイトに勉強を教えるおせっかいな子ども時代

病気の子や障害のある子たちの健やかな成長をサポートしていくには、医療的な支援ばかりでなく、心理的・社会的な支援も必要ではないか……。わたしは医師になって20年ほどになりますが、その初めの年に、ある少年との出会い(後述)を機にそう感じ、「子どものこころの診療に携わりたい」という想いを強くしました。
もともと、父は日赤病院の勤務医、母は助産師の資格をもつ看護師で、両親が医療従事者ということもあり、小学生のときには漠然と「お医者さんになりたい」と考えていました。弱い者いじめがきらいで、中学生のとき特定の女の子をいじめる男子に「なぜいじめるの!」とその現場に立ちはだかって注意したり、彼女が盲腸で入院したときには、だれに頼まれたわけでもないのに病院に行って授業の内容を教えたり。とにかく、人の世話を焼きたがるおせっかいな子でしたね。
そんな反面、わたしは緊張するとお腹が痛くなるたちで、中学の全校集会のとき、お腹が痛くてそわそわしてしまい先生に注意されたことがありました。「お腹が痛くなったんです」と理由を正直に言ったにもかかわらず、「うそをつくな!」と疑われてしまい、大きなショックを受けました。その不合理な注意に納得できず、その直後からその先生に反抗的な態度をとることが多くなりました(苦笑)。しばらくして、同じクラスの子からわたしのお腹の痛みのことを聞いたようで、先生が謝ってくれました。それからですね、いろんなことを話したり相談したりと、その先生とはすごく仲良くなりました。
勉強については、なぜかはわかりませんが「言われなくてもやらなくては」という使命感めいたものがあり、クラスで1番でないと気がすまないような子でしたね。ただ、高校に進学したころは、自分自身のことや友人関係で悩み、睡眠不足や食欲不振が続き、勉強が手につかなくて成績が落ちたりなど、まさに悩める思春期時代を過ごした記憶があります。「ガラスの自分」というタイトルで作文も書きました。そのときは、所属していた新聞部の仲間がはげましてくれましたね。今でもそのシーンは明瞭に思いだします。
この新聞部時代はたくさんの思い出があるのですが、「今どきの高校生」と題して自分が抱えた悩みをもとに、友人関係、身体の悩み、異性に関すること、そして将来の夢などを特集テーマにした号が、高校生新聞コンクールで全国1位になったのはうれしかったですね。仲間と作り上げたひとつの成果が評価されたことは、大きな自信にもなりました。
高校生も後半になると、小学生のときの「お医者さんになりたい」という漠然とした気持ちはいよいよはっきりとしたものになり、医学部をめざして勉強しました。結果として順天堂大学に合格できたのですが、やはり第一志望であったある国立大学をめざしたいと思い、「1年浪人させてほしい」と父に頼みました。すると、「順天堂は歴史のあるいい大学だよ」と言ってくれました。当時は悩みましたが、いまはこの一言にしみじみ感謝です。
「子どものこころを診ることができる小児科医になりたい」そう決意した研修医時代

小児科医になろうと心に決めたのは医学部5年生のときです。研修に入ってすぐ、2歳の子が髄膜炎で意識不明の状態で救急搬送されてきました。幸い2週間くらいで見事に快復したのですが、わたしが微笑みかけてもニコリともしません。わたしはその子の笑顔が見たくなり、臨床研修の最終日に「よくがんばったね。ごほうびをあげるよ。どれがいい?」とシールを見せたら、初めてニコッと笑ってくれたのです。そのとき、子どもの力のすばらしさを感じ、「小児科っていいな」と感じた瞬間でした。
そして、「子どものこころを診られる小児科医になりたい」と思うようになったのは、大学卒業後の研修医1年目のときです。小学1年生の男の子との出会いがきっかけでした。その子は原因不明の病気で、下痢がつづいて入退院のくり返し。わたしは主治医の回診に同行して彼を診るのですが、自分のベッド周りのカーテンを締め切り、いつもうつむいて何もしゃべらない……。
「どこか痛いのだろうか?」「気落ちしているのかな?」とその子が気になっても、回診中はつぎの子を診なくてはなりませんし、研修医なので勝手に彼の病室に残ることもできません。すべての回診の終了後に、その子の部屋にもう一度行き、いろいろ話しかけてみました。でも、何日たってもほとんど反応がありません。そうして、「わたしではだめなのかな」と思いはじめたころ、その子がポツリポツリと話しだしたのです。「なぜボクだけお腹が痛くなって、こんな検査ばかりなんだろう」「生きていたくない」と。その言葉から、彼の気持ちが痛いほど伝わってきました。それは、子どもの心のケアの大切さを感じた瞬間でもありました。
病院の検査は楽しいものではありません。がまんが必要だし、痛みをともなう検査もあります。それがたび重なれば、心が折れそうになることもあるでしょう。わたしは彼にこう説明しました。「いまね、わたしたちはきみのお腹の痛くなる原因を調べています」「そのために検査をしています。きょうの検査ではこんなことが、きのうの検査ではこんなことがわかるんだよ」と。何日かかけてくわしく話をすると、ようやく彼の表情が明るくなりました。そして、退院するころには「ボク、大きくなったらお医者さんになる」と言ったのでした。
このときです。「医学的に子どもたちの身体を診るだけでなく、子どものこころにやさしく触れながら、一人ひとりによりそう医療をめざしたい」と真剣に思うようになったのは。
心理学を学びにイギリスへ留学。帰国後、大学病院内に「発達グループ」を立ち上げる

一般的に、小児科医は身体的・運動的発達については学んでも、心理的な側面は学ぶ機会が少ないという現状がありました。わたしが医師になった当時は、多くの大学がそうであったように、順天堂大学の医学部にも「子どものこころ」の専門部門はなく、わたしは「肝臓グループ」に所属して、不登校や摂食障害の子を診ていました。ご存じのように、摂食障害の原因も複雑です。生育歴を含む家庭環境、学校や職場環境、それに自身の自尊感情の低さやもって生まれた性格なども絡みあっています。その複雑さがわかり、ますます心理的な側面の学びの必要性を痛感しました。
そんな気持ちが通じたのか、あるとき、教授からチャンスをいただき、イギリスのダンディー大学の心理学部へ留学できることになります。留学先では言語学や社会心理学の講義にも出ました。とくに、『子どもは心理学者――心の理論の発達心理学』を著したマーク・ベネット先生の講義は非常に興味深く、とても充実した留学生活を送ることができました。
イギリスには、病気の子どもの発達と成長を支援する「ホスピタル・プレイ・スペシャリスト」という国家資格があることも知りました。子どもの発達段階や個別性に配慮しながら、子どもはもちろん、親もいっしょに治療に進んで取り組めるように環境を整えたりする専門家です。わたしはそれも学びたくて、その資格が取れる学校にも通いました。そこで複数の病院を回りながら、遊びを介して子どもたちのケアがどのように行われているかを目の当たりにしたことで、帰国してから自分が大学病院でどんな活動をすべきかを具体的に考えられるようになりました。
その手はじめは、大学病院の外来に新しい診療枠をつくること。帰国した2004年に、後輩のひとりに声をかけ、小児科に「こころの発達グループ」という名称のチームを立ち上げ、「発達外来」として、おもに発達の気がかりや学校に行きたがらないなどのお子さんの診療にあたりました。診療をはじめたころは「何を診るの?」と院内でも質問されることがあったのですが、しだいに受診希望者が増えて「発達外来」の診療枠は週1枠から5枠に拡大。忙しさにも日に日に拍車がかかりました。
スタート時は後輩とわたしの2人だけだったスタッフも、気がついてみると15人と仲間が増え、わたしはその若い先生方の指導にもあたるようになったのです。うれしくありがたいことではありますが、この領域での自分自身の研鑽が本当に充分であるのか、つねに考えていました。そうした想いから、ほかの大学や医療機関での診療陪席などや講習会への参加などを密かに積極的に続けていたのを思い出します。のちに東京大学病院精神科、順天堂越谷病院の精神科に出向し、精神科の研修もつづけました。
こうして、留学先での学びを活かして新たなチャレンジをスタートし、それが軌道に乗りつつあったころ、わたし自身にも大きな転機が訪れることになりました。
関連リンク
こころの診療部 | 国立成育医療研究センター
 |
|
後編のインタビューから -結婚と出産を経験して、子どもたちとご家族への対応がどう変わったか? |