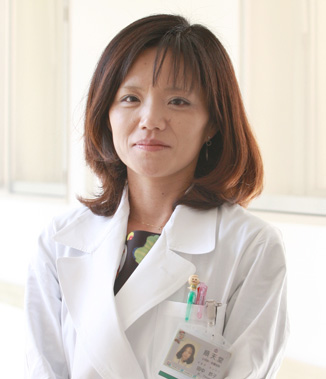ひとつでもいいから、昨日と違う新しいことを学びたい

2006年ごろから、それまでの環境のなかで自分ができることの限界を感じ、方向を変えてみることにしました。22年間勤めた大学病院を辞め、今の病院へと職場を変え、小児科を新設していただきました。今の病院は大学から近く、赤ちゃんのころから時をともにした子どもたちとご家族、仲間とつながっていることも幸せでした。2007年には周産期センターを開設していただき、そこで新生児医療に携わりながら、病院の外で活動する時間を増やしていただきました。病院のなかだけでできることは限られています。隣接地に看護学校もでき、助産科が併設され、助産院もできました。理解ある上司に恵まれ、これから先は、もっとできることが増えるように努力していきたいです。
これまでの診療経験から、社会の変化とともに、子どもたちが生きにくい時代になったように感じ、生きづらさを抱えている子たちが増えたようにも思います。背景には、社会が複雑化し、そのために思春期の終わりが遅れ、晩婚化が進み、特に父親の高齢化よる遺伝的な負荷が加わること、胎内環境を含めた環境要因が悪化していることなどが考えられます。
なかでも、人間が最も環境からの影響を受ける妊娠中はとても重要な時期です。低出生体重児とよばれる2500g未満の未熟児が増えているのも、女性の出産年齢が上がってきているほか、妊娠中の栄養状態、喫煙、ストレスなど胎内環境が関係しています。低出生体重児が増えると、発達上の問題も増加します。それを皆さんにもっと知っていただきたいのですが、産科医も小児科医も少なく、手が回らないのが実情です。
出産後のケアも大切です。お産を終えたお母さんが、赤ちゃんを抱っこしてお乳を与えることで、女性は「女性の脳」から「母性の脳」になります。母性というのは、自然につくられるものではなく、つくるためのプロセスが必要です。「母性の脳」になると、わが子を大切にして、子どもを中心に考えられるようになります。そうした妊産婦さんへのかかわりを大切にしたいと考え、2010年に周産期センターのとなりに助産院を開設しました。子どもを産む前とお産のときだけでなく、産んだ後も親子とかかわり、育児を地域で支える場として機能してほしいです。
こうしてお話しすると、いろいろ取り組んでいるように思われますが、私は何か問題が起きたらそれに対処しようとしているだけで、あまり考えていないかもしれません。何でも一所懸命してしまうように見えるのは、いつも自己不全感があるために、立ち止まれないのでしょう。それを苦痛に感じないのは、「昨日の自分ときょうの自分は、同じ自分ではないようにしたい」という思いがあるからです。「きょうはこれを憶えた。明日もひとつだけでいいから新しいことを知ろう、やってみよう」、それが学ぶということだと思っています。
そして、それができなくなったら、医療に携わるのは辞めようと考えています。過去に一度だけ、もう20年ほど前になりますが、「自分にはもう進歩がない」と感じて医者を辞めようとしたことがあります。周囲から説得されすぐに思い留まりましたが、このとき、借金をして家を建てました。自分を追い込んだんですね。今でも毎日、いろんな問題が起こり悩むことはありますが、2~3日すると立ち直る。立ち止まろうとするときに、亡くなった子どもたちが「先生、前に進もう」と後押ししてくれます。亡くなった子どもたちにも支えられて、“先ずは生きて”います。それが、私にとっての「先生」という意味かなとも思います。
親子の「愛着」、そして「心の安全基地」

小児科医になってすぐのころのことですが、児童精神科医になりたいと思っていました。職場を変わるときにそこを目指す道もあったのかもしれませんが、「したいこと」と「できること」を天秤にかけたとき、「したい」からうまくいくとは限らず、「できること」を続けたほうがうまく行くことが多いと考えました。
「専門」についても同様なことが言えると考えています。自分で「専門」と公言している場合と、周りが「専門」と認めるのとでは違います。早いうちから「専門医」になってしまうと、多くの場合、自分の専門分野以外はやらなくなってしまうので、私はなるべく専門分野はつくらないほうがいいと考えています。結果的に児童精神科医の道へは進みませんでしたが、今は新生児とともに、脳や心の問題にも触れさせていただき、それに少し近づいたように思います。
児童精神科に興味をもったのは、精神科の教科書を見ると、そこに記されている症状が自分に当てはまることがたくさんあったからです。そして、子どもたちの症状を自らに当てはめて考えるととても理解しやすく、生きづらさを抱えている子どもたちと共感できそうに感じました。
生きづらさを抱える子どもたちが生き易くなるには「心の安全基地」を持つことが大切です。「心の安全基地」とは、「自分は守られている」「困ったときには助けてくれる」といった、生きていくうえで心のよりどころのような気持ちです。多くの場合、その子にいちばん近いお母さんがもたらす、困ったときの助けです。
「女性の脳」から「母親の脳」へと変化すると、母親は怖いもの知らずになり、「母は強し」の存在として機能します。子どもが信頼を寄せることができる、本能に近いような基本的信頼関係、つまり「親子の愛着」が形成されると、安全基地としての役目を果たせるのです。もし愛着を獲得できなければ、何かに依存して、自分で安全基地と思い込むしかないのかもしれません。
安全基地があれば、そこをよりどころに活発に活動できるようになり、困った状況に陥り、心が傷つけられそうなときには防波堤の役目を果たすので、心はへこたれず、体さえ休められれば、また元気になれるのです。安全基地は幼少期の「親子の愛着」の形成により、容易に形成されますが、もし形成できなかったとしても、のちに、本当に自分を見つめてくれる人との間に「愛着」を形成することも可能です。見つめてくれて、本当に良いところをほめてくれる人に出会うことや、楽しく思い出すことができる、思い出づくりをすることでも、心は守られ、困難を乗り越えていく力になります。
ほかの人といっしょにいることの「心地良さ」を実感できる大人になるために

日本は資源が少なく、人と人とが協力しあうことが不可欠な国です。助け合い、分かち合って生きていくには、他の人といっしょにいて「心地良い」と感じることが大切です。それには、子どもが生まれたら、なるべく早くに抱っこして、心地良さを伝え、いつまでも笑顔が消えないようにしましょう。男性と女性とに性が分化する前に、心地良さを与えましょう。そのときにも、肌と肌が触れ合う抱っこがよいですね。そうすると、お互いが受け入れ合い、良いところを見つけて、ほめることができるようになります。大人がもし心に傷を抱えていても、薄まるかもしれません。
妊娠、出産、母乳を与えるときは、自然に母子のつながりが深まるときですが、そのときを過ぎても、なるべく多くの時間をともにすることが大切です。子どもが大人になっていく過程では、大人が子どもを導かなければなりません。成人して子どもができたら、わが子に対しても自分が伝えられたように伝えます。それがしつけです。大人の役割です。母子の医療にかかわる私たちはその方法を明確にしなければならないと考えています。
時をともにして、大人は、子どもが認めてほしいと思っているところを見つけて、ほめると、「やっぱり間違っていなかった。これでよかったんだ。こんな大人になりたい」と思えるでしょう。ほめた大人が、子どもにとって重要な存在になり、お互い高め合い、家族や社会などの心のつながりのある集団が出来上がります。自己肯定感の上に、新たな発想が創られます。
逆に、「あなたはこんなこともできないの」と言われて育つと、子どもには自己不全感が高まるだけではなく、大人に対する不信感が募り、子どもは混乱します。子どもを認める能力を失っている大人は、親として子どもを護ることができる重要な存在になれないのです。自分が育っていくうえでのお手本を欠いた子どもは、未成熟のまま成人してしまい、大人と子どもの境もなく、心地よい人間関係が築けず、本能的な関係でしか他人と関係性が持てなくなるかもしれません。帰るべき居場所(安全基地)と、自分の力を信じる力(自己肯定感)を与えられれば、人はいつでも大きな海に飛び出していけます。
医療の「ちょうど」、公文式の「ちょうど」、そして私が考える「ちょうど」

子どもに自己肯定感を育むことは、自分の力を信じ、子どもが今の社会を生きて、これからの社会を築いていくためにとても大切です。先日、公文公会長の生誕100周年記念の会に参加させていただきました。そこには、その子どもにあった「ちょうど」の教育という言葉がありました。とても温かく幸せな言葉でした。「ちょうど」とは言うのは簡単ですが、見極めることはとても難しく、与えることはもっと難しいです。新生児の医療も同様で400gで生まれた子どもに「ちょうどの医療」を怠ったら、生命は消えてしまいます。
その会には世界中から7,500人もの方々が参加されていました。「ちょうど」の教育は、これから社会が多様化し、複雑化していくなかで、さらに重要になっていくと思います。発達に問題を抱え、生きづらい日々を送る子どもたちには、この上ない教育です。特に、皆が同じように学校に通い、落ちこぼれないことを強要されやすい私たちの国では、後に「天才」と呼ばれる存在になるかもしれない、特別な才能を持つ子が「発達障害」と呼ばれてしまうことさえあるからです。
ほめることも、「ちょうど」を見極めないと、子どもがほめてほしいと思っているところと違うところをほめてしまい、やる気が失せてしまうこともあります。私はいつも、まだ開花していない才能を持つ子どもや、発達に大きな努力を必要とする子どもたちを公文の先生方に紹介します。公文の先生はほめ上手で、その子のいいところを見つけ、「ちょうど」の教育に導いてくれます。公文の教室に通うと天賦の才能が開花し、発達するのです。驚くばかりです。そして、お母さんとお父さんが、ほめ上手になることが理想です。
できないこと、足らないところを克服することも必要です。しかし、どうしてもできないこと、同じ時間を費やしてもなかなかできないことに多くの時間を費やすことは、子どもたちからするとどうなのでしょうか。それよりは、「ちょうど」のできることをしたほうがよいように思います。時間に追われ、子どもを見つめ、理解して、「ちょうど」を与えてくれる大人が減ってきた時代のようにも思います。
初老期を迎えた私の10年と、0歳児の10年は全く意味が違います。迷い、葛藤しながら過ごす時間の流れを、子どもに押し付けるわけにはいきません。子どもたちが健やかに育つためには、できることは何でもするという、「ちょうど」を見極める専門集団はこれからはもっと必要とされる時代になります。次の時代を担う子どもたちを「どんな手段を使ってでも、だれの力を借りてでも、強く育てていく」。それが私の思いです。