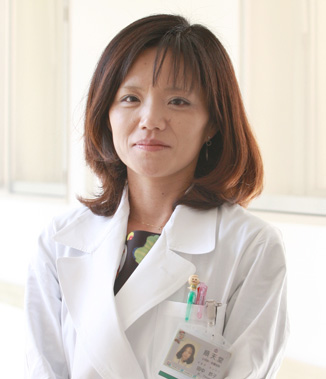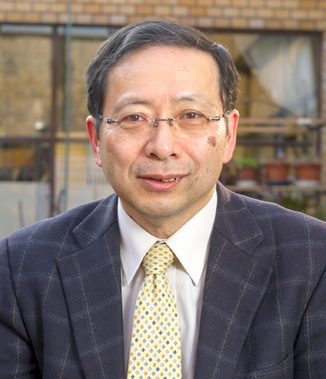結婚・出産を経験。子どもたちと親御さんへの「答えの引き出し」がさらに増える

大学を卒業し、小児科医の道を歩きはじめましたが、仕事はやってもやっても、まだまだたくさんある。「こんなに忙しかったら、妻として、母として、ちゃんと務められないだろうから、結婚はしない」と思っていました。イギリスへの留学が決まったときも、「帰国したら、さらに忙しくなるだろうから、やはり結婚は……」と思いこんでいました。実際、帰国後に新たな活動をスタートさせ、予想通りの忙しさでした(前編参照)。
けれども、その忙しさとはうらはらに、気持ちは結婚へと動いていました。留学先で知り合った同業の研究者との出会いで、気持ちが大きく変わったのです。「お互いの夢をかなえていくために、ともに人生を歩んで行こう」と結婚を決めました。互いの仕事に対する真剣な姿勢を尊重しながら、家族になることを思い描いたのです。その心境の変化には自分でもおどろいています。
ただ、仙台にある大学に職が決まっていた夫とは週末だけをいっしょにすごす、いわゆる「遠距離結婚」の生活。さびしさを感じる時間もないほど仕事が忙しい日がつづきましたが、あるとき妊娠がわかり、自分でもびっくり。小児科医としてたくさんの子どもたちを診ているし、すでに高齢出産の域で不安もありましたが、胎動をたしかに感じるようになってからは、「わたしはこの子を育てていける」という自信が湧いてきたのを実感しました。
お産は難産で、産後も大貧血でしたが、無事に生まれてくれたことに安堵しました。そして、出産後4ヵ月で職場復帰。子どもができてからの変化ですか?患児の親御さんに、医学的なお話だけでなく、「こんなことをしてみたらどうですか」と育児のアドバイスも自然にできるようになったことでしょうか。子どもたちにも親御さんたちにも、答えられる引き出しが増えたと感じています。
子どもの成長は早いもので、娘もこの4月で小学1年生になります。幸い大きな病気をすることもなく、すくすく育ってくれました。けれど、家でも仕事をしているわたしをちゃんと見ていて、「ママ、なんでもひきうけちゃだめだよ」と心配してくれることがあります。その気遣いが身に沁みますね。
仕事に熱中しすぎることもあり、さびしい想いをさせてしまっているのかなと感じることもありますが、うれしいことも。つい先日の保育園の卒園式で、「わたしは大きくなったら、赤ちゃんからお年寄りまで診るやさしいお医者さんになりたいです」と発表してくれたんです。わたしが小児科医で、夫は高齢者を研究する医師だからなのでしょうが、子どもは親の話をよく聞いているものだと、あらためて感心しました。
育児をしながらだと、仕事の時間はそれまでよりも限られてしまいますが、休日や娘の就寝後など、使える時間はできるだけ有効に使っています。そんな時間的にゆとりがない生活を送っているにもかかわらず、あまり人が引き受けたがらないような仕事でも、それを誰かが必要としているとわかると、進んでその仕事に取り組んでいる自分に気づきます。夫からは、「また!?」と言われることもしばしば。娘からも“ママ、またなの?あまりなんでもひきうけないでね”とお願いされるくらい、子ども時代からのおせっかいな性格(前編参照)はいまだ健在なようです(笑)。
たとえば「病後児保育」です。病気はほぼ治っているものの、まだ回復期にあり、ふつうの保育園に通うのがきびしい子どもたちを、親御さんにかわって一時あずかる施設(システム)です。厚生労働省が定めた子育て支援事業のひとつに位置づけられていますが、実際にやろうとするといくつものハードルがあり、運営もとても手間がかかります。しかし、働く親御さんたちにとって、わが子の病気は一大事ですから、誰かがサポートする必要があります。
東京都の文京区と順天堂大学とで2010年に立ち上げた「病後児保育」は医療機関併設型。つまり病院内の一時あずかり施設ですが、自らその事業担当を引き受け、ほかの同様の施設を数多く見学したり、保育士さんの面接、マニュアルづくり、備品類の発注、担当医の選任など、ものすごい勢いで整えました。開所直前まで準備がつづき、たいへんな経験でしたが、関係者のみなさんと課題ひとつひとつをじっくり話し合えたこと、たくさんのご協力をいただいたことで、無事に開所できました。そして、お互いの信頼関係をいっそう厚くすることができました。これも大きな財産だと思っています。
「愛着」は人が生きていくうえでの最大の基盤 いろんな人とのコミュニケーションのなかで育んでいきたい

3年ほど前からですが、東京都の虐待カウンセリング事業にもかかわっています。虐待の問題に向き合ってみて、あらためて「愛着」の大切さを痛感しています。ここでの「愛着」は、心理学での「愛着(attachment)」です。動物や人間でも、赤ちゃんがおかあさんにしがみついたり、後追いをしたりしますが、それも愛着のひとつの現れといわれています。人間の場合、生後6か月くらいで特定の人物(母親)への愛着が形成されはじめ、2~3歳ごろまで形成がつづき、この時期を順調にすごすことが、その後の対人関係や情動の正常な発達にとって重要とされています。
ですから、「愛着は人間が生きていくうえでの最大の基盤になる」ということもわかっていただけるのではないかと思います。しかし虐待は、その愛着の形成を妨げてしまうことになります。では、その親御さんを説得すればよいかというと、それもちょっと違う気がするのです。
子育てが苦手な親御さんたちのなかには、自分自身が無条件で愛された経験が少なく、人や子どもをどう信頼して愛したらいいかわからず、自己評価も低い。そういった共通点があるともいわれています。またご自身が受けた虐待をしつけの一部のようにとらえていて、わが子に同じことをしてしまうという「虐待の負の連鎖」もあります。親御さんと子どもだけでは、なかなか解決の道が見つけられない状態になっているのです。
苦手なことは誰でもあります。もちろん虐待という結果で示す行動は決して許されるものではないと思いますが、そこをただ単に責めたり非難したりするだけでは、虐待という社会現象は減ることはないと思います。だからこそ、だれかが早くに気づいて、非難するのではなく、親としての役割を可能な範囲で維持できるように、その苦手な部分は周りの人や社会が手助けしてあげることが大切です。
子育てが苦手という親御さんの場合でも、その親子や家族の関係を尊重しつつ、子どもの周りにいるいろんな人たちとのコミュニケーションのなかで愛着が形成できたら、もっとたくさんの子どもたちが健やかに育っていけると思います。
そのためには、親子や家族を周囲が温かく見守りつつ、適切なサポートをしていける社会の仕組みも必要です。きめ細かな配慮とかなりの時間を要しますが、今後やっていかなければいけないことだと考えています。そして、そのヒントのひとつが「Baby Kumon(ベビークモン)」だと思っています。歌と絵本の読み聞かせを子育てに活かすという考え方もいいですし、月に1回、親御さんが公文教室の先生とかかわりをもつことで、子育てに不慣れだったり、なかなか自信がもてないお母さんも、「これでいいんだ」と安心できます。その安心が、親子の心におよぼす影響は大きいはずです。
順天堂大学病院では10年ほど前から、病気や障害のある子たちの子育て支援の一環として、「わくわく広場」を月1回開催しています。おもちゃを介して楽しく遊ぶなかで、育児や発達相談を受けたり、地域でのメンタルヘルス事業につなげたりなど、子どもたちの成長や発達を、親御さんと医療スタッフで分かち合い、さらにその先につなげていくという活動です。
親御さんは子どもの遊び方や興味の引き出し方などを専門スタッフ(医療スタッフやおもちゃコンサルタントなど)に相談できます。わたしたちも、診療時とは違った親子のかかわりを間近に見ることで、「これからどう治療を進めていくか」「このお子さんのこんな素晴らしい力を伸ばそう」など、スタッフ間で話し合いながら、その後の診療につなげています。
また、2010年には「子ども療養支援協会」を立ち上げました。病気の子や障害のある子たちの支援は、医療のほかに心理的・社会的な支援が加わることで、格段に良いものになりますが、さらにきめ細やかさやていねいさも求められます。そこには、専門性の高い人がかかわることが大切で、イギリスの「ホスピタル・プレイ・スペシャリスト」(前編参照)、アメリカの「チャイルド・ライフ・スペシャリスト」に相当する、日本の文化や社会に合った専門家、「子ども療養支援士」の育成をめざしています。
気づいたことからは目をそらさず意思をもって、真摯に向き合っていきたい
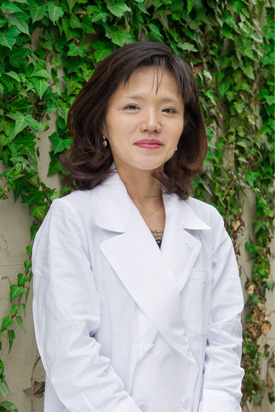
最近、わたしは金子みすゞの詩集がとくに気に入っています。東日本大震災のあと、テレビでくり返しその詩が流れたことで、たくさんの人たちの心を癒したことだろうと思いますが、やさしい言葉で記されていながら、じつは奥が深いところが好きです。『私と小鳥と鈴と』と題した詩の「みんなちがって、みんないい」というフレーズはすごくいいですよね。「あなたはこれができるし、こんなすばらしいところがある。そして、わたしにはこれができる」。これはすごく大事なことで、自己肯定感を育むことにつながると思います。
わたしは子どもたちや親御さんたちに、「たくさん、できること探しをしましょう」とよく話しています。子どもたち一人ひとり、強み・弱みはみんなにあり、それぞれ違います。「お子さんの強みやいいところをいっぱい見つけて、それを伸ばしていきましょう」と伝えるようにしています。お母さんがそうすれば、「家族みんなでいいところを見つけて伸ばしていく」こともできます。そして、子ども自身が「ボクにはこんないいところがあるんだ」と自覚できるようになれば、自分で自分を伸ばしていくこともできるようになります。
私事になりますが、この4月から国立成育医療研究センターで勤務しています。内科・外科などの身体科医師、看護師、CLS(*)、保育士、臨床心理士、社会福祉士などの方々とともに心理社会的支援の活動をチームで担当しています。そのチームのなかで「医師として自分には何ができるのか」をつねに考え、心あらたに子どもたちと向き合っていこうと思います。
*CLS:チャイルド・ライフ・スペシャリスト、療養中の子どもや家族に心理社会的な支援を提供する専門職
わたしの長年の命題は……。命題というとちょっとおおげさに聞こえるかもしれませんが、あえて命題と言わせていただきます。その命題のひとつは、CLS、子ども療養支援士、臨床心理士、保育士、社会福祉士といった専門家の方々とチームを組んで、療養中の子どもたちとそのご家族のこころの営みを支援するシステム作りです。それが日本の小児医療のすべてに実践できるようなシステムをつくっていけたらと思っています。
もうひとつの命題は、「思春期の子どもたちへのこころの支援」です。たとえば、思春期に慢性的な病気にかかり、「あれもできない」「これもできない」となると、成長後にうつ発症のリスクが高まるというデータがあります。また、日本では思春期の自殺が多く、その原因はいまだ明らかではないものの、自尊心や自己肯定感がうまく育っていない子が多いからでは、と考えられています。
わたしはこれまで、愛着の基盤を形成する重要な時期である乳幼児期の臨床を主に担当してきたわけですが、今後はその知識と経験をベースに、乳幼児期とはまた異なった脆弱性かつ柔軟性をもつといわれる思春期の子どもたちの支援に取り組んでいきます。
ひとりでも多くの子が「自分はこれでいい」「自分はこれでいく」と思える、つまり自己肯定感をしっかりもてるようなかかわり方をしていきたいです。もちろん、それには精神医学的な知識が不可欠なので、これからも研鑽を積んでいきたいですね。
わたしは「意志あるところに道はできる」という言葉が好きで、これまでも「意思をもって動いていく」「気づいたことからは目をそむけない」ことを意識してきました。これからもさまざまな課題や問題に直面すると思いますが、「自分にできることは何か」をいつも考えながら、意志をもって、真摯に向き合ってきたいと思っています。でも、当面いちばんの課題は、これから数年後には思春期を迎える時期になる娘の子育てなのかもしれません(笑)。
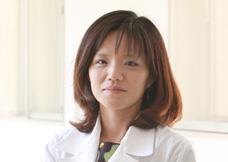 | 前編のインタビューから – 弱い者いじめがきらいで、おせっかいな子だった子ども時代 |