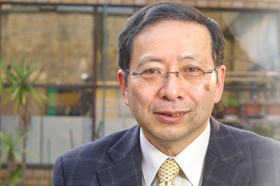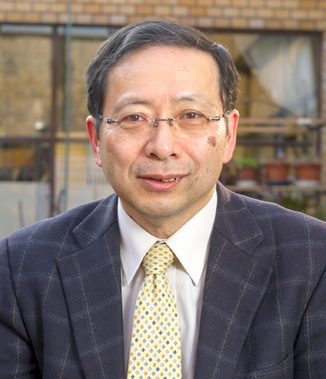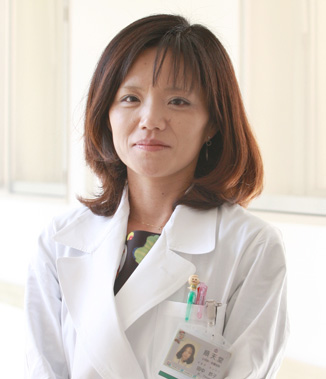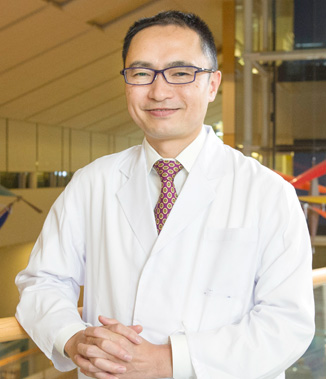視覚に障害がある人が、不自由なく暮らせるよう支援する「ロービジョンケア」

生まれてすぐの赤ちゃんの視力は0.01くらい、生後1ヵ月には0.02、3ヵ月では0.1、6ヵ月で0.2、3歳のころには1.0、というのが一般的な視力の発達と考えられています。このように、順調に視力をはじめとする視る機能が発達していけばよいのですが、子育てのなかで親御さんが「なんだかおかしいな?」「ちゃんと見えているのかしら?」と感じられる場合があります。このような不安を抱えた親子、病気や事故で視覚障害者となった成人の患者さんが、わたしたちのセンターを訪れます。
不安な表情の親子は診断と治療のために来られるわけですが、もっとも知りたいことは、「見えているのか、いないのか?」「見えているのなら、どう見えているのか?」とともに、「そういうわが子をどう育てればよいか?」なのだと思います。
そんなとき、わたしが大切にしているのは、まず親御さんを勇気づけることです。診察や検査の結果、わが子の視覚に何らかの障害や問題があるとなれば、心は沈みがちです。しかし、「もっている機能や力」を見つけ、最大限に引き出すことにより、日常生活に支障がないレベルにできる可能性を伝え、親御さんに前向きな気持ちになってもらうようにしています。親に「育てたいという気持ち」がないと、子どもは育たないからです。
そして、具体的な子どもへの接し方を詳しく伝え、すこしでも子育てが楽しくなるようにと心がけています。また、よりよく見えるようになる工夫や補助具、視覚障害に関する社会的な保障や支援制度、就学時の対応などについても説明していくと、親御さんは「この子はちゃんと生きていけるんだ」と表情が明るくなります。このような親御さんと連携した継続的な支援で、子どもたちの生活の質を向上できます。こうした医療だけではない、さまざまな支援を総合して「ロービジョンケア」といいます。
ただ、現時点において、「ロービジョンケア」は一般の方にはあまりなじみがない言葉で、じつは医療界においても、十分に理解されているとはいえないと思います。それを必要としている人たちは想像以上に多くいるのに、です。そんな現状を変えていきたくて、同じ想いの医療や福祉の人たちをはじめ、関係する分野の人たちに声をかけ協力を募っています。日本ロービジョン学会の設立、医療従事者向けの専門書や一般向けの解説書の出版なども、その活動の一環です。
開業医の家に生まれ、ごくふつうの眼科医になったが…

わたしがなぜ医者になったか…、ですか? 父が内科の開業医だったから、というのがいちばんの理由でしょうか。次男なので、兄が医者になって父の医院を継ぐものと思っていたら、兄は別の道へ行き、わたしが医学部に進学しました。
眼科を専門にした理由も、研修医時代に医局をまわったとき、眼科の先生が親切で、その先生の話がスムーズに頭のなかに入ってきたからだと思います。しかも、話は前後しますが、医学生のときのわたしは、学究の徒とはかけ離れた生活を送っていました。何をしていたかというと、毎日テニスです。テニス部に所属していて、年間200日以上は部活でテニス三昧の日々。医学生の最終学年6年生のときにようやくレギュラーになり、対抗戦に出たりしました。ただ、このときの経験から、「がんばればできるんだ」という自信はできました。肝心の、医者という職業については、「医者になってからしっかりやればいいんだ」と考えていました。若いということを差し引いても、安直な考えでしたね。
学びからはほど遠く、別の意味では充実していた学生時代を送っていたわけですが、卒業する直前に父が急逝。父が開業していたのは内科医院でしたが、わたしはまだ若すぎるし、経験もないということで継ぐことができず、その医院は廃業に。結局、眼科の道を歩むこととなり、そののち必死に研鑽を積みました。その間、慶應義塾大学病院時代の恩師が、福岡県にある産業医科大学(以下「産業医大」)の教授になられたので、わたしも講師・助教授としてそこで勤めることにしました。
ふり返ってみれば縁とは不思議なもので、それまで何のつながりもなかった九州で、医師となってからの人生の大半を過ごすようになるわけです。そして、眼科医としてのわたしの大きな転機となったのも、産業医大でのある患者さんとの出会いでした。
医療だけでは救えない「何か」。ある患者さんとの出会いが大きな転機に

産業医大では、眼科で緑内障を専門に診ていました。あるとき、ひとりの成人の患者さんに緑内障の手術をしたのですが、術後の経過が芳しくない。そこで眼圧を下げる薬を投与したところ、両眼の結膜が充血し、背中など全身の皮膚に水疱などができてしまいました。全身の皮膚細胞が重篤なダメージを受けるという薬の副作用(のちに薬害と判明)がでてしまったのです。最善は尽くしたものの、最終的には両眼球にも重い損傷が生じる状態になってしまいました。言葉がでないほどのショックでした。1992年の秋のことです。
副作用の症状がでたあと、その患者さんが入院中、症状の改善はもちろんのこと、何とかして立ち直らせたいと、われわれ病院スタッフは、ありとあらゆる知識や技術を総動員させました。患者さんの気持ちだけでも前向きにできないかと、精神科の先生のカウンセリングなども試みましたが、その患者さんは落ち込んでいくばかり。退院後の生活のめどもまったく立ちませんでした。
「どうしたらこの状況を打破できるのだろうか」。そう思い悩み続け、気がつけば2年近くの年月が経とうというある日、ひとりの歩行訓練士*に相談しました。そして、「奇跡」が起きたのです。その歩行訓練士が、たった3回その患者さんに接しただけで、患者さんの様子が一変しました。患者さんはみるみる元気になり、リハビリにも励み、やがて退院。そのあと、はり・きゅう・あんまなどを学ぶための学校に通い、個人で治療院を開業、立派に社会復帰をされたのです。そのどれもが、わたしたちにとっては驚きの連続でした。
*「歩行訓練士」:正式名称「視覚障害者生活訓練等指導者」
いったい、その歩行訓練士は、患者さんに何をしたのか? 詳しく聞いてみました。すると、それが「奇跡」ではないことがわかったのです。わたしたち医療従事者が、医療としての専門家であるだけにそこにしか目を向けていなかったところへ、その歩行訓練士はふつうに人としての心で患者さんと接しただけのことだったのです。
まず、患者さんと同じ立場で話を聞き、患者さんのいまの気持ちに真摯に耳を傾け、その気持ちについて率直に語りあっていました。さらに、患者さんが生活していくうえで直面するであろう課題や困難を、そのひとつひとつについて、どうすれば改善できるか、解決できるかをいっしょに考え、その具体的な対応や方法を提示していたのです。なるほど、と思いました。「将来の希望」を患者さんとともに考えていたのだと。これにより、患者さんは将来の自分をイメージできるようになり、歩行訓練士とさらにコミュニケーションを密にすることで、みるみる気力を取りもどしていったのです。わたしは、そういう術を知らなかった。そして気づきました。医療の技術だけでは救えない「何か」がある、と。これが、「ふつうの眼科医」だったわたしが「ロービジョンケア」に取り組むことになるきっかけでした。それからほどなくして、医療だけではなく、福祉や心理や教育など、さまざまな分野の情報や技術を総合して視覚障害のある人を支援する「ロービジョンケア」という考え方が欧米にあることを知りました。
しかし、国内ではその当時、「ロービジョンケア」の日本語訳の本もテキストもなかったので、それまで眼科医として培ってきた知識や技術を活かしながら、独学で学んでいくしかありませんでした。たいへんなことはたいへんでしたが、その患者さんのご苦労や心情を思えば、いまでも申し訳なさとやりきれなさとでいっぱいですが、患者さんのためにも、自分が日本での「ロービジョンケア」の道を拓いていかなければという思いを強くしました。
 | 後編のインタビューから – 「福祉関係者と医療関係者は、よきパートナーでありチームであるべきです」 |