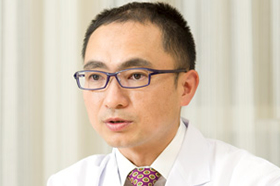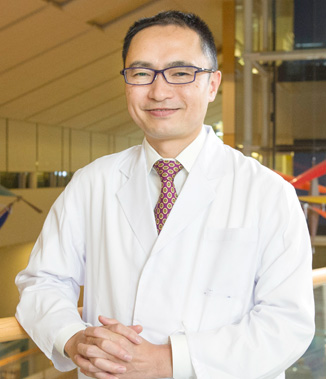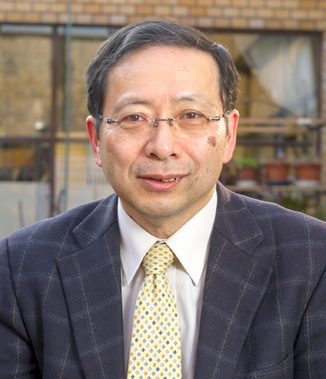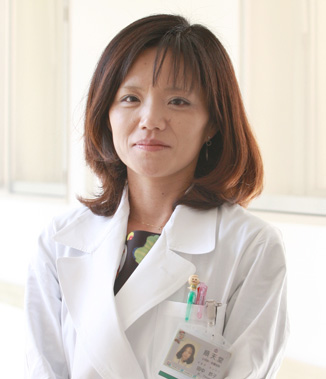「できない」ところを見るのではなく、「できる」ところを見よう
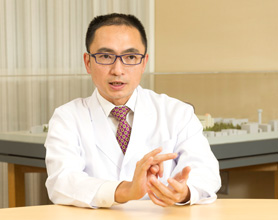
念願かなって医学部に入ったものの成績は芳しくなく、クラブ活動ばかりをしていました。ひとつだけ救いは、毎日のように疲れ果てるまで走り込み、基礎体力を育むことができました。成績については、さすがにこのままではまずいと、医学部6年生の後半、国家試験ぎりぎりで一日中猛烈に学び、なんとか国家試験にも合格し、医師としての道を歩み始めることができました。一度にいろいろなことはできないけれど、これと決めたひとつのことには没頭できるという、私の個性というか特性がそのときもいい方向に働いたようです。
そんな私の拙い経験から言えるのは、人間は本当にやりたいことでないと、本気にならないということ。私にとって学校の「お勉強」は、人から「やれ」と言われたことをお行儀よくすることでした。だから勉強をしなかったのかもしれません。勉強に限らず、やりたくないことを無理してやっても、うまくいかないと思います。けれども、好きで、得意なことであれば、放っておいてもやるし、どんどんうまくもなります。
このことはリハビリも同じだと思います。発達障害者や高次脳機能障害者の場合、自身の問題とされる症状や行動を自分でわかっていないことも多いので、本人はいたってケロッとしています。気にしているのは周りだけということもめずらしくありません。そういった自覚がない人に対し「これができていない」「あそこをなおせ」と言っても、本人はどんどん逃げてしまう。「できない」に目を向けるのではなく、「これができる」「これなら得意」に目を向け、それを伸ばす。リハビリはそれに尽きると思います。このことは、子育ても似ているかもしれませんね。
「できる」ということでいえば、公文式学習も言葉や記憶や認知など、高次脳機能の回復手段のひとつとして効果があると考えています。実際、私が以前勤めていたリハビリ病院では院内に公文式を教えてくれる家族会の先生がいらっしゃり、高次脳機能障害の入院と通院の患者さんたちが算数・数学と国語を学習していました。学習のスキルを高めるというより、集中力や記憶力や認知の面で効果がありましたね。リハビリはその時点での本人のレベルに合ったことをするのがポイントのため、「ちょうどの課題」を提供できて、「できる」ことをくり返す公文式はぴったりなのです。
「自分の“できる”“得意”を活かす」のは、私自身も実践しています。医学部に入りたてのころは外科医にあこがれていましたが、外科では手先の器用さがいちばん求められます。でも私は不器用。どうしようかと悩みましたが、人の相談にのったり、チームでコミュニケーションをとったりするのは得意だと自覚していたので、リハビリ科に進めば、それが活かせるのではと考えました。ある意味、マイナスをプラスに変えられたわけです。そう考えると「自分は何ができるか」を自覚するのが、夢に近づく第一歩かもしれませんね。
人には向き不向きがあり、それが何であれ、向いていれば生き生きと取り組め、やがて大成するのだと思います。どう考えてもビジネスマンに向いていないのに、ビジネスマンになる必要はなく、たとえば寿司が好きなら、寿司職人をめざす。親の職業や代々続く家業も確かにとても大切ですが、できれば得意なことで職業の役割分担をする。それが、これからの社会にはとくに大切だと思っています。
本人も家族も喜ぶ医療をめざしての挑戦
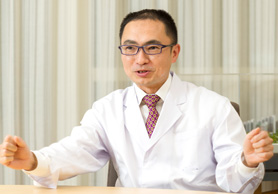
リハビリを専門にすることに決めたのは、医学部生の後半のころから。医学的には治療が済んでいても障害が残り、そこに対応する医師が少ないことを知ったからです。医師としてスタートするときも、「そういう専門家がたくさんいたら、患者さんたちがもとの生活に早くもどれ、本人も家族も喜ぶだろうな。それをやろう」と意識してきました。
リハビリ医になったとき、運動機能を扱う専門医はけっこういましたが、心や認知の部分、つまり高次脳機能を扱う専門医はまだ少なかったので、それを専門にしようと決めたのも同じ理由でした。しばらくして高次脳機能障害については国も支援に乗り出し、支援環境がだんだんと整ってきたので、つぎに何が足りないだろうと考えたとき、小児のリハビリ専門医がほとんどいないことに気づき、その領域に飛び込んだのも、同じ思いからです。
いま、全国から、かつての自分と同じようなハイリスク児がたくさん来てくれています。責任重大ですが、「自分と同じような子を助けたい」という気持ちで子どもたちと向き合っています。でも最近思うのは、もしかしたら、「かつての自分を応援したい」という無意識の意識もあるのかも…ということです。
私はいま、医療安全管理室に所属し、そこの責任者として、成育医療研究センター全体の医療安全にも力を注いでいます。「リハビリの先生なのに、なぜ医療安全を?」とたずねられることもありますが、私のなかではすべてつながっていることなのです。
患者さんや家族はもちろんですが、医療従事者自身が安心して仕事に臨める環境を作ることも重要な仕事だと考えています。患者さんを第一に考えればこそ、医療従事者の心や身体の健康状態も考えなくてはいけません。疲れていたり不安定な状態だったりすると、医療ミスが起きてしまう可能性もあるので、真剣に取り組むべき課題と捉えています。
何事においても同じだと思いますが、心が安定していれば、穏やかで良い行動が生まれます。逆に不安だと、イライラしたりしてよくないことが起こりかねません。患者さんもわれわれも、みんなが安全で安心している状態が、最善の医療につながるのだと思います。
変わったのは社会で、子どもは昔から変わっていないのでは?
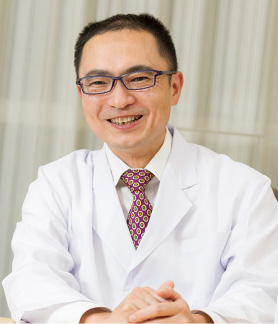
このインタビューの冒頭(前編)で、「ほかの子とちょっと違う子が増えてきた」とお話ししましたが、とても大切なことを言い忘れていました。子育てという視点で考えると、「ほかの子とちょっと違う」のは、家族、とくにお母さんからすれば、すごく心配になってしまうでしょう。「ちょっと違う」ことが「発達上の問題」だとすれば、さらに不安になってしまうと思います。
でも考えてほしいのです。「ほかの子とちょっと違う」ことはいけないことなのでしょうか。たとえば「落ち着きがない」「集中力に乏しい」というのも表面上のことで、その子をよく見てみると「つぎつぎいろんなことに興味をもつ」ということがわかったりします。これは見方を変えれば、優れた能力と考えることができます。
あるとき、ADHDと診断された双子を育てているシングルマザーが来院しました。4歳の子ども二人は片ときもじっとしていられない状態。お母さんも日々の子育てでイライラが募り、ノイローゼ寸前の様子。守秘義務があるため詳しいことはお話しできませんが、私はお母さんに「子どもを預けて、仕事をしてみては?」と勧めました。お母さんは「とんでもない!」という表情で、半信半疑というより疑っていたと思います。
結果はどうだったかといえば、子どもたちは見事に落ち着きました。お母さんもイライラが消え、とても元気になりました。このケースは、お母さんがイライラして、子どももイライラ。その子どものイライラを見て、お母さんがさらにイライラ…という悪循環に陥っていたのだと思います。お母さんが子どもを預けるには勇気はいるけれど、子どもから少しでも離れる時間を作ったほうがいいと判断してのアドバイスでした。
もうひとつよかったのは、お母さんが子どもたちの「よいところ」「できること」を見つけられるようになったことです。「集中するときはすごく集中する」「好き嫌いなく食べてくれる」といったことがわかると、お母さんの子どもの見方が変わってきます。そうなると、子どもたちは、そのお母さんの見方に応えようします。好循環になったのですね。
「ほかの子とちょっと違う子」は昔からいたはずですが、地域の絆というか、つながりが深かったため、お母さんひとりが悩むことは少なかったと思います。また、「みんな同じ」でなくても、「個性」として受け入れてくれる社会があったのだと思います。いまは「ほかの子とちょっと違う」ことが、「発達上の問題」とみなされることが多すぎるような気もします。子どもたちは何も変わっていなくて、変わったのは社会のほうではないでしょうか?
そういった意味で現代の日本は、子どもたちにとって生きづらいのかもしれません。そんな変わりゆく時代でも、普遍的なこととして、子どもたちと親御さんたちにぜひお勧めしたいことが3つあります。「規則正しい生活をする」「本をよく読む」「親子でできるだけ長い時間を過ごす」ということです。とくに3つ目は、共働きや塾通いなどにより、実行するのはむずかしいかもしれませんが、取り組むべき早急のテーマです。そうすれば「ほかの子とちょっと違う子」「発達に問題があるとされる子」はおそらく減っていくでしょう。
そのためにも、これからの時代に最も必要なのは、お母さんが笑顔で子育てができるようになるための社会環境の整備です。医療界に身を置く私としては、「女性医師がどうしたら笑顔で働きつづけられるか」ということが、これからの大きな課題だと考えています。
10年後、20年後はさらに高齢者が増え、子どもが少なくなり、世の中は想像できないほど変わっているでしょう。そのとき、この社会に生きるすべての人たちが笑顔で毎日を送っているか。そういうことを、みんなでもっと真剣に話し合い、その実現をめざして行動に移していければいいなと思っています。
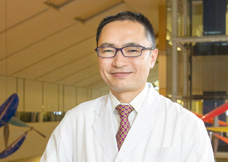 |
前編のインタビューから – 「リハビリ専門医」の橋本先生がめざす医療とは? |