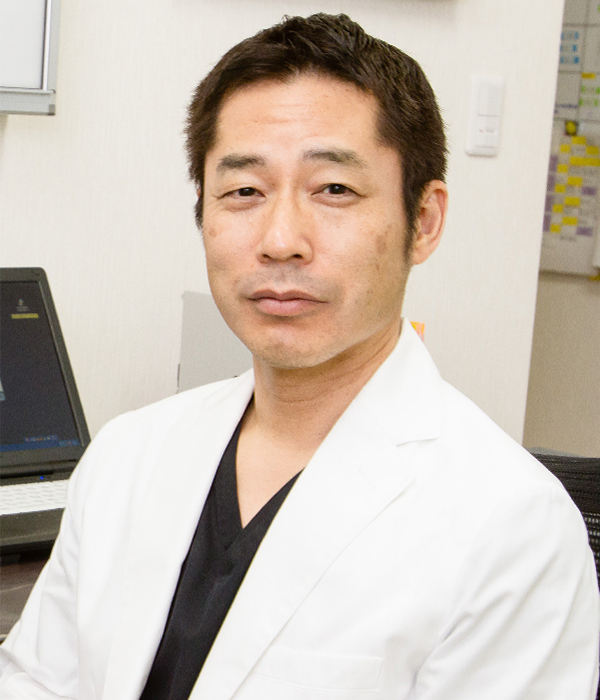モヤモヤしながら診察するなか、あるとき啓示が降りたように“気づき”が……
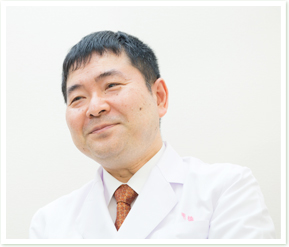
医学部を卒業後、最初の2年間は内科の研修医でした。内科にも摂食障害だったり、ガンで余命いくばくもなかったりと、精神的なケアが必要な患者さんがたくさんおられて、ますますメンタルな部分での診療は大切だと思うようになりました。
その後、名古屋大学で精神科医としてのキャリアをスタートします。来る日も来る日も、暴言を吐いたり、リストカットや自殺未遂をくり返したりする患者さんを診ていて、なぜこうなってしまうのか、ずっとモヤモヤ考えていましたが、あるとき、子ども時代が影響していることに気づきました。患者さんの生い立ちを見ていると、子ども時代にSOSのサインを出しているのです。不登校になったり、虐待を受けていたり……。そして「自分なんかどうでもいい」「自分は生きている価値がない」と自己否定するのです。「そうか、すべての元はここにある」と、啓示が降りたように気づきました。自己肯定感がしっかりと育っていれば、いまのような症状は出ないはずだ、と。
それで子どものメンタルケアに力を入れるようになり、スクールカウンセラーや児童相談所の嘱託医も引き受けるようになりました。私の予測通り、「どうせボクなんか」と自分の頭を殴ったりする、成人と同じような症状が子どもにも出ていました。20歳を過ぎると治療して恢復するには10年ほどかかりますが、小学生であれば1~2年で見違えるように変わります。やはり子ども時代のケアが大事と実感していると、今度は保育園でもそういう症状が出てきている子たちがいると、園長先生から相談を受けました。
なぜそうなってしまうのか。親がいっぱいいっぱいで、つい怒鳴っていたり、カリカリしていたりするから、ということが見えてきました。ならば、親のケアも必要ではないか。それで子育て支援から、親支援に行き着いたのです。そこが改善できれば、子どもの健全な成長が見えてきます。
イラストの親しみやすさもあって、多くの方々に手に取っていただいている『子育てハッピーアドバイス』は、子育ての現場から見えてきた、この「自己肯定感」と「親支援」の大切さを一貫して記しています。私は医者としてはまだまだ未熟だと思っていますが、この2つの重要性は、間違っていないと確信しています。
「ありがとう」と言われることが、私のエネルギーの源
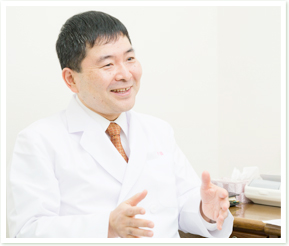
私が理事長を務めているNPO法人「子どもの権利支援センターぱれっと」では「親の会」も開催していて、親支援の重要な活動のひとつと位置づけています。この会は、マンツーマンでアドバイスするのではなく、ほかの親の悩みに共感したり、自分がアドバイスする側になったりします。はじめのうちは支援される側だった親がだんだんと支援する側になり、「ありがとう」と言われます。そうしたくり返しで、皆が元気になっていくのです。「親の会」を立ち上げたばかりのころは、会の開始から終わりまで、みな私にアドバイスを求める感じでしたが、現在は会の始めのほうはともかく、会の終盤になると、私の入る余地はなく、親同士で盛り上がります。それでいいんです。
ところで、私の自己肯定感はというと、けっして高いとはいえない子どもでした。自分の本音を出したら嫌われるのではと、人に合わせるいわゆる「いい子」で、自分のことも好きではありませんでした。それが「こんな自分でもいいのかな」と思えるようになったのは、本を書くようになって、いろんな方たちが「本を読んで助けられました」と読者カードを寄せてくださるようになってからです。それで、ようやく「自分がしていることも少しは意味があるのかな」と思えるようになりました。医者としてつらいことがあると、「私が医者でいいのかな……」と思うときもあります。それでも続けていられるのは、「おかげで良くなりました」「ありがとう」と言われることがあるからです。
講演に呼ばれるのも嬉しいですし、本音トークのなかで、「同じ思いでやっているんだな」と、人とのつながりを実感します。「親の会」に参加される親御さんたちと同じで、私も共感されたり「ありがとう」と感謝されたりすることで自分が肯定され、元気になっていく。大人でもそうなのですから、成長さかんで多感な子どもならなおさらでしょう。
子どものことでイライラするのも、子どもを愛しているからこそ

「ありがとう」は自己肯定感を高める魔法の言葉です。子どもの話を聞いて受けとめ、行動を認めたり褒めたりすることも同じ効果があるでしょう。その意味では公文式学習は、自己肯定感をきちっと押さえて教育を考えていると思います。一律に「ここまでやりなさい」だと、クリアできない子は「自分なんかどうせやってもダメだ」となりがちですが、そうではなく、一人ひとりに合わせた課題設定をして、「できた」「わかった」という喜びを大事にしているからです。
公文の先生方は親との対話も大切にされていますね。親御さんとの面談や保護者懇談会など、子どもだけを教えるのではなく、親支援もしている点に、私と共通する思いを感じます。公文式のように自己肯定感を育む学習方法は広がりつつありますが、それでもまだ、自己肯定感の大切さがきちんと認識されているとはいえません。そこで、「自己肯定感を育む子育て」をアドバイスできる人材を養成したいと考え、育成講座を企画中です。このところ、中国や韓国、米国などにも呼んでいただき講演することも増え、子育ての課題は世界共通だと実感しているので、日本のみなならず世界に広めていければ、と思っています。
親も子も忙しくなってきている今、余裕がなくてカリカリしてしまうこともあるでしょう。ですが、何が一番大事かをよく考えてみてください。もちろんしつけや勉強も大事ですが、その土台となる自己肯定感をしっかり育てていけば、本当の人間としての力になっていくし、大きな挫折を経験しても簡単には折れないのではないでしょうか。自己肯定感がしっかり養われれば、しつけも身につくし勉強も伸びていきます。
こうお話ししてくると、「私はいつもイライラしてしまうダメな親」と思い悩む方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。それは、子どものことを愛しているからこそだと言えます。そういう親がいる限り、日本社会はまだまだ大丈夫だと思っています。