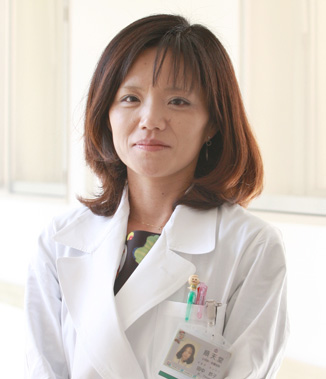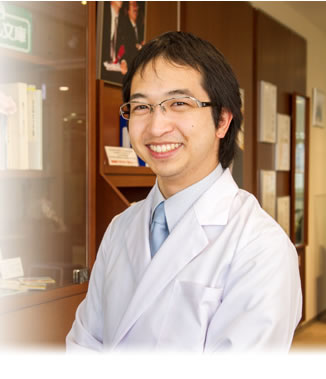病院で待つよりも、地域に飛び込み「火の元」を消したい

この仕事をしていますと、たくさんの患者さんに出会いますが、あるとき、これといった身体障害もなく、20歳なのにトイレもひとりで行けない患者さんに出会いました。カルテには、「0歳のときに泣き声がうるさいと、親にベッドの下に押し込まれ、周りを布団で固められて放置され、それを見かねた親類が児童相談所に伝え、施設に入所した」という記録がありました。泣いても、泣いても、誰も来てくれない。そのときの孤独感はいかほどのものでしょうか。小さいときにそんな思いをしなければ、今のような症状も出ずに、穏やかな人生を過ごすことができたでしょう。
心療内科医という仕事は一言でいうと、内科医と精神科医の中間と言えますが、日本ではメンタルな部分に重点をおく内科医が診る場合と、精神科医が診る場合があります。例えば「お腹が痛い」という症状では、食べ物が原因かもしれませんし、ストレスなどの心理的な原因なのかもしれません。こうした心理的な要因の病を「心身症」と言い、その診療をするのが心療内科医です。
私はスクールカウンセラーとして、学校でも子どものカウンセリングをしたり、親への育児のアドバイスをしたりしています。こういうことは、ふつうは臨床心理士がすることが多いと思います。医師がすることは少ないでしょうね。しかし、私がスクールカウンセラーをしている、いや、しなければと思うのは、どんな病気でも予防が大事だと考えているからです。
火事でも燃え広がってから消火するのではなく、火がついた段階で火の元を消せば、被害は少なくなるように、症状がひどくなる前に手当てを始めれば恢復も早い。病院で待つだけでなく、地域の中で子どものSOSに早く気づきたいと考えたのです。そして多くの患者さんを診るなかで、子ども時代に思いを受けとめること、自己肯定感を高めるような子育ての大切さを実感し、それを広めるために講演活動や執筆活動も積極的に行っています。
池に浮かんだ大量の魚を見て、科学を絶対視することに疑問

私は、暗くなるまで野球をするなど、子どもらしい子ども時代を送っていました。親から「勉強しろ」と言われたことは一度もなく、しかし「早く寝ろ」と厳しく言われて育ちました。最近の子どもたちは寝るのが遅いようですが、せめて10時には寝ることをお勧めします。早く寝ればスッキリ目覚め、学校の授業もきちんと聞けます。授業が分かれば、勉強も面白くなります。それはもしかしたら早寝のおかげかもしれないと、親には感謝しています。
そんな私ですが、「大人になったら社会の役に立ちたい」と考え、小学生のころから漠然と「医者になろう」と思っていました。その思いが強くなったのは小学校高学年のころ、通学路のわきの池に、ある日大量の魚が死んで浮かんでいたのを見たのがきっかけです。農薬が原因でした。光化学スモッグなど公害がクローズアップされていた時代で、世の中に役立つ科学技術であっても、逆に人間を苦しめることがあると思い知らされました。ならば、絶対に人のためになる仕事をしようと、医者の道を選んだのです。
栄養学の研究者だった父が医学の博士号も持っていて、父に勧められたことも影響しているかもしれません。それで中学・高校時代には、真剣に医学部に入ろうと勉強を頑張りました。もともと勉強は嫌いではなかったのですが、その原点は、小さいころ、母が毎晩してくれた読み聞かせにあるように思います。しかし母の読み聞かせは、ドキドキするような場面で急に話が止まることがありました。読みながら眠ってしまうんですね。早く続きを知りたい私は、寝てしまった母から本を取り自分で読むこともありました。そうしているうちに、新しいことを知る楽しさを知り、漢字もだんだんと覚えるようになりました。
音楽雑誌社に泊まり込み、授業には出なかった医大生時代
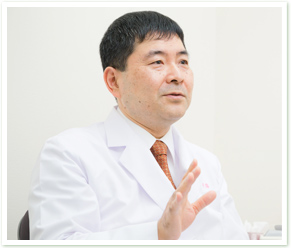
一年浪人の末、なんとか国立大学の医学部に入学できた私ですが、大学1年の秋くらいから授業には出なくなり、代わりにロック専門の音楽雑誌社の編集室に泊まり込むようになりました。訳詩したり原稿を書いたり、東京から来たバンドのマネジメントをしたりしていたのです。けれど、急にそうなったのではなく、高校時代の反動がきた、ということだと思います。
小さいころから音楽に親しんでいた私は、中学時代はクラシック、高校時代にはロック音楽、中でもパンクロックにハマり、時間があれば聴いていました。パンクの歌詞は、ある意味哲学的で、既成の枠組みを壊すようなメッセージ性があり、そこにひかれたのです。とはいえ、医学部を目指し、受験勉強をしなければと考え、聴くのを自粛。大学入学後、それがはじけて雑誌社に入り浸るようになったのでした。
試験のときだけ大学に行き、気づいたらもう5年生に。このままではマズイと、ようやく大学にもまじめに行くようになりました。あるとき、心配した父が「こういう本があるぞ」と手渡してくれたのが、日本における心身医学の創始者ともいえる池見酉次郎先生(いけみ ゆうじろう)の『心療内科』(中央公論社)でした。そこには精神と肉体の関わりを示す症例やデータが紹介されていて、非常に興味を覚えました。例えば「断腸の思い」という言葉がありますが、実際にストレスがかかっただけで腸の動きがまったく変わる、といったことが記されていたのです。
この本との出会いが、精神科に進むきっかけになったといえますが、もともと子どものころに「科学だけでは限界がある」と感じていて、人間の心や精神的なものに関心があったことも影響していると思います。医学部の授業よりも、文学部の哲学の授業のほうをまじめに受けていたほどでしたから。パンクロックに熱中したのも、その精神性やメッセージ性でしたし、精神科であれば今までやってきたことが活かせるかなと考えたのです。