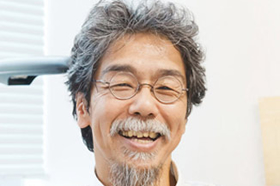読み聞かせは「豊かな心を育てる」ことを脳科学的に実証

東京都の研究所のあと日本大学へ移り、さらにアメリカの大学へ留学し、「行動と脳の関係」の研究を霊長類でしていたのですが、留学から帰ってすぐ東北大学の川島隆太先生と知り合いになりました。そのとき川島先生は人の脳活動を計測する脳機能イメージングの最先端技術を留学先から日本に持ち帰ってこられたところでした。そのおかげで、日本ではまだほとんど行われていなかった脳機能イメージング研究を川島先生と一緒に始めることができました。これも、めぐり合わせ、いいタイミングとしか言いようがありません。2002年に仙台でHuman Brain Mappingという国際学会を開催したのは懐かしい思い出です。
脳機能イメージング研究を始めた結果、研究の幅が社会的な領域にまで広がりました。川島先生と一緒に高齢者対象の「学習療法」の立ち上げに関われたのもそうですし、心理学の先生方や公文との共同研究でもある「読み聞かせと脳の関わり」の研究もそうです。
読み聞かせについては、昔から「聞く力が養われる」「賢い子が育つ」などと言われてきましたが、科学的になぜなのかは検証されていませんでした。そこで、脳科学的に確かめようということで、研究が始まりました。
心理学の世界では「賢い子が育つ」といわれてきた読み聞かせですから、仮説では、「思考・記憶・創造などを司る前頭前野という部分が活動しているのでは?」と考えていました。しかし、子どもの頭にNIRS(近赤外線分光装置)という機器をつけて脳の働きを見たところ、前頭前野に活動は見られませんでした。
仮説は残念ながら崩れたのですが、こんどはfMRI(機能的磁気共鳴画像装置)という機器で調べてみると、大脳辺縁系と呼ばれる部分が活動していることがわかりました。この部分は、喜怒哀楽など心の動きや情動を司ります。そのため、僕はわかりやすく「心の脳」といっています。読み聞かせによって、「心の脳」が発達し、子どもは豊かな感情を育むことができる――そんな結果を導き出しました。
この結果は、公文式教室の先生方や図書館などで読み聞かせを実践している人たちに、大きな共感をもって受け入れてもらえました。読み聞かせしている人たちは、「自分がしている読み聞かせという行為は“知育”とか“本好きな子に育てよう”という方向性とは何か違う」という思いを持っておられたようです。それが、「子どもの“心の脳”に働きかけている」という解釈を聞いて、「スッと腑に落ちました」と納得されたのです。
このように、読み聞かせが脳のどの部分に働きかけているかを調べることで、どんな効果を生み出しているのか解明できたわけです。その後、「歌いかけ」も読み聞かせと同様に「心の脳」を活動させるということがわかりました。こうした科学的な立証もさることながら、子どもの顔を見つめながら歌ってあげたり、心を込めて語りかけたりすることが、子どもたちの心の安定につながっているのは間違いありません。親も子どもをよく見るようになり、コミュニケーションが深まります。読み聞かせや歌いかけは、親子の絆をしっかり育むのです。
高齢者の介護施設で実感した「人の学びの力」
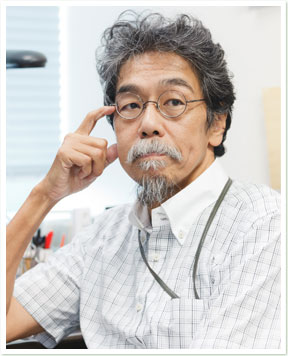
先ほど川島先生と「学習療法」の立ち上げに関わったとお話しました。その間に大きな気づきを得ました。それは、人には「学びたい」という欲求が根本に、いや本能としてあるのだなということです。「学びたい欲」とでも言うのでしょうか、「学ぶ遺伝子」が人には備わっていると思います。
「学習療法」立ち上げのための準備研究で施設をたずねたときのことです。右半身がマヒして字が書けなかった80歳の女性は、手紙を書きたい一心で学び、部屋には公文式のプリントの束がズラリと並んでいました。彼女は遺書を残していましいたが、そこには、「すべてが公文のおかげで、公文によって救われました。何と御礼もうしあげたらいいでしょう。公文に出会わなかったらこんな幸せはありません。」と書かれていました。文中の「公文」は「学習」に置き換えていいと思います。人生の最晩年で楽しく学ぶことができた。それを生きがいと感じていたことがわかります。また、「学習療法」が始まってからは、99歳から英語を学びはじめ、「100歳になるまで100の単語を覚える」という夢のような目標を実現した女性もいました。
「学習療法」を始めるにあたっては、高齢者が本当に学習してくれるか、「馬鹿にするな」と怒り出すのではないかと不安でしたが、いざ初めてみると、皆さん、学習の時間になると、学習室の前に車椅子の行列ができました。そして学習後は、にこやかな顔になられて部屋に戻られるのです。中には、学習が終わって数分すると、学習していたことすら忘れてしまうのに、また、次の日のその時間になるとが、ちゃんと学習室にいらっしゃる方もいました。まさに「学びたい欲」のなせるわざとしか言いようがありません。
この方たちのなかには「小さいころ、貧しくて勉強できなかったから」という理由で「学びたい」と思った方もいるのでしょう。しかし、そういった方も含めて、人は何歳になっても環境が整いさえすれば「学ぶ遺伝子」がONになる、ONにすることができるのだと感じました。
「ちょうどいい」「ほめる」「くり返し」が、「学ぶ遺伝子」をONにする

では、何が「学ぶ遺伝子」をONにしたのでしょうか。また、どうすれば「学ぶ遺伝子」をONにできるのでしょうか。そのポイントは、公文式ではないですが、「ちょうどいい」「ほめる」と、その結果としての「くり返し」にあると思います。
僕には子どもが二人いますが、上の男の子が小さい時に、計算プリントを手作りしてやらせていました。くり上がりの計算ができたら、つぎは筆算というように、段階を踏み、ちょっとむずかしいかなと思ったら、簡単な問題に戻ったりしていました。当時、僕は公文式を知りませんでしたが、ほとんど同じことをわが子にしていたわけです。
むずかしすぎない、かといって易しすぎない「ちょうどいい」問題は、解き手に「やった!」「できた!」の気持ちをいだかせてくれます。そして、そのときに「よくできたね!」とほめてあげることで、解き手に「うれしさ」をあじあわせ、「もう一回!」のモチベーションを高めます。
また、つまずいたら少し簡単なところに戻し、こちらが手を出さずに、本人にやらせることで再度「やった!」「できた!」と満足感をいだかせるのです。
もう一つ、大きなポイントがあります。それは、「ちょうどいいを見つける」、「ほめる」ためには、解き手をよくよく観察している必要があるということです。学ばせる側の観察がないとこの方法は成功しないのです。
じつは研究で使っている動物(おさるさん)も全く同じです。テレビゲームのようなことを教えるのですが、彼らには言葉で説明することはできません。まずは装置に触っただけでほめてあげる(彼らの場合はえさやジュースをあげるのですが)と、本当に簡単なことからはじめ、コントローラーを操作して画面上のカーソルを自由に動かしゲームができるように学習させていくのです。この場合も彼らの隣にすわって、一日中お付き合いをするのです。
「やった!」「できた!」の体験を通じてほめてもらうことが「うれしさ」を生み出します。「うれしい、たのしい」体験は「またやろう」というモチベーションを高めます。そしてそのくり返しの結果、高齢者も子どもも(おさるさんも!)「学ぶ遺伝子」がONになるのだと思います。このやり方は学習の基本原理なのだと思います。
関連リンク 歌・読み聞かせの効果 Baby Kumon