小学生時代に「原子力」と「脳」の本に興味をもったことが、今のボクの原点
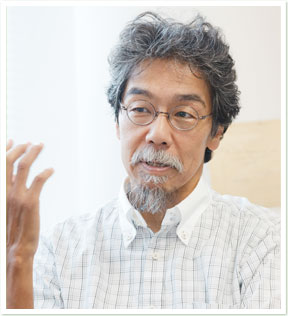
平面に描かれた絵が立体的に見える、という経験はどなたもお持ちでしょう。なぜそう見えるのか、そのとき脳はどのように活動しているのか。僕はそんな脳の機能の研究を続けてきました。神経の動きから脳の働きを解明する研究で、「神経生理学」といいます。わかりにくいので、一般的には「脳科学」といっています。
なぜ脳の研究をするようになったかと問われれば、ひとつ思い当たることがあります。それは、小学校の図書室にあった、図鑑のようなシリーズ本との出会いです。何冊かのシリーズのうち、とても興味があったのが、「原子力」の本と「脳」の本でした。「原子力」の本については、町工場を営んでいた叔父がいたため、モノづくりへの関心が高かったのだと思います。
一方、「脳」の本は、よく図鑑にあるようなヘビの脳に始まり、いろいろな動物の脳、そしてヒトの脳までが図解されたもので、それに強く引き付けられ、関心をもつようになった……ような気がしています。実はこの記憶は後付けで作られたものかもしれないのですが、原点として子ども時代にこの2つに関心があったことはたしかです。
僕は三重県で生まれ育ち、小学校は当時としては非常にユニークな教育を実践していた私立校に通学していました。学校はこじんまりとしていて、先生方の目も隅々までとどくし、同級生もみんなが一緒という感じで、学校生活は楽しかったです。魅力的な先生方と出会い、そのためか、成績もそこそこ良かったのですが、運動は姉と比べてあまりできませんでした。けれども、中学ではバスケットボール部に所属し、県大会で優勝。これで運動にも自信がつきました。
町工場を営む叔父にあこがれ、いったんは建築の道を志すが……
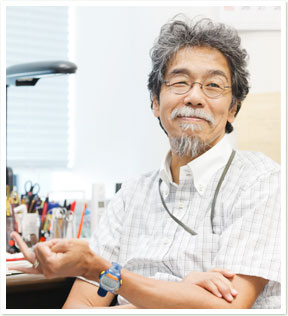
高校は兵庫県の進学校へ進みました。小・中学校ではそれなりに勉強していた僕ですが、高校ではまったく勉強をせず、ラグビー三昧でした。高校時代に出会った友人は何事にも代えがたい財産だと思っています。成績はひどかったものの、幸い有名私大の建築学科に進学することができました。
なぜ建築だったかというと、先にも話した町工場を経営していた叔父がすごく好きで、小さいころから叔父の町工場にある製図道具を見て、技術屋にあこがれていたから。それで、進学先は建築系かな、と漠然と考えていたのです。
ただ大学入学後も、せっかく建築を学ぶなら東大へ、とひそかに思っていたので、いわゆる「仮面浪人」として東大を受験したのです。残念ながら落ちてしまったものの、当時の受験の慣習で、併願していた東京医科歯科大学の歯学部には合格できました。医科歯科大は当時は二期校で出願倍率30倍、実質15倍くらい、よく合格したものです。
その結果、私のなかで迷いが生じました。というのも実は、小さいころから、母方の祖母に「医者になれ」と言われていたことが心にひっかかっていました。母方の家系が代々医者だったので(当時は廃業していましたが)祖母はそう言っていたのだと思います。結局、国立大学で学費も安いし、祖母も喜ぶということもあり、方向転換して歯学部に進むことに決めました。そこから改めて、自分の進む道を歩み直したわけです。
自分を認め引っ張り上げてくれた師との巡り合い、そして“いま”がある

歯学部に入学したころは、「歯科医として開業するのもいいかな」と思っていましたが、生理学の講義で当時の脳科学の第一人者である中村嘉男先生と出会い、関心は脳に移りました。潜在的にあった、脳への興味が目覚めたのかもしれません。歯学部でも、顎の動きと脳の仕組みなど、脳についても学ぶのです。実は中村先生の講義はロクに聞いたことがなかったのですが(笑)、学部の学生なのに、なぜか研究室に出入りするようになり、この道のいろいろな先生や先輩と出会って話すうちに、研究者として大学に残るのも選択肢として考えるようになりました。それは、当時は今と違って、大学院を終えてから大学でポジションを得ることは比較的容易だったことにもよります。
さて、大学院でも動物の脳で研究をしていたのですが、人の脳のことを知るためには人に近い霊長類で研究をしたいと思い、当時、霊長類の脳を使って研究していた数少ない機関のひとつ、東京都の神経科学総合研究所(現・財団法人東京都医学総合研究所)へ行くことを希望し、幸いなことに、「流動研究員」という、いまでいうポスドクとしてたまたま雇ってもらうことができました。
こうしたいいタイミングに巡り合えたことも、僕が研究者の道を歩み続けられるようになった要因のひとつだと思います。ほかのことでも同じだと思いますが、何かを究めるには、個人の能力に加え、人とのつながりやタイミングも大きく影響しているのではないでしょうか。自分でできる範囲の努力に加え、自分のことを認めてくれる周りの世界がないと、究めるのは簡単ではないかもしれません。
僕の場合、中村先生との出会いが転機になりましたし、研究所時代に自分が研究者としてやっていけるのか不安だったときに、いろんな先生方が励まし、認めてくれました。それが非常にうれしかったです。公文の学習も、ほめたり励ましたりを大切にしていますが、それは大人も同じだと思います。
もうひとつ、研究していたことが時流に乗ったという幸運もあります。研究というのは、基本的にはどんどん細分化していくもので、例えば脳の研究なら、脳の機能を細分化し、それぞれ研究していくようになります。しかし、僕は細分化して突き詰める研究ではなく、マクロ的な研究をしたいと思っていました。
マクロ的な研究とは、簡単に言えば、「行動と脳の相関関係」を調べるもので、「人が何か行動しているとき、脳はどのように働いているか」といった研究です。いわば心理学的な研究手法を脳科学に応用した研究です。ただ、こうした研究は、それまでの手法とくらべて大雑把すぎて、当時はまだあまり受け入れられませんでした。
つい先日亡くなられた研究者、日本大学時代の恩師である酒田英夫先生はこうした研究のパイオニアで、さらに海外で、「もっとマクロ的に脳の機能を研究する必要がある」という流れになってきました。僕がやりたかった研究が、うまくそこにはまったのです。
関連リンク 歌・読み聞かせの効果 Baby Kumon
























