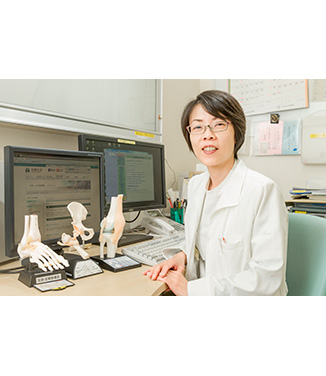農業政策のスペシャリストを目指して
 |
私は数か月前までインドにある国際半乾燥熱帯作物研究所(以下、ICRISAT)というところに所属していました。国際連合の枠組みの中にあるユニセフやユネスコは多くの方がご存じだと思うのですが、それらと同じ国連の一組織として、国際連合食糧農業機関(以下、FAO)があります。
FAOは“世界の農林水産省”として世界の農業政策の提言をしており、ICRISATはそのFAO等が主導して設立された国際組織である、国際農業研究協議グループ(CGIAR)傘下の農業研究所の一つです。
ICRISATの担う主な活動のひとつが担当作物の「遺伝資源を保護すること」です。たとえば、お米のなかでも人気のあるコシヒカリやゆめぴりかだけを今後100年、200年と作り続けていくと、その他の品種はいつしか人為的に淘汰されてしまいます。そのような状態で、もしコシヒカリに特化した病気が発生したらわれわれのお米は一網打尽です。しかし、もし食味は良くなくても病気に強い品種が保存されていれば交配によって病気に強い次世代コシヒカリを作り出すことが可能です。このように個々の作物についてそれぞれの大事な“種”、つまり遺伝資源を積極的に残していくということはとても重要なことなのです。
私がICRISATで担当していたのは「ソルガム」というトウモロコシに似た穀物で、日本では「モロコシ」とも呼ばれます。主に家畜の飼料として使われますが、ソルガムはグルテンフリーなので小麦アレルギー対応の代替品にもなり、近年はヘルシー雑穀としても注目されています。また品種によってはサトウキビのように糖を高いレベルで蓄積することから、私はソルガムを原料にしたバイオエタノールの研究もしておりました。
ICRISATを含むCGIARの目的は、(特に開発途上国における)持続可能な食糧安全保障を確立すること。簡単に言うと、例えば食糧増産と貧困撲滅です。そのためには単に収量を増やしたり、経済価値の高い品種の育種といった作物の研究だけでなく、それが持続可能な農業システムの上に成り立っていることが求められます。多くは農家の収入向上や教育、社会インフラなど地域や社会構造の改変を含むパッケージ的な提案が必要となります。
ICRISATで5年間研究者として勤め、現場に近い所で活動する中で、研究を含む「農」の方向性や枠組みを決定する仕事、すなわち農林水産省やFAO等の政策に携わる場所で働くことへの想いがますます強くなりました。研究者としてのキャリアを終えることは大きな決断ではありましたが、現在は米国農務省で米国と日本の農林水産政策の調整や日本での市場アクセス向上などの職務に携わっています。これまでの経験と今後培う専門性を併せ持つことで、米国や日本だけでなく世界の農業の向上に貢献できるよう尽力したいと思っています。
「生きる」ことを強烈に感じたインドネシア
 |
幼少期の勉強は学校と公文のみで、もっぱら運動や遊びがメインの毎日でした。習い事としては、公文の他に水泳と野球に通い、人並みに甲子園を目指して真剣に取り組んでいました。むしろ公文の先取り学習で時間に余裕があった分、学校の宿題等を特に気にすることなく運動に打ち込めたというのはあったと思います。
そんな私の人生が大きく動いたのは、中学3年生のとき。父親の仕事の転勤で、インドネシアに引っ越したのです。それまで海外旅行すらしたことのなかった中学生が、初の海外でそれも発展途上国、突然路上で子どもが物を売っている様子を目の当たりにしたその衝撃たるや。
私はそういった途上国の現実に、「生きる」ということに対する強烈な印象を受けました。惰性的な生活ではなく、その日に売り上げがなければ食べるものすら困るという“リアル”。ひょっとしたら「困っている人のために何かしたい」という原点はここからきているのかもしれません。実際、今でも発展途上国に行き現地の人々と触れ合うと、日本では享受しづらい「生きる」ことへのエネルギーを感じると同時に、初心に戻ってしっかり頑張ろう!という良い意味での刺激を受けます。
そんな私が初めての海外生活にすんなり馴染めたのは公文のおかげだと思います。英語の基礎ができていましたし、数字に国境は無いですからね。公文の教室には6歳から通い、日本にいたときと同じようにジャカルタでも現地の公文の教室に通いました。公文が私の学習の根幹にあったので、海外に引っ越しても公文をやめるという発想はなかったんですね。とはいえ、別に勉強が大好きだったというわけではなく、好きか嫌いかというより「負けるのが嫌い」というのが原動力だったように思います。公文の教材で100点を取れないことですら嫌でしたし(笑)。結果的に数学、英語、国語の3教科とも最終教材まで修了することができました。
でも公文を長く継続し、最終教材まで修了できたのは間違いなくお世話になった先生方のお陰です。今でも変わりませんが、私は自分で納得しないと決して前に進まない人間でしたので、先生方も手を焼いたことと思います。先生方はそんな頭でっかちな私を常に諭してくださり、根気良く頭を突き合わせて、一緒に問題を解いてくださったことも一度や二度ではありませんでしたから。それにスイス公文学園高等部の存在をいち早く入手して、薦めてくださったのも公文の先生でした。
スイス公文学園高等部で感じた
「慣れる」ことの大切さ
 |
スイス公文学園高等部(以下、KLAS)に行きたいという思いは、その存在を紹介された10歳の頃からうっすらとありました。両親は子ども特有の一過的な願望だと思っていたみたいですけどね(笑)。私の場合、インドネシアに住んだことで海外生活への抵抗感もなく、むしろ更なる異文化への興味や探究心も後押ししていたかと思います。
実際に今振り返ってKLASで最も良かったのは、多文化、多言語、多人種という海外環境に「慣れる」ことができたこと。外国人と接しても違和感を感じなくなるような環境やプログラムだったことがよかったです。「慣れ」を覚えたことで、現在でもアウェイであるといった環境要因によって自身のパフォーマンスが低下するということはないですね。
またヨーロッパという土地柄、さまざまな文化に直接触れ、その空気を肌で感じる経験ができたというのも、今に生きる貴重な経験でした。こういった異文化経験は、特に新しい出会いの際にお互いの距離を縮めるコミュニケーションツールとしても大変重宝しています。例えば、われわれ日本人も旅先で出会った外国人に「日本行ったことあるよ」、「東京のどこそこ知ってる」などと言われたら急に親近感が沸きますよね。
「慣れる」という意味ではKLASの先生方も多様なバックグラウンドをお持ちでした。私の在籍時のKLASの先生方の出身地は、覚えているだけでもアメリカ、カナダ、イギリス、フランス、スイス等々。同じ英語でも、それぞれが違った発音や表現をされるので、今思えば良い訓練になったと思います。
私の場合、高校3年の時にホームルーム担当だった先生の影響が大きいように感じます。彼は生粋の英国人でしたが、日本に対する理解が深く、生徒が話す“ジャパングリッシュ”を汲み取ってくれる方でした。公私にわたっていろいろとサポートをしていただいたためでしょうか、現在勤務する米国大使館でも「どうして君はそんなにイギリス英語なんだ?」とよくからかわれます。その先生に言わせたら「まだまだ」と言われるでしょうけどね(笑)。
英語はKLASで学び、「慣れる」重要なものの一つですが、何も授業だけで修練するものではないといったところもKLASらしいところでしょうか。例えばKLASではミュージカルのプログラムがあるのですが、その担当だったカナダ人の先生はコルクを噛んで行う発音練習を導入していました。ご想像の通り、英語に限らずコルクを噛むと発声しづらくなります。そのため舞台からしっかりと観客の方々に伝えるためには、よりはっきりと口と舌を動かさなければなりません。この練習をくり返すと、おのずと口と舌の動かし方を覚え、発音の矯正が行えるという訓練で大変役に立ちました。今でも時折実践している方法の一つです。このようにそれぞれの先生が、先生方の個性と経験を最大限に活用し指導をしてくださっていたのだと感じます。
関連リンク米国農務省(United States Department of Agriculture)米国農務省日本代表事務所 (USDA Foreign Agricultural Services Japan)国際半乾燥作物研究所 (International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics; ICRISAT)スイス公文学園高等部
 |
後編のインタビューから -今の道を目指すようになったきっかけ |