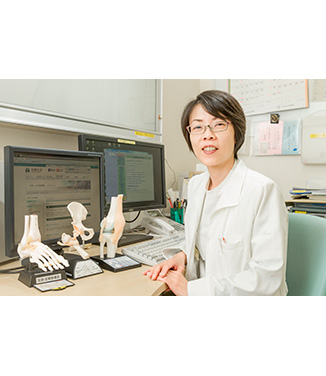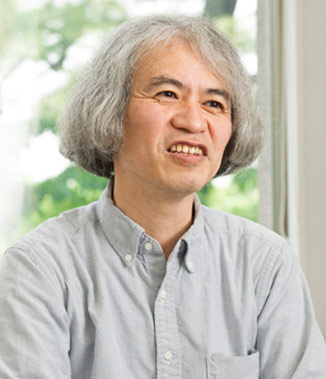日本での大学受験、そして大学生活
 |
スイス公文学園高等部(以下、KLAS)での充実した3年間を過ごして、帰国した私を待ち構えていたのは大学受験でした。KLASの卒業式は6月。そこから翌年の日本の大学受験までは予備校に通いました。小さい頃からの「医者になりたい」という漠然とした夢に向かって医学部の受験を目指していた私に、母が「おもしろい入試があるよ」と情報を持ってきてくれたのが、宮崎医科大学のユニークな入試方式でした。
残念ながらその入試方式は現在行われていませんが、当時は一定以上の学力プラス「高校3年間で何かを成し遂げた経験」がある子を積極的に入学させようという方針での入学枠がありました。国立大医学部合格がゴールになってしまって、そこで燃え尽きてしまう子も少なくない。そこで私のように「自分の好きなことをやってきた」学生たちの“伸びしろ”に賭けようという意図があったようです。
ただ、もちろん入学してからは厳しかったですね。医者の卵を育てる大学ですから、当然ながら進級はとてもシビア。6年で卒業できるのが6割程度と言われていました。大学での勉強は大変でしたが、私の場合は自分で希望して目指してきた分野だったので、それを苦には感じませんでした
整形外科医としてのやりがいは
アスリートたちの復帰した姿と感謝の気持ち
 |
大学卒業後、整形外科医になりました。大学6年間、とくに5・6年生での臨床実習を通してスポーツに関する仕事に携わりたいと思っていた私にとって、スポーツ整形はやりがいのある仕事です。さらに、たまたま医局の先輩に、サッカーの日本代表に関わっているドクターがいらっしゃいました。大学受験のときにはそんなことは知らずにいましたが、私がいまサッカーの代表活動に携わることができているのも、そういうご縁のおかげだと思います。
現在、整形外科医として向き合うことが多いのは、スポーツをしている方々です。アスリートのケガや故障の治療では、手術を含めた治療の選択やその見通し、リハビリの進め方などを説明し、「どこに目標を設定するか」を明確にしてアスリート本人と共有することを治療のスタートにしています。高校生なら「総体までに復帰を目指す」、「総体には間に合わないが、その後の大会での復帰を目指す」、「総体に出場してから手術をして復帰を目指す」とか。そのうえで、その目標に照準を合わせて、どの時期にどういう治療やリハビリを行うか計画をたてていきます。とくにリハビリは本人が納得しないと続きませんから、医者としてのアドバイスを押しつけるだけでなく、本人の考えや希望も大事にしています。そうやって診てきた選手が、ケガや故障から復帰した姿を見たときや目標としていた試合で納得いくプレーができて「ありがとうございます」と言われたときには、この仕事を選んで良かったなと思います。
U-20サッカー日本女子代表のチームドクターとしての仕事では、時に厳しい判断もしなければいけません。ケガを負っても多くの選手は「大丈夫です」と言います。そういう選手の気持ちは痛いほど分かりますが、医者として専門家の立場から、客観的な診断をくださなければなりません。チームドクターとしての今の目標は、今年11月に開催予定のU-20女子ワールドカップを全力でサポートし、無事に終えることです。
やりたいことをやるなら
まずは日々の仕事と真摯に向き合うこと
 |
私がスポーツ整形の分野で仕事をしていて思うのは、小さい頃、とくに神経系が発達する重要な時期には外でめいっぱい遊ぶことの大切さですね。神経系統の発達は5歳で80%、12歳でほぼ100%になると言われています。この時期は積極的に体を動かしたほうがいいです。
私は小さい頃からやりたいことしかやってこなかったわけですが、勉強をやるために部活をやめるとか、考えたこともなかったですね。部活をやっている子は限られた時間の中で、どれだけ集中して勉強するか考えます。そもそも人間の集中力には限界がありますから、オン・オフをしっかり切り替えることは、効率を上げるためにも重要なこと。そういう意味で、「時間」ではなく「枚数」で区切られていた公文の学習法は私に合っていたと思うんです。
ただし、やりたいことをやり続けるためには、周りを納得させることも必要ですよね。もし学生時代にスポーツに打ち込みたいなら、やらなければならない勉強もしっかり取り組むとか。単に自分の主張だけを声高に言うだけでは周りの理解を得ることは難しいと思います。
私がそう考えるようになったのには、KLASでの3年間の経験も影響しているように思います。KLASにはたくさんの自由がありました。ただし、その自由をはき違えると、厳しい事態に陥ります。自由というのは何より自分の行動に自分で責任を持つということ。もしかしたら規則でガチガチに固められるより、キツイことかもしれません。
今、私はU-20サッカー日本女子代表のチームドクターを務めていますが、海外遠征や大会の帯同で長いときには何週間も家や職場を空けるため、家族の協力はもちろん、同僚たちの理解も欠かせません。この仕事を続けていくためには、周りの方々との信頼関係が不可欠であると痛感しています。だからこそ「やりたいことがあるのだから、職場にいるときには仕事をしっかりやろう」と考えています。いざというときに「行ってもいいよ」と言ってもらえるように、日々の仕事に真摯に向き合うことを心がけています。目の前のことにしっかりと取り組んでいったその先に、きっと充実した将来があると信じています。
 | 前編のインタビューから -体を動かすことにひたすら打ち込んだ幼少期 |