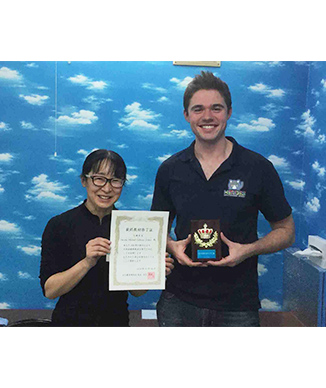足かけ20年以上「きぼう」の技術者として従事
 |
私は1995年に今の宇宙航空研究開発機構(JAXA)の前身である宇宙開発事業団(NASDA)に入り、2年半を除いて「国際宇宙ステーション計画」にかかわっています。途中「セントリフュージ」という実験室を2年間し、残りの20年以上は「きぼう」の開発・運用・利用を担当してきました。「きぼう」はISSの中で最大の実験棟で、船内実験室と船外実験プラットフォームの2つの実験スペースで構成されています。「きぼう」自体の開発は終わっているのですが、いろいろな実験を実施しているので、新しい実験装置などを作ったり、メンテナンスや改良を行ったりしています。
今やライフワークといえる私の業務は、「きぼう」の環境制御系、熱制御系を扱うことからスタートしました。環境制御系というのは、無重力な船内に空気の対流を起こすようにファンで空気を撹拌したりすること、熱制御系というのは、船内に通っている水配管が凍らないようにヒーターで制御したりする作業です。
その後、「きぼう」の中に搭載する実験装置との間の技術調整を担当しました。例えば、実験後の血液を入れる冷蔵庫ラックというのがあるのですが、船内に搭載する時に冷却水の凍結などが起きないように調整したりしました。
2005年からは技術の仕事を離れて、丸の内のオフィスでJAXA全体の予算折衝を行う部署に移りましたが、2009年から再び技術現場に戻り、「きぼう」の実験装置の運用に携わることができました。
その後、幸運にも、新しい実験装置、ExHAM(簡易曝露実験装置)の企画から構想・開発・運用までを一貫して担当できました。これは、真空や宇宙放射線など、地球上では得られない環境を利用して、民間企業などが実験をしたいという場合に、実験サンプルなどを「きぼう」船外にロボットアームで取り付ける装置です。船外に何かを取り付けるには、従来は宇宙飛行士が宇宙遊泳をして実施していましたが、宇宙服のなかは0.3気圧と低気圧になっており、1気圧との間をゆっくり気圧を変化させるために丸一日かかってしまいます。そこで、その作業をロボットで行えるように開発したのです。
ExHAMを使うと、例えば、人工衛星アンテナを新しい材料で作る時、宇宙環境で歪まないかどうかを確認することができます。宇宙にさらした実績があると、その後、大型衛星などで採用される可能性が高まり、その後につながるので企業の方にも喜んでいただけました。自分の担当した実験装置で産業界、学界などの様々な人の役に立てることは私にとっても大きな喜びでした。
今、私が一番力を入れている仕事は、将来の探査に向けた技術開発を進めるために、民間のロボットを使って宇宙での活動を自動化・自律化させる開発です。開発のスピードを上げるために、民間のロボット技術を有効に生かすことが仕事の中心を占めています。
中身がどうなっているのか知りたくて
父から贈られたおもちゃを分解
 |
私は、同窓会に参加すると、友人たちから「色白でおとなしいという印象しかなかった」と言われるほど、幼稚園や小学校の時は人と話さず、一人で考えているような子でした。一方、機械とか動くモノに興味があり、父が初めて買ってくれたおもちゃ、歯車で動くブルドーザーを、すぐにバラして壊してしまったことがあります。中がどうなっているのかを知りたかったんです。私はとても楽しかったのですが、父がすごくガッカリしてるのは、子どもながらにわかりました。
じつは先ほど紹介したExHAMも電気製品を使っておらず、アームがボルトを回しているという「からくり」的な駆動を考えて作りました。
小5の頃にはラジオを作りました。中学生くらいまで秋葉原で電子キットを買って作るのが好きで、インターホンやお風呂の水がたまったら知らせる検知器など、ひたすらハンダゴテを使って工作していました。
製薬会社に勤めていた父ですが、電気の専門学校に通っていたことがあり、自宅にはハンダゴテや工具がたくさんありました。そんな父は農業を営む親戚の家にテレビを直しに行っては、果物や野菜をもらって帰ってきたりしていたほどです(笑)。私がエンジニアを目指したのは、父の影響が大きかったと思います。
母からは、「勉強しなさい」と言われた記憶はありません。いつでも「大丈夫、大丈夫」と言ってくれて、常に私の可能性を信じてくれていました。今でもそうです。小1の時、公文式に出会ったのも母のお陰です。通っていた教室の先生にはずいぶん長くお世話になり、結局国・数・英の3教科を高3まで続けていました。長く続けられたのは、進度が遅かったからなのですが、私は黙々とやることは好きだったので、自分のペースでできる公文式のスタイルが向いていたのでしょう。
公文式の教材は、完全に段階的にやれるようにできていますよね。仕事で行うプロジェクトマネジメントでも、基本設計、詳細設定を行い製造していく、という段階的な流れをたどりますから、このときの学習で身につけた力は今の仕事にも役立っています。
宇宙への興味はテレビ番組がきっかけ
スペースシャトルの活躍に胸を躍らせる
 |
宇宙に関心を持ったのは、NASA(アメリカ航空宇宙局)の開発したボイジャーという惑星探査機を取り上げたテレビのドキュメンタリー番組『コスモス』をみたのがきっかけです。私が小5の頃で、7歳上の姉も好きで一緒に観ていました。番組はアメリカの天文学者、カール・セーガン氏が監修しており、番組で紹介された「宇宙を向くと地球の国境が消えて、人類が一致団結できる」という考えには大変感銘を受けました。
この時は惑星への憧れから関心を持ちましたが、天体観測ではなくて、むしろ惑星探査機など機械の方に興味が向いていましたね。中学時代には、将来の夢として「ロボット工学者」と書いていました。
そして、高校1年生の時に忘れられない出来事が起こります。1986年1月に起きたアメリカのスペースシャトル「チャレンジャー」の爆発事故です。NASAはもう一度打ち上げようと、原因を解明するなどして、1988年9月に「ディスカバリー号」、12月に「アトランティス号」の打ち上げに成功しました。
じつは私は当時、大学受験に失敗して再挑戦していた時期。このスペースシャトルの再挑戦に心を揺さぶられ、浪人中も頑張ることができました。そして自分もそうした宇宙開発に関わる仕事に就きたいと思うようになりました。
しかし、大学に入れたのはいいのですが、3年生になる前、専門分野を決める際に試練が訪れます。本来は「宇宙工学科」に進みたかったのですが、選考に通らず、「産業機械工学科」に進むことになったのです。夢が破れたというか、なかなか航空に縁がありませんでした。ところが、ここで熱・環境制御やロボットの基礎を学べたことが、今とても役立っています。
ISSの開発に加わりたいと思うようになったのは大学院時代です。1993年12月のニュースで、アメリカとロシアがISSを通じて協力するという構想を聞いたことがきっかけでした。当時、軍事や経済で対立していた両国が協力するということに、「宇宙開発によって、冷戦が終了し国境がなくなろうとしている!」と感動し、ISSに関われそうな宇宙開発事業団(当時・現在のJAXA)の入社を目指しました。
関連リンク JAXA宇宙航空研究開発機構
 |
後編のインタビューから -難しい道を選ぶ意義 |