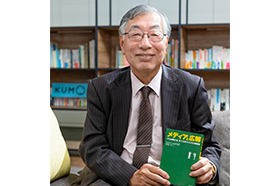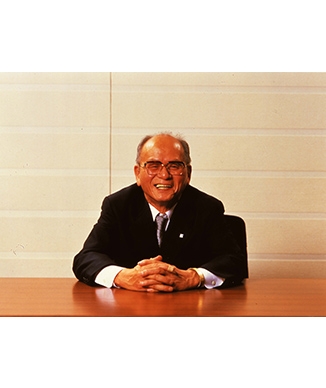メディアと広報の「越すに越されぬ溝」を埋めるために
 |
私が新聞社を定年退職したのは2010年。その1年前に、定年後に向けて3つの目標を作りました。1つめは「地元への貢献」です。これは地元の教育委員や少年野球チームの代表という形で実現しています。2つめは「マスコミの後輩を育てる」。実際、複数の大学でマスコミ論や広報メディア論を教え、10数人の教え子を記者として送り出すことができました。そして3つめが、「メディアと企業広報をつなぐ」ことです。そのために「メディアと広報研究所」を立ち上げて活動しています。
私は新聞記者として約20年、さまざまな企業や人物を取材し、その後約15年は広報部長や宣伝部長など務め、取材を受ける側になりました。立場が逆転し、取材する側・される側の両方を経験したことで、メディアと広報にはお互いに「誤解」があることに気づいたことが、この研究所を立ち上げるきっかけになりました。
「誤解」とは、例えばメディア側は、「企業の広報は自分の会社をガードするだけ。自社内のことはよく知らないのに、マスメディアに対しては偉そうにしている」。その一方、広報を仕事にしている側は、「メディアはわかったふりをして聞いているが、本当にわかっていないのではないか」といったことです。それぞれが勝手に思い込み、「越すに越されぬ溝」がある。その溝を埋めたくて定年退職を機に活動を始めました。
具体的には、企業広報の幹部、中堅、若手担当者を対象に、メディア関係者を講師に招き、マスコミ業界の実情や取材対応のコツなどを解説する研修を開催したり、企業広報についてのコンサルティングを行ったりしています。
こうした研修は、他でも開催されていますが、多くは参加者が40~50人規模です。対して私の研修会では、「少人数広報研修会」と銘打ち、最大でも10数人、かつ1業種1社としています。そうすることで、よりホンネで語り合いやすく、濃い情報交換が期待できるのです。
近年はデジタル化、リモート化が進み、直接会わなくて済むことも増えてきました。コロナ禍でそうした傾向は加速してきています。しかし私は、コミュニケーションというのは直接会ってこそ深まるものだと考えています。そこをどうカバーできるかが、これからの課題です。
私の研修会もコロナ禍でオンラインでの実施となって、ちょっともどかしく感じているところです。一方でSNSなどにより、いろいろな情報が簡単に得られるようになってきました。企業も、よりメディアを意識することが増えてきているのではないかと思います。
普遍的な人間教育だからこそ国際的に普及する公文式学習
 |
私の小規模の研修会にKUMONの広報社員が参加してくれており、今回のインタビューに繋がったわけですが、実は今は成人している私の3人の子どもたちも、小さい頃公文式教室に通っていました。また妻が、KUMONの子育てに関わる相談員として長年勤めています。そのためKUMONにはよいイメージしかありませんが、一番素晴らしいと感じていることは、国際化が進んでいることです。
公文式学習は、50を超える国、地域に展開されているそうですが、偏った地域にだけ普及しているのではなく、同じ学習スタイルでいろいろな地域に浸透していることに何より驚嘆します。こうしたことは、日本の新聞社には残念ながらマネできない快挙です。KUMONのように日本発の教育産業が海外で通用しているケースはそれほど多くはありません。
日本の近代教育は、明治時代に欧米から輸入されて発展しました。しかし過度な画一性を求めたり、過剰な管理をしたりと問題が指摘されるようにもなりました。いわゆる有名な学校への入学を目指した「受験教育」は、現在も続いていると感じます。
一方、公文式学習は、そうした子どもたちを締め付けるような教育ではありません。今はコロナ禍なので難しいこともあるかもしれませんが、公文式学習は人間教育の普遍的な方法であり、だからこそ地域や民族を越えて普及し、国際的に通用しているのではないかと思います。日本の教育レベルの高さを示す意味でも、日本発の教育サービス企業として、今後も国際的に発展することを期待しています。
中高時代の趣味は野球、ロック、そして新聞
 |
私は子どもの頃からずっと新聞記者になりたいと思っていました。きっかけは小学生のときに観た『連続ドラマ 事件記者』というテレビ番組です。そこでは新聞記者たちが昼間はマージャン、夜は居酒屋でワイワイし、その合間に刑事さながらに事件を解決してしまう。自由でありながら社会の役にも立っていて、記者っていいなと憧れました。
当時、自宅では朝日新聞と読売新聞の2紙をとっていましたが、特に新聞に興味があるからという積極的な理由ではなく、付き合いでとっていたようです。読売新聞については、野球好きな一家だったので、ジャイアンツの記事を読みたかったのでしょうね(笑)。
中学生になると新聞委員になって壁新聞を作っていました。高校時代は野球をしたりビートルズなどのロックに熱中したり。両方とも当時の流行でした。私は根がミーハーなのです。友人とバンドを組んでドラムを担当し、自宅のガレージで練習していると、騒音だと苦情がきたこともありましたね。
大学は新聞記者になる人が多い早稲田大学か慶應義塾大学を志望していましたが、どちらも受からず、1年浪人したのち学習院大学へ。入学してすぐに新聞部の部室へ直行したところ、先輩たちから「授業はいいから部室に来い」などと言われ、その熱心な様子に「これなら新聞記者を目指せるかも」とワクワクしたことを覚えています。それにマージャン台を囲んだり、何かあるとお酒を飲みに行ったりと、夢を抱くきっかけとなったドラマと同じ風景が繰り広げられていたことも、新聞部に入部したきっかけとなりました。
私の入学当時は「学習院新聞」といって、付属の小学校までにも配布している新聞でした。でも大学生が作っていたので、高校以下のことはほとんど記事にはしておらず、私が中心になって大学生だけを読者とする「学習院大学新聞」に改変しました。私は初代編集長となり、著名な卒業生をインタビューしたり、映画研究会の友人を通じて映画の新しい見方を執筆したりして、年に10数回くらい発行していました。読者の反響はあまり記憶にありませんが、作る側としては楽しかったですね。
そして大学4年になり新聞社を受けるわけですが、当時は新聞社や通信社、大手出版社の入社試験はこぞって同じ日に行われ、1社しか受けられませんでした。ところがその1社に落ちてしまったので、1年留年した後、幸運にも読売新聞社へ入社することができました。
関連リンク メディアと広報研究所
 |
後編のインタビューから -記者人生20年の中で学んだこととは? |
おすすめ記事
-

学習経験者インタビュー
Vol.093
弁護士・ニューヨーク州弁護士
松本慶さん少しずつでも前進すれば大丈夫 「一日一歩」の精神で歩いていこう
-

KUMONグループの活動
Vol.251
療育のなかのKUMON-放課後等デイサービスでの取り組み
障害のある子たちによりそい 一人ひとりが幸せになるサポートをしたい ~ ライフステージに合わせた“つながる療育支援”をめざして ~
-

KUMONグループの活動
Vol.510
公文式英語で世界とつながる経験をきっかけに
将来を一つひとつ切り開くことができた 間違いをおそれずに挑戦しよう
-

KUMONグループの活動
Vol.486
学校でのKUMON-長岡英智高等学校
『やればできる』の体験が チャレンジ精神を育み 夢や目標を描く力となる
Rankingアクセスランキング
- 24時間
- 月間