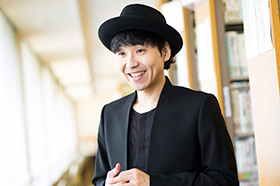自然が遊び場、いつも「なぜ」と疑問を持っていた
 |
ぼくが研究しているオノマトペとは、フランス語で「擬声語」、つまり「擬音語」と「擬態語」の総称です。「擬音語」はものが発する声や音で、たとえば「ニャーと鳴く」「雷がゴロゴロ鳴る」、擬態語は状態や心情を表すもので、「星がキラキラ光る」「ワクワクする」などです。一言でものごとの本質を言い当てたり、秘めた力を引き出すなど、魔法のような力をもっています。
これらを日常生活に取り入れることで、人生をより楽しくしていけるのではないかと、言語学、音声言語情報処理、ヒトの情報処理特性の視点から分析・測定して研究しています。理論だけでなく、たとえばストレッチをするとき、無言よりも「ニャー」と言いながらのほうが伸びるなど、実験をくり返してその効果を検証しています。
ぼくは、小さいころから声を出しながら走るなど、少し変わった子ではありました。声を出して走ると早く走れるんじゃないか、と潜在的に思っていたのかもしれません。喜怒哀楽も激しく、よく笑いよく泣く子でした。今でもうれしいことがあると人より強くそのうれしさを感じるので、「共感力が高い」と言われます。
子どものぼくに対して両親は「あの池でカエルが泣いているね」「あの木にカブトムシがいるみたいね」と、ぼくの興味を引き、行動を促す言葉かけをよくしてくれました。そう言われるとそこへ行きたくてたまらなくなり、1日中飽きずにカエルや昆虫を観察していました。すると、「このカエルはなんというカエルかな?」「トンボはなぜ飛べるのかな?」と、いろんな疑問が生まれてきます。そしてその疑問を自分で図書館で調べるようになりました。
仲間とザリガニ釣りをしたり、姉と一緒に花を観察したり、当時をオノマトペで表現すれば、ルンルン、ワクワク、ドキドキ、ハラハラな毎日。やはり自然と戯れると、思わず「ワーッ!」と感動の声が出ます。声が出れば出るほど、気づきがあり、得る物が大きくなるのだと思います。
家にじっとしていられず毎日野山を駆け回っていたぼくですが、家の中で唯一集中できたのがマンガです。読むのも描くのも大好きでした。マンガには「ドン」とか「バーン」など、オノマトペが多用されています。分厚いマンガをあっという間に読めたのは、オノマトペがあってリズムよくページをめくれて、臨場感たっぷりで面白かったからだと思います。
紆余曲折を経てたどりついたオノマトペ研究への道
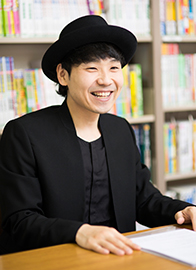 |
高校時代は、コム・デ・ギャルソンを立ち上げたファッションデザイナーの川久保玲さんに大きな影響を受け、デザイナーになりたいと思っていました。服飾関係の専門学校に進みたかったのですが、母から「あなたのデザインした服は本当に評価されるの?大学に進んで、まだどうしてもデザイナーになりたかったら、そこで考えたら」と言われ、悩みに悩んだ末に大学へ進みました。
でも在学中、頭の中はデザインのことばかり。独学でデザインの勉強を続けていたので、今でも自分でジャケットなど作れるほどですが、当時はデザインを究めるのは難しいかなと感じていたこともあって、もう1つ関心があったオノマトペに集中するようになりました。
大学卒業後は、大学院に進みました。やりたいことの整理がつかず、時間が欲しかったんですね。進学に際して母からは、「親がとやかく言うのは大学まで。あなたの人生なのだから100%自分で決断しなさい。進学でも就職でも海外へ行ってもいい。ただ、生きる力、稼げる力、専門的な知識は極めたほうがいいんじゃないかな」と言われましたね。今思うと、デザイナーへの道は迷っていた時点でダメだったと思います。いけると思えばいけるし、ダメかなと思ったらダメ。直感を大事にしたほうがいいと思います。
大学院では心理学や生理学、音声言語情報処理、教育工学などを学際的に学びました。当時オノマトペの研究には、言語学的なアプローチしかありませんでしたが、ぼくはその機能を身体性に持ち込めないかと考えていました。オノマトペは声に出すことで、心と体にプラスの作用を及ぼすことがわかってきたので、身体性とオノマトペ、ICTとオノマトペというように、言語学だけに閉じ込めておくのはもったいないと感じたのです。
オノマトペにはまったきっかけは、 長嶋監督の「ビューっと来たらバシンと打て」
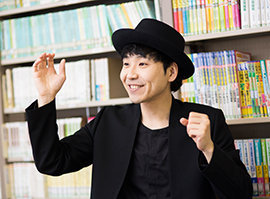 |
そもそもオノマトペに興味をもつようになったのは、小学生のころ。「グッ」「サー」など擬音語、擬態語を多用する長嶋茂雄さんの指導法を知ってからです。本当に選手に伝わっているのか疑問でしたが、「ビューっと来たらバシンと打て」と指導された選手が直後に活躍したという伝説もあり、その効果を調べたいと思ったのです。
それまで擬音語、擬態語ということばは知ってはいましたが、それが「オノマトペ」でフランス語だということは図書館で調べて知りました。小さいころから「不思議だな」と思ったら図書館で調べる習慣が生きたのですね。考えてみればマンガでも使われていたし、自分もよく描いていました。断片的なピースがひとつの塊、「ワンピース」になってきたと感じました。
じつは博士課程に進む前、周囲からは「オノマトペの研究で博士課程に進んで、その先どうするの?」と言われましたが、やりたいことをやらなければ後悔すると思い、動じませんでした。覚悟をもっていたので、3年間必死でした。普通にしていても道はない、できることはとことんやろうと思いきり、学会では著名人が使っているオノマトペをテーマにプレゼンしたりしました。
そのうち「オノマトペをコーチングに活かせないか?」と、コーチングの専門誌から声がかかり、原稿を書くことに。その後に上梓したのが『スポーツオノマトペ――なぜ一流選手は「声」を出すのか』(小学館)です。一人でも多くの人に読んでいただきたかったので、自分でPOPを作成し、「この本の著者ですが……」と、さまざまな書店に売り込みに行きました。すると本を平積みにしていただけて。書店員さんたちに情熱が伝わったのかなと、うれしかったですね。今でも出た本は全部、当時と同じように手作りPOPを手に自分で書店を回っています。
その後、著書を出したことでテレビやラジオからも出演依頼が来るようになり、大学院生時代からメディアでオノマトペを発信するようになりました。
関連リンク
私のオノマトペスタイル 藤野良孝