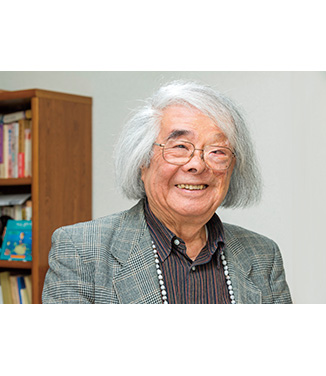昔話は音楽と同じ
リズムの楽しさを壊してはいけない
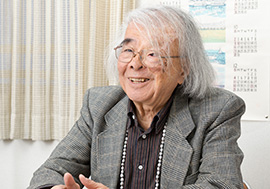 |
みなさんは「昔話」というと、何をイメージしますか。昔話は、口で伝えられてきたお話です。口で伝えられてきたということは、「耳で聞いて」伝えられてきたということ。聞き終ったら消えてしまう、聞いている間だけのもので、音楽と同じ「時間にのった文芸」なのです。
昔話は同じ場面が出てきたら同じ言葉で繰り返します。これも音楽と同じです。しかも繰り返しはだいたい3回。たとえばグリム童話の『白雪姫』は、1度目は紐で、2度目は櫛で、3度目は林檎で殺されます。アニメや映画では林檎だけなので、ご存じない人もいるかもしれませんが、じつは3回殺されているのです。
音楽も、同じメロディを2回繰り返します。そして3回目は少し長く、一番強調されています。つまり3回目が一番大事だということです。これが音楽の基本的なリズムで、このリズムは昔話にもあります。白雪姫も林檎のシーンが一番長いでしょう。ホップ、ステップ、ジャンプという陸上競技のリズムも同じです。人間にとって、このリズムが一番自然だからです。
このリズムは、子どもだけでなく、大人にとっても心地よいもの。そしてその楽しさを壊さないことが大事です。けれども残念なことに、昔話に関しては、たくさん本が出ていたり映画にもなったりしていますが、3つのリズムの前の2つを省略してしまうなど、本来の昔話の「語り口」から離れてしまっているものが多いように感じます。そのことに気づいてもらい、「語り口」がきちんとしている文章を選んでほしいし、さらにそう指導できる人を日本中に広げたい。そんな思いから、全国各地で開く「昔ばなし大学」に、いま力を入れているところです。
「涙を知るのはいいことだ」
敗戦を迎えて父が言った言葉は忘れられない
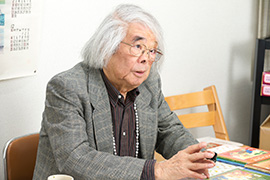
ぼくは満州事変が起こる1年前、昭和5年に満州で生まれ、小学5年生までを北京で過ごしました。とにかくわんぱくで、悪さばかりしていましたね。当時暮らしていた中国の家は、隣家と屋根がつながっていて、屋根から屋根へひょいと伝い歩けるので、屋根伝いにどこまでも行ったりして。
父は満州で歯科医をしていましたが、その後政治団体に関わるようになります。昭和15年頃になると、父は「この戦争は勝てない」と言い出します。政治評論集を作り、軍部批判をしていたので、軍部からは睨まれ、自宅には毎日憲兵が来て監視されていました。
翌年には父以外の家族が日本へ戻り、その2年後には父も日本へ。東京の立川に住みましたが、そこにも今度は特高警察が毎日来る。それでも父は国のことを憂いて平気で軍部批判をするので、いつ捕まるかとヒヤヒヤする日々を過ごしました。
ところが結局そのまま終戦を迎えましたが、その後父が亡くなったとき、特高として監視していた方から、ていねいなお悔やみの手紙をいただいたのには驚きました。そうした方たちも、父が憂国をもって信念を貫く姿を、じつは慕っていたのかもしれません。そしてぼくも、こうした父の姿に大きな影響を受けたのは言うまでもありません。
父が敗戦直後には、「この敗戦は日本にとっていいことだ。日本は日清戦争以来、負けていないから涙を忘れてしまった。これで涙を知るのはいいことだ」と言ったのも忘れられません。そして、ぼくら子どもたちには、「お前たち、好きなことをやれ」と言いました。
母はクリスチャンで、ぼくらも教会の日曜学校に通い、賛美歌を習いました。それが我が家の音楽との付き合いの始まりでした。すぐ下の弟(=小澤征爾氏)は指揮者になりましたが、ぼくも音楽が大好きになり、コーラスは今も現役で続けています。
柳田國男先生の一言で、
日本の昔話の研究を始める
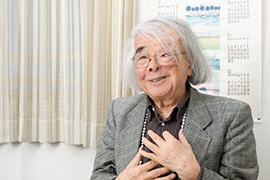
音楽と同じくらい好きだったのが文学です。なかでも、医師であり神学者、音楽家でもあるシュヴァイツァーに心酔し、関連図書をたくさん読みました。そのうち原書で読みたくなり、ドイツ語を学ぼうと、ドイツ文学者の関泰祐(せきたいすけ)先生が在職されていた茨城大学へ進学しました。
2年目に、二人の先生がドイツ語の教科書としてそれぞれ「ふしぎなオルガン」と「グリム童話」を読んでくれたときに気がついたのですが、同じドイツのメルヒェンなのに何か違う。先生に質問すると、「グリムは昔話だから」と言うのです。それまでぼくは、グリム童話はグリムの創作だと思っていたので驚きました。そして昔話なら民族の考えや風習などが読み取れるのでは、と興味がわき、研究することにしました。
大学の図書館からグリム童話の原書を借り、辞書を引きながら読むと、がぜんおもしろい。衝撃的だったのが、日本の昔話と同じ話を2つ見つけたことです。1つは「たいこたたき」で、これは「天の羽衣」。もう1つは「コベルスさん」で、これは「さるかに合戦」と同じストーリーです。なぜこういうことが起きるのか。この時にグリムを卒論にしようと決めました。
研究を続けたくて東北大学大学院へ進み、修士論文を書いている時のこと、ドイツのある専門雑誌で調べたいことが出てきました。その雑誌は、日本民俗学の創始者である柳田國男先生の研究所にしかないことがわかり、ドキドキしながら訪問し、雑誌を見させていただきました。帰り際に柳田先生から、「何を研究しているのか」ときかれ、ものすごく緊張しながら答えました。ぼくが話し出すと、先生は「ちょっと待って」と、なんとぼくの言ったことをノートし始めたのです。こっちはまだ20代で駆け出しもいいところ。かたや80歳を越えられた先生は神様のような存在です!年齢差は関係なく、知らないことは全部吸収しようとする姿勢に、「学者とはこういうものか」と、感動しました。
ぼくは勉強したばかりだったので、うれしくていろいろ話しました。そしてお暇しようとすると先生が「きみ、グリム童話をやるなら、日本の昔話もやってくれたまえ」とおっしゃった。「そうか、ぼくは日本人なのだから、日本の昔話も研究しなくちゃ」と、その時に決めました。
柳田先生は、戦後の日本の昔話の状況をとても心配されていたのです。というのも、「昔話は無知な農民がつくったものだから、もっと文学的なものにしなければ」というブームが起こった結果、話の内容が変わったり、過剰な装飾が施されたりして、本来の昔話の姿ではないものが流布してしまっていたからなのです。
関連リンク 小澤昔ばなし研究所
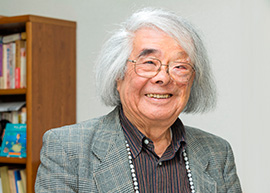 |
後編のインタビューから -研究者になるために決意した3つのこと |