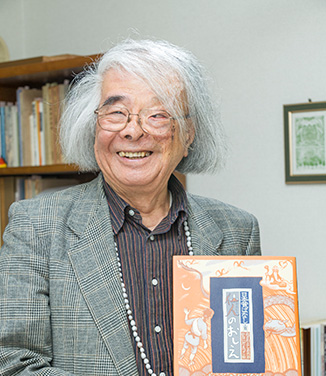研究者になるために決意した3つのこと
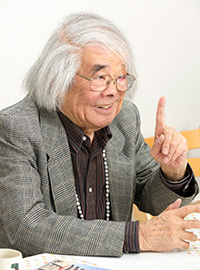 |
ぼくは大学での研究生活のあと、1992年に「昔ばなし大学」を全国で開講し、1998年に「小澤昔ばなし研究所」を創りました。グリム童話に始まり、昔話をずっと研究してきたわけですが、その間、迷いは一切なかったですね。
大学入学時、専攻していたドイツ文学では、優秀な仲間がたくさんいて、それに比べると自分は並の研究者だと気づきました。でも、昔話の研究者になりたい。そのためにはどうしたらいいか、3つのことを考えました。1つは幅を広げないようにすること。2つめは人より3倍時間をかけること。3つめは人より長期間やること。その原則でいままで来ています。逆に才能のありすぎる人はいろんなことをやりたがり、まとまった成果を上げられなくなります。学生たちを教えていた頃にも、よくこの原則の話をしました。
大学院卒業後、東北薬科大学でドイツ語を教えながら、グリムの勉強もずいぶんしました。初めてドイツへ渡航したのは36歳のときで、研究者としては遅いほうです。でもぼくは「いつか行けるだろう」と考え、焦らなかった。最初は世界のメルヒェンの百科事典を制作する手伝いのために半年間、その数年後に客員教授として招かれ、家族同伴で2年間ドイツに暮らしました。
「昔話は聞くのが楽しい」というのは、フィールドワークで実感していたので、息子たちにも聞かせたりしていました。そして今は孫に読んでいます。いや、逆に孫が読んでくれますね。もちろんぼくは、相づちを打ちながら一生懸命聞きます。相づちは、語りと対なので、とても大切です。お父さんもお母さんも、子どもが何かを言ったら、聞き流さないではっきり相づちを打って聞いてくださいね。
昔話は人間の成長の姿を語っている
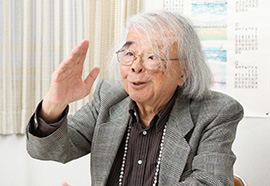
大学で教えていた時は、学生を連れてあちこちの農村を訪ね、土地のおじいさん、おばあさんに聞き取りして、昔話を調べていました。ある78歳のおじいさんは、「うちのじんつぁま(=じいさま)から聞いた」と、12話も語ってくれました。「じんつぁま」から聞いたのは8歳くらいの時までで、大人になっては二度兵隊に行っているし、お孫さんにも語ったことがないという。なのに、なぜ70年前の話を思い出して語れるのか、不思議でした。
でも、1話終わると、ひじをついてじっと思い出している姿を見て気づきました。思い出しているのは昔話だけではなく、「じんつぁま」のたばこのにおいや囲炉裏のにおい、周りの暗さ……話を聞かせてくれた「じんつぁま」全体とその情景全体なのだ。それで昔話も思い出せたのだ、と。
「じんつぁまのこと、思い出すだろうね」と言うと、「うん、思い出すね」。その一言でぼくはそれを確信しました。話の言葉を覚えるのとは違う、語り手の姿、ぬくもりを覚えている。「じんつぁま」との強い人間的な結びつきがあるから、その「じんつぁま」が語ってくれた昔話を思い出せるのです。そうやって昔話は語り伝えられてきたのです。
そのおじいさんが「じんつぁま」から語り継がれてきたように、昔話は、おじいさん、おばあさんが孫に伝える「隔世遺伝」です。おじいさんは、昔は悪ガキだったわが子でも、今は親をやっている姿を見ているから、「子どもはちゃんと育つ」ことがわかっています。
昔話というと、「はなさかじい」など教訓ものが有名ですが、昔話にも「子どもの成長」が織り込まれています。教訓ものに登場するのは、じいさんかばあさんで、良いじいさんは最後まで良いじいさんと性格は変わりませんが、多くの昔話は主人公の性格は変わります。はじめは間が抜けていても、最後は賢くなる。
「三年寝太郎」のお話が好例です。寝てばかりいる若者が、あるとき悪知恵を出して長者の娘の婿になる話で、大人は「道徳的によくない」と言います。でも、ちょっとした悪知恵を働かせることは誰にでもあり、その意味で本当の人間の姿を伝えています。そして、「寝太郎」の姿は「若者の変化」そのものです。だからぼくはこの話が大好きです。
若いときにはいい加減でも、30~40歳になればちゃんとやっている。そんなぼくの「寝太郎理論」にあてはまる人はいっぱいますよ(笑)。ぼくは長い間大学で教えましたが、勉強しない学生がたくさんいました。でも卒業して20~30年も経つと、皆、すまして立派な大人になっていますから。
子どもは「育てる」のではなく「育つ」もの
大人は子どもを信頼しよう
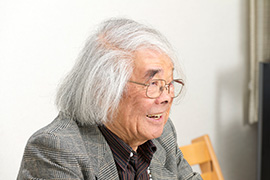
昔話からわかるように、子どもは自らの力でちゃんと育ちます。それを理解し、子を信頼すればよいのですが、今は、親が子どもに口を出し過ぎてはいないでしょうか。
もみの木をご存じでしょう。我が家の息子たちが小さいとき、クリスマスツリーにしようと、庭にもみの木の苗を植えたら、少しずつ先の尖ったきれいな形に育ってきた。クリスマスが楽しみだと思っていたら、それらしく揃い始めていた上の方を、ある日植木屋さんにバッサリ剪定されてしまいました。がっかりしたんだけど、しばらくするとまた見事に先の尖ったきれいな形に戻ったのです。もみの木は「おれの姿はこういう姿なんだ」と主張しているのです。
もみの木でさえ、自分の意思を持ち、復元力がある。だから人間の子だって、「自分はこういう姿でありたい」という意思をもっているはずだと思うのです。大人が脇から「こうしなさい」「早くやりなさい」「もっとたくさんやりなさい」などと言うのは、大人の支配欲ではないでしょうか。大人がやるべきことは、子どもがもみの木みたいに、すくすく生きていけるよう手助けをすること。信頼し、育つ環境を作ってやることです。今、子どもはあまりにも手を加えられ過ぎている。人は盆栽ではないのです。
ぼくの母は、ぼくらの手が離れたころ、「わたしはうちのなかで空気のような存在でありたいと思っていたのよ」とポツリと言ったことがあります。空気はふだんはその存在に気づきませんが、でもなければ生きていけません。父はぼくらの家が戦後貧しかったときに、音楽好きなぼくらのためにピアノを買ってくれた。「こんなに貧乏なのに……」と、親戚からは批判されたようですが、父は「おれの自由教育が正しかったかどうかを証明するのはお前たちだ」とぼくらに言ったことがあります。ぼくは「証明できないはずはない」と思いましたね。父も母も、ぼくら子どもたちを完全に信頼していました。
その目で見ると、現代の親子関係の状況はとても気がかりです。「子どもは無限の可能性を持っている」とよく言いますが、それは「大人が干渉さえしなげれば」という条件つきです。幼いときから、大人が子どもの可能性を一生懸命つんでしまっていないか、心配です。子どもは自ら成長し、変化するもの。そうした当たり前で大切なことを、昔話は教えてくれています。大人は、慌てずに焦らずに、子どもたちを信頼して、温かく見守っていてください。
関連リンク 小澤昔ばなし研究所
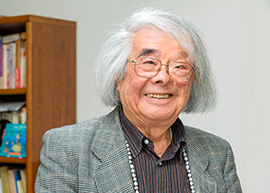 |
前編のインタビューから -昔話が大事にしているリズムとは? |