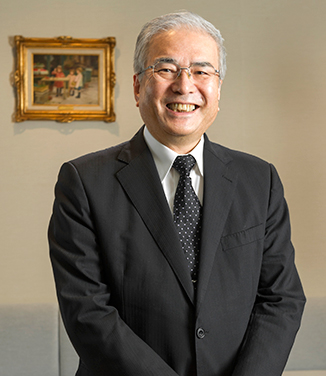大阪外国語大学学長を経て
真の国際的人材を育成しているAPUへ

そうして中国現代文学の研究者としての道を歩み、鹿児島経済大学や大分大学、そして母校の大阪外国語大学での教授を経て、2003年には大阪外語大学の学長に就任しました。その後、2007年には大阪大学との統合をまとめることになります。もともと大阪外国語大学は司馬遼太郎や陳舜臣などを輩出した、素晴らしい歴史をもった大学でした。そのDNAを引き継ぎ、大阪大学の外国語学部に25言語の専攻課程を残せたことは、私にとって重責を果たせた点だと思っています。
何よりこのときは、教職員をひとりも辞めさせることなく統合をまとめることができて、ほんとうにほっとしましたね。結局辞めることになったのは、学長職がなくなった私だけでした。そんなときにAPUに声をかけていただきました。大阪外国語大学と大阪大学の統合が達成できたくらいなら、多言語・多文化のAPUでも学長が務まるのでは、と思われたようです。
大分県別府市のAPUは、周囲には何もなく、“修道院”と呼ばれるような約42万平方メートルの広大なキャンパスが広がっています。初めて訪れたときには驚きましたね。統合の際に両大学が掲げた理念「真の国際的人材を育成する」が、APUではすでに実践されていたからです。
どういうことかというと、まずAPUには「言語のバリア」がありません。多くの大学は特別なコース以外は日本語ができないと学べませんが、APUは日本語ができなくても構わない。英語で学ぶことができます。もちろん、日本語ができない学生は入学してから徹底的に教えますが、スタート時点での言語的な束縛がないのです。
もうひとつは、どんな少人数のクラスでも多国籍だということです。そのため、授業の中で国籍や民族の違いが鮮明になることもあります。そこでは、民族的な自我や利己的な意識を持っていては人間関係をうまく築いていけません。つまり、APUでは誰もが一人の人間としてどうあるかを問われ、「心の中の国境が消える」のです。
自己変革を促す「マジックキャンパス」
 APUではグローバル化に即応したカリキュラムを組んでいますが、現実生活としての寮やサークルでは、自身のアイデンティティが問われます。それは、「アイデンティティを消す」ということではなく、自国の言語や文化、宗教を見直し、「自分はこういうものだ」と再定義して、自分とは異なる他者と付き合うということです。
APUではグローバル化に即応したカリキュラムを組んでいますが、現実生活としての寮やサークルでは、自身のアイデンティティが問われます。それは、「アイデンティティを消す」ということではなく、自国の言語や文化、宗教を見直し、「自分はこういうものだ」と再定義して、自分とは異なる他者と付き合うということです。キャンパスに足を踏み入れた時点で異文化に投げ込まれるわけですから、そこで人間関係を築いていくには、まず自分を確かめないといけません。APUでは学生たちにそういう意識が自然と生まれ、その意識が広大なキャンパス全体に行きわたっているのを感じます。
一言でいえば、APUは「マジックキャンパス」。“自分は変われる、変わろう、成長しよう”という気持ちを起こさせるキャンパスなのです。私も含めた教職員も学生も、ここで大学生活を送ることで、“自分は変わりたい”という気持ちを持つようになります。私はこの9月で72歳になりましたが、この年齢になっても自己変革をしようと思えるほどです。
私が2012年に博士号を取得したのも、このキャンパスの力かもしれません。APUでは駐日大使に顧問になっていただき、「いつでも視察にきて留学生と話をしてください」とお伝えしているので、各国の駐日大使がよくキャンパスにみえます。その方々の多くは博士号をもっています。ですから、私も「自分も取らなくては」という気になったのです。
そんなAPUのこれからについては、学長として、いまあるシステムを継続していきつつ、カリキュラムの精度を上げ、教授陣の質を高めていきたいと思っています。APUは国際経営学部とアジア太平洋学部の2本の柱で動いていますが、この分野でアジアにおけるトップクラスの大学にしていきたいと考えています。
自分という存在はかけがえのない大切なもの
親や教師はその認識を伝えていこう
 「グローバル人材」が話題となる昨今ですが、日本人にとってのグローバル化の課題は、語学というよりは、日本人のメンタリティにあると思います。APUの学生たちからは、出身地域による先入観や排除意識は感じられません。その意味でも、APUは「真の国際人」が育っていると自負できます。
「グローバル人材」が話題となる昨今ですが、日本人にとってのグローバル化の課題は、語学というよりは、日本人のメンタリティにあると思います。APUの学生たちからは、出身地域による先入観や排除意識は感じられません。その意味でも、APUは「真の国際人」が育っていると自負できます。自分とは異なる他者を排除したり差別したりしない、言い換えれば、真のグローバル人材になるには、親や先生の言動の影響が大きいのは言うまでもありません。いまの教育現場や子どもを育てる環境においては、いじめや虐待をはじめ、さまざまな問題が指摘されています。
まずは親も先生も、「自分という存在は、ほかにはなく、大切なものなのだ」「生まれてきた一人ひとりがどれだけ尊い存在なのか」ということを、子どもたちにきちんと教えるべきではないでしょうか。それが伝われば、自分とは異なる他者が現れても、「相手も大切な存在なのだ」と、相手の存在も認めることができ、仲間はずれや差別意識が生まれることはない。他人を傷つけることもなくなるはずです。
家庭では、親は子を慈しんでほしいですね。家庭に帰って、自分が守られていると感じられれば、子どもは安心して健やかに育つのではないでしょうか。その意識がベースにあれば、子どもは夢を持ち、自信をもって迷いなく突き進んでいける。それが、最終的には「人々が夢を持てる社会」につながっていくと思います。
関連リンク
立命館アジア太平洋大学
 | 前編のインタビューから -絵を描くのが好きだった子ども時代 |