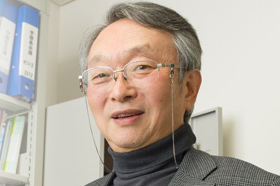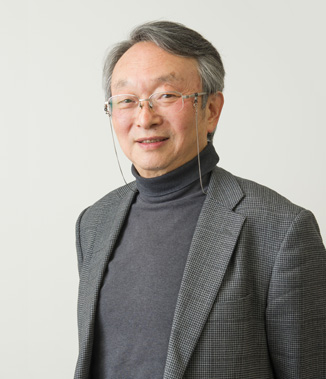英語教育の大きな転換期だからこそ その課題と解決策を見出す

2011年度から、小学校では5・6年生において、「外国語活動」として英語が必修になっていますが、これが正式な教科に格上げされることが検討されるなど、いまはちょうど日本の英語教育が大きく変わろうとしている時期です。そうしたなか、わたしは英語教育の具体的な課題とその解決策を明らかにするための調査や研究活動も行っており、大学での講義はもちろん、文部科学省が主催する委員会や各種会議にも関わっています。
大学では学部と大学院で講義を受けもっています。赤ちゃんがどうやって言葉を学ぶかという言語習得から、ヒトがどうやって言葉を使うかの心理的な側面での言葉の使い方を研究する「心理言語学」のほか、バイリンガル教育、外国語教授法などを教えています。
調査や研究の一例をあげると、小学校での英語の実質的な指導者となる、約1,800人のALT(外国語指導助手)と約6,000人の補助教員の人たちを対象とした意識調査があります。小学生の英語が教科化されるとなると、きちんと教えることができる先生が必要ですが、現状では専門の先生が配置されている小学校はわずか6%ほど。ALTや民間組織で資格を取得した外部の人たちが、補助教員として手伝わないとやっていけない状況ですが、実際に英語をどう教えているか。また、教えるにあたりどんな課題があるかなど、それぞれの立場からヒアリングしています。
この調査を通じて、たくさんの意見が寄せられています。とくに日本人の補助教員の方たちは、文字通り「補助」なのですが、学校によってはメインで指導をしたりしています。待遇も時給あつかいだったりボランティアだったりとさまざま。学校や授業内容について言いたいことはたくさんあるようです。そうした意見だけでも何百ページにもなり、小学校の英語教育だけでも、まだまだ課題があるのが実情です。そうした課題を解決するために、いくつもの改革が行われようとしています。それらの改革を見届け、またそのために自分ができることをしっかりやっていきたい、と気を引き締めているところです。
戦後10年目、小学1年生でアメリカへ 中学1年生のおわりに帰国して中学2年生を2回経験
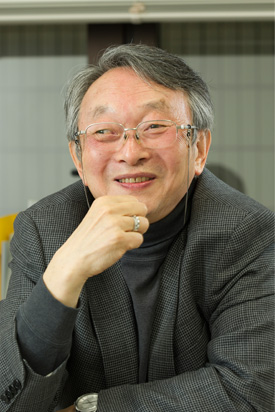
わたしが英語教育を仕事にするようになったのは、子ども時代に海外で生活していた影響が多分にあります。初めてアメリカに行ったのは、第2次世界大戦の終結から10年後の1955年、小学1年生のときでした。商社勤務の父の転勤で、一家でニューヨークへ。両親の話では、「京都在住者で戦後アメリカ行きの査証(ビザ)を家族で取得した初めてのケース」、渡米で使ったアメリカの航空会社でも「日本人で家族での搭乗は初めて」だったそうです。単身赴任はともかく、家族で渡米することはまだまだめずらしい時代でした。
そんなですから、海外からの転校生用の語学の補習校などもなく、編入した小学校の先生は、英語を聞くことも話すこともできないわたしをどう教えたものかと困ったようです。とりあえず、わたしは教室の最後列の席になり、画用紙とクレヨンを与えられて、ずっと絵ばかり描いていました。それでも英語が少しずつわかるようになり、3ヵ月もするといちばん前の席にすわるようになりました。大戦後10年ほどのころですから、敵国だった日本人だというだけで差別的に呼ばれていじめられたこともありました。もちろん、声をかけてくれ、遊びにさそってくれるクラスメイトもいて、しだいに学校になじんでいきました。
こうして、学校にもなじみ、親しい友人ができるようになった小学2年生のおわりごろ、父の転勤でこんどはカナダのモントリオールへ。現在とはまるで違い、日本人はアメリカよりさらに少ないようなところでした。おまけにモントリオールはフランス語圏ですから、英語も通じるものの、現地の小学校ではフランス語をゼロから学ぶことになりました。そして2年がたち、小学4年生がもうおわろうとするころ、「キミには小学5年生の授業は必要ないだろう」と先生から言われ、なぜかいきなり6年生に。ですから、わたしはいまだ小学5年生を経験していないんです(笑)。
カナダはアメリカより楽しかったですね。多民族国家で、アフリカ系やヨーロッパ系、中国系など、さまざまな民族や国の友だちができ、野球やアイスホッケーをしたり、家族でスキーに行ったりと、楽しい思い出がたくさんあります。
このままずっとカナダでもいいかなと思っていましたが、中学1年生の秋に、父の転勤で日本にもどることになりました。日本では一家で大阪に住むのですが、カナダでカトリック系の中学校に通っていたため、京都にあるカトリック系の私立学校に編入することになったのです。これには少し理由がありました。アメリカでもカナダでも、両親は家のなかで日本語を強制することもなく、妹との会話もずっと英語でしたから、そのころのわたしの日本語力はほぼゼロ。京都のその学校は校長先生がカナダ人で、英語で学力試験を受けさせてくれたこともあり、編入することができたのです。
とはいえ、帰国当初は日本語はほとんどわからずで、授業についていけない。でも、ここでも友だちがいろいろ助けてくれました。何よりよかったのは、すぐに野球部に入ったことです。そこでは言葉は関係なく、ボールを追えばいいのですから、日本語がわからなくても楽しくて、心の大きなよりどころになりました。
中学の英語の授業は「きみには簡単すぎるだろう」という理由で、アメリカのハイスクールで使われている英文学の教科書4冊を渡され、それを読んでいました。しかし、ほかの教科も総合した成績は、中学2年生の1年間ずっとビリ。中高一貫の進学校だったので、中学3年生になると、高等部に進んでもたいへんそうな生徒は呼び出され、公立高校の受験準備をするように勧められます。
ところが、わたしは中学2年生のおわりに呼び出されました。公立高校受験のことなのかなと思っていたら、先生は「このままだと高等部に進めないかもしれないから、もう1回、中2をやってみるか?」と聞くのです。わたしは「やります!」と即答し、中学2年生を2回やることになりました。たいして成績は上がらなかったものの、2回目だったこともあってそれなりにできるようになり、無事、高等部に進学できました。小学5年生はカナダでパス(飛び級)しているので、これでちょうど計算が合ったことになります(笑)。
ESSサークルで教えた後輩が英語弁論大会で準優勝 その自信が英語教師の道へといざなう
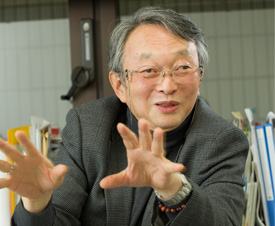
ふり返れば恥ずかしいエピソードはたくさんあります。たとえば、高校では古文の授業がありますよね。英語の時間に、「英文を日本語で訳せ」と言われたときには、古語と現代語の区別がつかなくなってしまい、古語と現代語をまじえたおかしな日本語で解答してしまったこともありました(笑)。進学校だったので周りは優秀な人たちばかり。わたしが、なぜミスをしたり、なぜおかしな答えをするかを理解してくれていたので、かえって劣等感はなかったですね。
とはいっても授業は苦手。でも、部活のおかげで学校へ行くのは好きでした。中学3年生までは野球をしていたのですが、あるとき肩を壊してできなくなってしまいました。さあ部活をどうしようかと悩んでいたところへ、「2回目」の中学2年生時代の友人から、「お前は英語ができるから」と勧められ、英語サークルをつくることになりました。英語が得意だった、というより英語しかできなかったこともあり、楽しくて、やりがいもありました。そして、高校ではESS(English Speaking Society)に入って活動することになり、それに熱中していました。
英語教師を志すようになったのは、このころのことです。わたしは高校1年生のとき、英語スピーチの全国大会(チャーチル杯争奪全日本高等学校生英語弁論大会)で優勝したのですが、翌年から、わたしのような「帰国子女」は参加できなくなってしまいました。そこで、後輩の指導をすることになるのですが、これが自分にとても合っていました。
スピーチ原稿の構成を考え、原稿を書き起こす、発表での原稿の読み方や発音まで。わたしがずっと指導していた後輩が、全国準優勝になりました。当時から、わたしはニックネームで「よしけん」と呼ばれていたのですが、準優勝した後輩が朝礼で表彰されたとき、英語の先生が「よしけんがいなければ、この表彰はなかった」と、全校生徒の前でほめてくれたのです。それがとてもうれしくて、とても大きな自信になりました。このとき、「もしかしたら人に教える才能があるのかも」と思うようになったのです。
 | 後編のインタビューから -大学時代、人類史上初となるアポロ11号月面着陸(1969年)をラジオで同時通訳 |