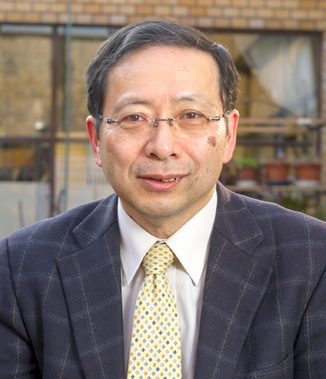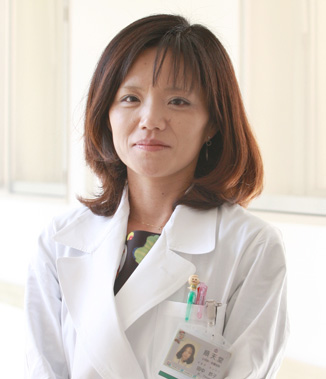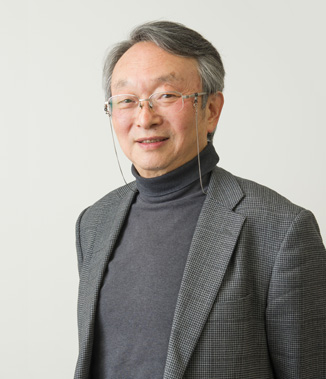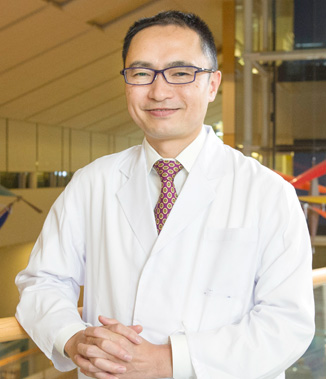福祉と医療の壁を取りはらい、たがいに連携を深める

「ふつうの眼科医」だったわたしの人生は、あるひとりの患者さんとの出会い(前編参照)を機に大きく変わりました。「ロービジョンケア」を知り、その研究と実践に没頭するようになったのです。
とはいえ、周囲の眼は冷ややかなものでした。当時、わたしは大学病院の助教授だったのですが、医師たちはロービジョンケアにあまり関心を向けてはくれませんでした。それは、ロービジョンケアというものにそれまで医師が関わることをむしろ拒否し、どちらかといえば福祉の領域のことだったからです。また、論文にもなりにくいことであったのも、関心を示さない理由のひとつだったのかもしれません。そんなロービジョンケアを、わたしがなぜそんなに熱心にやるのか理解しにくかったのでしょうね。
一方で福祉側からも歓迎されませんでした。福祉の領域へ、眼科医であるわたしが入り込んでいったものですから、福祉の専門家からすれば、「何をしたいのかな?」という疑問をもったのだと思います。お互いに相手側の領域の理解不足があり、福祉界と医療界に立ちはだかる壁を感じました。
けれども、患者さんのことを考えれば、壁などはないほうがいいので、患者さんの心を前向きに変えた歩行訓練士*に教えを請い、ほかの福祉の人たちからも真摯に学ぶことにしました。そして、福祉関係者と医療関係者は、それぞれ役割分担はあるものの、お互いに連携を深め、良きパートナーとして、強いチームとして患者さんに向き合うことが大事だとの考えに至りました。
*「歩行訓練士」:正式名称「視覚障害者生活訓練等指導者」
こうして1996年に念願かなって、当時勤務していた産業医科大学病院(福岡県)の眼科にロービジョンクリニックを開設しました。さらに、ロービジョンの人たちが抱える問題を解決するには、多くの職種の人たちと連携することが重要だと考え、北九州視覚障害研究会や九州ロービジョンフォーラムを発足させ、このときの同志ともいえる仲間たちとの研究や実践を、『ロービジョンケアの実際 視覚障害者のQOL向上のために』(医学書院、2006年5月)という専門書にもまとめました。
その後、柳川リハビリテーション病院勤務を経て、わたしが北九州市立総合療育センターに赴任したのは2008年です。じつはそれ以前から、このセンターでは視能訓練士を中心とした「ロービジョンケア」をしていましたが、現在ではより進化し、眼科スタッフに歩行訓練士が加わり、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床心理士やソーシャルワーカーなどの異なる分野のスタッフたちとチームを組んで、患者さんに向き合うようにしています。
患者さんのもっている力を見つけ、最大限に引き出し、ときには背中を押す
 |
 タイポスコープの活用 反射のない黒い紙に窓を開けたものです。 これを使用すると固視が良くなり、コントラストも上がり、まぶしさが軽減し読みやすくなります。 |
わたしが考えるに、視覚に障害がある患者さんに対してわれわれがまずすべきことは、患者さんの「それぞれに異なる見え方」を理解して、本人や身近なご家族にそれを伝えること。そして、どうすれば「見える」ようになるのかを、患者さんとともに考え、生活のなかで実践に移し、初めはわずかであっても、「見える」ことを自覚して、希望をもってもらうことだと思います。
たとえば、視野の真ん中が見えにくい「中心暗点」という症状があります。この症状の場合、視野の周囲は見える状態ということも多いので、「目を上げてみて、何か見えますか?」と聞いて、見えたら「何センチくらい上げた感覚で見えましたか?」とさらに聞き、その感覚を憶えてもらいます。すると、患者さんは見えることに喜び、だんだんと「見える」ための目の使い方がわかるようになります。もちろん、その感覚や目の使い方を身につけるには、毎日くり返し練習することが必要です。
どうして、そんなことをするかですが、一般的に人は目の中心でものを見ようとしています。その中心部が病に侵され、ただでさえ見えにくくなっているのに患者さんは、見えないところで見ようとしてしまう。そのため「見えない」と思い込んでいることが少なくないからです。それをわたしたちが診察や検査をして、「どうすれば見えるか」を判断し、「見えるようになるための工夫や方法」を患者さんといっしょに実践するようにしています。
補助具による、よりよく見える工夫も伝えます。その一例が「タイポスコープ」です。これは反射のない黒い紙に窓を開けた(枠を切った)もので、本などで何行も文がならんだ部分に当てると、文字情報が適量になってぐっと読みやすくなります。わたしのセンターでは牛乳パックを再利用して手作りしています。ちなみに、真ん中に開ける「窓」の大きさは、使う人に文字を書いてもらい決めます。「書ける字」は「読める字」だからです。
ほかにも、病気や事故で視野が狭くなっている患者さんでも、視力が良い場合には縮小ルーペ(凹レンズ)を使うと視野が拡大できるなど、その人がもっている、あるいは残っている視覚の機能や力を最大限に活用するための方法や補助具はいろいろあります。患者さんのいまの状態や日常的な悩みをよく聞きとって、どうすれば見えるようになるかを、患者さんとともに考えていきます。
こうして「見えない」あるいは「見えづらい」状態を、すこしでも「見える」ように変え、これまで日常生活でできなかったことを、ひとつずつでよいのでできるようにし、「つぎに何をしたいか?」をいっしょに探していけば、患者さんは自信を取りもどします。やがて希望が生まれ、早い時期に社会復帰が可能になります。
そのために、患者さんに寄り添う「ケア」から、もう一歩踏み込む必要性を感じています。それでわたしは最近、「ロービジョンケア」ではなく「ロービジョンハビリテーション」「ロービジョンリハビリテーション」という言葉を使います。発達期・成長期にある子どもたちに大切な、新たに機能や能力を獲得するための「ハビリテーション」。おもに成人対象の、機能や能力を取りもどすための「リハビリテーション」です。どちらもロービジョンケアのなかで、これまでもしてきたことですが、われわれも、そしてなにより患者さんにしっかり意識してもらい、自身の将来にもっと前向きになってもらうために、この言葉を使うようになりました。
本来の意味とはちがいますが、「ロービジョンハビリテーション」「ロービジョンリハビリテーション」には、「背中を押す」という想いも込めています。患者さんより医師が優れているところがあるとすれば、それはさまざまな患者さんを診ていることです。その経験や知見から、患者さんが「困ったな」となる前に、「こうすれば困らないよ」とアドバイスができ、さらに「こうすれば、できるようになるよ。がんばってみる?」と、背中を押してあげることもできます。
この考えは、ときに「患者さんが望んでいないのに、やらせている」と誤解されることがあります。しかし、ご家族も含め、患者さん自身は「困るであろうこと」はなかなか予測しにくいので、いったん困った状態になると対処がおくれてしまうことがあります。たとえば、就学・就職や結婚など、人生において重要なタイミングはいくつもありますが、わたしたちのセンターに来られるのは、たいていそうしたタイミングのときが多いのです。
そういうときは患者さん、ご家族ともに、心にも時間にも余裕がなく、本人には十分な機能や能力があるのに、「普通学級は無理かな…」「この仕事できるのかな…」「わたしなんかが結婚していいのかしら…」と、つぎへの一歩を踏み出せないでいることがあります。これは、ぼくらが背中を押すことが使命だと思うのです。いわば「親切なおせっかい」をするわけです。「寄り添う(ケア)」ことと「背中を押す」ことの、両方が必要なのですね。
学んできたものは、人の役にたってこそ、初めて「学び」となる

患者さんはできることが増えると、それに伴い達成感が増してきます。公文式学習と同じですね。日々のロービジョンのトレーニングも、日々の公文の学習も、ときにはやめたいと思うことがあるかもしれません。けれど、患者さんも教室の生徒さんも、その日できるようになったことを認められ、それをともに喜んでもらえることが大きな励みになっているはずです。その積み重ねの先に、「こういう人生を歩みたい」「こういう学校で学びたい」という大きな目標がつくられていく。「日々の100点主義」の大切さは、ロービジョンケアも公文の学習も同じなのだと思います。
そんなふうに思えるようになって、自身の半生をふり返ってみて痛感するのは、「患者さんたちがわたしの先生」ということです。「ふつうの眼科医」だったわたしを、ロービジョンの専門医として育ててくれたのは、数えきれないほどの患者さんたちです。「これはうまくいった」という成功例の患者さんもたくさんいますが、わたしの大きな転機(前編参照)となった患者さんのように、治療がうまくいかなかった例も少なくありません。もちろん、それに伴う悩みや苦しみも。
たとえば、視覚障害になると心はうつ状態になりやすいということを十分理解できていなかったころ、「やればできる!」とがんばらせすぎて、結果的に自信をなくさせてしまった少年がいました。なぜ、彼の心を和ませる一言をかけてあげられなかったのか。いまでも悔やんでも悔やみきれません。患者さんからすれば、わたしの身勝手な言葉に聞こえるだろうことを覚悟して言いますが、「二度とあんな失敗はしない。苦しみや失敗を教訓として、つぎの患者さんのために活かそう」と心に決めています。
こんなわたしが言っても説得力に欠けますが、「すべてのプロフェッショナルはプロフェッショナルに徹すべし」というのがわたしの信条です。わたしは眼科医というプロです。その意味では、ひとりの患者さんに対して、視覚検査のプロ、歩行訓練のプロ、補助具製作のプロなど、それぞれのプロが、それぞれのもてる力を存分に注ぎ、各自が学んできたものを患者さんに役立つように活かす。それができて初めて、学んできたことが「学び」として結晶するのだと思います。人の役に立ってこその、「学び」だと思うからです。
わたしが、これから新たに取り組んでいこうと考えているのは、学習障害(LD)のひとつ、「読み書き障害」という領域の研究と実践です。わたしがいるセンターには発達障害の子どもたちも多く来院していて、その子たちには少なくない割合で読み書き障害という課題があります。そこにロービジョンケアを実践している眼科医としてできることがあるのでは、と考えているのです。
もちろん、世界中のたくさんの専門家の方たちが連綿と研究を続けている領域ですから、すぐに何らかの成果がでるとは考えていません。とはいえ、センターに来る子どもたちを見ていると、成長期にある彼らにとっては、ある意味、時間との戦いという側面もあります。子どもたちの読み書き障害の事例と実情をより深く知り、彼らに寄り添うことで見えてくるものもあると思うのです。数年のあいだには、なんとか読み書き障害の対応への道筋をつけて、眼科医が実践できるモデルをつくり、多くの眼科医とも共有できるようにしていきたい。いま、そんなことを考えています。
 |
前編のインタビューから – 「わが子の視覚に問題があるのでは?」と悩む保護者に、まず高橋先生がすること |