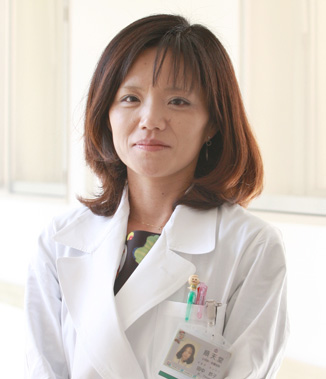子どもには「インフォーマルな知識」がある
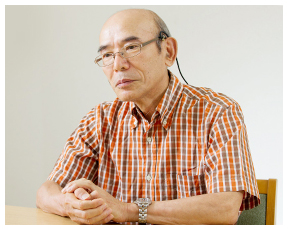
大学院で教育心理を学んだあと、大学の教育学部の講師となった私は、本格的に教育心理学と関わるようになります。教育心理学というのは、おもに子どもの教育と発達を研究して、健やかな発達を支援することを目的とする学問分野です。
たとえば、「勉強がきらい」という子は、どの学校にも少なからずいるでしょう。こうした子どもたちの授業の理解や学力の低さについてはたびたび問題になりますが、その背後には、現在の授業が、私の言葉で表現すると『教科の理論』で行われているからではないかと考えています。教科の理論とは、数学・理科・英語など各教科の論理体系を、子どもにもわかるように簡潔にまとめたものを教育カリキュラムとしていることです。これで、子どもたち全員が授業についていければ問題はありませんが、現実にはそうではありません。
そうならないためには、『教科の理論』から、これも私の言葉ですが『子どもの理論』によるカリキュラムに転換すべきだと思っています。『子どもの理論』とはどういうことかというと、その要素は2つあります。1つめの要素は、子どもは日常生活から得た知識がいろいろあるということ。それを私は「インフォーマルな知識」と呼んでいますが、それがどのくらいあるかを具体的に知ることです。
インフォーマルな知識とは、たとえば、「割合」は「比べる量を基(もと)になる量で割る」ものですが、この公式は小学5年生で教えられるものなので、4年生の子は知りません。けれども、学校で習っていなくても割合の元になる考え方を持っている子はいます。スーパーで3割引きの商品と4割引きの商品のどちらが安いかと聞くと、答えられる子が少なくないからです。
実際、私の研究では、子どもたちは大人が考える以上に、豊かなインフォーマルな知識を獲得していることがわかっています。しかし、多くの大人はそのことをほとんど知りません。インフォーマルな知識は「学びの素」であり、これがあれば、基礎的なことは理解できるので、それを踏まえて教えれば学習はスムーズに進みます。
「楽しい学び」には健康に育つ生活環境が大切

『子どもの理論』のもうひとつの要素は、新しい内容を学習するとき、どこでつまずくのかをはっきりさせることだと考えています。障害物競争に例えれば、目の前にネットがあるのか、跳び箱があるのか。ネットであれば身を低くし、跳び箱ならジャンプしますね。障害物は何なのかをはっきりさせれば、おのずと対処の方法を考えられます。このように子どもの目線から考えたカリキュラムで教えれば、子どもは学習しやすくなり、勉強ぎらいの子たちはかなり減ると思います。
もちろん、こうしたアプローチは教育のプロである教師が実践することですが、ご家庭でも、たとえばスイカを食べるとき、「家族5人だから平等に分けましょう」とか「お父さんお母さんの分は大きく分け、残りを3等分しましょう」など、一言付け加えながら切り分ければ、言葉と実際の行動が一致し、それが子どもの経験となって、インフォーマルな知識や基本的な概念が育つようになります。
わが子が「勉強ぎらい」にならないようにと心配する親御さんもいると思いますが、学びをきちんと吸収できるようになるには、まず、子どもが健やかに発達していることが前提になります。健全な発達ができる日常生活や家庭環境が必要なのです。
学校のあとすぐに塾に行き、夜10時に帰宅するような生活では、子どもとしての精神的な発達が十分でない可能性もあり、教育を行うためのいちばんの基礎ができてないという心配もあります。その時期は問題なくても、発達は日々の積み重ねですから、のちのち問題となって出てきます。年齢だけ重ねても、基礎ができていなければ、次のステップに行くときに心が不安定になりがちです。
たとえば「ギャング・エイジ」といわれる小学校中学年くらいは、特定の複数の友人と遊び、そこで「自分」と「複数の他人」という関係ができ、これが対人関係の基礎となります。しかし、その遊ぶ機会がないと、基礎を築けず、青年期に1対1の人間関係をつくりにくいことが多いのです。
「どうしてだろう?」と疑問をもつことが、学びを楽しくする

私は「学び」はとても楽しいことだと考えています。新しい知識を得られるのは、本能的に楽しいはずですから。ですが現代は、なぜか、学びを楽しくさせない環境のように思います。その要因を明確にすれば、学び本来の楽しさをもっとたくさんの人たちが体感できるのではないでしょうか。
子どもたちには「新しいことを知ることはおもしろいんだ」という場面を、自分からも探してほしいと思います。いろいろな活動をしていくことを大切にし、知らないことやわからないことがあったら「どうしてだろう?」と疑問をもつ。それが学びを楽しくする手がかりになるでしょう。
その意味では、できることをくり返しながら先の教材へと進んでいける公文式学習は、学ぶ楽しさを体感できる学習法ですね。また、自分の力で解き進み、新しいことを知ることで、もっと学ぼうという意欲が高まるところもいいと思います。
「未知のことを知る楽しさ」は大人も同じです。たくさんの「常識」が確立されている現代ですが、それにとらわれ疑問をもたなければ、そこから先へは進めません。新たな「学び」もないと思うのです。「学び」は子どもだけはなく、ヒトという種の生涯を通したテーマなのかもしれませんね。
「学び」、「生涯」ということでいえば、立命館大学では、2006年から「高齢者プロジェクト」として、地域の健康な高齢者の認知機能や日常生活機能を維持・向上させることを目的に、音読や易しい計算などの学習活動を実践する教室を運営しています。まさに公文式と同じく読み書き計算をする学習です。私もそのプロジェクトに携わっていますが、認知機能、たとえば記憶や抑制機能など、学習活動で訓練していない機能も改善しているといった効果も見えてきました。
そのプロジェクト活動で、人間の学びの力を強く再認識した出来事がありました。2年間ほどプロジェクトの教室に通われていた90歳近くの女性が、病気になり入院されました。ふつうなら、それだけ高齢ですとほぼ寝たきりの状態になる方が多いと聞いていますが、その女性は病室のベッド横に教材を置き、他界される1週間前まで学習されていたのです。ご家族からは「学び続けることで、逝くまでの日々を安らかに過ごすことができました」と感謝されました。学びは一生続くもの。ぜひ楽しく学び続けていただきたいと思います。

|
前編のインタビューから – いま、吉田先生が特に関心をよせている3つのこととは? |