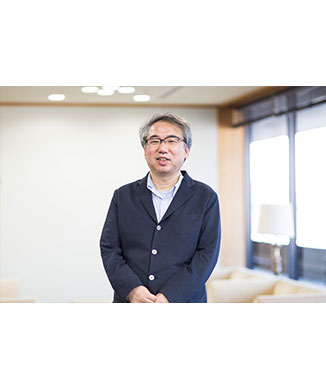漆は人間の肌と同じ、水分を吸収して潤う
 新技法で開発された擦れに強い漆器 |
私の実家「輪島キリモト」は、江戸後期の1700年代に「塗師屋(ぬしや)」として創業しました。塗師屋とは、「塗り」と「販売」を兼ねた、いわば製造販売業。その後、昭和の初め、5代目のときに「木地屋」に転業しました。「木地」は原木を彫ったりして漆器のベースをつくる工程です。輪島塗は徹底した分業生産で、各工程に専門の職人がいます。全部で120工程にもなりますが、大きく「木地」「下地塗り」「上塗り」「加飾」の4工程に分けられ、実家ではその土台となる工程を担っていたというわけです。
7代目の父のとき、デザイン提案から仕上げまで行う一貫生産販売体制をとるようになります。いわば、独自路線を歩み出したわけです。「輪島塗」という伝統的工芸品の定義としての技法に加え、金属性のスプーンと一緒に使えるような新技法を創出しています。
「輪島塗」の起源は諸説ありますが、私は室町時代につくられていた説を信じています。約400年も長く受け継がれている理由のひとつは、「土地の力」があること。輪島は漆が育つのに適した風土で、輪島塗の特徴である「輪島地の粉」(漆と混ぜて下地にする珪藻土)を産出する大地があります。そうした土地の力のもとに、職人が集まってきて産地が形成されました。
「もの」として長く使われている理由は、丈夫で長持ちするから。親子孫三代どころか、私が使っているお椀には、「明治44年作」と記されているものもあります。「漆器は手入れが大変」と思われていますが、じつは日々使うことが一番のメンテナンス。人の肌と同じで、水分を吸ったり吐いたりしているので、使って水分を吸って潤うことで長く使えるんです。
逆に1年に1度しか使わないと、水分が抜けてヒビが入ってしまいます。こうした漆の特徴が正しく伝わっていないことはとても残念です。そこで、「漆の魅力をしっかり伝えよう」。もっと言うと「漆を再定義しよう」と、「IKI」というブランドをこの3月に立ち上げました。フランス留学の経験から学んだことが、クリエイターたちと一緒になることで形になったんです。
ぜったいに継ぎたくなかった
でも夢を描きたくても描けなかった
 |
私が生まれ育った輪島は自然が豊かな地。子どもの頃はクワガタをとったり秘密基地を作ったりと外遊びが大好きで、昆虫博士になりたいと思っていました。でも、将来の夢をきかれると、本意でなく「職人」と答えていました。周りを気にしていたんですね。
というのも、漆器業界は私が生まれたころから右肩下がり。食卓では祖父と父が事業の方向性について、よく言い争いをしていました。周囲の塗師屋も倒産していく……。そんな状況を見ていたので、「ぜったいに継ぎたくない、そもそも産地自体が長くないだろう」と思っていました。
だから、自分は自分で生きていく道を探そうとしました。ところが、見つからない。家業や家族のことも気になっていて、夢を描きたいけど描けなかったんです。学校のキャリア教育や進路指導がすごくイヤで、「早く輪島を出たい。輪島にいるから夢が見つからないんだ」と思っていました。
18歳までずっとそんな気持ちで過ごしていました。私の気持ちを知ってか知らずか、父は一度も「継いでほしい」と言ったことはありません。毎日仕事で忙しくしていた父とは遊んだ記憶がありません。でも、父のことはすごく尊敬していました。苦しくてもあきらめないし、新しい技法を開発したりしている。ただ、だからこそ、自分には同じことはできないという思いがありました。
そんな学生時代の実家での忘れられない出来事があります。私が中学2年生だった2007年3月、能登半島地震が発生しました。その復興チャリティ企画として、フランスからルイ・ヴィトンの次期社長が輪島キリモトに来て、同じく輪島キリモトの次期社長である父とコラボレーションして、ものづくりをしたんです。それを目の当たりにして、「家業が国境を越えることがあるんだ!」と、衝撃を受けました。その時は「フランス人が輪島に来た、すごいな」と思っただけでしたが、今から振り返ると、この出来事は私の原体験ともいえる体験だったと感じます。
「過去の自分を超えた」という達成感が味わえた公文式
 |
私にとって、母から受けた影響も大きかったかもしれません。母は大阪の出身で、父との結婚を機に輪島へ。もともとは英語を子どもに教えたかったそうですが、慣れない土地で職人さんの世話をしたりして、大変だったと思います。でも決して父のことも家業のことも悪くは言いませんでした。
猪突猛進な性格の父に対し、母は常に冷静で客観的。「お父さんがこうしているのはこういう理由があるから」と、かみ砕いて教えてくれました。「家業とは何か」「産地とは何か」ということは、母との会話の中で理解するようになったように思います。
私が公文式に通うきっかけも母でした。母が公文式教室で英語指導の手伝いをしていたため、私も小学校低学年から通うようになり、算数と英語を中学1年まで続けていました。
公文式のよさは、“過去の自分”と“いまの自分”の立ち位置がわかることだと思います。問題をくり返し解く中で、「先週は10分かかったのが、今週は7分でできた」とか、「前回はミスが多かったけど、今回はミスがなかった」というふうに、「過去の自分を超えた」達成感が味わえます。しかも押しつけではなく、自主性を尊重してくれる。だから、公文の教室に通うのは楽しかったですね。
公文式で実感した「他人と比べすぎずに、過去の自分を超えていこう」という考えは、いま私が漆の魅力を伝えるうえで意識している「ナンバーワンよりオンリーワン」という姿勢に繋がっていると思います。
関連リンク 輪島キリモトウェブサイトトビタテ!留学JAPAN
 |
後編のインタビューから -大きな転機となった出来事とは? |