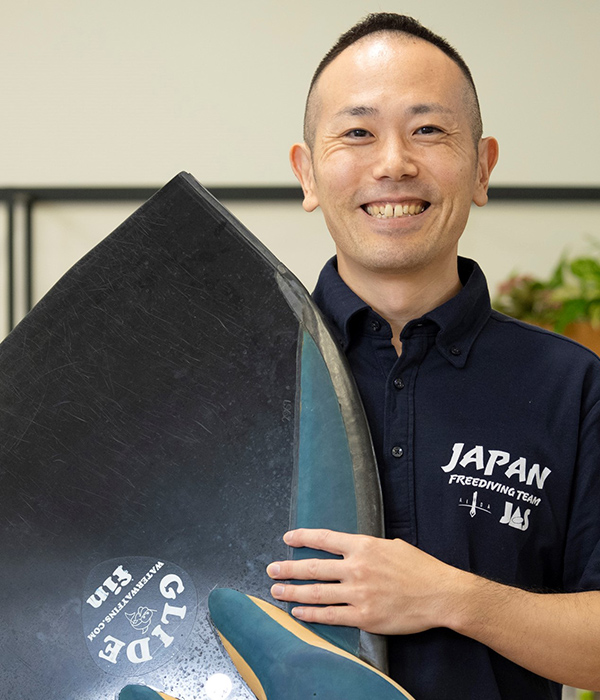聞こえの良い言葉の背景にあることを伝えたい
 |
現在私が特に関心を持っているのは、「東南アジアで熱帯林がどんどん減少していくなか、現地では何が起こっているのか」ということです。
1990年代、地球環境を守るために「気候変動枠組条約」や「生物多様性条約」といった国際的な条約が作られました。その一環で、熱帯林を含め、世界の森林を守ることが重要だと言われるようになりました。グローバルな環境保全の重要性が唱えられる中、そのこと自体は確かです。しかし、森林の現場で何が起きているのかということはあまり知られていません。現地に行き、そこに住む人たちから話を聞く中で、「国際的な合意のもとにつくられた条約や政策が、ローカルの住民にとってどんな意味があるのか、また、それが地域でどう活かされているのか」を明らかにするのが私の研究の目的です。
東南アジアなどの途上国には、森林に依存して生活している人たちがたくさんいます。ですから、ただ単に森林を保全するだけではなく、そうした人たちのことを考える必要があります。しかし、そもそも森林減少の背景には、政治的、社会的、経済的な側面が絡み合っていて、問題はそう単純ではありません。その混沌とした状況の中で、どこに問題の根源があるのかということも研究しています。
たとえば、途上国の森林や生物多様性を守るために国立公園が設定された地域では、その地域にずっと昔からそこに住み、森林資源を利用していた先住民が立ち退きを命じられたり、公園内にある資源にアクセスできなくなるという問題も発生しています。そこで、公園を管理する側と住民が共存できる道を探ることも研究テーマの1つになります。
「生物多様性保全」や「森林保全」などはよく聞く言葉だと思いますが、その背景では、先進国に住む私たちには見えないことがたくさん起きています。そこに入り込めるのが研究者です。プラスもあるけれどマイナスもある。そういう中で地球環境問題を多面的に考えていく必要があるのです。
原点は「アユが獲れなくなってきた」という実体験
 |
私は小学5年生まで京都で育ちました。勉強はそっちのけで、野球やザリガニとりをしたり、秘密基地をつくったりと、遊びに夢中でした。今の子どもたちは知らないかもしれませんが、カードを地面において、自分のカードを投げて相手のカードをひっくり返すという、メンコ遊びが強いのが自慢でした。
小5の時、滋賀県に引っ越してさらに自然に触れる機会が増えたのが、今の私の原点になっていると思います。週末になると、妹と私は山好きな両親に連れられて、比良山や比叡山など、近くの山に登りました。川では、友達とアユを素手で獲っていましたね。禁漁時期でない時には自由に獲れたんです。私が引っ越してきたころは、まだずいぶん環境がよかったのでしょう。岩の下に手を入れるとアユがたくさん獲れました。友だちとスーパーのビニール袋にどっさり入れて持ち帰り、母に佃煮にしてもらいました。
ところが、それがだんだん獲れなくなっていきました。そこで竿を買ってもらい、一本釣りをするようになりました。それでも獲れなくなってきて、ついに投網(とあみ)を買ってもらいました。自己流で投げていると、大阪から来ていたアユを専門に獲る業者のおじさんが投げ方を教えてくれました。今でもインドネシアの先住民の村で、その特技を披露しています。
以前は素手で獲れたものが獲れなくなってきたことに、「環境が変わってきている」と子ども心に感じていました。この実体験が、環境や森林の研究をするようになった、今の研究生活の基盤になっている気がします。
小学校の時には、勉強らしい勉強は公文の教室に通っていたくらいです。実は、滋賀に引っ越したのを機に、母が公文の教室をはじめ、私も通うようになったんです。科目は算数・数学、国語、英語で、小5から中学1年生まで学習しました。特に算数は計算がかなり速くできるようになり、試験でも計算ミスはしなくなるなど、大変役に立ちました。計算が強いことで自信もつきましたね。また、集中力も公文の学習を通じて培われたと感じています。
「自分にしかできないこと」を常に考えるように
 |
子どもの頃、両親からは「自分にしかできないことをやりなさい」と言われて育てられました。研究者になった今も、研究テーマを含めて自分にしかできないことをやろうと常に思っています。また、中学生の頃、「自分にしかできないこと」をと考え、当時、将来研究者を目指していた友人の影響もあって、自分も大学の先生になって研究をしようと決めました。
農学部に決めたのは、地球環境問題を勉強できると思ったからです。そのころには自分の中で、環境への関心が膨らんでいたのでしょう。子ども時代に経験したことが原点にある一方で、海外、とくに途上国に対するあこがれがありました。そして大学2、3年生の頃、地球温暖化や森林破壊などの環境問題がマスコミで話題となり、「自分の興味はそこにあるのかもしれない」と気づきました。
しかし、農学部入学後、今の研究分野にたどりつき、大学教員になるまでには、紆余曲折がありました。大学では、最初は「育種学研究室」で作物のDNAを研究し、修士課程では「造林学研究室」に所属して、熱帯の森林が順調に生育するための光合成や土壌の科学的な成分などについて、自然科学の手法を用いて研究していました。でも、ちょっと違う、もう少し人間味のある研究をしたいと思うようになり、博士課程では、熱帯の自然と人間の関わりをテーマに社会科学的な手法で研究をする「林政学研究室」に進みました。さらに、大学を出てからも、JICAのプロジェクトや研究機関で経験を積みました。
そのような回り道をした私が言えるのは、人生は一度で決めなくていいということ。自分が思っていることがうまくできなければ、その時々に得た経験をもとに、また新しいことをやってみればいい。実際、複数の研究室やいくつかの職場を経たことによりいろいろな知見や経験が得られて、それらは、現在の仕事にも大いに役立っています。回り道は無駄ではなく、その後の人生に役に立つことも多いのです。
関連リンク名古屋大学大学院 生命農学研究科 森林資源利用学研究室
 | 後編のインタビューから -今の研究へ向かう転機となったインドネシアでの出会いとは |